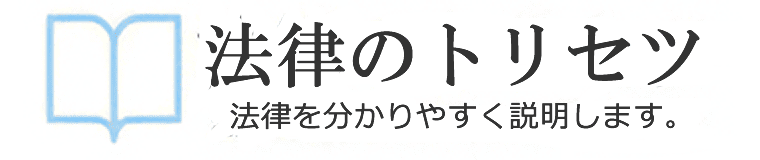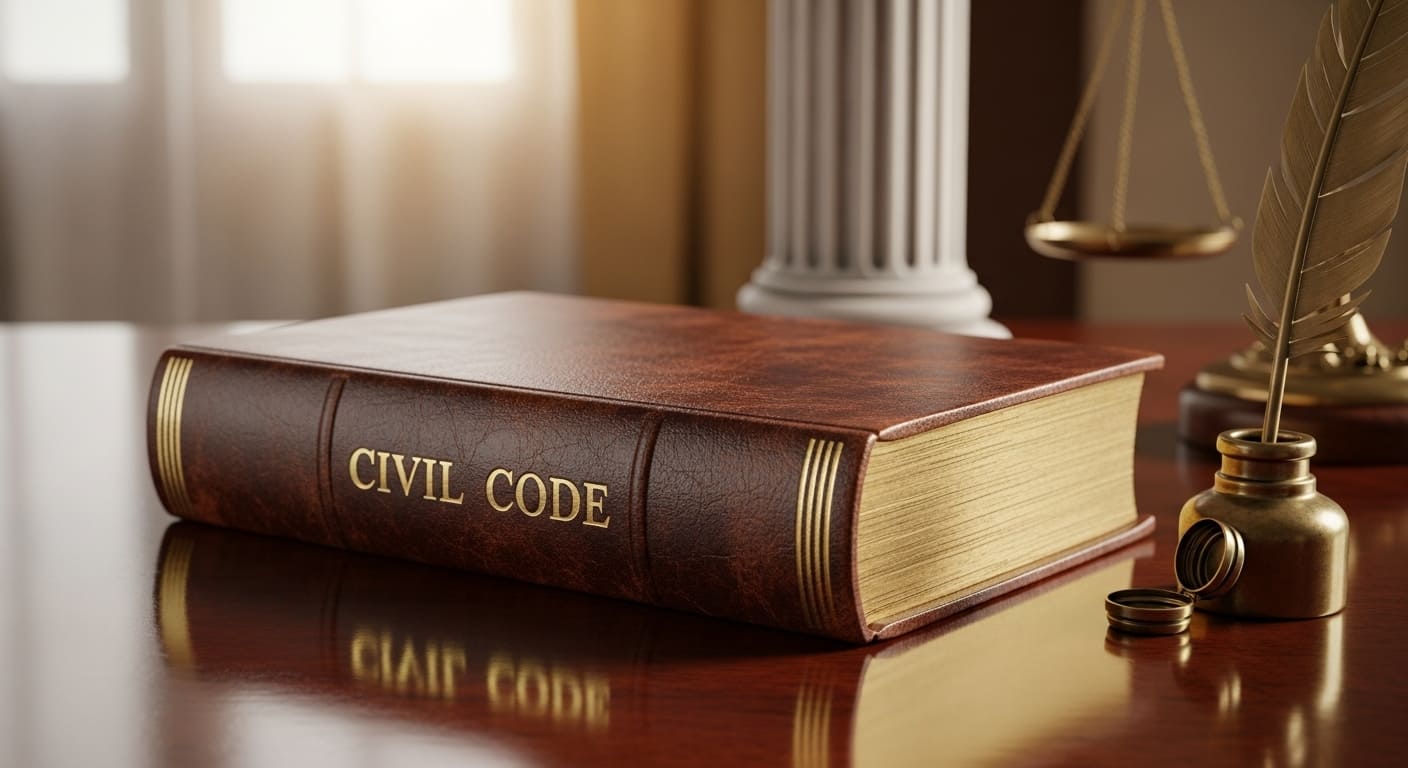この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
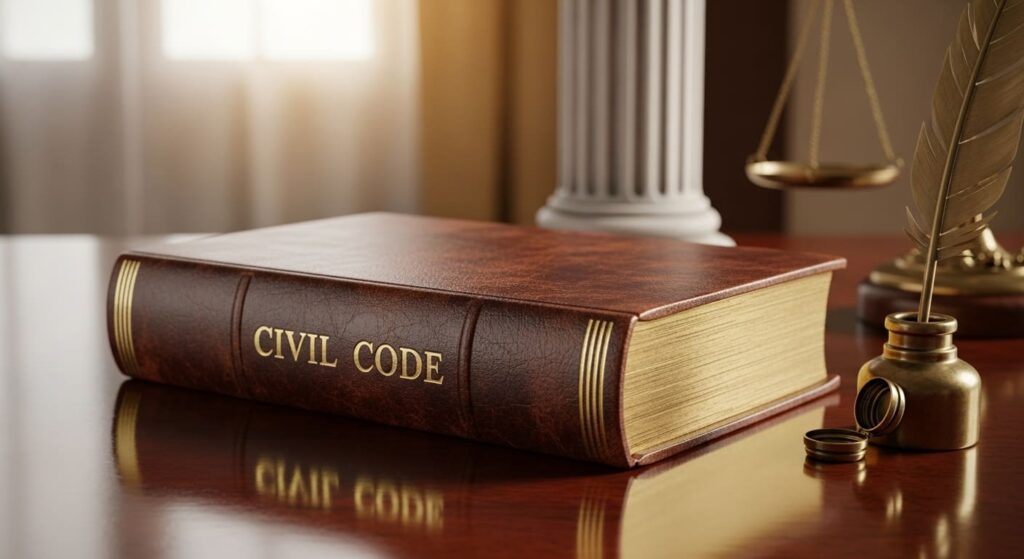
刑事法の領域だけではなく、民事法の領域でも時効制度があります。民事上の時効制度は、民法にその原則が定められています。
民事上の時効とは、ある事実状態が一定期間継続したことにより、その事実状態に合わせて権利または法律関係の発生・喪失・変更を生じさせる制度です。この民事上の時効には,大別すると,取得時効と消滅時効があります。
民事上の時効制度
法律上,「時効」という制度があります。
一般的には,犯罪を起訴する期限という意味での公訴時効が広く知られているかもしれません。よくニュースなどで「○○事件の時効まであと□年」というような報道がなされることがありますが,これが刑事における公訴時効です。
もっとも,法律上,時効という場合,上記の刑事における時効だけではなく,民事においても時効の制度があります。民事時効は、民法その他の法律において規定されています。
民事上の時効(民事時効)とは、ある事実状態が一定期間継続したことにより、その事実状態に合わせて権利または法律関係の発生・喪失・変更を生じさせる制度です。
この民事上の時効制度には、取得時効と消滅時効あります。
取得時効とは,一定期間の経過によってある権利を取得するという時効制度です。他方,それとは反対に,消滅時効とは,一定の期間の経過によってある権利が消滅するという時効制度です。
民事時効制度の趣旨・目的
なぜ民事において時効という制度が認められているのかについては,以下のような趣旨・目的があると解されています。
- 永続した事実状態の尊重
- 「権利の上に眠る者は保護せず」
- 証拠の散逸による不利益の防止
永続した事実状態の尊重
時効制度の趣旨は,永続した事実状態を尊重するところにあります。
一定の事実状態が長く続くと,その事実状態を信頼して取引などが発生することになります。
しかし,実はそれが法律に適合していなかったとして継続していた事実状態を覆してしまうと,その事実状態を信頼して取引などを行っていた人たちに不利益をもたらすおそれがあります。
そこで,長く続いている事実状態と法律関係を一致させて,法的な安定を確保するところに,時効制度の趣旨のひとつがあると解されています。
権利の上に眠る者は保護せず
時効制度の趣旨のひとつとして挙げられるのが、「権利の上に眠る者は保護せず」です。
つまり,法的な権利があるからといって何らの措置もとらずに,法律関係と一致しない事実状態を放置していたような場合には,その権利を失うようなことになってもやむを得ないという考え方です。
証拠の散逸による不利益の防止
実際問題として,5年,10年・・・と長い期間が経過すると,証拠資料が散逸してしまい,法律関係などの立証が困難になります。
時効制度には,そのような証拠の散逸による不利益を救済するという意味もあると考えられています。
民事時効制度の種類
民事時効には、「取得時効」と「消滅時効」という2種類の制度があります。
取得時効は一定期間の経過により権利を取得でき、消滅時効は一定期間の経過により権利を消滅させるという正反対の効果を持っています。
取得時効
取得時効とは、一定の時効期間の経過によってある権利を取得できる時効制度です(民法162条、163条)。
消滅時効は比較的知られていますが,取得時効は,あまり一般的には知られていない制度かもしれません。しかし,強力な効力を有する制度です。
例えば,他人の土地上に建物をたて,その土地上に長期間住み続けていた場合,取得時効によって,その土地の所有権を取得できるということすらあります。
民法上認められる取得時効には、以下のものがあります。
| 権利の種類 | 取得時効期間 |
|---|---|
| 所有権(民法162条) | 原則20年間 占有開始時に善意無過失の場合は10年間 |
| 所有権以外の財産権(民法163条) | 原則20年間 占有開始時に善意無過失の場合は10年間 |
消滅時効
消滅時効とは,一定の時効期間の経過によって,ある権利を消滅させる時効制度です(民法166条以下)。
例えば,借金などの債務を,決められた返済期日を過ぎてからも長期間支払わないままでいた場合,その貸金債権が消滅し,借金を支払わなくてよくなることもあります。
民法上認められる消滅時効には、基本的なものとして以下のものがあります。
| 権利の種類 | 消滅時効期間 |
|---|---|
| 債権(民法166条1項) | 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間のいずれか早い方 |
| 債権・所有権以外の財産権(民法166条2項) | 権利を行使することができる時から20年間 |
| 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権(民法167条) | 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から20年間のいずれか早い方 |
| 定期金債権(民法168条1項) | 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間または各債権を行使することができる時から20年間のいずれか早い方 |
| 確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利(民法169条1項) | 確定時(または効力発生時)から10年間 |
なお、これらの他にも、権利の種類によっては、さらに個別の消滅時効期間が設けられている場合もあります(例えば、不法行為に基づく損害賠償請求権など)。
民事時効の効力
民法 第144条
- 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
取得時効や消滅時効など民事時効が成立すると、起算日にさかのぼって効力を生じます(民法144条)。
時効の起算日とは、時効期間を数える最初の日のことです。
例えば、時効期間が2025年1月1日から開始されたのであれば、その日が起算日です。この場合に、2035年1月1日に時効が成立したとすると、その時効の効力は、2035年1月1日ではなく、起算日である2025年1月1日にさかのぼって発生することになります。
取得時効であれば、2025年1月1日に対象となる権利を取得したことになり、消滅時効であれば、2025年1月1日に対象となる権利は消滅したことになるのです。
時効の援用
民法 第145条
- 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
取得時効や消滅時効が成立するには、一定の期間(時効期間)が経過することが必要です。しかし、時効期間が経過しただけでは、時効の効果は確定的に生じません。時効の効果を確定的に発生させるには、「時効の援用」をする必要があります(民法145条)。
時効の援用とは、時効による利益を享受する旨の意思表示です。簡単に言うと、時効の効果が生じていることを主張することです。
時効によって権利を取得したり権利を消滅させたりすることを潔しとしない人もいるかもしれません。そのため、時効の効力発生を時効によって利益を受ける人の意思に委ねるため、時効の援用が必要とされているのです。
時効の援用には、特別な手続は必要とされていません。時効の利益を受ける人が、時効によって権利を失う人に対して、時効を援用する旨を伝えれば足ります。実務では、配達証明を付けた内容証明郵便を使って通知するのが一般的です。
時効の利益の放棄
民法 第146条
- 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
時効の利益とは、時効によって得られる利益のことです。取得時効であれば、権利を取得できるという時効の利益を得られますし、消滅時効であれば、相手方(原権利者)の権利を消滅させて自分の義務を免れるという時効の利益を得られます。
これら時効の利益は、時効期間が満了して時効が完成するまで、放棄することができません(民法146条)。
時効によって不利益を被る当事者が、暴行・脅迫など不当な手段で、時効によって利益を受ける人に時効の利益を放棄させようとすることを防止するためです。
ただし、時効期間が満了してすでに時効が完成した後は、時効の利益を放棄することができます。
時効の更新(旧「時効の中断」)
前記のとおり,民事上の時効が成立すると,一定の時効期間の経過によって,権利が消滅したり,または権利を取得したりすることになります。
もっとも,消滅時効によって消滅する可能性のある権利の権利者や,取得時効によって権利を失うことになる可能性のある原権利者も,時効が完成してしまうまで,何も対処をすることができないわけではありません。
権利の上に眠ることなく,権利を主張すれば,時効の完成を防ぐことができます。すなわち「時効の更新」(民法改正前は「時効の中断」と呼ばれていました。)の措置をとる手段があります(民法147条、148条、152条)。
時効が更新されると,それまで進行していた時効期間は全部リセットされます。すなわち,時効が更新されると,その更新時から再び一定の時効期間が経過しなければ,時効は完成しないことになります。
この時効更新の措置をとれば,消滅時効は完成しないことになり,権利者は権利を失わずに済みますし,取得時効も完成しないので,元の権利者は権利を取られてしまうことはなくなるというわけです。
例えば、以下の場合に時効が更新されます。
時効の完成猶予
時効によって不利益を受ける原権利者がとり得る措置として、時効の更新以外に「時効の完成猶予」という制度も用意されています。
時効の完成猶予は、時効の更新のように時効期間をリセットしてしまうほどの強力な効力はありません。しかし、一時的に、時効の完成を遅らせることができます。
あと数日で時効が完成してしまうものの、時効更新の措置をとっている時間がない場合に、この時効完成猶予を行って時効完成を遅らせ、その間に時効更新の手続を準備することができます。時間を稼ぐことができるのです。
具体的には、以下のような場合に、時効完成猶予の効力が発生します。
- 裁判上の請求、支払督促、訴え提起前の和解、民事調停、家事調停、破産手続参加、民事再生手続参加、会社更生手続参加をした場合、それらの手続をしている間(民法147条1項)
- 上記各手続が、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく終了した場合は、手続終了時から6か月を経過するまでの間(民法147条1項)
- 強制執行、担保権の実行、財産開示手続などの手続をしている間(民法148条1項)
- 上記各手続が、申立ての取下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによって終了した場合は、手続終了時から6か月を経過するまでの間(民法148条1項)
- 仮差押え、仮処分の手続の終了時から6か月を経過するまでの間(民法149条)
- 催告をした場合、催告時から6か月を経過するまでの間(民法150条)
- 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合、合意時から1年、当事者で定めた協議を行う期間、協議続行拒絶通知時から6か月のいずれか早い時までの間(民法151条1項)
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内1(第二版)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
続 時効の管理(改正民法対応版)
著者:酒井廣幸 出版:新日本法規出版
時効に特化した実務書。具体的な分野ごとに時効の問題をピックアップして解説しています。時効管理のために、持っておいて損はないでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎1(総則)第5版
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。
スタートアップ民法・民法総則(伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。