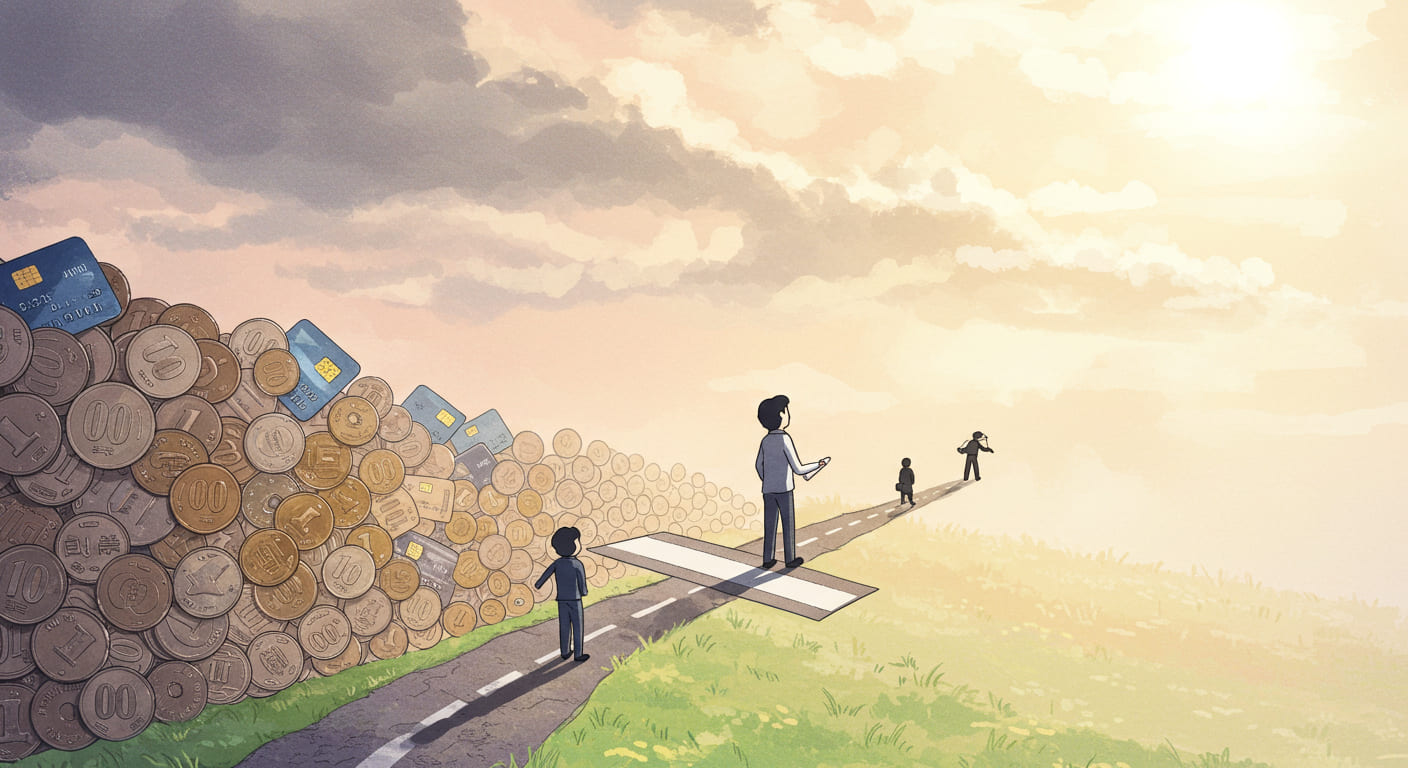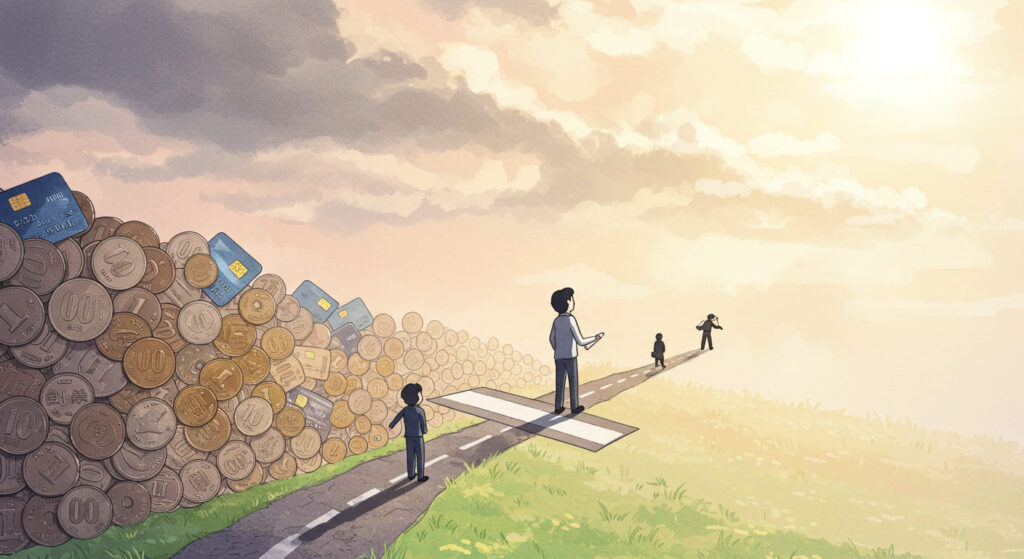
自己破産における同時廃止手続とは,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる簡易型の手続です(破産法216条1項)。
管財手続と異なり,破産手続が開始と同時に終了となるため,管財手続よりも,手続が迅速で,費用も廉価です。
自己破産における同時廃止手続
破産法 第216条
- 第1項 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
- 第2項 前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。
- 第3項 裁判所は、第1項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。
- 第1号 破産手続開始の決定の主文
- 第2号 破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨
- 第4項 第1項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 第5項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 第6項 第31条及び第32条の規定は、第1項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する。
自己破産の手続は,大きく分けると,「管財手続」と「同時廃止手続」に分けることができます。
管財手続とは,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し,それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。
これに対し,同時廃止手続は,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる簡易型の手続です(破産法216条1項)。
管財手続になるか,同時廃止手続になるかによって,破産手続の複雑さや期間の長さ,そして,裁判費用も大きく異なってきます。
管財手続との違い
前記のとおり,管財手続の場合には,破産管財人が選任され,その破産管財人が各種の調査や財産の換価処分等を行っていきます。この管財手続が破産手続の原則的な形態です。
これに対し,同時廃止の場合は,破産手続開始と同時に破産手続が終了になるため,破産管財人は選任されません。したがって,破産管財人による調査や換価処分なども行われないことになります。
同時廃止の場合には,実質的に破産手続が行われないため,実際に行われる手続は,免責審尋のみとなります。
また,管財手続の場合は,破産管財人による調査や管財業務が完了するまで破産手続は終了しません。最短では3か月ほどですが,事案によっては,それ以上の期間がかかることもあります。
これに対し,同時廃止の場合は,破産手続の同時廃止後,免責審尋しか手続がありません。そのため,2か月半から3か月で手続が終了します。
加えて,管財手続の場合には,破産管財人報酬を担保するため,引継予納金を納付する必要があります。
東京地裁や大阪地裁など多くの裁判所では,引継予納金の額を少額化した少額管財の運用が実施されていますが,それでも引継予納金として最低20万円は必要になります。
これに対し,同時廃止の場合,破産管財人が選任されませんから,引継予納金は不要です。そのため,費用面でも,同時廃止と管財手続はかなり異なってきます。
同時廃止手続になる場合
上記のとおり,管財手続に比べると,同時廃止の方が手続期間が短く,費用も廉価であるため,破産を申し立てる人の立場からすると,同時廃止の方が有利と言えるでしょう。
とはいえ,同時廃止は例外的な手続ですから,同時廃止になる場合は限定されます。
同時廃止になるのは,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です(破産法216条1項)。
具体的に言うと,引継予納金(少額管財であれば20万円)を支払えるだけの財産が無い場合です。
ただし,外見上,引継予納金を支払えるだけの財産が無いとしても,調査をすれば財産が発覚する可能性がある場合には,そのための調査が必要になります。そのような場合には,管財手続になるでしょう。
したがって、同時廃止になるのは、自由財産を除いて、引継予納金を支払えるだけの財産が無いことが明らかな場合に限られてきます。
ただし、東京地裁では33万円以上の現金を所持している場合に、大阪地裁でも現金と預貯金を併せて50万円以上を有している場合には、管財手続となるとされています。
また,財産が無いことが明らかでも,否認権を行使すれば財産を回収できる可能性がある場合には,その調査や否認権行使のために,管財手続になります。
加えて,財産も否認権行使の可能性も無いとしても,免責不許可事由がある場合やその可能性がある場合には,その調査のために管財手続になります。
したがって,まとめると,同時廃止になるのは,以下の条件をすべて充たしている場合ということになります。
- 引継予納金を支払えるだけの財産(自由財産を除く)が無いことが明らかなこと
- 東京地裁の場合は、現金が33万円未満であること
- 大阪地裁の場合は、現金・預貯金合計額が50万円未満であること
- 否認権の対象となる行為が無いことが明らかなこと
- 免責不許可事由が無いことが明らかなこと