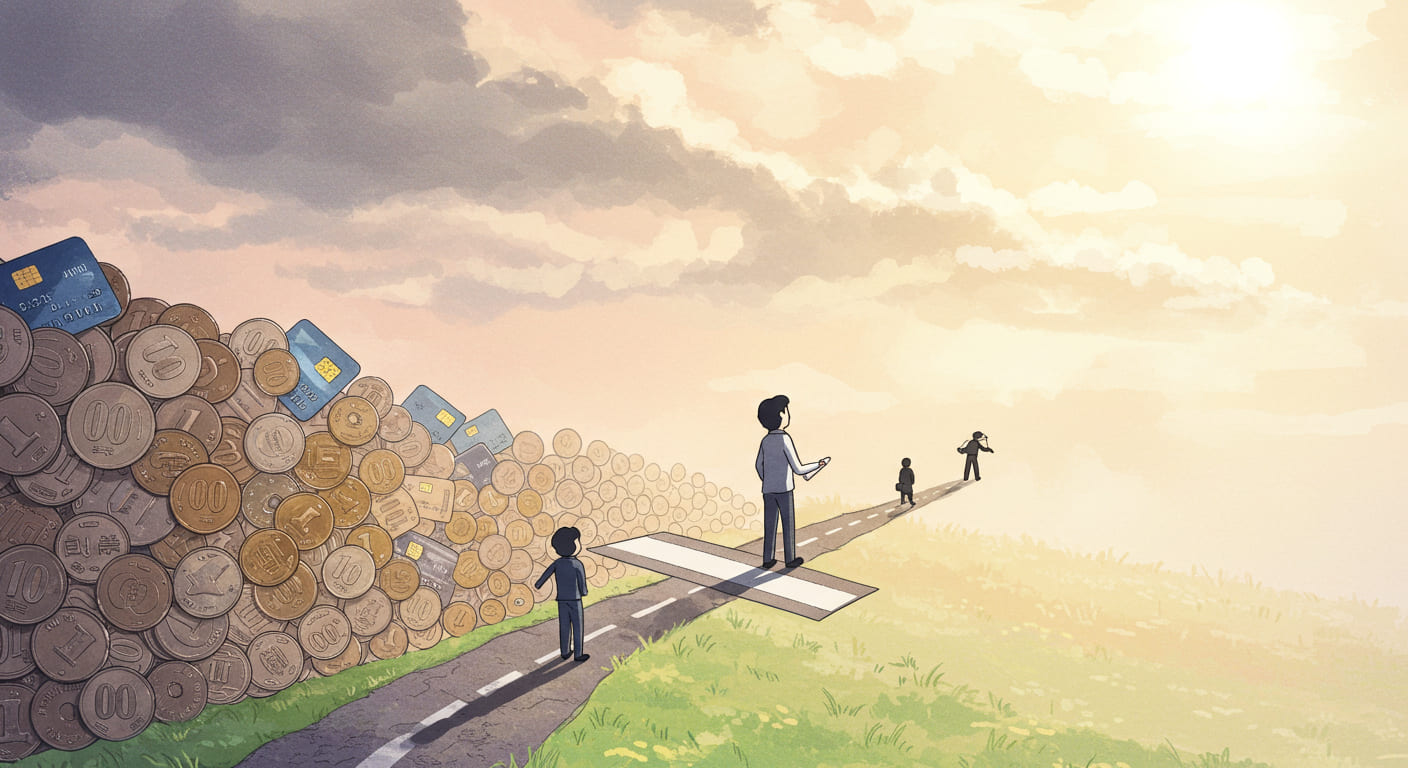この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
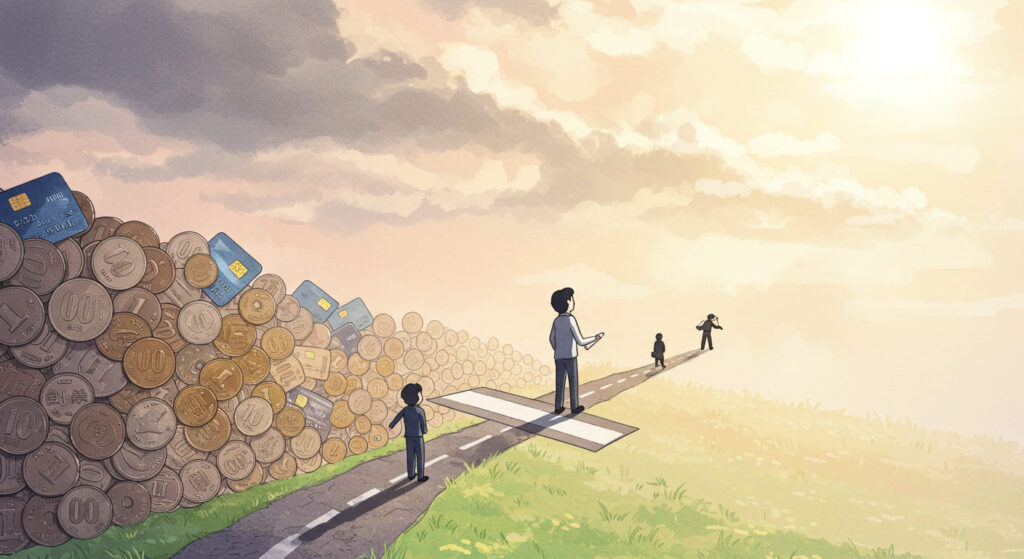
偏頗行為とは,既存の特定の債権者のみに対して担保の供与や債務の消滅行為(返済など)をすることをいいます。破産者が支払不能になった後または破産手続開始の申立てがあった後にした偏頗行為は,破産管財人による否認権行使の対象となります(破産法162条1項1号)。
ただし,否認されるのは,返済等を受けた債権者が,支払不能であったこと(支払停止があったこと)または破産手続開始の申立てがあったことを知っていた場合に限られています。
「破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後にした偏頗行為の否認」とは
破産法 第162条
- 第1項 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
- 第1号 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。- 第2号 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
偏頗行為否認とは,既存の債務についてされた担保の供与または債務の消滅に関する行為のうち一定のものを否認権行使の対象とする場合をいいます。
この偏頗行為否認のうちの類型の1つに,破産法162条1項1号に規定されている「破産者が支払不能になった後または破産手続開始の申立てがあった後にした偏頗行為の否認」があります。
偏頗行為否認の原則的形態といえます。
破産者が支払不能等の後にした偏頗行為の否認の要件
破産者が支払不能または破産手続開始の申立て後にした偏頗行為が否認される場合としては、文字どおり、支払不能後に偏頗行為が行われるタイプと破産手続開始の申立て後に偏頗行為が行われるタイプの2つのタイプがあります。
支払不能後の偏頗行為であった場合
支払不能後に偏頗行為をした場合には,その受益者が,債務者(破産者)が支払不能であったことまたは支払の停止があったことを知っている場合のみ破産法162条1項1号によって偏頗行為否認をすることができます(同号イ)。
したがって,要件は,以下のとおりです。
- 破産者の行為であること
- その行為が偏頗行為であること
- 偏頗行為が破産者の支払不能または支払停止後にされたものであること
- 偏頗行為を受けた債権者が,偏頗行為の際に,破産者が支払不能であったことまたは支払停止があったことを知っていたこと
破産手続開始申立て後の偏頗行為であった場合
破産手続開始の申立て後に偏頗行為をした場合には,その受益者が,債務者(破産者)について破産手続開始の申立てがされていることを知っていた場合のみ,破産法162条1項1号によって偏頗行為否認をすることができます(同号ロ)。
したがって,その要件は,以下のとおりです。
- 破産者の行為であること
- その行為が偏頗行為であること
- 偏頗行為が破産手続開始の申立て後にされたものであること
- 偏頗行為を受けた債権者が,偏頗行為の際に,債務者が破産手続開始の申立てをしたことを知っていたこと
破産者の行為であること
破産者が支払不能または破産手続開始申立ての後にした偏頗行為の否認の対象とされる行為は,破産者の行為に限られます。第三者の行為では,この偏頗行為否認の対象になりません。
偏頗行為であること
支払不能または破産手続開始の申立て後にされた偏頗行為の否認の対象となるものは,「破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為」です。
ここでいう「行為」とは,偏頗行為のことを意味します。
では,偏頗行為とは何かと言うと,「既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為」のことです。
既存の債務とは,新しく負担したのではない債務という意味です。これについて担保供与や債務消滅行為をすることが偏頗行為ということになります。
担保供与行為の具体的な例は,たとえば,既存の債務を被担保債権として抵当権を設定することなどです。
債務消滅行為の具体的な例としてもっとも分かりやすいものは,弁済してしまうことです。こういう弁済を「偏頗弁済」と呼ぶことがあります。
支払不能または破産手続開始申立て後にされたものであること
単に偏頗行為をしただけでは,「破産者が支払不能等の後にした偏頗行為否認」の対象にはなりません。
「破産者が支払不能等の後にした偏頗行為否認」の対象となるのは,その偏頗行為が,破産者が支払不能になった後または破産手続開始の申立てがなされた後にされた場合にだけ対象となります。
なお,非義務的偏頗行為の場合には,支払不能前30日以内でも偏頗行為否認の対象となることがあります(破産法162条1項2号)。
偏頗行為を受けた債権者が悪意であること
破産法162条1項1号ただし書きには,「ただし,債権者が,その行為の当時,次のイ又はロに掲げる区分に応じ,それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。」と規定されています。
これはどういう意味かと言うと,支払不能後または破産手続開始の申立て後に偏頗行為がなされたとしても,その偏頗行為の相手方である債権者が,偏頗行為の当時,イまたはロに規定されている事実を知っていた場合しか,否認することができないという意味です。
つまり,「破産者が支払不能等の後にした偏頗行為否認」が成立するには,債権者がイまたはロの事実を知っていたことが必要となるということです。
法律的にいえば,債権者が悪意であることが必要となるということです。
なお,ここでいう「悪意」とは,一般的に用いられている悪い意思のような意味ではなく,単に事実を認識しているという意味です。
悪意の対象
では,イまたはロの事実とは何かというと,2つの場合に分けて規定されています。
まず,支払不能後の偏頗行為の場合には,債権者の悪意の対象は,破産者が支払不能であったことまたは支払停止していたことのいずれかが悪意の対象となります。
次に,破産手続開始の申立て後の偏頗行為の場合には,債権者の悪意の対象は,破産手続開始の申立てがあったことです。
つまり,支払不能後の偏頗行為を否認しようとするためには,その行為の当時,破産者が支払不能状態であったことまたは支払停止をしていたことを,債権者が知っていなければならないということです。
また,破産手続開始の申立て後の偏頗行為を否認しようとするためには,その行為の当時,破産手続開始の申立てがすでにされていたことを,債権者が知っていなければならないということです。
悪意の推定
破産法 第162条
- 第2項 前項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
- 第1号 債権者が前条第2項各号に掲げる者のいずれかである場合
- 第2号 前項第1号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合
前記のとおり、支払不能または破産手続開始の申立て後にされた偏頗行為の否認の要件として、債権者の悪意が必要となります。一定の場合、この債権者の悪意が推定されることがあります。
一定の債権者については、「支払不能であったこと又は支払の停止があったこと」や「破産手続開始の申立てがあったこと」を知っていたものとして扱ってしまうということです。
つまり,債権者の方で,自分は悪意ではなかったということを証明しない限り,悪意であったとされてしまうのです。
ではどのような場合に悪意が推定されてしまうのかというと,以下の場合です。
- 破産法161条2項各号に定められている場合(破産法162条2項1号)
- 破産者が支払不能または破産手続開始申立ての後にした偏頗行為が破産者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合(同項2号)
破産法161条2項各号に定められている場合の悪意の推定
破産法 第161条
- 第2項 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が同項第2号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
- 第1号 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者
- 第2号 破産者が法人である場合にその破産者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
イ 破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ロ 破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を子株式会社又は親法人及び子株式会社が有する場合における当該親法人
ハ 株式会社以外の法人が破産者である場合におけるイ又はロに掲げる者に準ずる者- 第3号 破産者の親族又は同居者
前記のとおり、「債権者が前条第2項各号に掲げる者のいずれかである場合」は、偏頗行為を受けた債権者が悪意であることが推定されます。
この「前条第2項各号」とは、破産法161条2項各号のことです。
破産者と破産法161条2号各号に定める関係にある者は,ぐるになっている可能性が高く,そうでなくても支払不能等の事実を知っている可能性が高いため,悪意と推定されるのです。
個人破産の場合であれば,破産法161条2項3号の場合,つまり,親族や同居者に偏頗行為をしてしまった場合,その親族や同居者は悪意と推定されることになります。
非義務的偏頗行為の場合の悪意の推定
前記のとおり、「前項第1号に掲げる行為が破産者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合」も、偏頗行為を受けた債権者の悪意が推定されます。
破産法162条2項2号の「前項第1号に掲げる行為が破産者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合」とは,偏頗行為をすることが,債務者の義務に基づくものでない場合です。
このような義務のない偏頗行為を「非義務的偏頗行為」といいます。
何らかの法的義務があるために弁済等をしてしまったというのならまだしも、何の法的義務もないのに担保の供与や弁済等をするというのは、偏頗行為を受けた債権者以外の他の債権者を害する度合いが高いことから、否認権行使を容易にできるように、悪意を推定するものとしているのです。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になりましたら幸いです。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
レ・ナシオン法律事務所
・相談無料
・全国対応・メール相談可・LINE相談可
・所在地:東京都渋谷区
弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・休日対応・メール相談可
・所在地:東京都台東区
弁護士法人ひばり法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
・全国対応・依頼後の出張可
・所在地:東京都墨田区
参考書籍
本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。