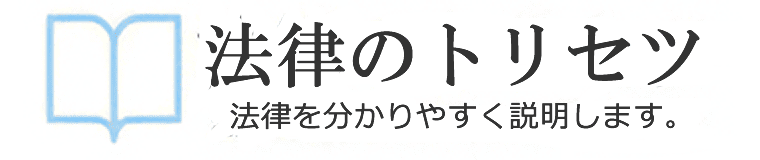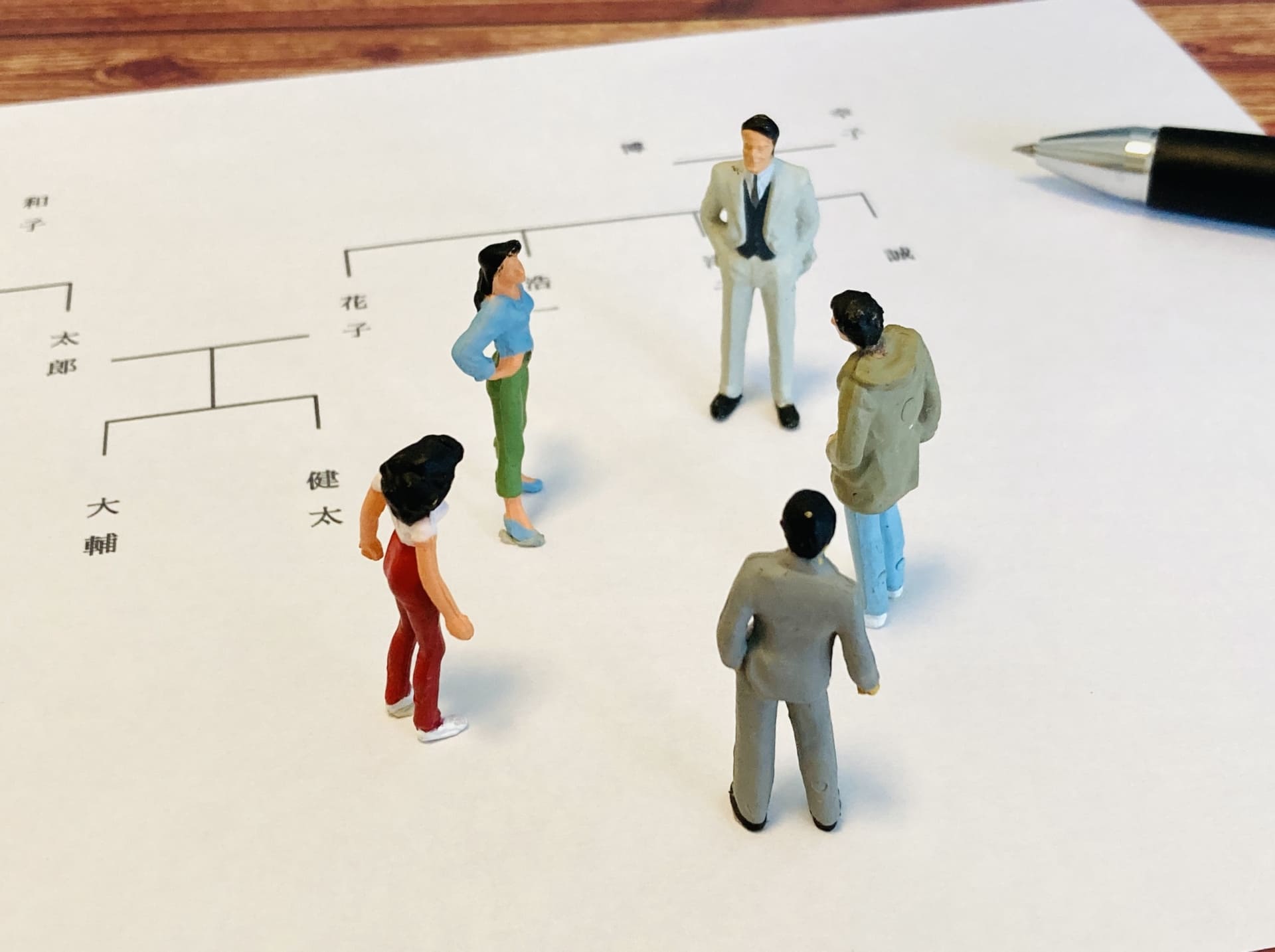この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
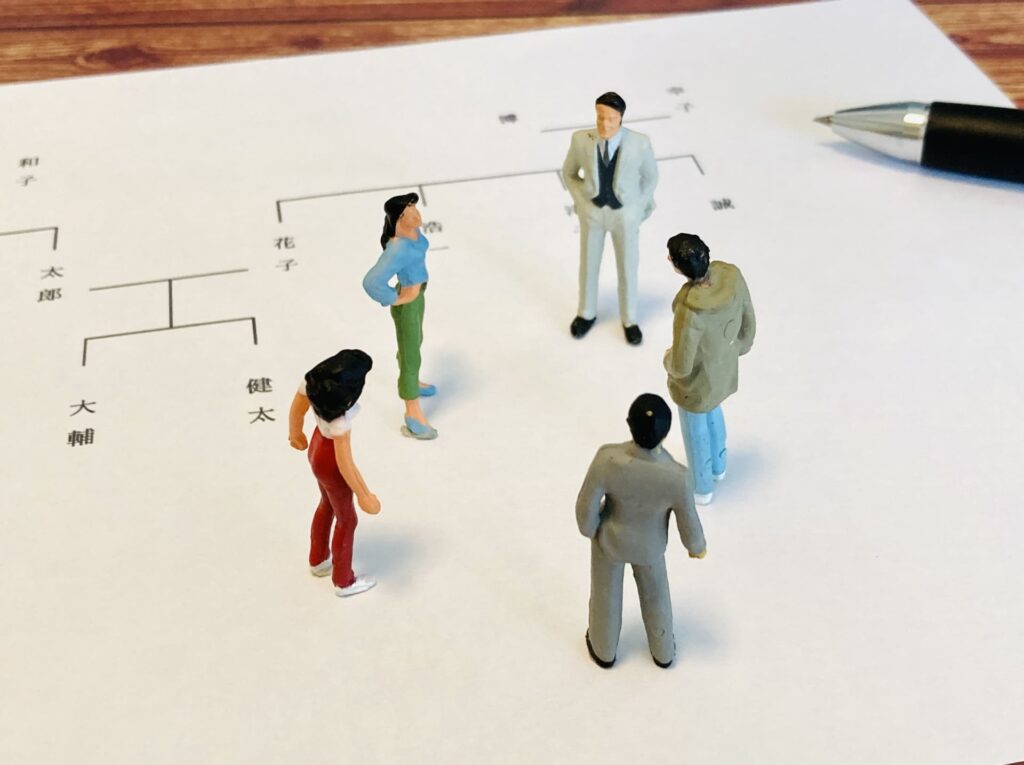
公務員の被相続人が死亡した場合に、遺族等に対して死亡退職手当が支払われることがあります。この死亡退職手当は、相続財産には含まれないと解するのが一般的です。
相続における死亡退職手当の取扱い
被相続人が生前,企業等で勤務していた場合に,被相続人の死亡によってその勤務先企業等から死亡退職金が支払われることがあります。
このことは,公務員の場合でも同様です。被相続人が公務員であったという場合は,被相続人が死亡すると,法令に基づいて死亡退職手当が支払われます。
もっとも,この死亡退職手当の金額がかなり大きな金額となることがあります。その場合,遺産相続において,この死亡退職手当をどのように取り扱うのかということが問題・紛争となることが少なくありません。
この点,一般の私企業の場合ですと,死亡退職金は,非常に例外的な場合を除いて,相続財産(遺産)には含まれず、受給者固有の財産となると考えるのが一般的です。
そこで,公務員の場合はどうかというと,これは,死亡退職金支給の根拠となる法令の規定の仕方にもよりますが,基本的には,私企業の場合と同様に,死亡退職金は受給者固有の財産となり,相続財産には含まれないと考えることになります。
被相続人が国家公務員の場合
被相続人が国家公務員である場合には,国家公務員退職手当法に基づいて,死亡退職手当が支払われることになります。
国家公務員退職手当法2条は,「遺族」に死亡退職手当を支給するものと規定しており(同法2条1項),しかも,法定相続人の範囲・順位とは異なる人をその「遺族」として定めています(同法2条の2)。
つまり,法は,国家公務員の死亡退職金の受給者は,法定相続人ではなく,被相続人の収入で生活していたと考えられる人であると定めています。
そうすると,死亡退職手当支給の法の趣旨は,法定相続人への分配ではなく,被相続人の収入で生活していた人の生活保障をすることにあると考えられます。
したがって,国家公務員の死亡退職手当は,法令によって定められた受給者の固有財産であって,相続財産(遺産)ではないと考えられているということです。
被相続人が地方公務員の場合
前記のとおり,被相続人が国家公務員である場合には,国家公務員退職手当法の解釈により相続財産ではないものと解されています。
他方,被相続人が地方公務員の場合には,地方自治法には具体的な定めがなく,退職手当等については条例によって決めなければならないと定めています(地方自治法204条3項)。
そうすると,被相続人が地方公務員である場合には,当該勤務先である地方自治体の条例の規定の仕方によって,その死亡退職手当が受給者の固有財産となるのか,それとも相続財産となるのかが異なってくるといえるでしょう。
もっとも,基本的に,地方公務員の退職手当については,国家公務員の退職手当に準ずるものとされており(地方公務員法24条3項)、前記国家公務員の場合と同様の取扱いがなされているのが通常です。
したがって、地方公務員の死亡退職手当も、受給者固有の財産となり、相続財産には含まれれないことになるのが通常でしょう。