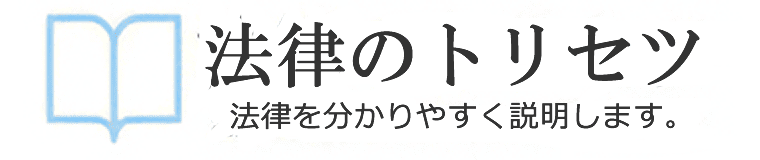本サイトの記事で取り扱った最高裁判例(昭和の判例)を年代順に取り上げています。
昭和20年代(20年~29年)
最高裁判所第二小法廷昭和27年4月25日判決(民集第6巻4号451頁)
裁判要旨
賃貸借は当時者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、民法第五四一条所定の催告を要せず、賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
最高裁判所第二小法廷昭和28年9月25日判決(民集第7巻9号979頁)
裁判要旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
最高裁判所第一小法廷昭和29年4月8日判決(民集 第8巻4号819頁)
裁判要旨
相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。
昭和30年代(30年~39年)
最高裁判所第三小法廷昭和30年5月10日判決(民集 第9巻6号657頁)
裁判要旨
一 民法第895条の規定は、受遺者が、相続人廃除の手続進行中、相続人から遺贈の目的物を譲り受けた第三者に対し、右目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
二 民法第1012条の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
三 禁治産者でない通常人が民法第976条による遺言をなす場合には、医師2人以上の立会その他同法第973条所定の方式を必要とするものではない。
最高裁判所第三小法廷昭和30年5月31日判決(民集 第9巻6号793頁)
裁判要旨
一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
二 遺産の分割に関しては、民法二五六条以下の規定が適用せられる。
最高裁判所第一小法廷昭和30年9月22日判決(民集 第9巻10号1294頁)
裁判要旨
賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または賃借物の転貸をした場合であつても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項による解除権を行使し得ないものと解すべきである。
最高裁判所第三小法廷昭和31年6月26日判決(民集 第10巻6号730頁)
裁判要旨
賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて 賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は民法第五四一条所定の催告を要せず賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
最高裁判所第三小法廷昭和31年9月18日判決(民集 第10巻9号1160頁)
裁判要旨
一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合には、右遺言は、特段の事情のないかぎり、なんらの効力を生じない。
二 家督相続人指定の遺言書中に、甲を家督相続人に指定する旨および乙等に対し財産の一部を遺贈する旨の記載があるにとどまり、他に遺言者に包括遺贈の意思があつたことを看取するに足る表示行為と目すべき事実上の記載がないときは、右遺言に包括遺贈の効力を認めることはできない。
三 相続人は、被相続人の遺言執行者を被告となし、遺言の無効を主張して、相続財産につき持分を有することの確認を求めることができる。
最高裁判所第一法廷昭和32年9月19日判決(民集 第11巻9号1574頁)
裁判要旨
一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。
二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)としてなした限定承認および債務弁済のための相続財産の競売申立につき、被相続人夫婦と表見相続人とは親子関係がなく、代理権のない者のなした不適法な行為であることを理由として、その効力を争うことはできない。
最高裁判所第二小法廷昭和33年6月20日判決(民集第12巻10号1585頁)
裁判要旨
売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする。
最高裁判所第三小法廷昭和33年8月5日判決(民集 第12巻12号1901頁)
裁判要旨
不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。
最高裁判所第三小法廷昭和35年6月28日判決(民集 第14巻8号1547頁)
裁判要旨
家屋の賃貸借において、賃借人が、一一ヶ月分の賃料を支払わず、また、それ以前においても屡々賃料の支払を遅滞したことがあつても、賃貸借を解除するには、他に特段の事情がないかぎり、民法第五四一条所定の催告を必要とする。
最高裁判所第二小法廷昭和36年4月28日判決(民集 第15巻4号1211頁)
裁判要旨
一 店舗用家屋の賃借人が賃貸人の承諾をえないでこれを転貸した場合に、右転貸が賃借人との共同経営契約に基くもので、転貸部分は家屋のごく一小部分に過ぎず、右共同経営のために据え付けられた機械は移動式で家屋の構造には殆ど影響なく、その取除きも容易であり、しかも転借人は右家屋に居住するものではないこと、また、家屋の所有権は賃貸人にあるが、その建築費用、増改築費用、修繕費等の大部分は賃借人が負担し、その上、賃貸人は多額の権利金を徴していること等の事情(原判決理由参照)があるときは、右転貸は賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情があるものであり、賃貸人のした契約解除は無効と解すべきである。
二 前項の場合において賃貸人は転借人に対し転借部分の明渡を求めることはできない。
最高裁判所第三小法廷昭和39年7月28日判決(民集第18巻6号1220頁)
裁判要旨
家屋の賃貸借において、催告期間内に延滞賃料が弁済されなかつた場合であつても、当該催告金額九六〇〇円のうち四八〇〇円はすでに適法に弁済供託がされており、その残額は、統制額超過部分を除けば、三〇〇〇円程度にすぎなかつたのみならず、賃借人は過去一八年間にわたり当該家屋を賃借居住し、右催告に至るまで、右延滞を除き、賃料を延滞したことがなく、その間、台風で右家屋が破損した際に賃借人の修繕要求にもかかわらず賃貸人側で修繕をしなかつたため、賃借人において二万九〇〇〇円を支出して屋根のふきかえをしたが、右修繕費については本訴提起に至るまでその償還を求めたことがなかつた等判示の事情があるときは、右賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除は信義則に反し許されないものと解すべきである。
最高裁判所第一小法廷昭和39年10月15日判決(民集 第18巻8号1671頁)
裁判要旨
一 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。
二 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。
最高裁判所大法廷昭和39年11月18日判決(民集 第18巻9号1868頁)
裁判要旨
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第491条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
昭和40年代(40年~49年)
最高裁判所第三小法廷昭和40年2月2日判決(民集 第19巻1号1頁)
裁判要旨
一 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。
二 前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。
最高裁判所第一小法廷昭和41年4月21日判決(民集 第20巻4号720頁)
裁判要旨
一 建物所有を目的とする土地の賃貸借中に、賃借人が賃貸人の承諾をえないで借地内の建物の増改築をするときは、賃貸人は催告を要しないで賃貸借を解除することができる旨の特約があるにかかわらず、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで増改築をした場合において、増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり、土地賃貸人に著しい影響を及ぼさないため、賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないときは、賃貸人は、前記特約に基づき、解除権を行使することは許されないものというべきである
二 前記の特約がある場合において、借地人がその居住用建物の一部の根太などを取りかえ、二階部分を拡張してアパート用居室として他人に賃貸するように改造をしたが住宅用普通建物として前後同一であるなど判示事実(判決理由参照)のもとでは、賃貸人が右特約に基づいてした解除権の行使はその効力を生じないと認めるのが相当である
最高裁判所第二小法廷昭和42年3月30日判決(集民 第86号773頁)
裁判要旨
原審認定の事実関係のもとでの長期にわたる賃料の不払は、それ自体賃貸借契約の継続を困難ならしめる背信行為にあたるから、催告なしに右契約の解除をすることができる。
最高裁判所第一小法廷昭和42年4月27日判決(民集 第21巻3号741頁)
裁判要旨
民法第九二一条第一号本文による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しなが相続財産を処分したことを要するものと解すべきである。
最高裁判所第二小法廷昭和43年5月31日判決(民集 第22巻5号1137頁)
裁判要旨
遺言執行者がある場合においては、特定不動産の受遺者から遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告適格を有する者は、遺言執行者にかぎられ、相続人はその適格を有しない。
最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日判決(民集 第22巻10号2257頁)
裁判要旨
一、債権者と債務者間に数口の貸金債権が存在し、弁済充当の順序について特約が存在する場合において、債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息を支払つたときは、右超過部分に対する弁済は、右特約の趣旨に従つて次順位に充当されるべき債務で有効に存在するものに充当されるものと解すべきである。
(反対意見がある)
二、裁判所は、利息制限法所定の制限をこえて任意に支払われた利息・損害金の存在することが弁論にあらわれ、これを確定した以上、当事者から右制限超過分を残存元本等に充当すべき旨の特別の申立ないし抗弁が提出されなくても、右弁済充当関係を判断することができる。
三、連帯債務者の一人が利息制限法所定の制限をこえる利息を支払つても、他の連帯債務者に対して右制限をこえる利息相当金を求償することはできない。
四、金銭を目的とする消費貸借上の利息について利息制限法第1条第1項の利率の制限をこえる約定があるが、遅延損害金の約定がない場合には、遅延損害金についても利息制限法第1条の制限額にまで減縮され、その限度で支払を求めうるにすぎない。
(反対意見がある)
最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決(民集 第22巻12号2526頁)
裁判要旨
利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払つた金額の返還を請求することができる。
最高裁判所第一小法廷昭和43年11月21日判決(民集 第22巻12号2741頁)
裁判要旨
家屋賃貸借契約において、一箇月分の賃料の遅滞を理由に催告なしで契約を解除することができる旨を定めた特約条項は、賃料の遅滞を理由に当該契約を解除するにあたり、催告をしなくても不合理とは認められない事情が存する場合には、催告なしで解除権を行使することが許される旨を定めた約定として有効と解するのが相当である。
最高裁判所第一小法廷昭和44年4月24日判決(民集 第23巻4号855頁)
裁判要旨
夫は宅地を賃貸し妻はその地上に建物を所有して同居生活をしていた夫婦の離婚に伴い、夫が妻へ借地権を譲渡した場合において、賃貸人は右同居生活および妻の建物所有を知つて夫に宅地を賃貸したものである等の判示事情があるときは、借地権の譲渡につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるというべきである。
最高裁判所第一小法廷昭和44年7月3日判決(民集 第23巻8号1297頁)
裁判要旨
甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。
最高裁判所第三小法廷昭和44年11月25日判決(民集 第23巻11号2137頁)
裁判要旨
債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。
最高裁判所第一小法廷昭和45年1月22日判決(民集 第24巻1号1頁)
裁判要旨
一、第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。
二、定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても、右仮処分は、甲に乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。
三、独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
最高裁判所第一小法廷昭和47年11月16日判決(民集 第26巻9号1603頁)
裁判要旨
一、賃貸借契約の当事者の一方が、右契約に基づき信義則上当事者に要求される義務に違反して、その信頼関係を破壊することにより、賃貸借関係の継続を著しく困離ならしめたときは、他方の当事者は、催告なくして賃貸借契約を解除することができる。
二、建物所有を目的とする土地賃貸借契約の賃借人が、借地の約半分にあたる空地をトラツク置場とし、無免許で自動車運送事業を営み、また、そのトラツクが完全に格納できずに公道上に約一メートルはみ出し公衆の通行を妨害している場合においても、格納を完全にするための工事が比較的容易であり、近隣や歩行者から苦情が出たこともない等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、賃貸人は、用法違反または信義則上の義務違反を理由として、賃貸借契約を解除することはできない。
最高裁判所第二小法廷昭和48年6月29日判決(民集 第27巻6号737頁)
裁判要旨
被保険者死亡の場合、保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う旨の保険約款の条項は、被保険者が死亡した場合において被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解すべきであり、右約款に基づき締結された保険契約は、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同様、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であると解するのが相当である。
最高裁判所第二小法廷昭和49年4月26日判決(民集 第28巻3号467頁)
裁判要旨
不動産の賃貸借において、賃借人が、約九年一〇か月の長期間賃料を支払わず、その間、当該不動産を自己の所有と主張して賃貸借関係の存在を否定し続けたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、催告を要せず賃貸借を解除することができる。
最高裁判所第一小法廷昭和49年9月2日判決(民集 第28巻6号1152頁)
裁判要旨
家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定のないかぎり、同時履行の関係に立たない。
最高裁判所第三小法廷昭和49年12月17日判決(民集 第28巻10号2040頁)
裁判要旨
一、不法行為により死亡した被害者の夫の妹であつても、この者が、跛行顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた等判示の事実関係があるときには、民法七一一条の類推適用により加害者に対し慰藉料を請求しうる。
二、不法行為による生命侵害があつた場合、民法七一一条所定以外の者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうる。
昭和50年代(50年~59年)
最高裁判所第一小法廷昭和50年2月20日判決(民集 第29巻2号99頁)
裁判要旨
賃貸人が、ショッピングセンターとするために一棟の建物を区分してこれを青物商果物商等の店舗として各賃貸するにあたり、ショッピングセンターの正常な運営維持のため賃貸契約に特約を付し、賃借人が、粗暴な言動を用いたり、濫りに他人と抗争したり、あるいは他人を煽動してショッピングセンターの秩序を棄したりすること等を禁止している場合において、賃借人が右禁止に違反して他の賃借人に迷惑をかける商売方法をとつて他の賃借人と争い、そのため賃貸人が、他の賃借人から苦情をいわれて困却し、そのことにつき賃借人に注意しても、賃借人がかえつて暴言を吐き賃貸人に暴行を加える等判示のような事情があるときは、賃貸借契約の基礎である信頼関係は破壊され、賃貸人は右契約を無催告で解除することができる。
最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決(民集 第30巻7号689頁)
裁判要旨
石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。
最高裁判所第二小法廷昭和51年7月19日判決(民集 第30巻7号706頁)
裁判要旨
相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである。
最高裁判所第二小法廷昭和51年8月30日判決(民集 第30巻7号768頁)
裁判要旨
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。
最高裁判所第一小法廷昭和51年12月17日判決(民集 第30巻11号1036頁)
裁判要旨
訴訟上の和解によつて、建物の賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは賃貸借契約は当然解除となる旨の定めがされた場合においても、賃料の延滞が一か月分であり、賃借人は、和解成立後賃貸人から賃料の受領を拒絶されるまで、約二年間右一か月分を除いては毎月の賃料を期日に支払つており、右延滞もなんらかの手違いによるものであつて賃借人がその当時これに気づいていなかつたなど判示の事情があり、賃貸借当事者間の信頼関係が賃貸借契約の当然解除を相当とする程度にまで破壊されたといえないときは、右和解条項に基づき賃貸借契約が当然に解除されたものとは認められない。
最高裁判所第二小法廷昭和52年9月19日判決(集民 第121号247頁)
裁判要旨
共同相続人が全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、分割債権であり、各相続人は相続分に応じて個々にこれを行使することができる。
最高裁判所大法廷昭和53年12月20日判決(民集 第32巻9号1674頁)
裁判要旨
共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。
最高裁判所第一小法廷昭和54年2月22日判決(集民 第126号129頁)
裁判要旨
共同相続人が全員の合意によつて遺産分割前の相続財産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、特別の事情のない限り、右相続財産に属さない分割債権であり、各共同相続人がその持分に応じて個々にこれを分割取得するものである。
最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決(民集 第34巻1号61頁)
裁判要旨
商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。
最高裁判所第二小法廷昭和56年4月3日判決(民集 第35巻3号431頁)
裁判要旨
相続に関する被相続人の遺言書又はこれについてされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が右方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、民法八九一条五号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、右相続人は同号所定の相続欠格者にあたらない。
(反対意見がある。)
最高裁判所第二小法廷昭和56年11月13日判決(民集 第35巻8号1251頁)
裁判要旨
終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合には、右遺言は、その後にされた協議離縁と抵触するものとして、民法1023条2項の規定により取り消されたものとみなすべきである。
昭和60年代(60年~63年)
最高裁判所第一小法廷昭和60年2月14日判決(集民 第144号109頁)
裁判要旨
債務者が債務整理の方法等について弁護士と相談し、右弁護士との間で破産申立の方針を決めたとしても、他に特段の事情のない限り、破産法74条1項にいう「支払ノ停止」があつたとはいえない。
最高裁判所第一小法廷昭和60年5月23日判決(民集 第39巻4号940頁)
裁判要旨
一 共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産にそれぞれ債権者を異にする後順位抵当権が設定されている場合において、乙不動産が先に競売されて一番抵当権者が弁済を受けたときは、乙不動産の後順位抵当権者は、物上保証人に移転した甲不動産に対する一番抵当権から甲不動産の後順位抵当権者に優先して弁済を受けることができる。
二 物上保証人が、その所有の不動産及び債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で、債権者の同意がない限り弁済等により取得する権利を行使しない旨の特約をしても、物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者は、物上保証人が弁済等により代位取得する抵当権から優先弁済を受ける権利を失わない。
三 債権の一部につき代位弁済がされた場合、右債権を被担保債権とする抵当権の実行による競落代金の配当については、代位弁済者は債権者に劣後する。
最高裁判所第一小法廷昭和61年3月20日判決(民集第41巻7号1445頁)
裁判要旨
一、民法九二一条三号にいう相続財産には相続債務も含まれる。
二、民法九二九条に違反する弁済による損害額は、限定承認に伴う清算手続が未だ完了していない場合であつても、同法九二七条一項所定の期間が満了したのちは、算定が不能であるとはいえない。
最高裁判所第一小法廷昭和62年10月8日判決(民集第41巻7号1445頁)
裁判要旨
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
平成・令和の判例
平成・令和の判例索引は、以下のページです。