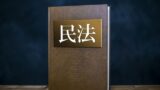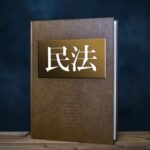この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
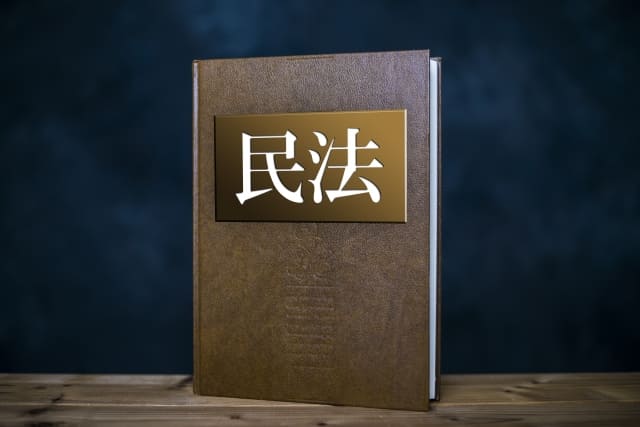
民法は私法の一般法です。民法をはじめとする私法には,権利能力平等の原則・所有権絶対の原則・私的自治の原則という基本原理・原則があります。
私法・民法の基本原理・原則
民法は,私法の一般法です。私法とは,私人相互間の法律関係を規律する法のことをいいますが,そのうちでも最も基本的かつ一般的な法律が民法です。
近代的な私法においては,以下の3つの原理・原則があると解されています。
- 権利能力平等の原則
- 所有権絶対の原則
- 私的自治の原則
民法は私法の一般法ですから,当然,民法においても,上記の基本原理・原則が妥当するということになります。
権利能力平等の原則
民法をはじめとする私法における基本原理の1つに,「権利能力平等の原則」があります。
権利能力平等の原則とは,すべての人は,その国籍・階級・職業・年齢・性別等にかかわらず,平等に権利能力を有するとする原則です。
権利能力とは,権利義務の帰属主体(主体または客体)となることのできる地位または資格のことです。
民法においても,「私権の享有は,出生に始まる。」(民法3条1項)と定められており,国籍・階級・職業・年齢・性別等にかかわらず,人として出生した時に権利能力を取得する(権利義務の帰属主体になりうる)ことを明らかにしています。
所有権絶対の原則
民法をはじめとする私法における基本原理の1つに,「所有権絶対の原則」があります。
所有権絶対の原則とは,所有権は国家の法にも優先する絶対不可侵の権利であるとする原則です。
日本国憲法29条においても財産権を基本的人権の1つとしており,民法206条でも,「所有者は,法令の制限内において,自由にその所有物の使用,収益及び処分をする権利を有する。」と定めています。
また,民法の解釈上,所有権を侵害された場合,その所有権者は,侵害者に対して,返還請求や妨害排除請求等の物権的請求権を行使できると解されていますが,この物権的請求権も所有権絶対の原則のあらわれの1つということができるでしょう。
ただし,所有権「絶対」とされていますが,公共の福祉に基づく制限を受けることはあります。民法206条が「法令の制限内において」所有権を認めているのは,公共の福祉による制限があることを示しています。
なお,「所有権」とされていますが,他の財産権も基本的には不可侵であるべきです。その意味では,所有権絶対の原則は,財産権全般に妥当する原則といえます。
私的自治の原則
民法をはじめとする私法における基本原理の1つに,「私的自治の原則」があります。
私的自治の原則とは,私法的法律関係については,国家権力の干渉を受けずに,各個人が自由意思に基づいて自律的に形成することができるとする原則のことをいいます。
ただし,私的自治の原則であっても,公共の福祉による制限は存在します。
私的自治の原則からは,さらに以下の原則が派生します。
法律行為事由の原則
私的自治の原則からは,「法律行為自由の原則」が導かれると解されています。
法律行為自由の原則とは,私法上の法律行為については,国家権力の干渉を受けずに,各個人が自由意思に基づいて自律的に行うことができるとする原則のことです。
法律行為の最も典型的なものは「契約」でしょう。法律行為自由の原則には,「契約自由の原則」も含まれています。
また,自身の財産を誰に承継させるかについては「遺言」を作成しておくことができます。この遺言も法律行為です。したがって,法律行為自由の原則には「遺言自由の原則」も含まれてきます。
つまり,個人は,国家権力の干渉を受けずに,自由に契約を締結したり遺言を作成するなどの法律行為ことができるということです。
過失責任の原則
私的自治の原則からは,さらに「過失責任の原則」が導かれると解されています。
過失責任の原則とは,個人の行為によって他者に損害を与えた場合であっても,その個人に故意または過失がない限りは,その損害について法的責任を負担しないとする原則のことをいいます。
前記のとおり,私的自治の原則は,個人の自由意思に基づく行為を尊重しようとする原則です。そうすると,個人の自由意思に基づかない行為にまで責任を負担させることは私的自治の趣旨に反します。
そこで,故意または過失がない場合,つまり,個人の自由意思が認められない場合には法的責任を負担させないとする過失責任の原則が導き出されるのです。
この過失責任の原則を,所有権絶対の原則・私的自治の原則と並ぶ私法の基本原理であるとする見解もあります。
民法においても,例えば,民法709条の不法行為責任が成立するためには,行為者の故意または過失が必要とされています。
基本原理・原則の制約
民法 第1条
- 第1項 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
- 第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
- 第3項 権利の濫用は、これを許さない。
前記のとおり,民法をはじめとする私法においては,権利能力平等・所有権絶対・私的自治という三大原理・原則が存在しています。
これらは,基本原理というくらいですから,当然,第一に守られなければならないものです。とはいえ,どのような場合でも必ず守られなければならないとすると,かえって他者の権利を不当に侵害する場合もあります。
そこで,民法では,権利能力平等・所有権絶対・私的自治の三大原理であっても,制約される場合があることを規定しています(民法1条)。
- 公共の福祉による制約
- 信義誠実の原則による制約
- 権利濫用の禁止による制約
これらに該当する場合には,権利能力平等・所有権絶対・私的自治の三大原理であっても制約されることがあり得るのです。
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である民法案内1(第2版)やダットサン民法1 総則・物権法(第4版)などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
新注釈民法(1) 総則(1):1~89条
著者:山野目章夫ほか 出版:有斐閣
民法全体の逐条解説書。全20巻!民法について知りたいことは、ほとんど解説されています。実務家向けの辞書です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎1 総則(第5版)
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。
スタートアップ民法・民法総則 (伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。