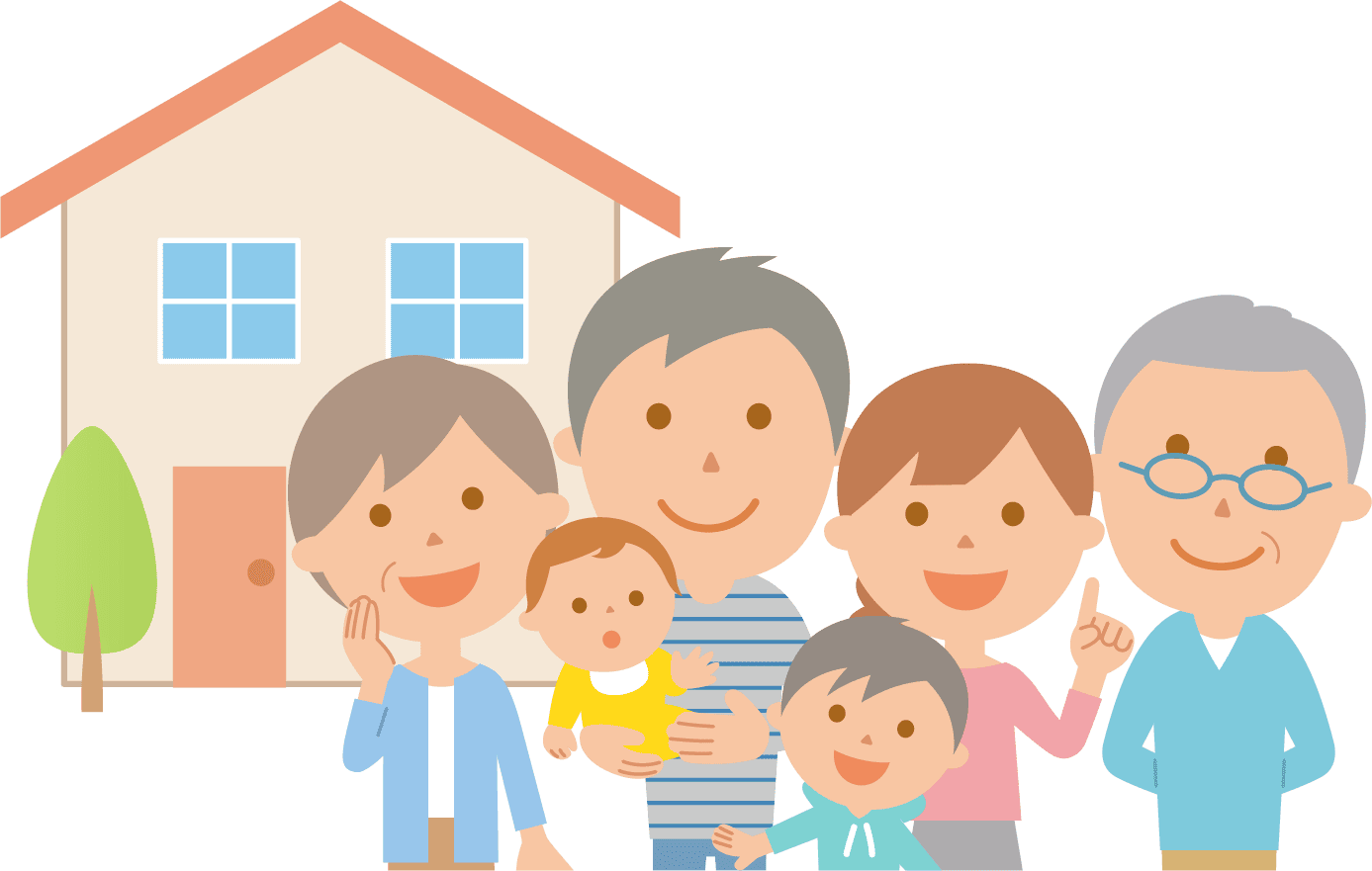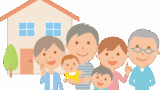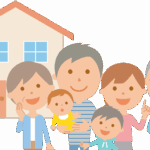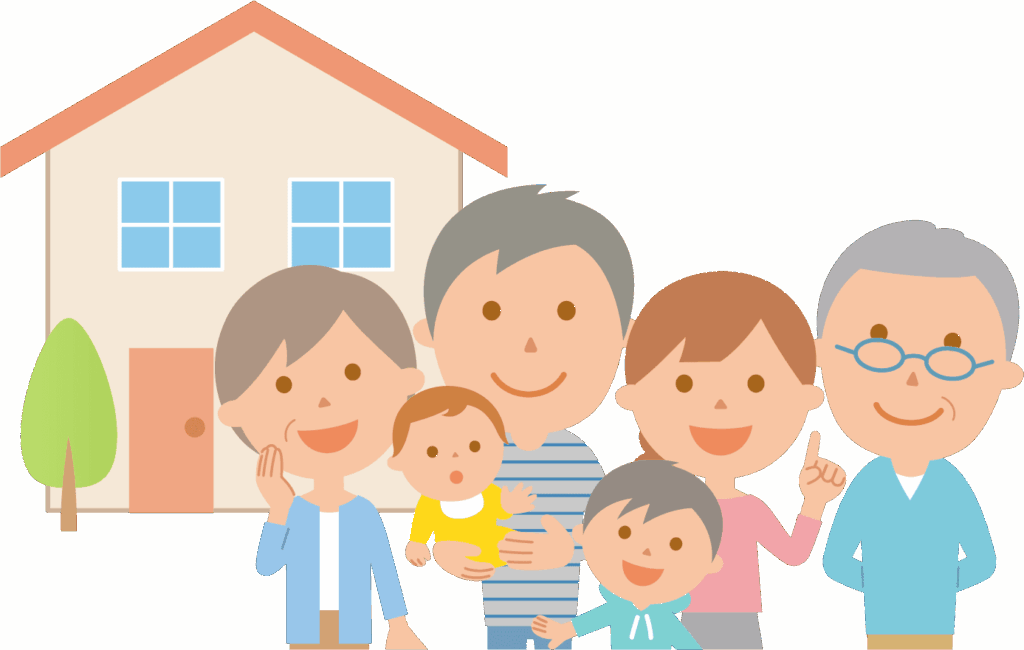
法律上の親族の遠近関係を表す単位のことを「親等(しんとう)」といいます。親等の数え方には独特なところがあります。縦に数えるというイメージです。
親等(しんとう)とは?
親族間の関係を表す言葉に「親等(しんとう)」という言葉があります。親等とは,親族関係の遠近を表す単位です。ある人とある人との間の,親族としての関係の距離を測る意味を持っています。
最も近い関係にある親族の場合は1親等,その次が2親等,以下3親等,4親等,5親等・・・と続いていきます。
民法上,親族とは6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことをいいます。親等は,この法律上の親族といえるかどうかを図る基準となります。
また,相続人が直系尊属である場合には,親等が近い順に相続人となる順位が決まりますから,親等は相続においても問題となってきます。
親等の数え方(親等の計算)
民法 第726条
第1項 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
第2項 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
親等は,上記のとおり,関係性の近い順に数えていくことになります。もっとも,一般的な感覚とは少し違う部分もあります。
例えば,兄弟姉妹は,一般的な感覚からすると一番近いので1親等と考えてしまいがちですが,実際には2親等です。
親等の数え方は,世代で数えます。いったん同一の始祖までさかのぼってから数えていくことになります。考え方としては,「横」に数えるのではなく「縦」に数えるというイメージ,と言った方が分かりやすいかもしれません。
血族の親等
血族は,血縁関係のある人のことです。
前記のとおり,親等は世代を「縦」に数えるイメージですから,1親等は,自分の1つ上の世代=父母と,自分の1つ下の世代=子ということになります。
2親等は,まず,自分の2つ上の世代=祖父母,自分の2つ下の世代=孫です。さらに,兄弟姉妹も2親等です。これは,1親等である父母の子と考えます。つまり,1回上にあがって,1回下にさがるというイメージです。2段階を経るので2親等ということになります。
3親等は,3つ上の世代=曾祖父母,3つ下の世代=曾孫のほか,2つ上の世代(祖父母)の1つ下の人=おじ・おばも3親等になります。また,2親等である兄弟姉妹の子=甥姪も3親等ということになります。
さらに,4つ上の世代=高祖父母,4つ下の世代=玄孫,3つ上の世代(曾祖父母の1つ下の人)=祖父母の兄弟姉妹,3親等であるおじ・おばの子=いとこ,兄弟姉妹の孫も4親等です。
さらに同じように,5親等,6親等と数えていくことになります。
姻族の親等
姻族は,配偶者の血族です。姻族の親等は,自分ではなく,自分の配偶者を基準として親等を数えます。数え方は,親族の場合と同様です。
例えば,配偶者の父母は1親等ですし,配偶者の祖父母は2親等です。
また,血族の配偶者は,その血族と同じ親等の姻族となります。例えば,自分の兄弟姉妹の配偶者は2親等の姻族となりますし,自分のいとこの配偶者は4親等の姻族となるということです。
配偶者の親等
自分の配偶者には親等はありません。いってみれば,0(ゼロ)親等というようなものになります。