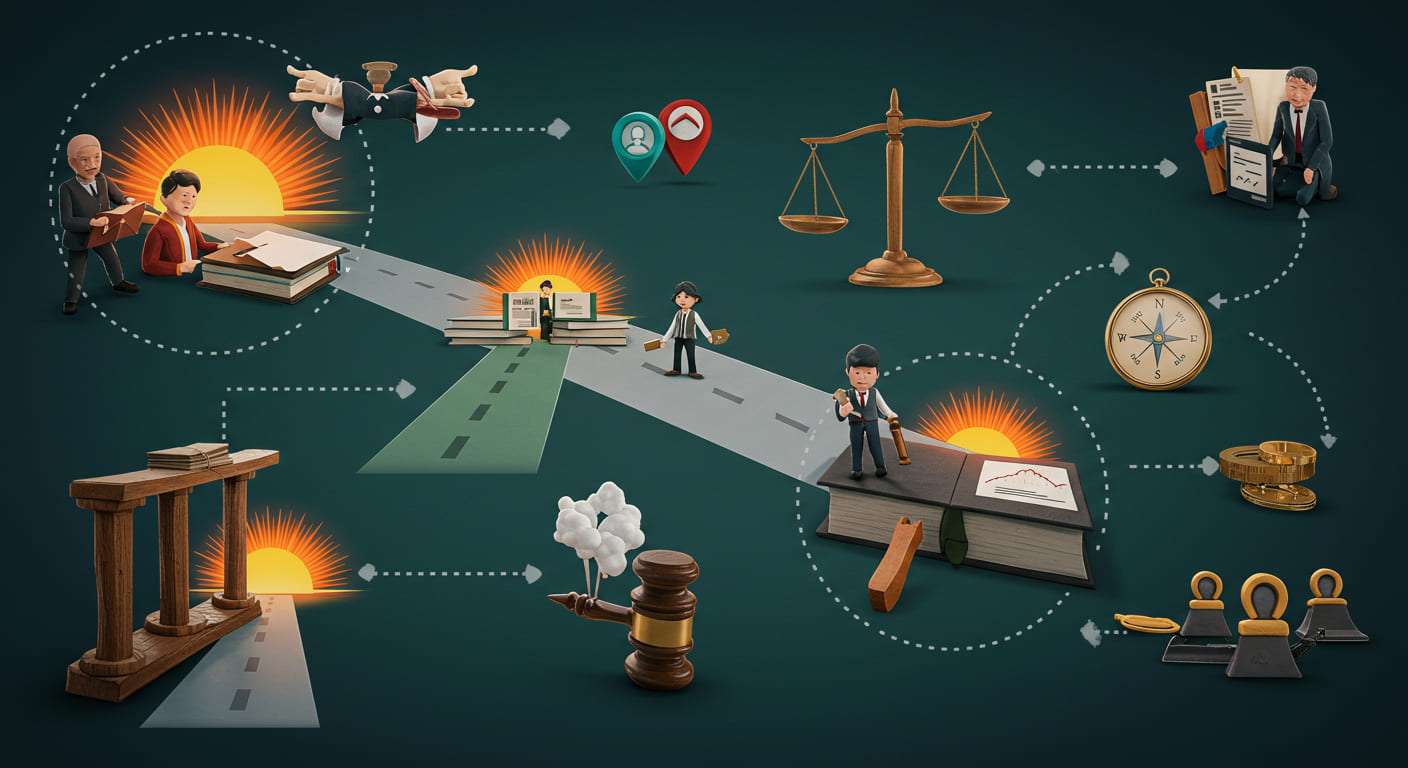同時死亡の推定とは,「数人の者が死亡した場合において,そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは,これらの者は,同時に死亡したものと推定する」という制度です(民法32条の2)。
死亡の先後が問題となるケース
例えば、事故などで、誰かが亡くなったのと同時に別の人も亡くなっていたという場面はあり得ます。このような場合に、どちらが先に亡くなったのかが問題となるケースがあります。具体的に言えば、相続の場面です。
相続には,同時存在の原則という原則があります。すなわち,被相続人が亡くなった時(相続開始時)に相続人が存在していなければ,その相続人について相続は発生しないという原則です。
したがって,被相続人が亡くなった時に,すでに相続人となるはずの人も亡くなっていれば,その相続人となるはずだった人については,遺産相続は発生しないことになります(ただし,代襲相続は発生する場合があります。)。
被相続人と相続人(となるべき人)とが同時に亡くなった場合も,被相続人の死亡の時点で,それと同時に相続人は死亡しているのですから,相続開始の時に相続人が存在していないということになります。
したがって,被相続人と相続人がまったく同時に死亡した場合には,やはりその相続人について相続は発生しないことになります。
しかし、前記の事故などの場合のように、被相続人と相続人のいずれが先に亡くなったのか、亡くなった順番が分からないというケースもあるでしょう。そのような場合に、死亡の先後をどう決めるのかが問題となってくるのです。
死亡の先後が分からない場合の同時死亡の推定
民法 第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
例えば,被相続人と相続人が一緒に乗っていた飛行機が墜落し,その事故で2人とも亡くなったものの,どちらが先に亡くなったのかが分からないというような場合が挙げられます。
このような被相続人と相続人の死亡の先後が不明であるという事態に備え,民法では「同時死亡の推定」という規定が用意されています。
同時死亡の推定とは,「数人の者が死亡した場合において,そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは,これらの者は,同時に死亡したものと推定する」という制度です(民法32条の2)。
上記の飛行機の事例でいえば,被相続人と相続人とは同時に死亡したものとして推定されます。そして,その結果,同時存在の原則により,その相続人については相続は発生しないということになります。
なお,この同時死亡はあくまで「推定」です。したがって,後にどちらが先に亡くなったかの先後関係を示す証拠がでてくれば,その推定を覆すことが可能です。