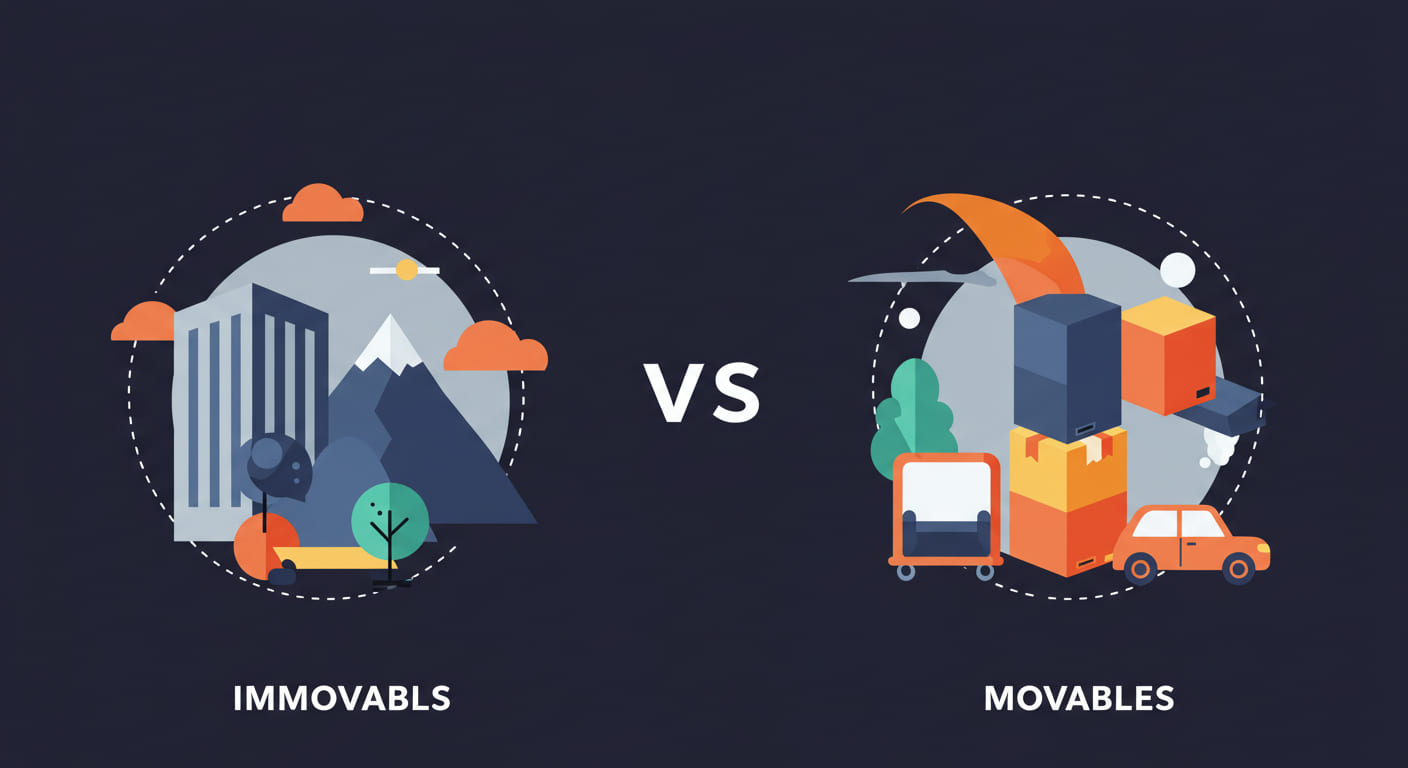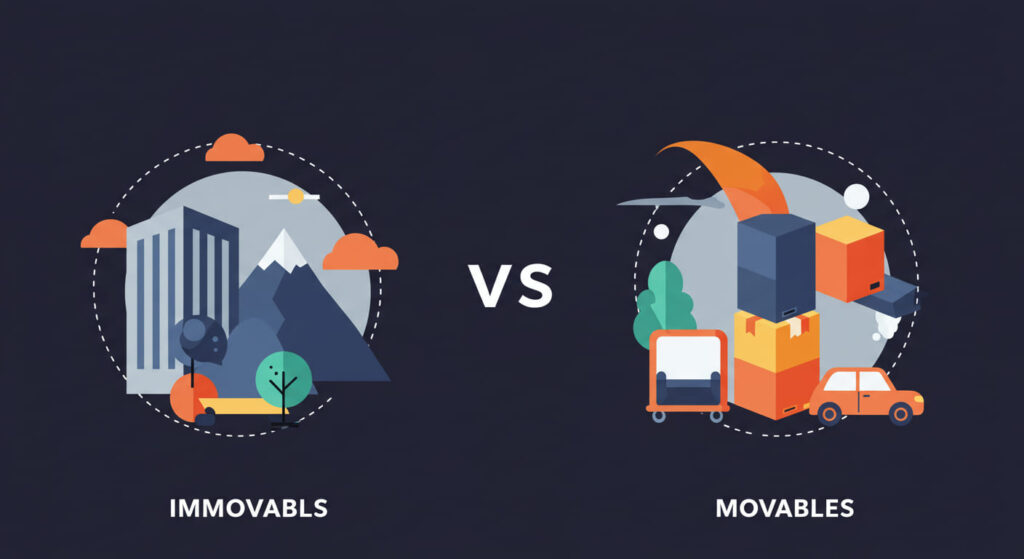
法律上の「物」は,動産と不動産に分けられます。このうち不動産とは,土地及びその定着物のことをいいます。
不動産とは
民法 第86条
第1項 土地及びその定着物は、不動産とする。
第2項 不動産以外の物は、すべて動産とする。
法律上の「物」は,動産と不動産に分けられます。このうち「不動産」とは,土地およびその定着物のことをいいます(民法86条1項)。
不動産に対比される概念として「動産」があります。不動産以外の物は,すべて動産として扱われます。法律上,不動産と動産は取扱いがまったく異なるので,不動産と動産の区別が重要となる場面もあります。
土地とは
前記の定義にもあるように,不動産といえば,最も代表的なものはやはり「土地」でしょう。
土地は,法的にいえば,一定範囲の地面に,その空中と地中とを包含させたもののことをいいます。もちろん,空中・地中といっても,その範囲は合理的な範囲に限られます。
土地の個数は,土地登記簿の表題部上の分界線によって定められます。つまり,帳簿上の区分がそのまま土地の個数の基準となるということです。そして,土地の個数は,1筆,2筆・・・というように,「筆」という単位で数えられます。
土地の定着物
前記のとおり,「土地の定着物」も不動産として扱われます。
この土地の定着物とは,土地に付着され,かつ,その土地に継続的に付着された状態で使用されるのがその物の取引上の性質であるものをいうとされています。
土地の定着物の代表的な例は,いうまでもなく「建物」です。我が国の民法では,土地と建物とは別個の不動産とされています。
したがって,ある土地上に建物がある場合,その土地と建物とは1個の不動産ではなく,別個の2つの不動産として取り扱われることになり,また,取引上も,別々に取引の対象とすることができます。
また,特別法により,立木も,土地定着物の1つとして,土地とは独立の不動産として扱われることがあります。
なお,土地上の物が,その土地の構造物となるのか,それとも建物のように土地定着物として独立の不動産として扱われるのか,あるいは,独立の動産となるのかの区別が問題となるという場合があります。
土地の構造物であれば,土地とともに取引の対象とすることができますが,独立の不動産であれば,別々に取引の対象としなければなりません。
また,動産であれば,それは土地と一体のものとして扱われる従物といえるのか,それともまったく独立の動産として扱われるのかなどが問題となってきます。