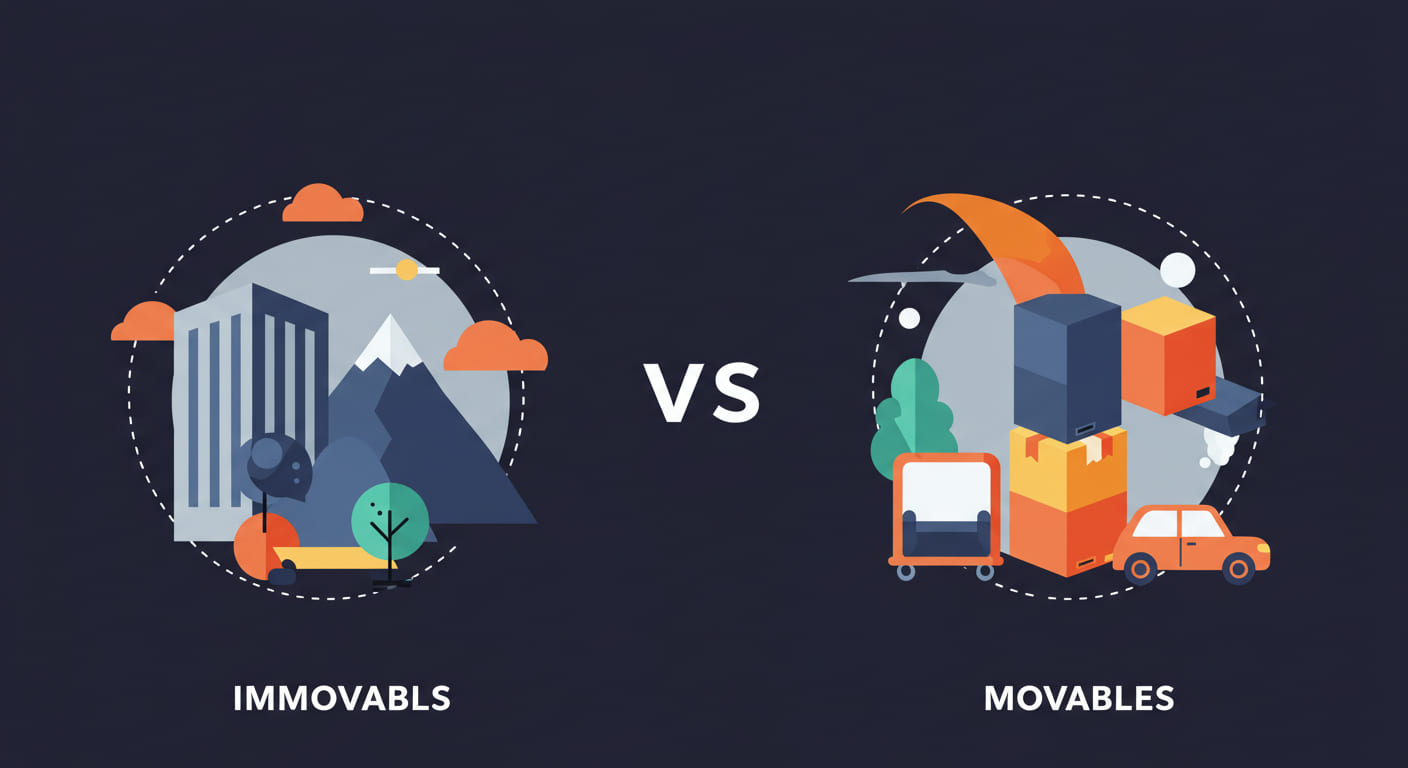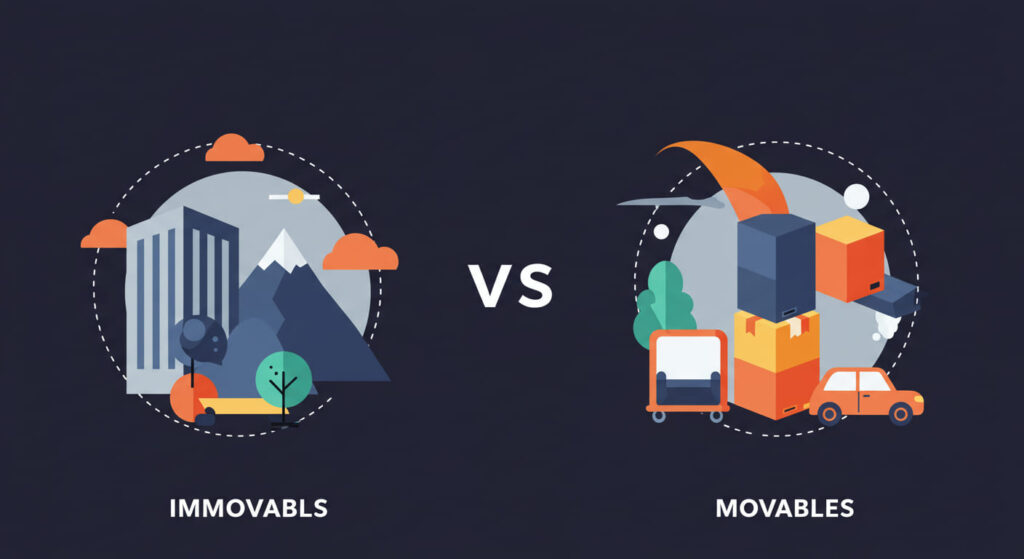
不動産とは土地とその定着物のことをいいますが,土地の定着物として代表的な物は,もちろん「建物」です。
不動産登記規則111条は、不動産登記の場面における建物について、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」と定義しており、建物の一般的定義を考える上で参考になります。
土地と建物
民法 第86条
第1項 土地及びその定着物は、不動産とする。
第2項 不動産以外の物は、すべて動産とする。
法律上の物である不動産とは,土地およびその定着物のことをいいます(民法86条1項)。この土地定着物の代表的な物が「建物」です。
諸外国では,建物を土地の構成部分として捉えていることが通常です。この場合,建物と土地は1個の不動産として扱われることになり,別個の不動産とはしていないということになります。
日本でも,民法起草の際には土地と建物とを別個のものとしては扱っていませんでした。しかし,土地と建物とは別個の物として取り扱うという日本の慣行や独特の取扱いがあったため,現在我が国では,土地と建物とは別個の不動産として扱われることになっています。
したがって,我が国では,土地上に建物が建っている場合であっても,土地と建物という2つの不動産があるという扱いになります。
建物とは
建物とは何かというと,なかなか難しいものがあります。
不動産登記規則111条は,「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」と定義しています。
上記規定は,不動産登記の場面における建物の定義であって,一般的な建物の定義として規定されているものではありませんが,建物とは何かという場合に参考となる定義です。
もっとも,建物といっても,何をもって建物というかは,その取引の内容によって異なってきます。したがって,物理的な構造のみをもって建物とは何かを判断するべきではありません。
たとえば,取引の対象となる建物が住宅であれば,単に屋根や壁があればいいというものではなく,天井や床も当然必要となってくるでしょうし,それが倉庫であれば,屋根さえあれば天井などは必要ないということになるかもしれません。
建物といえるかどうかは,結局,上記不動産登記法111条の定義を参考としつつも,その対象となっている物が,取引や利用目的からみて社会通念上建物といえるかどうかを,個別に判断するということになるでしょう。
建物の個数
前記のとおり,建物といえるかどうかは,社会通念によって個別に判断すべきことになります。
したがって,建物の個数についても,それが1つの建物といえるかどうかを社会通念によって個別に判断するということになるでしょう。
具体的には,その建造物の物理的な構造,種類,規模,用途等を総合的に考慮して,それに独立性や一体性があるかどうかを個別に判断することになります。
そして,その建造物が1つの建物といえる場合には,1棟の建物として登記されることになります。