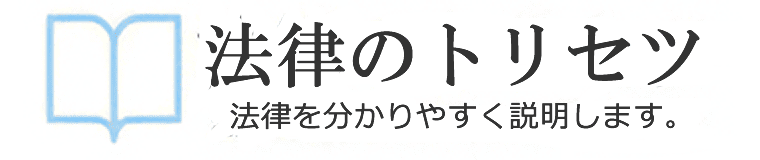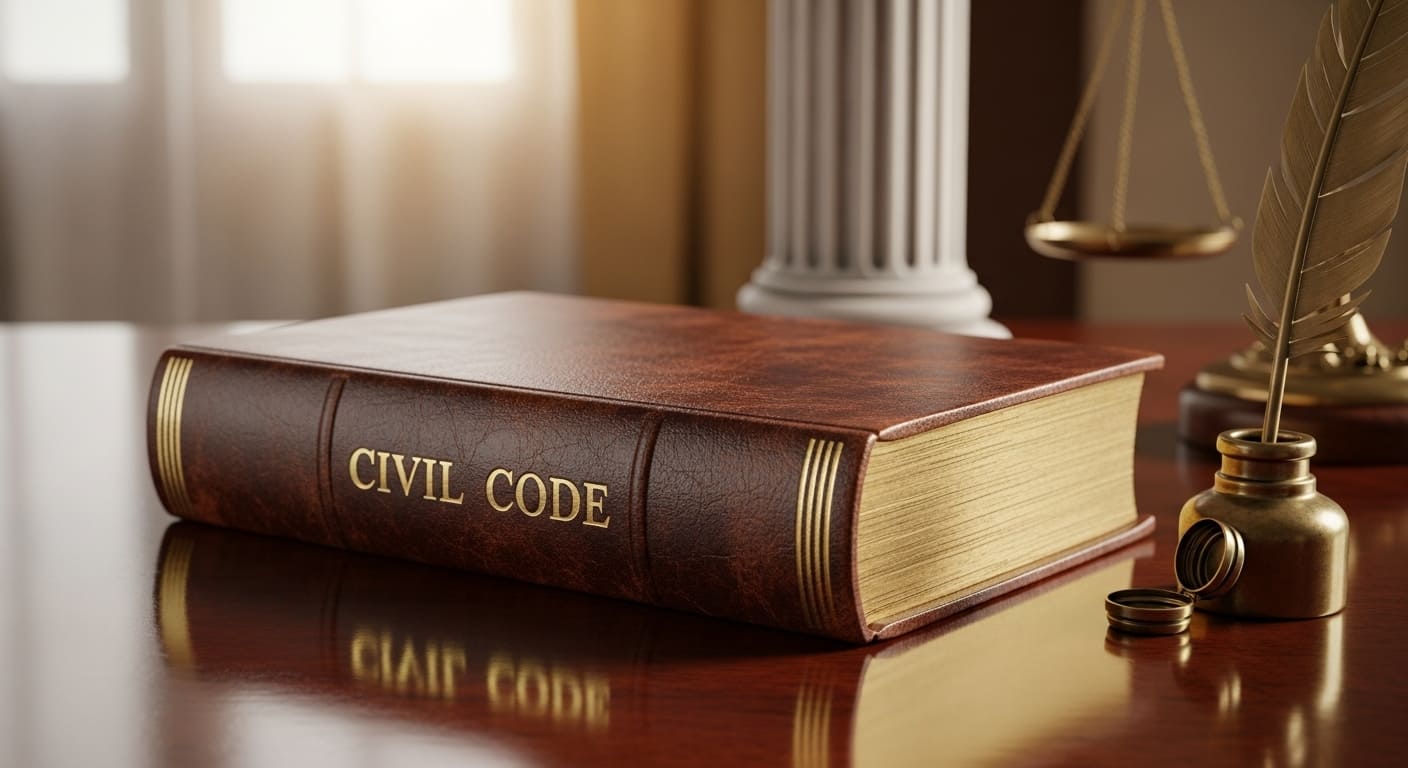この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
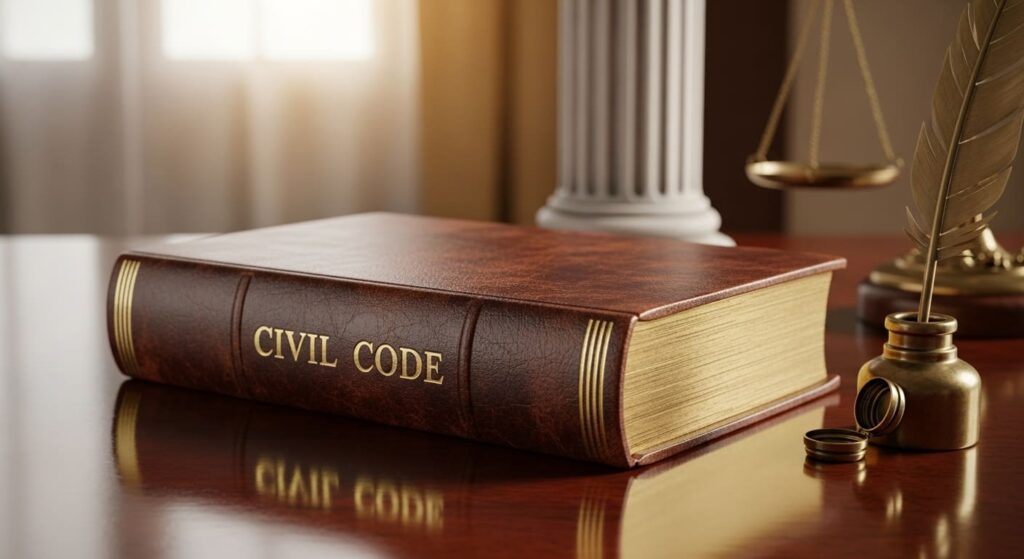
法律上の「物(もの)」とは有体物です。この法律上の「物」は、動産と不動産に分けられます。また、動産・不動産の別のほかにも、主物と従物、元物と果実などの分類がなされています。
法律上の「物(もの)」とは
民法 第85条
- この法律において「物」とは、有体物をいう。
法律上の「物」とは何かというと,民法では「『物』とは,有体物をいう」と規定されています(民法85条)。
有体物とは,空間の一部を占めるものです。具体的にいえば,固体・液体・気体のいずれかに属するものが,基本的な「物」ということになります。
もっとも,上記のもの以外であっても,法律上の排他的支配が可能なものであれば「有体物」に含まれると考えるのが一般的です。判例も同様に解していると考えられています(大判昭和12年6月29日)。
法律上の物の分類
法律上の物については,以下のような区別・分類がなされることがあります。
不動産・動産
民法 第86条
- 第1項 土地及びその定着物は、不動産とする。
- 第2項 不動産以外の物は、すべて動産とする。
法律上の物には,不動産と動産という区別があります。「不動産」とは土地とその定着物(典型的には建物)で,他方,「動産」とは不動産以外の物とされています(民法86条)。
主物・従物
民法 第87条
- 第1項 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
- 第2項 従物は、主物の処分に従う。
法律上の物には、主物と従物という区別もあります。
民法87条1項は、「物の所有者が,その物の常用に供するため,自己の所有する他の物をこれに附属させたときは,その附属させた物を従物とする」と規定しています。この規定の場合に,「従物」を附属させられた方の物を「主物」といいます。
例えば,建物の中に畳を取り付けた場合,建物が主物となり,畳は従物ということになります。
元物・果実(かじつ)
法律上の物には、元物と果実という区別もあります。
ある物から産出または発生する物があった場合,その産出・発生の元となる物を「元物」といい,元物から産出・発生した物を「果実」といいます。
果実は、物の用法に従い収取する産出物である「天然果実」と物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物である「法定果実」があります(民法88条)。
例えば,リンゴの木からリンゴの実が取れた場合には,そのリンゴの木は元物であり,リンゴの実は法律上の天然果実ということになります。
また,自分の所有する家を他人に貸し,家賃の支払いを受けた場合,家は元物であり,その家賃は法定果実となります。
学説上の分類
上記の3分類は民法に規定がありますが,学説上は,さらに以下のような分類がなされることもあります。
- 私法上取引できる物を融通物といい,取引できない物を不融通物といいます。
- 性質や価値を減ずることなく分割できる物を可分物といい,そうでない物を不可分物といいます。
- 物の用法に従って利用すると繰り返し利用できない物を消費物といい,繰り返し利用できる物を非消費物といいます。
- 一般の取引上,個性に着目して取引される物を不代替物といい,そうでない物を代替物といいます。
- 一般的にではなく個別具体的な取引において個性に着目して取引される物を特定物といい,そうでない物を不特定物といいます。