債務整理
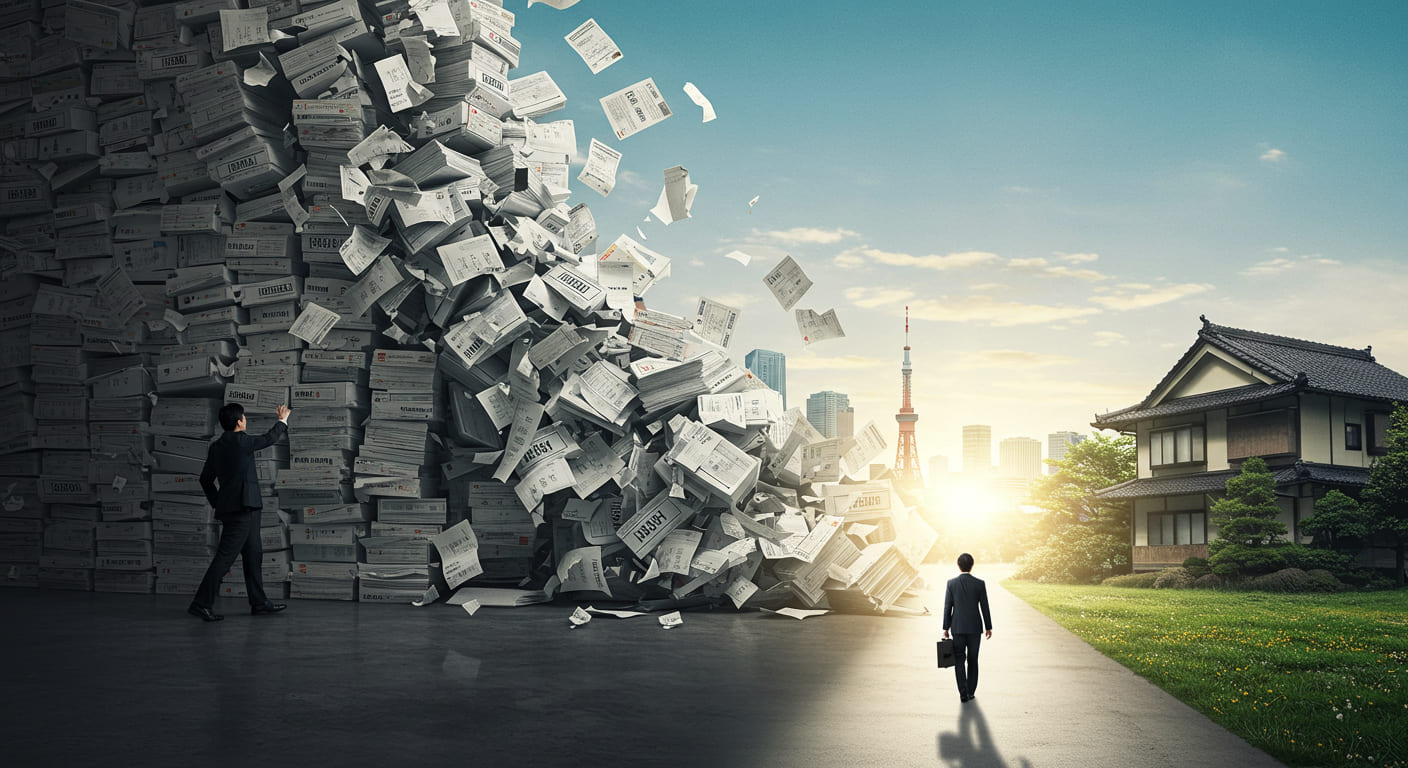 債務整理
債務整理 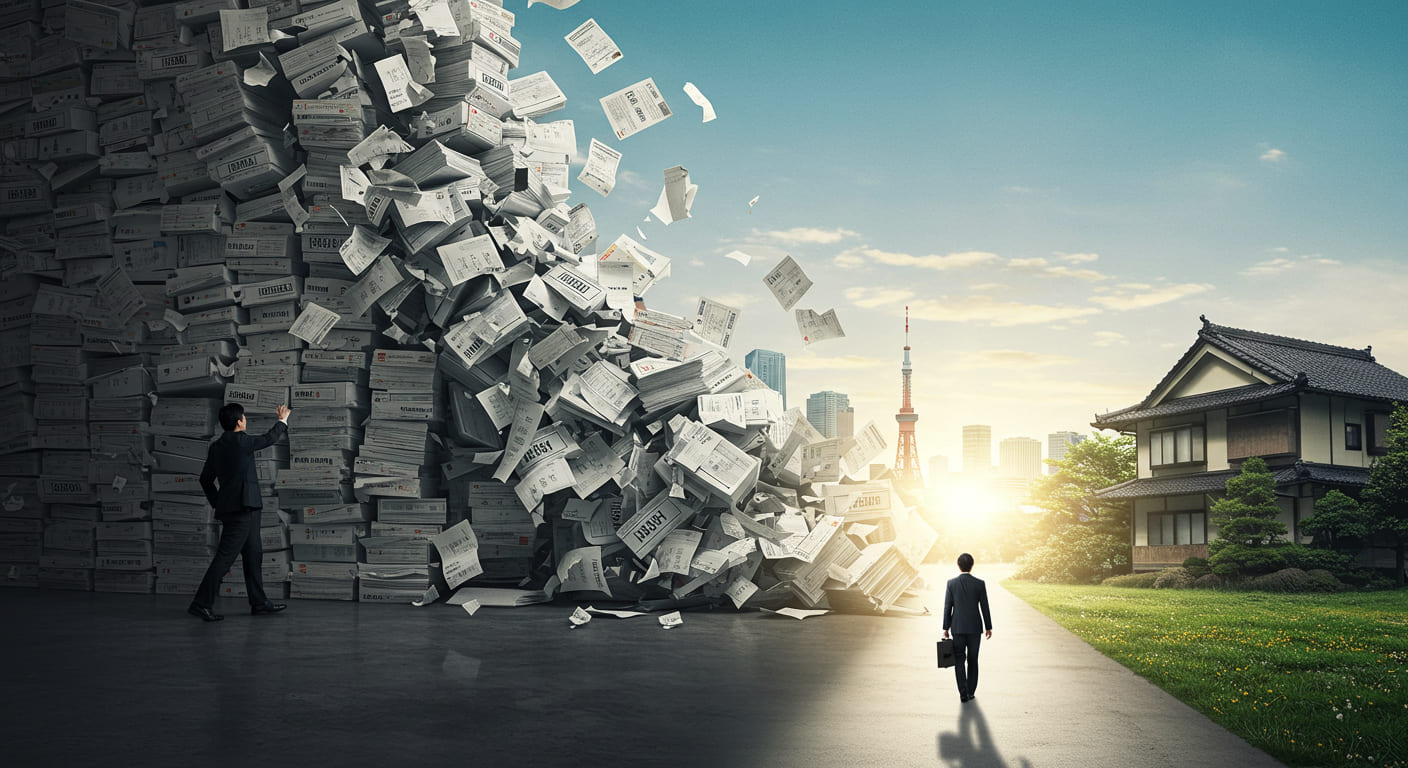 債務整理
債務整理  住宅資金特別条項の要件
住宅資金特別条項の要件  住宅資金特別条項の要件
住宅資金特別条項の要件  住宅資金特別条項の要件
住宅資金特別条項の要件  住宅資金特別条項の要件
住宅資金特別条項の要件  給与所得者等再生の効果
給与所得者等再生の効果  給与所得者等再生の効果
給与所得者等再生の効果  可処分所得要件
可処分所得要件  再生債権者一般の利益
再生債権者一般の利益  給与所得者等再生の要件
給与所得者等再生の要件  給与所得者等再生の要件
給与所得者等再生の要件