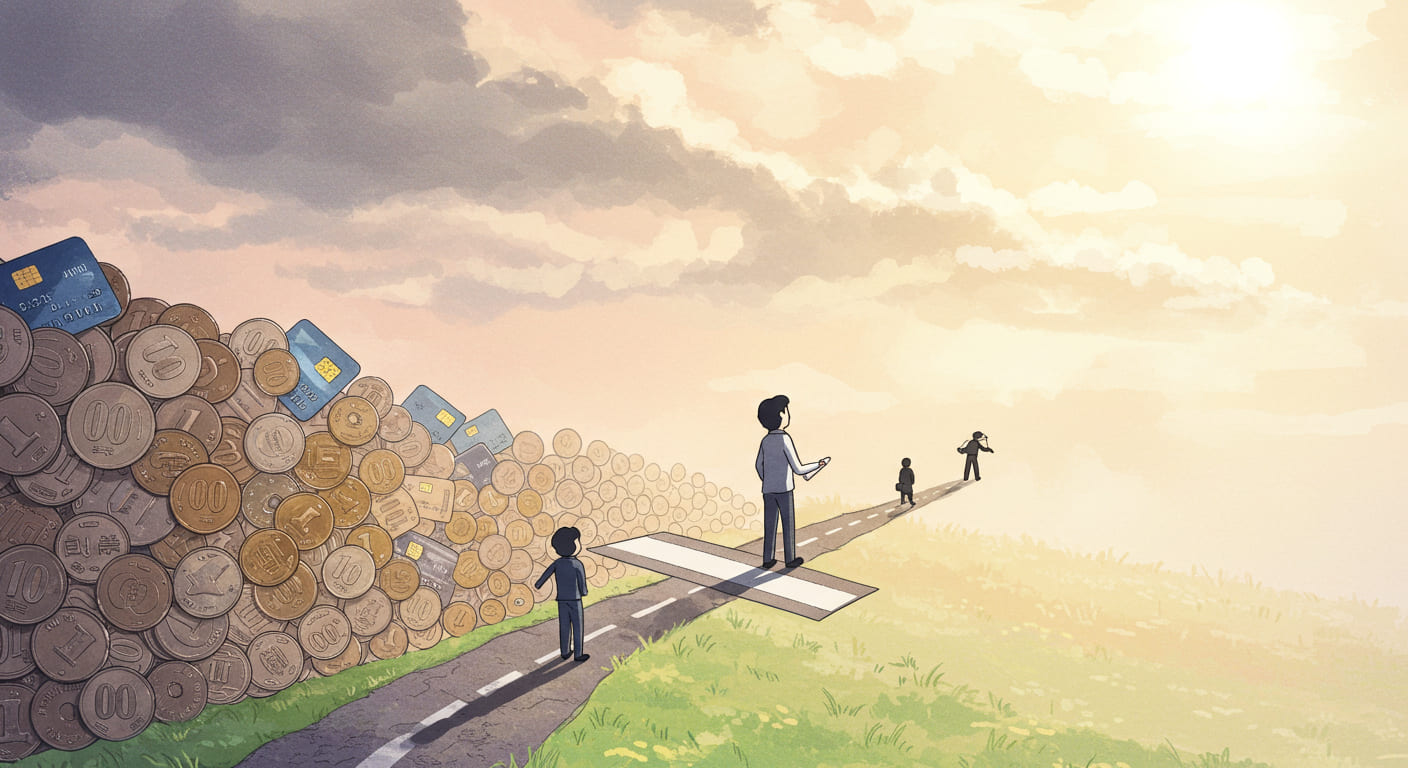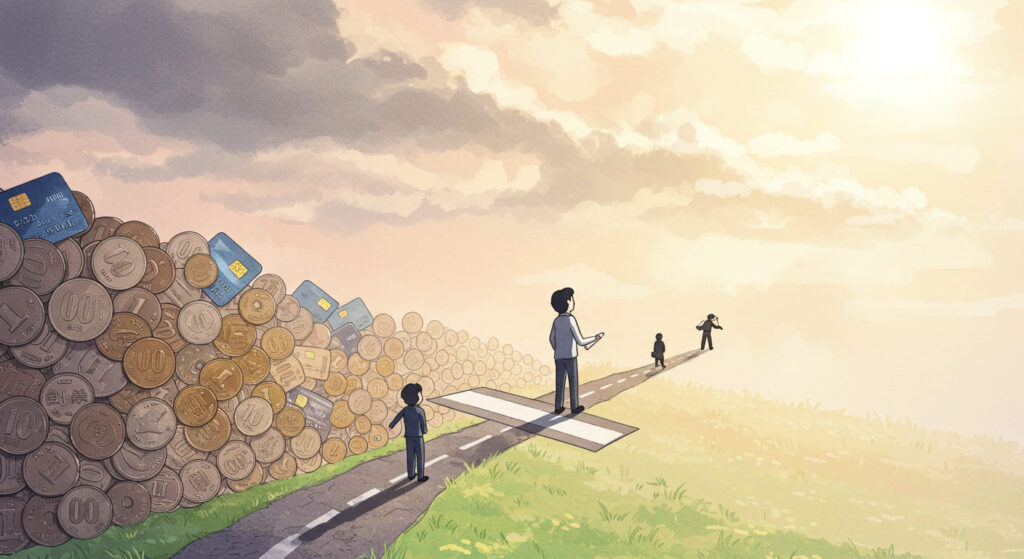
自己破産手続には,大きく分けると,破産管財人が選任され,その破産管財人が財産の調査・管理・換価処分や免責の調査を行う「管財手続(管財事件)」と,破産管財人が選任されず,破産手続開始と同時に破産手続が廃止により終了する「同時廃止手続」とがあります。このうち管財事件が原則とされています。
ただし,管財手続であっても,東京地裁や大阪地裁など多くの裁判所で,引継予納金の金額を低額化した少額管財の運用がとられています。
管財手続(管財事件)
破産手続とは,破産者の財産を換価処分して,債権者に公平に弁済・配当するという手続です。したがって,破産手続においては,破産者の財産を調査・管理・換価し,これを配当するという手続が必要となってきます。
もっとも,これら財産の管理業務等のすべてを裁判所が行うわけではありません。これらの手続をすべて裁判所が行うとなると,裁判所の負担が大きくなりすぎてしまいます。
そこで,これらの財産管理業務等は,裁判所が選任した破産管財人によって行われます。破産管財人に選任されるのは,破産管財人の登録をしている弁護士のみです。
いってみれば,破産管財人は裁判所から外部の弁護士に外注され,破産管財人に選任された弁護士が財産の調査・管理・換価・配当などを行うことになります。そして,裁判所は,基本的に,その破産管財人の活動を監督するということになります。
この破産管財人が選任される破産手続のことを「管財手続(管財事件)」と呼んでいます。破産手続の基本形態はこの管財手続ですので,自己破産の手続も,原則として,管財手続として進められていくことになります。
個人の自己破産における管財手続の場合は,後述するように,通常の管財事件よりも手続が簡易化され,裁判所に納める引継予納金の金額が少額で済む,少額管財という手続によって進められるのが通常です。
なお,個人の自己破産の管財事件は,異時廃止(破産手続開始決定後に,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められる場合になされる破産手続廃止の決定)によって終了することが多いことから,その場合には,異時廃止事件と呼ばれることもあります。
同時廃止手続(同時廃止事件)
前記のとおり,破産手続は,管財事件を原則としています。
しかし,破産手続の目的は,破産者の財産を換価処分して債権者に弁済・配当することです。
したがって,そもそも換価処分すべき財産がないことが明らかな場合にまで,わざわざ破産管財人を選任して手続を進めていくというのも,(破産管財人にも報酬を支払わなければなりませんので)コスト的に無意味となってしまいます。
そこで,破産法では,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」は,破産手続開始決定と同時に,破産手続廃止決定がなされるとされています。
廃止の決定を破産手続の開始と同時に行うことから,「同時廃止」と呼ばれています。
破産手続の廃止とは,破産者の財産を換価処分しても,破産手続の費用すら支払えない場合に,破産手続を終了させることをいいます。
つまり,同時廃止とは,破産手続を開始する段階から,すでに破産手続の費用を支払うだけの財産もないことが明らかであるときは,コストが無駄になるおそれがあるので,破産手続開始と同時に手続を廃止にしてしまうということです。
同時廃止事件では,破産手続の開始と同時に破産手続は終了してしまうのですから,当然,破産管財人が選ばれることもありません。極めて簡易に破産手続が終了することになるのです。
法律的にみれば,この同時廃止は破産手続の例外です。もっとも,個人の自己破産の場合には,この同時廃止事件が少なくありません。
東京地方裁判所でも,個人の自己破産事件の場合,管財(少額管財)事件が3~4割程度,同時廃止事件が6~7割程度のようです。
少額管財の運用
東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとして,多くの裁判所では,少額管財という運用がなされています。
管財事件は,破産管財人に報酬を支払うことから,裁判所に納める引継予納金の金額が高額となることがあります。
しかし,特に個人の自己破産ですと,そのような高額の予納金を支払うことすらできないという場合も少なくありません。
とはいえ,あくまで同時廃止事件は例外ですから,すべての事件を同時廃止とすることはできません。
また,破産管財人が選任されない同時廃止事件においては,同時廃止とするために虚偽申告等がなされるという問題も頻発していました。
そこで,予納金を少額におさえながらも,管財事件として破産管財人による調査をする「少額管財」という運用がなされるようになりました。
現在,東京地方裁判所や大阪地方裁判所などでは,個人の自己破産の管財事件のほとんどが,この少額管財によって行われています。おそらく,少額管財を行っている裁判所は,どこもそうだと思います。
ただし,この少額管財は,あくまで各裁判所の「運用」です。少額管財という法律上の制度があるわけではありません。したがって,地域によっては,少額管財の運用をしていない裁判所もありますので,注意が必要です。