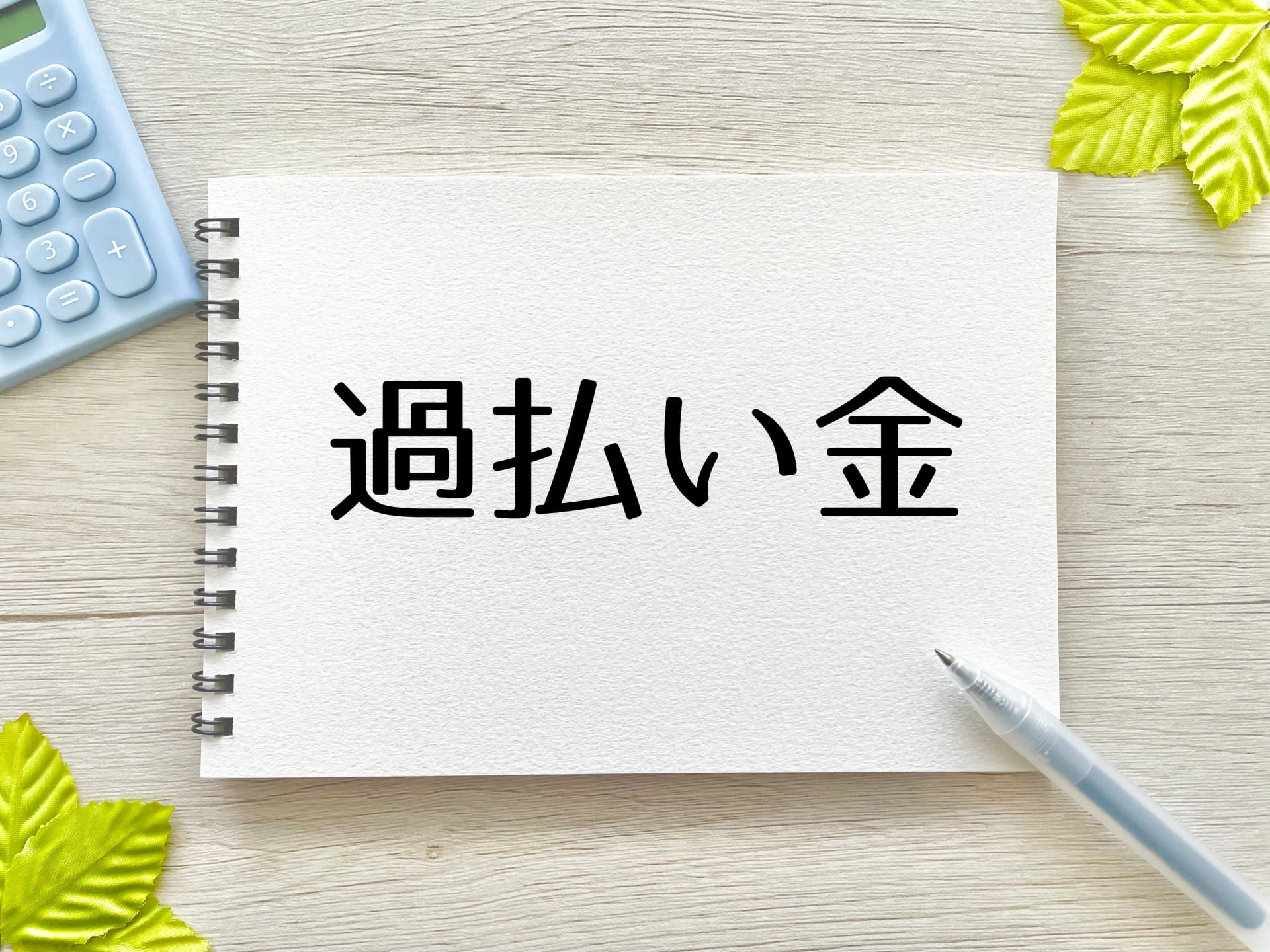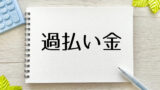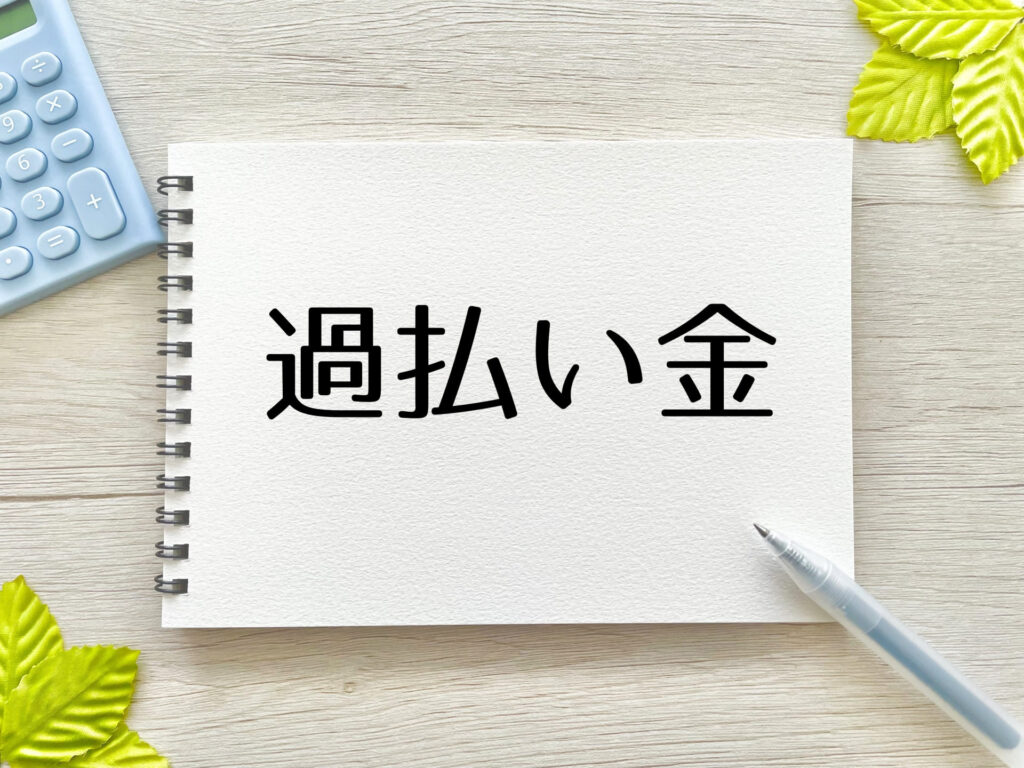
過払金返還請求権には商事消滅時効は適用されず、その消滅時効期間は10年であるということを明らかにした最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決(最一小判昭和55年1月24日)があります。
過払い金返還請求権の消滅時効期間
過払金返還請求権の法的性質は、不当利得返還請求権です(民法703条)。この不当利得返還請求権も債権ですから、消滅時効の対象になります(民法166条1項)。
消滅時効とは何かというと、上記のとおり、ある一定の期間が経過した場合、その権利行使がなされなかったという継続した事実状態を尊重して、その行使されなかった権利を消滅させてしまうという制度です。
過払い金返還請求権も時効消滅するということは、つまり、ある一定期間が経過すると、過払い金が発生していたとしても、それの返還を請求できなくなってしまうということです。
この過払金返還請求権の消滅時効という問題は、過払い金返還請求における重要な争点の1つですが、まず第一に問題となってくるのは、この過払金返還請求権の消滅時効が完成する時効期間は何年なのかという点です。
現在における過払金返還請求権の消滅時効期間の考え方
過払金返還請求権の消滅時効の期間は、民法166条1項を適用するというのが、現在の考え方です。
具体的には、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間のいずれか早い方となるというのが、現在では当たり前になっています。
過払金返還請求権の消滅時効期間に関するかつての論争
もっとも、かつては、過払い金返還請求権の消滅時効期間については、民法の規定を適用すべきか、あるいは、商事消滅時効を適用すべきかという争いがありました。
民法の規定を適用すべきとする考え方とは、過払い金返還請求権も不当利得返還請求権という一般的な債権であるから、通常の一般債権と同様、その消滅時効期間は、民法の規定を適用すべきという考え方です。
他方、商事消滅時効を適用すべきとする考え方は、過払い金返還請求権は(基本的に)貸金業者という商人との取引であるから一般債権ではなく商事債権であり、商事消滅時効が適用されるので、その消滅時効期間は短期消滅時効として5年とすべきであるというものです。
なお、さらに上記商事債権とする見解には、仮に商事債権そのものとはいえないとしても、それに準ずる債権であるから、やはり商事消滅時効が類推適用(または準用)されるという見解もあります。
言うまでもありませんが、消滅時効期間を長く捉える方が消費者側に有利であり、短く捉える方が貸金業者側に有利となります。
仮に短期消滅時効が適用または類推適用されることになるとすると、過払金返還請求権の消滅時効期間は、権利を行使できる時から5年間ということなっていたでしょう。
この争点に決着をつけて、過払金返還請求権の消滅時効期間は10年である(民法の規定が適用される)とした最高裁判例が、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決です。
この判決当時は、民法改正前ですから、民法上の債権の消滅時効には、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間という規定はなく、権利を行使できる時から10年間の時効期間のみでした。
最一小判昭和55年1月24日の解説
最一小判昭和55年1月24日は、以下のとおり判示しています。
商法522条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ、利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によつて発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によつて生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年と解するのが相当である。
引用元:裁判所サイト
前記のとおり、かつては、過払金返還請求権の消滅時効期間について、民法を適用するか商事消滅時効を適用するかという争点がありました。
消滅時効期間を長く考えた方が借主(消費者)側にとっては有利です。
そのため、民法を適用すべきとする説は消費者側から、商事消滅時効を適用すべきとする説(または類推・準用説)は貸金業者側から主張されていました。
最一小判昭和55年1月24日は、過払い金返還請求権が不当利得返還請求権であることを強調し、商事債権でもないしそれに準ずるものともいえないから、一般債権として扱い、その消滅時効期間は10年であると判示しました。
なお、10年としているのは、この判決当時、まだ民法が改正されておらず、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間という規定が加えられていなかったからです。
この判例を現在の民法166条1項に当てはめると、過払金返還請求権の消滅時効期間は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間のいずれか早い方となります。
実務に与えた影響
現在では、過払い金返還請求権の消滅時効期間には、商事消滅時効ではなく、民法の規定が適用されるということで、実務上争いはないといってよいでしょう。
また、この判決は、すでに完済している貸金業者が相手であっても過払い金返還請求が可能であるということを示唆している判決ともいえます。
仮に消滅時効期間には商事消滅時効5年間が適用されるとなっていたら、過払金返還請求できる人がかなり減っていたかもしれません。
その意味で、最一小判昭和55年1月24日が実務に与えた影響は、非常に大きいと言えます。