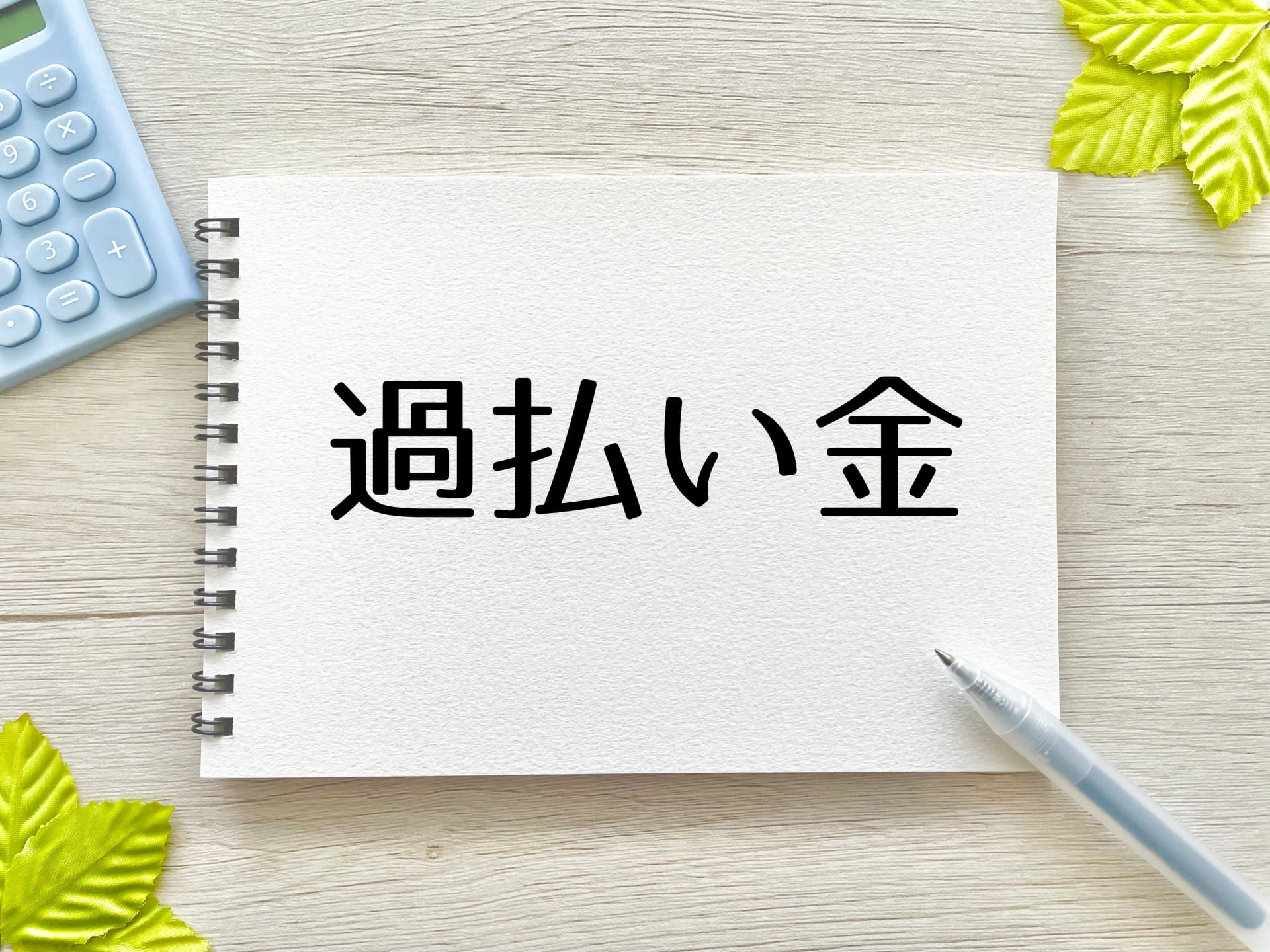過払金返還請求において最も争いの激しい争点は、取引の個数です。複数の取引がある場合に、一方の取引で生じた過払金を別の取引における貸付金に充当できるのか、または、いったん完済した後に再度借入れをした場合、その複数の取引を一連のものとして扱ってよいかという問題です。
取引の個数に関する記事一覧
取引の個数に関する記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
取引の個数の概要
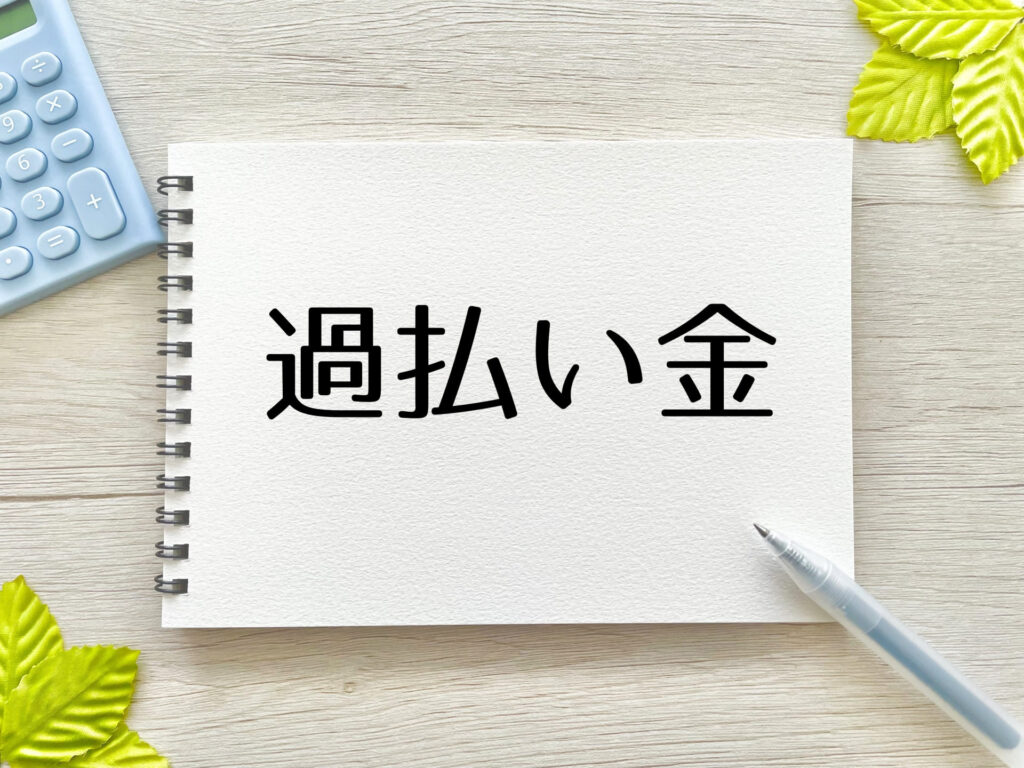
前記のとおり、過払金返還請求において最も争いの激しい争点は、取引の個数です。
この取引の個数の問題には、以下の2つの類型があります。
- 取引分断型(取引中断型):いったん完済した後に再度借入れをしたことによって、取引が複数になる場合
- 取引併存型:複数の取引が併存している場合
取引分断型の場合は、分断前の取引において発生した過払金を分断後の取引における借入金債務に充当して、複数の取引を1個の一連取引として引き直し計算できるのかが問題となります。この計算を一連計算(一連充当計算)と呼んでいます。
取引併存型の場合は、一方の取引で発生した過払金を別の取引の借入金債務に充当することができるかが問題となります。この計算を横飛ばし計算と呼んでいます。
弁護士の探し方
「過払金返還請求をしたいけれど、どの弁護士を選べばいいのか分からない」
という方は少なくないでしょう。
現在では、多くの法律事務所が債務整理・過払金返還請求を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、過払金返還請求を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理・過払金返還請求の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、過払金返還請求の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
参考書籍
本サイトでも過払金返還請求について解説していますが、より深く知りたい方のために、過払金返還請求の参考書籍を紹介します。
編集:名古屋消費者信用問題研究会 出版:民事法研究会
過払金返還請求の教科書のような本。やや古いので判例や論点のアップデートは必要ですが、過払金返還請求を知るためには、よい本です。
監修:名古屋消費者信用問題研究会 出版:民事法研究会
タイトルどおり、過払金返還請求に関するほとんどの論点を網羅している実務の解説書。ただし、最新の判例などのアップデートは必要です。
著者:輿石武裕 出版:日本加除出版
簡易裁判所裁判官による過払金返還請求の裁判例解説書。最高裁判例だけでなく下級審裁判例も多く掲載。ただし、こちらも古い本なのでアップデートが必要です。
編集:岡口基一 出版:ぎょうせい
岡口元裁判官による実務家に人気の要件事実の解説書。第4巻には、過払金返還請求の要件事実についても解説されています。