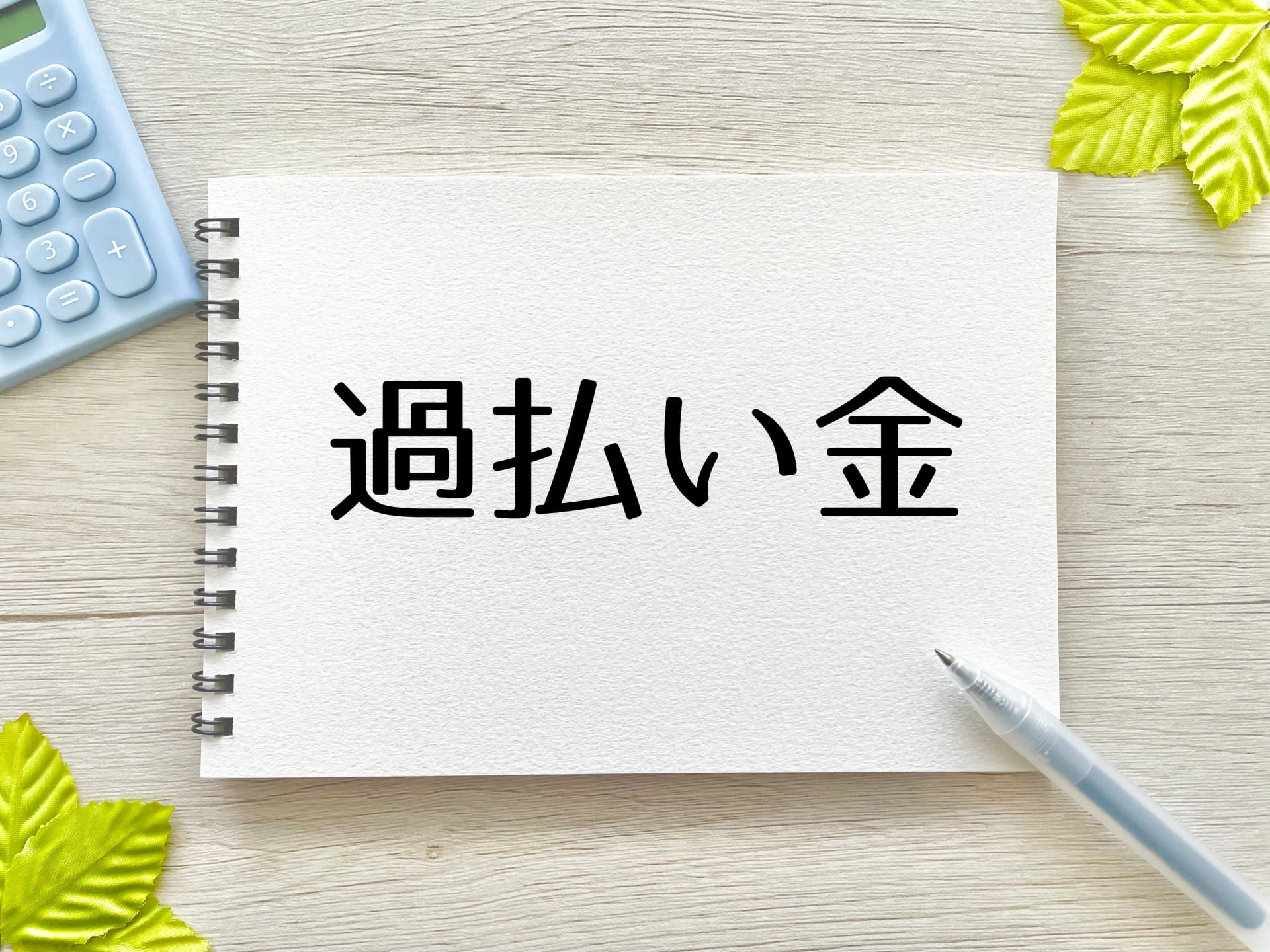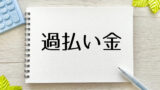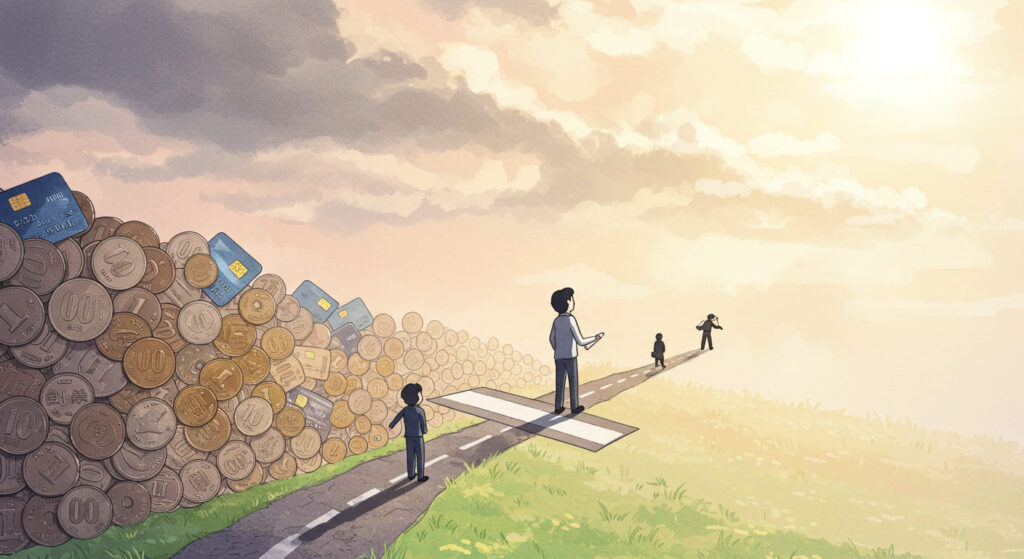
取引の個数が問題となる類型の1つに取引併存型があります。この取引併存型において各取引の基本契約が同一でなかった場合に,過払い金の充当計算ができるのかについて判断した判例として,最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決があります。
最三小判平成19年2月13日の争点
最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決の事案は,同一の基本契約がない2つの取引が併存しており,その一方の取引について過払い金が発生したという事案です。
この判決では、2つの争点について判断しています。
1つは、同一の基本契約がない併存する取引の一方で発生した過払金を他方の取引における借入金債務に充当できるかという問題です。
もう1つは、過払金の利息の利率について、民事法定利率を適用するか商事法定利率を適用するかという問題です。
このページでは、主に、過払金の充当に関する判断の点について説明します。
過払い金の充当(取引の個数)に関する判断
過払い金返還請求において最も問題となる取引の個数の問題には、取引の分断(取引分断型・取引中断型)と取引の併存(取引併存型)の2つの類型があります。
取引併存型とは、ある貸金業者との間で複数の取引が併存している場合です。
この場合に、そのうちの1つの取引において発生した過払い金を別の併存する取引における貸付金債務に充当することができるかが問題となります。
この複数の併存する取引について同一の基本契約がある場合を「基本契約取引併存型」といい,同一の基本契約がない場合を「非基本契約取引併存型」と呼ぶ場合があります。
最三小判平成19年2月13日の事案
前記のとおり、最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日判決の事案は、同一の基本契約がない2つの取引が併存しており、その一方の取引について過払い金が発生したという事案です。したがって、非基本契約取引併存型に分類される事案です。
ただし,この判決の事案は,一方の取引で過払い金が発生した当時には,まだ他方の取引が始まっておらず,過払い金が発生した時点では他の借入金債務が存在していないという事案です。
過払いとなっている一方の取引について,過払いとは知らずに返済をしている途中で,さらに他方の借入れもしたというものです。
過払い金発生後に新たな借入れをしているという点で,同一の貸金業者との取引が中断し,一定期間後に再度取引を開始するというタイプ(取引分断型)にも通じるところがあります。
そのため,この判例は,「非基本契約取引併存型」について判断した判例と評価されていますが,「非基本契約取引中断型」の場合の判断にも通じるところのある判断であると評価されています。
結論としては,以下のとおり,基本契約がない取引併存型(非基本契約併存型)や取引中断型(非基本契約取引中断型)の場合には,原則として一連計算できないという判断をしています。
最三小判平成19年2月13日の判断
最三小判平成19年2月13日は,以下のとおり判示しています(一部抜粋)。
貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下,この過払金を「第1貸付け過払金」という。),その後,同一の貸主と借主との間に第2の貸付けに係る債務が発生したときには,その貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,その貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り,第1貸付け過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務には充当されないと解するのが相当である。なぜなら,そのような特段の事情のない限り,第2の貸付けの前に,借主が,第1貸付け過払金を充当すべき債務として第2の貸付けに係る債務を指定するということは通常は考えられないし,第2の貸付けの以後であっても,第1貸付け過払金の存在を知った借主は,不当利得としてその返還を求めたり,第1貸付け過払金の返還請求権と第2の貸付けに係る債権とを相殺する可能性があるのであり,当然に借主が第1貸付け過払金を充当すべき債務として第2の貸付けに係る債務を指定したものと推認することはできないからである。
引用元:裁判所サイト
前記のとおり,この判決は,非基本契約併存型に関する判例ですが,「第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず」と判示されているように,非基本契約中断型についても通用する判断をしていると評価されています。
この判決によれば,同一の基本契約のない場合、つまり、非基本契約併存型および非基本契約中断型の場合には、原則として、一方の取引で発生した過払い金を他方の取引の貸付金に充当することはできないとしています。
ただし,常に充当計算できないわけではなく,「特段の事情」がある場合には,充当計算できるとしています。
そして,その「特段の事情」の例として,「基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた」ことや,「貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在する」ことが挙げられています。
最三小判平成19年2月13日の問題点
前記のとおり、最三小判平成19年2月13日は、原則として、過払金の充当を認めないとしつつも、特段の事情がある場合には、過払金の充当が認められることがあるとしています。
しかし,実際問題として,中断前の貸付の際に中断後の貸付についても想定している場合は稀でしょう。
ましてや、そもそも過払い金が発生しているなど知らないで再度貸付を受けるのですから、借主が、一方の取引で過払い金が発生したら他方の取引の貸付に充当するなどという特約をするわけがありません。
貸金業者は過払いについて知っているでしょうが,貸金業者が親切に,借主に過払金が発生したら有利に取り計らいますよなどといって,わざわざそのような特約をするはずもないことは明らかです。
つまり,この「特段の事情」はほとんど現実的にあり得ないものということになり,基本契約がない場合には,過払い金の充当がほとんど認められないということになってしまいます。
そのため,この判決には,最二小判平成15年7月18日と整合性がないとか,借主に不利益を与えるものであり,利息制限法の趣旨に反するなど多くの批判がなされました。
実務に与えた影響
この最三小判平成19年2月13日以降,過払金充当合意の理論など,この判決を是正するような多くの判例が出されることになりました。その意味では,取引の個数に関する現在の錯綜した状況の一因となった判例といえるでしょう。
過払い金の利息の利率に関する判断
前記のとおり、この最三小判平成19年2月13日は、上記取引の個数の問題のほかに、過払金の利息の利率について、民事法定利率を適用するか商事法定利率を適用するかという問題についても重要な判断をしています。
具体的に言うと、最三小判平成19年2月13日は、過払金の利息の利率には、商事法定利率ではなく、民事法定利率が適用されると判示しています。