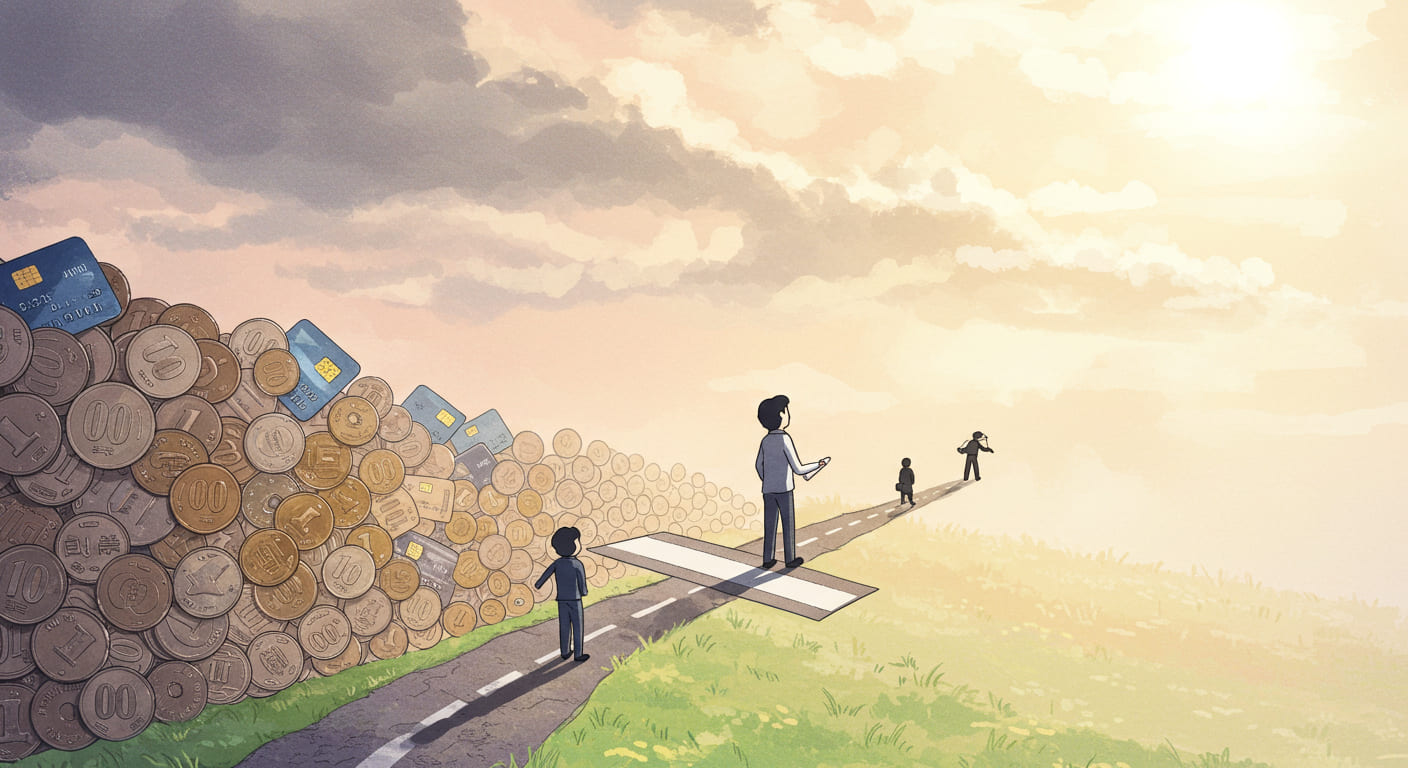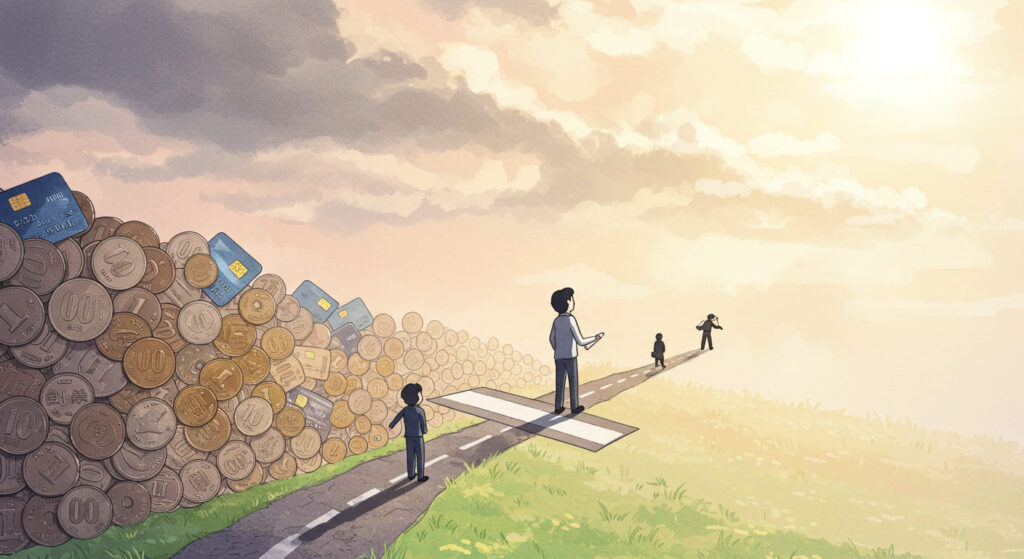
自己破産における管財手続とは,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し,それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。
これに対して,破産管財人が選任されず,手続開始と同時に破産手続が廃止により終了する同時廃止手続がありますが,管財手続が原則とされています。
東京地方裁判所や大阪地方裁判所など多くの裁判所では,管財手続を簡素化して破産管財人の負担を軽減することにより,引継予納金の額を少額化する少額管財の運用が行われています。
自己破産における管財手続
自己破産の手続は,大きく分けると,「管財手続」と「同時廃止手続」に分けることができます。
管財手続とは,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し,それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。
これに対し,同時廃止手続は,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる簡易型の手続です。
破産手続の原則的形態は,管財手続です。同時廃止は,例外的な取り扱いとされています。
破産管財手続の概要
前記のとおり,管財手続になった場合,破産手続の開始と同時に,裁判所によって破産管財人が選任されます。
そして,破産者の財産の管理処分権は,破産管財人に専属することになります。つまり,破産者が自分で勝手に財産を処分することができなくなるということです。
管財手続においては,破産管財人が,破産者の財産を調査・管理して換価処分し,それによって得た金銭を債権者に弁済または配当します。
破産者は,この破産管財人が行う調査や管理処分に協力しなければなりません。
管財手続と同時廃止手続の違い
前記のとおり,自己破産手続の原則的な形態は管財手続ですが,例外的な形態として同時廃止手続があります。
同時廃止の場合には,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終了します。
そのため,管財手続と同時廃止手続では,以下のような違いが生じます。
- 管財手続の場合には破産管財人による調査や財産の管理処分が行われますが,同時廃止の場合にはそのような調査や管理処分は行われません。
- 管財手続の場合には破産管財人による管財業務が完了するまで手続きが終了しませんが,同時廃止の場合は手続開始と同時に終了となるので,管財手続の方が同時廃止よりも終了までの期間は長くなります。
- 管財手続の場合は引継予納金を裁判所に納める必要がありますが,同時廃止の場合は引継予納金の納付は必要ありません。そのため,手続費用は,管財手続の方が同時廃止よりもかなり高額となります。
上記のとおり,管財手続に比べると,同時廃止の方が手続期間が短く,費用も廉価であるため,破産を申し立てる人の立場からすると,同時廃止の方が有利と言えるでしょう。
少額管財と特定管財
前記のとおり,管財手続よりも同時廃止の方が,簡易迅速かつ廉価です。しかし,管財手続が原則であり同時廃止は例外であるため,同時廃止となることは限られてきます。
もっとも,管財手続の予納金はかなり高額となることがあります。予納金が高額であるため,自己破産を選択できないとなると,債務者の経済的更生を図る法の趣旨に沿いません。
そこで,東京地方裁判所や大阪地方裁判所など多くの裁判所では,「少額管財」と呼ばれる運用が行われています。
少額管財とは,管財手続として破産管財人による調査・管理処分が行われるものの,手続を簡素化して破産管財人の負担を軽減することにより,引継予納金の額を少額化するという運用です。
東京地方裁判所も大阪地方裁判所も、少額管財の場合の引継予納金の額は20万0000円からとされています。
この少額管財または少額管財に類似する運用は,東京地方裁判所や大阪地方裁判所以外の裁判所でも採用されています(ただし,少額管財の運用をとっていない裁判所もあるため,事前に確認しておいた方がよいでしょう。)。
少額管財はもともと特別な運用ではありましたが,現在では,個人の自己破産については,むしろ少額管財が原則的な運用となっています。
そのため、例えば、東京地裁などでは、少額管財を「通常管財」として扱い、少額管財でない本来の管財手続を「特定管財」として扱っています。
なお、少額管財が利用できるのは、弁護士が破産者の代理人になっている場合に限られます。
管財手続(少額管財)になる場合
少額管財手続になるか,同時廃止手続になるか,手続の内容や費用に関わってきます。そのため,自己破産を申し立てる際には,意外と切実な問題です。
具体的には,以下のような場合に同時廃止ではなく管財手続になります。
- 換価処分できる20万円以上の財産(自由財産を除く。)がある場合
- 現金と預貯金の合計額が50万円以上ある場合
- 否認権行使が必要となる場合
- 免責不許可事由がある場合または免責不許可事由の調査が必要となる場合