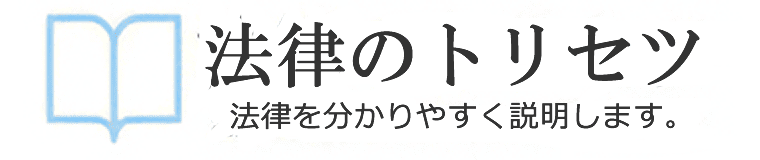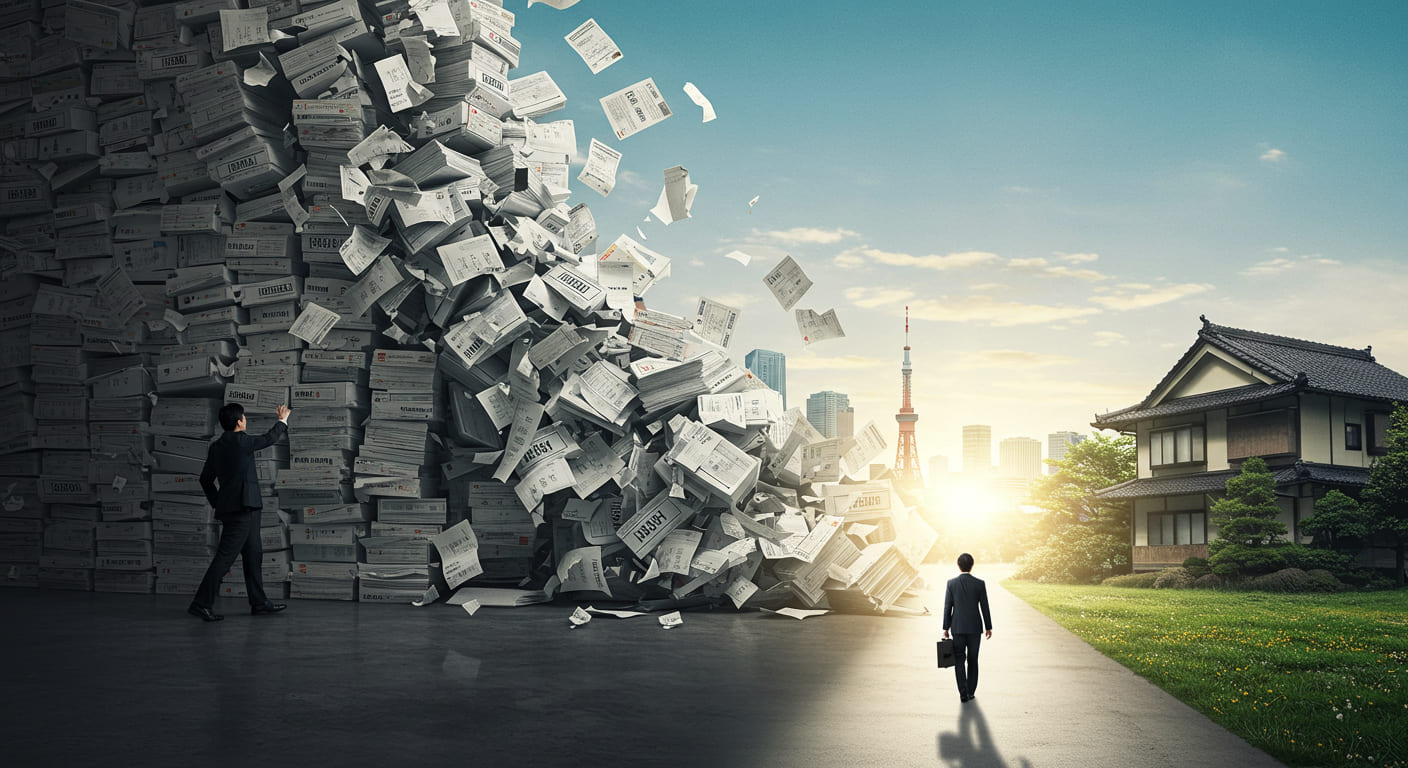この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
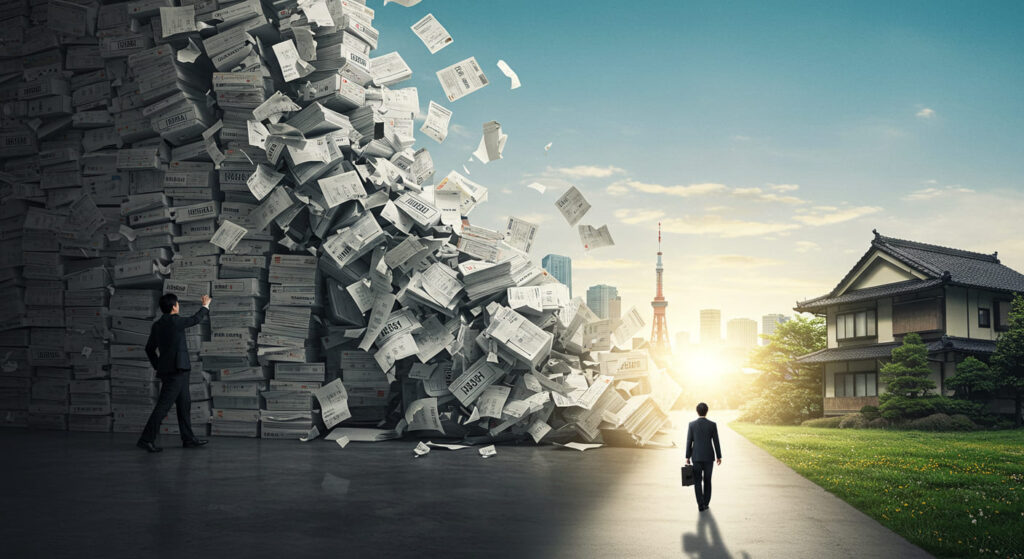
小規模個人再生における再生債権者による再生計画案の書面決議において、不同意回答をした議決権のある再生債権者が、議決権者総数の半数以上である場合か、または、その議決権の額が議決権者の議決権総額の2分の1を超える場合、再生計画案は否決されます。
債権者の不同意により再生計画案が否決された場合、再生手続は、再計計画を認可するかどうかの判断をする前に廃止(打ち切り)になってしまうので、小規模個人再生の再生計画は認可されません。
小規模個人再生における再生計画案の決議
小規模個人再生においては、裁判所による再生計画の認可・不認可の判断に先立って、再生債権者による再生計画案の決議が行われます。
この再生債権者による再生計画案の決議は、通常の民事再生の場合の決議のように債権者集会は開かれず、もっぱら書面によって行われます(書面決議)。
書面による決議とは、議決権を有する再生債権者が、裁判所に対して書面で再生計画案に同意しない(不同意)旨を回答する方式で議決を行うことです。
不同意回答をしなかった再生債権者は再生計画案に同意したものとみなされます。積極的に同意したわけではなく、不同意ではないものを同意とみなすだけでなので、消極的同意と呼ばれます。
消極的同意をした(不同意回答をしなかった)再生債権者が一定数以上いれば、再生計画案は可決されます。
再生計画案が否決された場合
小規模個人再生における再生債権者による再生計画案の決議において、再生計画案が否決された場合、再生手続は廃止されます。
再生手続が廃止されると、その時点で再生手続が強制的に終了させられてしまいます。再生計画が認可されないまま手続が打ち切られてしまうのです。
したがって、小規模個人再生においては、再生計画案が可決されるかどうかが、再生計画の認可を得るための重要な条件になっています。
再生計画案が可決されるための要件
民事再生法 第231条
- 第6項 第4項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
それでは、どのような場合に小規模個人再生における再生計画案が可決されるのでしょうか?
債権者全員が消極的同意をしなければ(1人でも不同意の債権者がいれば)、再生計画案の決議が否決になってしまうわけではありません。しかし、一定数以上の消極的同意は必要です。
具体的に言うと、以下の場合に、再生計画案の決議は可決したものとみなされます(民事再生法231条6項)。
- 不同意回答をした議決権のある再生債権者が、議決権者総数の半数に満たない場合
- 不同意回答をした議決権のある再生債権者の議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えない場合
逆に言うと、不同意回答をした議決権者が議決権者総数の半数以上である場合、または、不同意回答をした議決権者の議決権の額が議決権者の議決権総額の2分の1を超える場合、否決されます。
したがって、再生債権者の人数だけではなく、各再生債権者の有する債権額も重要となってくるのです。
可決要件の具体例
例えば、以下の再生債権者がいるという状況であった場合について考えます。
- 債権者A:債権額100万円
- 債権者B:債権額200万円
- 債権者C:債権額300万円
- 債権者D:債権額400万円
- 債権者E:債権額500万円
- 債権者F:債権額1500万円
この事例で、債権者A・債権者B・債権者Cが不同意回答をしたとすると、債権額は合計でも600万円に過ぎませんが、議決権者総数6人のうちの3人が不同意をしていることになります。
したがって、議決権者総数の「半数」以上が不同意をした場合に該当するので、当該再生計画案は否決ということになります。
次に、この事例で、債権者Fのみが不同意回答をした場合はどうなるのかというと、人数としては1人だけですが、議決権者の議決権の額総額3000万円のうち1500万円を有する債権者が不同意をしていることになります。
もっとも、議決権の額による場合は、議決権総額の2分の1を超える場合(過半数以上の場合)に否決されます。3000万円のうち1500万円であれば2分の1を超えていないので、再生計画案は可決されます。
最後に、この事例で、債権者A・債権者Fが不同意回答をした場合について考えると、人数としては2人だけですが、議決権者の議決権の額総額3000万円のうちA・F合計で1600万円を有する債権者が不同意をしていることになります。
したがって、議決権総額の2分の1を超える場合に該当するので、再生計画案は否決されることになります。
住宅資金特別条項を利用していた場合の具体例
なお、上記事例で、住宅資金特別条項を利用しており、以下の債権者がいた場合はどうなるでしょうか。
- 債権者G:住宅資金貸付債権額2000万円
この場合には、結論をいうと、何も関係がありません。なぜなら、住宅資金特別条項を利用する場合の住宅資金貸付債権者は、議決権を有していないからです。
したがって、住宅資金貸付債権者を議決権者の人数に加える必要はありませんし、また、議決権の額に加える必要もありません。
いずれにしても、小規模個人再生を選択する場合には、議決権者となる再生債権者の数、各再生債権者の有する債権の金額を考慮しておく必要があるでしょう。