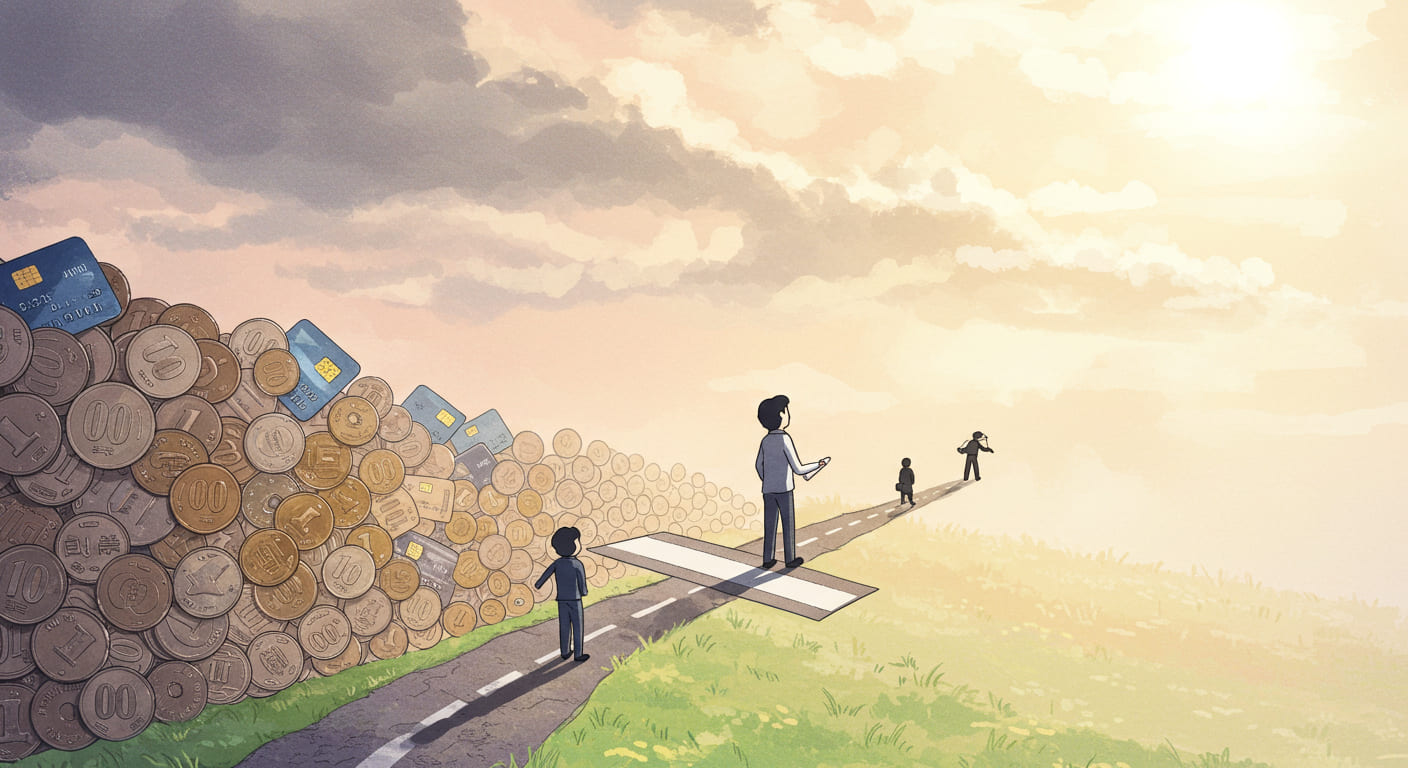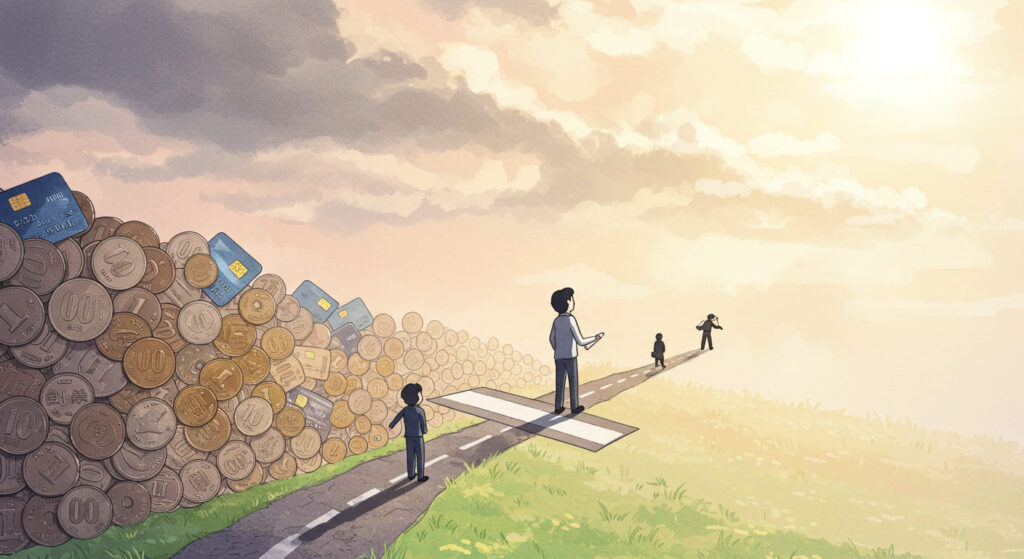
自由財産の拡張がどのような場合に認められるのかについては,一律の基準があるわけではありません。破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類や価額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を総合的に考慮して判断されます(破産法34条4項)。
自由財産拡張を認めても,財産の総額が99万円以内で収まる場合には比較的拡張が認められやすい傾向はあります。
なお,各地方裁判所ごとに,あらかじめ,一定の財産について自由財産の拡張を認めるという基準(換価基準・自由財産拡張基準)が設けられています。
自由財産の拡張の判断
破産法 第34条
- 第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
- 第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
- 第3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
- 第1号 民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
- 第2号 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは,この限りでない。
- 第4項 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
- 第5項 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
- 第6項 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
- 第7項 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
自己破産をした場合でも処分しなくてよい財産のことを「自由財産」といいます。どのような財産が自由財産に該当するかについては,破産法で定められています。
もっとも,破産法上に定められていない財産であっても,裁判所の決定によって自由財産として扱うことができるとされています。これを「自由財産の範囲の拡張(自由財産の拡張)」といいます。
この自由財産の拡張には,一律の判断基準がありません。
上記破産法34条4項のとおり,破産者の生活の状況,破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類及び額,破産者が収入を得る見込みその他の様々な具体的事情を総合的に判断するものとされています。
しかし,その判断の根本にあるものは,自由財産拡張を認めなければ破産者の経済的更正を図ることができないのかどうかということです。
自由財産の拡張は,破産者自身が申し立てるか裁判所が自ら判断するかのどちらかによってなされますが,いずれにしろ,破産者の側で自由財産の拡張を認めてもらうために具体的な事情や必要性を十分に説明する必要があります。
自由財産の拡張が認められる範囲(99万円基準)
前記のとおり,破産者の経済的更生に必要な財産については,自由財産の拡張が認められることがあります。
しかし,そうであるからといって,破産者の経済的更正に必要であれば何でも自由財産の拡張が認められるわけではありません。
何でも自由財産にしてしまっては,破産法の一番の目的である破産債権者への配当ができなくなってしまいます。
それに,そもそも破産者の経済的更正のために,99万円以下の現金や差押禁止財産などの本来的自由財産が認められているのですから,本来的自由財産だけでは最低限の生活さえ維持できないというような事情が必要となってきます。
したがって,自由財産の拡張が認められるのはなかなか難しいということです。
上記のとおり,99万円以下の現金が本来的自由財産とされていることとの均衡から,自由財産の拡張の1つの目安は,99万円だといわれています。
つまり,財産総額が99万円を超えてしまうような結果となる自由財産の拡張は認められにくいということです。この99万円を一応の基準とすることを「99万円基準」と呼ぶこともあります。
例えば,すでに50万円の財産が自由財産とされている場合であれば,それら以外に,さらに49万円を超える財産について自由財産の拡張を認めてもらうことは難しいということになります。
各地方裁判所における換価基準(自由財産拡張基準)
前記のとおり,自由財産の拡張が認められるのは、限られた場合ということになります。特に、財産総額99万円を超える自由財産の拡張は限定されてきます。
もっとも,各地方裁判所では,あらかじめ,一定の財産について自由財産の拡張を認めるという基準を公開しています。「換価基準」「自由財産拡張基準」などと呼ばれています。
つまり,この基準に該当する財産については,本来的自由財産ではないものの,個別具体的な必要性等の証明なくして,自由財産として拡張されるということです。
自己破産申立てを考えている場合には、申立てをする予定の地方裁判所における換価基準・自由財産拡張基準についてもあらかじめ検討しておく必要があるでしょう。
ただし、この換価基準・自由財産拡張基準が設けられている代わりに、この基準に掲げられていない財産について自由財産の拡張が認められるのは、それなりの理由がない限り、かなり難しくなっています。
例えば、足が不自由なため移動に自動車が必須であるとか、重病を患っているため今後生命保険等に加入することは難しいことから、加入している生命保険を解約できないなど、特別な事情がなければ、換価基準を超える自由財産の拡張は難しいということです。
※なお、換価価値20万円未満の自動車や解約返戻金の額が20万円未満の生命保険などは、各地方裁判所の換価基準において自由財産として扱われることがありますので、上記の例は、それを超える換価価値・解約返戻金の額がある場合の話です。
まとめ
まず、本来的自由財産(破産手続開始後に取得した新得財産、差押禁止財産、99万円以下の現金)は、処分されません。また、破産管財人によって破産財団から放棄された財産も、処分されません。
加えて、各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)で認められている財産も、処分されません。これは、各裁判所によって異なります。
この本来的自由財産・破産財団からの放棄財産と各地方裁判所の換価基準に含まれていない財産について自由財産の拡張が認められるかどうかは、財産の総額が99万円を超えるか否かが重要な基準となってきます。
99万円以内であれば、自由財産の拡張は比較的認められやすいですが、99万円を超える場合には、かなりの必要性がないと、自由財産の拡張は認められにくいでしょう。