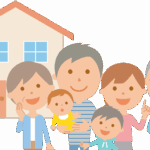契約は法的な拘束力を持った約束ですから,容易に解消することはできません。もっとも,一定の場合には,契約を解除(解約)して契約関係を解消することが可能な場合があります。
契約の解除
契約は,一方当事者の申込みの意思表示と他方の当事者の承諾の意思表示が合致した場合に成立する法律行為です。そして,契約が成立すると法的な拘束力が発生します。つまり,契約を容易に解消することはできなくなるということです。
もっとも,契約を「解除」できる場合には,その解除によって契約を解消することができます。
すなわち,契約の解除とは,当事者の一方による契約を解消させる旨の意思表示です。契約が解除されると,原則として,その契約は遡及的に消滅し,契約成立前の状態に戻ることになります。
契約解除の効果
前記のとおり,契約が解除されると,その契約は遡及的に消滅,つまり,契約の締結時にさかのぼって無かったことになります。これにより,契約の当事者は,契約の拘束力から免れることができます。
そのため,まだ残っている債務(未履行債務)は履行しなくてよいということになります。
また,契約が解除されると,法律関係は契約の締結前の状態に回復することになります。具体的には,契約の当事者は,相互に,契約締結前の状態に戻すように請求することができます。これを原状回復請求といいます。
原状回復請求をすることによって,すでに履行済みの債務(既履行債務)をもとに戻すように請求できることになります。
なお,損害が発生している場合には,契約解除とは別に損害賠償請求をすることも可能です。
契約解除の手続
契約解除は,当事者の一方による意思表示です(民法540条1項)。
つまり,当事者のどちらかが,契約を解除するという意思表示をし,それが他方に到達すれば,契約解除の効力が発生するということになります。
具体的には,まずは,配達証明付きの内容証明郵便で契約を解除する旨の意思表示をするのが,一般的でしょう。それでも,解除について当事者間に争いが生じた場合には,裁判手続を利用することになります。
契約を解除できる場合
前記のとおり,契約の解除は当事者の一方の意思表示をすれば足りますが,もちろん,これは契約解除の要件を満たしている場合の話です。
契約は,いわば法的な約束ですから,容易には解消できません。したがって,一定の要件を満たす場合にしか,契約の解除はできないのです。
契約解除ができる場合の1つは,法律に定めがある場合です。これを「法定解除」といいます。法定解除については,民法540条以下に基本原則が定められています。
法定解除の場合には,法律で定められた要件を満たしている場合のみ,解除することができます。
第2は,当事者間で解除権が留保されている場合です。簡単にいえば,法定解除の要件がない場合でも一定の場合には解除できるということを,当事者間で取り決めていたという場合です。「約定解除」と呼ばれます。
約定解除の場合は,約定で決めた条件を満たせば解除できるということになります。
約定解除には,「手付解除」の場合もあります。これは,契約の際に当事者の一方が解約手付を交付していた場合に認められる解除です。
基本的には売買契約で認められるもので,売主が手付解除する場合には,受領した手付にさらに同額の金銭を加えた金額(要するに手付金の倍額)を売主に交付することにより,買主が手付解除する場合には,手付を放棄して契約を解除することができます。
また、「合意解除」もあります。これは、当事者間で契約を解除することに合意することです。当事者が解除に合意している以上、特に制限なく解除が認められます。