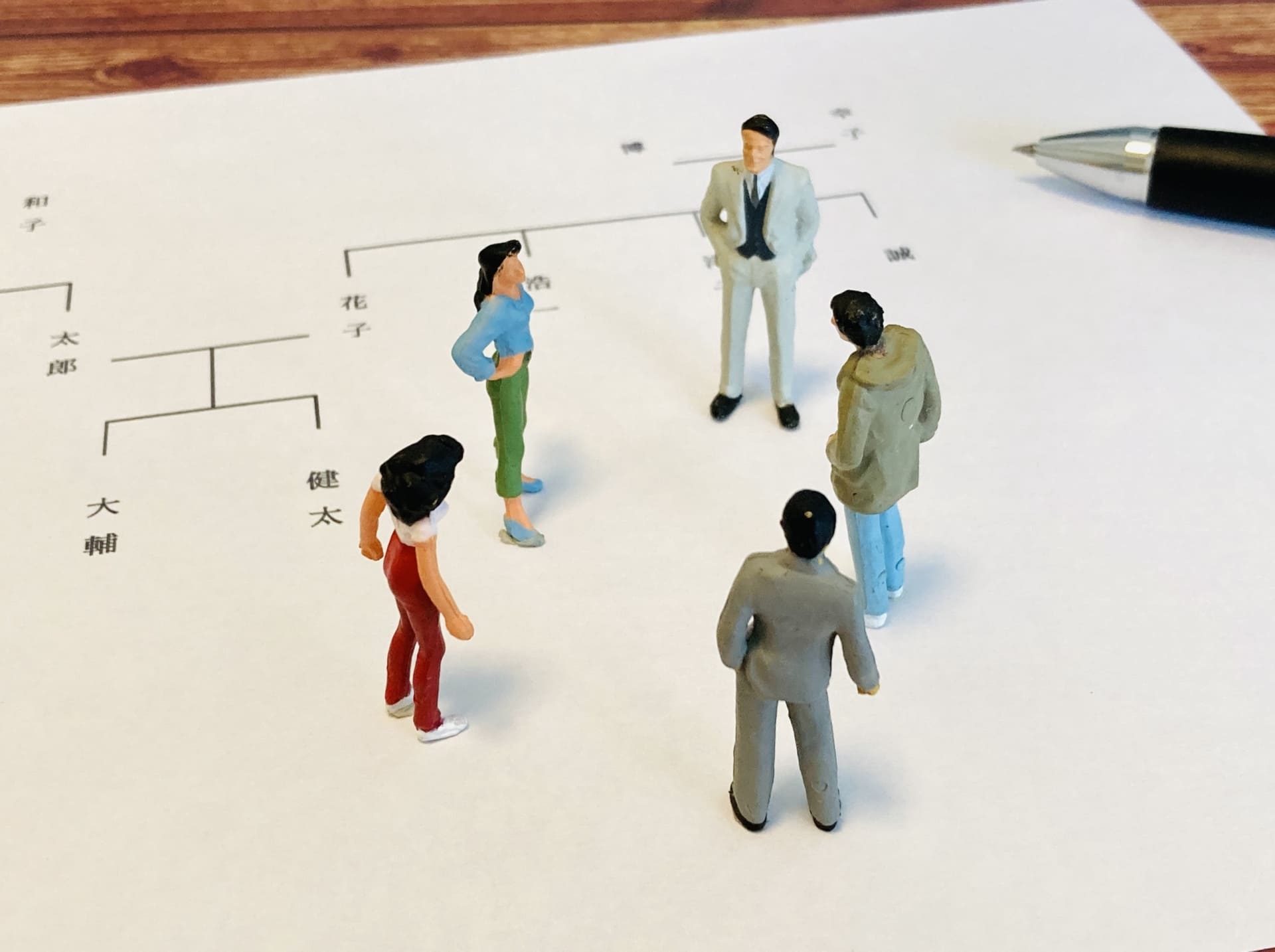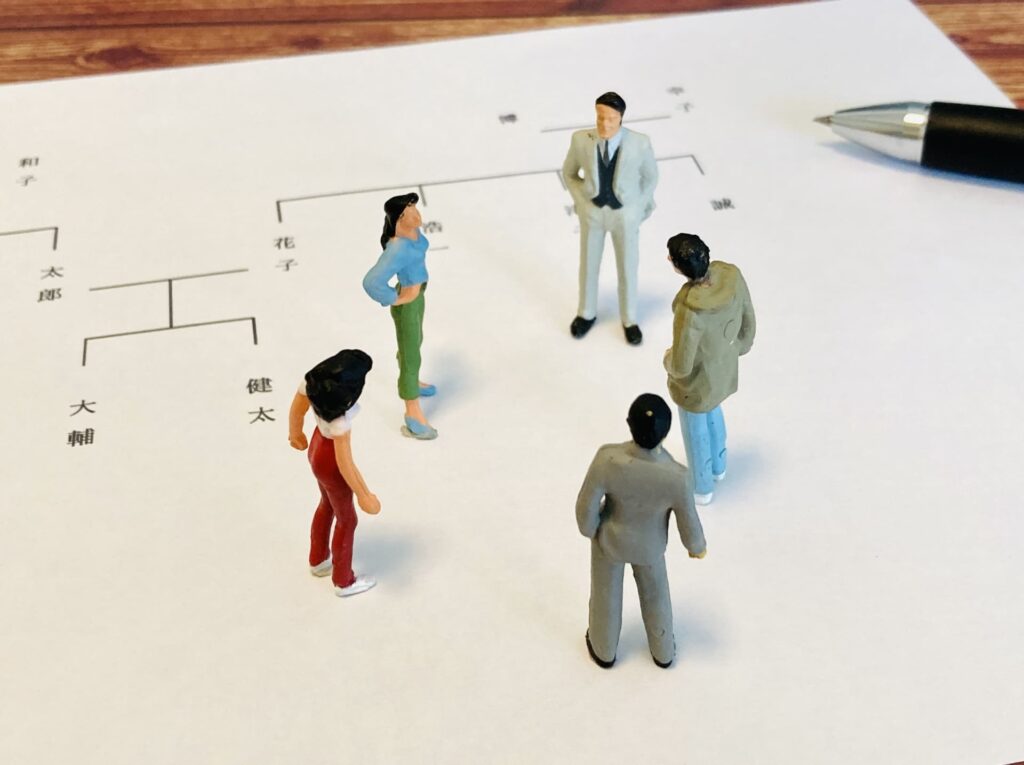
相続において,相続財産を遺して亡くなった立場の方のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
被相続人とは?
遺産相続の場面において,相続財産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」(ひそうぞくにん)といいます。他方,相続財産を受け継ぐ側の人は「相続人」(そうぞくにん)と呼ばれます。
遺産相続は,被相続人の死亡の時に開始されます。そして,相続において相続人に引き継がれることになる相続財産は,この被相続人が生前に有していた一切の権利義務ということになります。
また,誰が相続人となるかは,民法によって定められています。相続人となるのは,「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」ですが,この子や直系尊属などといった立場は,すべて被相続人を基準にした場合の立場を指します。
例えば,被相続人の子が,相続人となる「子」に当たるということです。
被相続人が誰かということは,当たり前のことですが,相続人が誰になるのかなど様々な面で,相続における基準となっているのです。
被相続人の意思の尊重
遺産相続という制度は,被相続人が遺した財産をめぐって紛争が生ずるなどの弊害を防止するために設けられている公的な制度です。
そのため,前記のように,誰が相続人となるのか,各相続人の相続分はどのくらいの割合になるのか,どのように相続財産を分配するのかなどは,法律(民法)によって定められています。
もっとも,そもそも相続財産とは,被相続人が生前に有していた権利義務です。その財産を築いてきたのも,被相続人であるということです。
したがって,被相続人の意思は,例え亡くなっているとはいっても,相続の場面においてもできる限り尊重されるべきです。
そこで,相続が開始した後にも,被相続人の意思が効力を発揮する場合があります。
その代表的な場合が,被相続人が「遺言」を作成していた場合です。被相続人が生前に遺言を作成していた場合,その遺言が法律の要件を満たす有効なものであれば,遺言の内容について法的な拘束力が生じます。
つまり,相続財産の分配について,その遺言の内容に従った分配がなされることになり,それによって,被相続人の意思が尊重されることになります。
また,被相続人による推定相続人の廃除も,被相続人の意思が相続開始後に効力を発揮する場合の1つです。推定相続人の廃除とは,一定の事由がある場合に,被相続人の意思によって,相続人となる人(推定相続人)から相続資格を奪うという制度です。
相続資格を奪われれば,その人は相続人となれませんから,これも被相続人の意思を尊重する制度といえるでしょう。
このように,法は,遺産相続において,公権的な制度体制を設けながらも,被相続人の意思を尊重するための制度を用意しているのです。