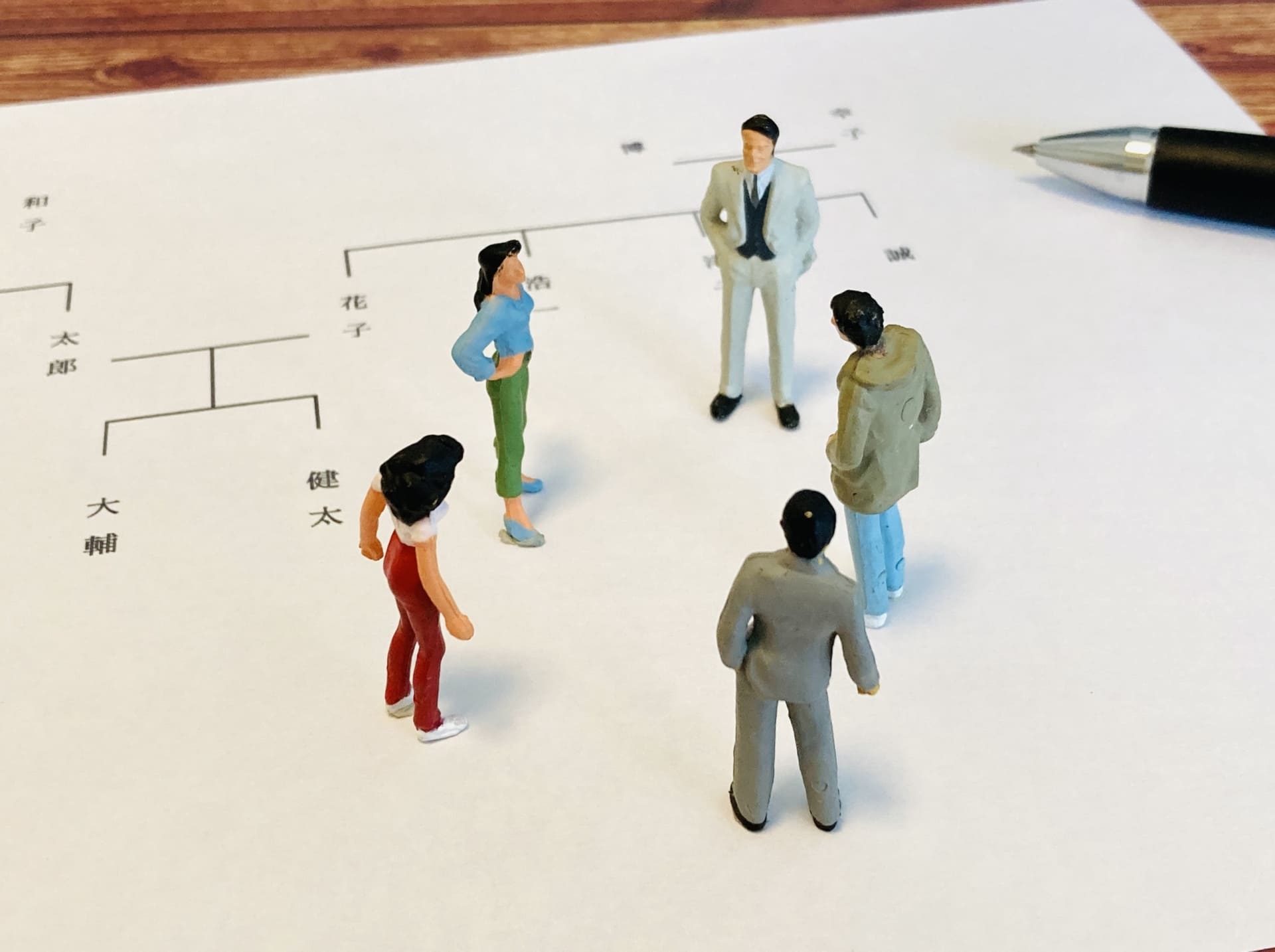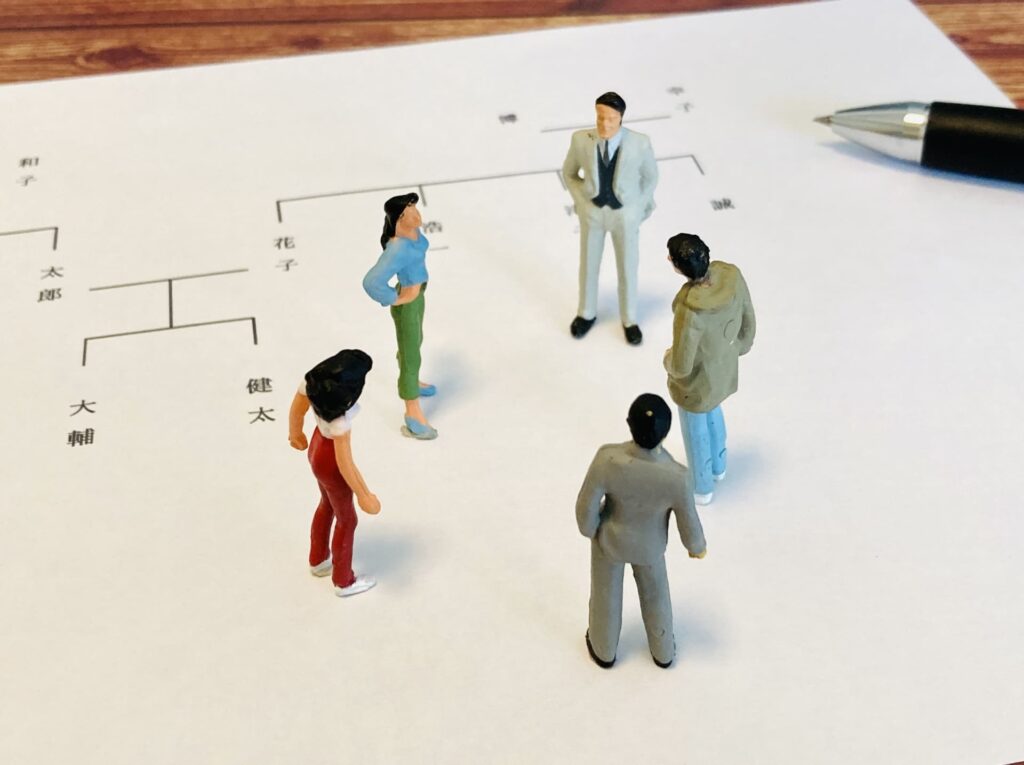
遺産分割の対象となる財産(遺産)は,遺産分割時に存在する相続財産です。
ただし,可分債権のように,相続財産であっても遺産分割の対象にならないものもあります。また,相続財産ではないものの,紛争解決の観点から,遺産分割の対象とすべきではないかということが問題となる財産もあります。
遺産分割の対象となる財産
被相続人が亡くなり,相続が開始されると,被相続人が有していた一切の権利義務は,被相続人の一身に専属するものを除いて,相続財産として相続人に承継されます(民法896条)。
相続人が複数人いる場合,相続財産は,原則として,その複数人の相続人(共同相続人)間で一時共有となり,遺産分割によってはじめて,個々の共同相続人に帰属することになります。
この遺産分割における遺産確定の基準時は,遺産分割時であると解されています。
したがって,遺産分割の対象となる財産は「遺産分割時に現存する相続財産」です。
より具体的に言うと,相続開始時に被相続人が有していた財産のうち遺産分割時にも現存していた財産が,遺産分割の対象となるということです。
ただし,相続財産のすべてが遺産分割の対象となるのかというと,そういうわけではありません。相続財産の内容・性質によっては,遺産分割の対象にならないものもあります。
逆に,そもそも相続財産そのものとはいえないものの,紛争解決の観点から,遺産分割の対象とすべきではないかということが問題となる財産もあります。
また,遺産分割協議等において,相続人らの合意によって,遺産分割の対象とする財産の範囲を決めることも可能です。
相続財産であるが遺産分割の対象とならない財産
前記のとおり,遺産分割の対象となるのは,遺産分割時に現存する相続財産です。
ただし,すべての相続財産が遺産分割の対象になるわけではありません。相続財産であっても,遺産分割の対象とならない財産もあります。
金銭その他の可分債権
相続財産であっても遺産分割の対象とならないものとは,可分債権です。
可分債権とは,可分な(分けることができる)給付を目的とする債権のことをいいます。最も代表的なものは,金銭債権です。
判例・通説によれば,金銭債権その他の可分債権は,遺産分割を経ることなく,法律上当然に分割され,各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得すると解されています(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日等)。
可分債権は,相続が開始すると,はじめから,各共同相続人に,それぞれの相続分に応じた金額ごとに振り分けられるので,遺産分割をする必要がないということです。
預金・貯金の払戻請求権(預貯金債権)
ただし,可分債権のうち,預金・貯金の払戻請求権(預貯金債権)だけは扱いが別です。
預金・貯金(預貯金債権)も,法的にいえば預貯金の払戻請求権という金銭債権ですから,この可分債権に含まれます。
そのため,かつては,預貯金債権も,他の可分債権と同様に,相続開始とともに法律上当然に分割されて,各共同相続人が相続分に応じて権利を取得するため,共同相続人間でそれを遺産分割の対象とする旨の合意がない限り,原則として遺産分割の対象とならないと解されていました(最三小判平成16年4月20日等)。
しかし,預貯金は,現金に近い財産と考えられており,実際の遺産分割においても,共同相続人間での合意のもと遺産分割対象財産に加えられるのが通常となっていました。
そこで,現在では,預貯金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると解されています(最大判平成28年12月19日,最一小判平成29年4月6日)。
したがって,預金・貯金(預貯金債権)は,遺産分割の対象となります。
仮払いされた預金・貯金
民法 第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治29年法律第89号)第909条の2の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。
前記のとおり,預金・貯金(預貯金債権)は,遺産分割の対象となります。そのため,遺産分割が確定するまで,各共同相続人は単独で預貯金を引き出すことができないのが原則です。
もっとも,葬儀費用などのために急ぎ預貯金の払戻しが必要な場合があることから、改正民法(2019年7月1日から施行)では,新たに,仮払いの制度が設けられました。
具体的には,各共同相続人は,150万円を上限として,相続開始時における預貯金債権額の3分の1に自身の法定相続分を乗じた金額までなら,それぞれ単独で預金・貯金の払戻しができるようになりました(民法909条の2前段,民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)。
この仮払いによって共同相続人の一部が預貯金を払い戻した場合,その払戻額について,その共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなすものとされています(民法909条の2後段)。
つまり,仮払いにより払戻しを受けた預貯金については,自動的に一部遺産分割したとみなされるということです。
したがって,すでに遺産分割済みということになるので,その後の(本番の)遺産分割の対象にはなりません。
ただし,払戻額が仮払いを利用した相続人の具体的相続分を超えていた場合には,後の(本番の)遺産分割において,その超過部分についての精算は必要となります。
なお,後述のとおり,超過部分については,払戻しをした者以外の共同相続人全員の同意により,遺産分割時に存在するものとみなして遺産分割を行うことも可能です(民法906条の2)。
相続財産でないが遺産分割の対象とするかが問題となる財産
遺産分割は,あくまで相続財産共同相続人間で分配するための制度ですから,相続財産でない財産は遺産分割の対象にならないのが原則です。
また,前記のとおり,遺産分割の対象となるのは,遺産分割時に現存している相続財産ですから,相続開始時に現存していた財産であったとしても,遺産分割時においてすでに無くなっているものは,遺産分割の対象とならないのも原則です。
とはいえ,原則論を貫くと,かえって共同相続人間の公平を害してしまうこともあり得ます。そのため,相続財産ではない財産であっても,遺産分割の対象とすべきかどうかが問題となるものがあります。
以下では,代表的なものを挙げます。
生命保険金
生命保険金(請求権)は保険金の受取人固有の財産であると解されています。したがって,受取人が指定されている場合には,そもそも相続財産(遺産)に含まれず,遺産分割の対象にはなりません。
ただし,判例によれば,保険金等の受取人と他の共同相続人との間に著しいほどの不公平が生ずるような場合には,その受領した生命保険金等が特別受益持戻しの対象となり,それによって,一定の調整を図ることができると解されています(最二小判平成16年10月29日)。
他方,受取人が指定されていない場合や受取人に「相続人」としか指定がされていないような場合には,相続財産に含まれ,遺産分割の対象になると解されることもあります。
死亡退職金
死亡退職金(請求権)も,前記生命保険金と同様,受取人固有の財産であると解されています。したがって,受取人が指定されている場合には,そもそも相続財産に含まず,遺産分割の対象にはなりません。
また,受取人が明確に指定されていない場合でも,退職金の根拠規程や法令の解釈によっては,特定の遺族(配偶者など)固有の財産であり,遺産分割の対象にならないと解されています。
相続財産の代償財産
相続の開始から遺産分割までの間に,何らかの理由で相続財産が逸出してしまったものの,これに代わる財産的利益が発生することがあります。この相続財産に代わる財産的利益を「代償財産」と呼んでいます。
例えば,相続財産であった不動産が火事で滅失したため,代償として火災保険の保険金が発生する場合などが考えられます。
この代償財産は相続財産そのものではないので,遺産分割の対象とならないのが原則です。しかし,相続財産から生じているのですから,これを分割対象にしないと不公平を生ずることもあります。
そこで,遺産分割手続において共同相続人間で対象財産とする合意がなされれば,遺産分割対象財産として扱われることになります。
相続財産からの果実
相続の開始から遺産分割までの間に,相続財産から「果実」が生じる場合もあります。典型的なものは,相続財産である不動産について賃料収入が生じる場合などです。
この相続財産からの果実も相続財産そのものではないので,遺産分割の対象とならないのが原則です。
もっとも,遺産分割手続において共同相続人間で対象財産とする合意がなされれば,遺産分割対象財産として扱われることになります。
なお,遺産分割の対象としない場合,相続財産からの果実は,共同相続人間での共有となるか,果実が可分債権であれば,各自の相続分に応じて各共同相続人に分割承継されることになります。
祭祀に関する財産
祭祀に関する財産は,被相続人の財産ではあっても,通常の相続とは異なる形で財産の承継が行われる財産です。したがって,遺産分割の対象になりません。
もっとも,誰を祭祀の継承者とするかも,相続人間で話し合って決めることを妨げる必要はありません。
したがって,相続人間で遺産分割の手続内で話し合って誰を祭祀継承者とするかを決めることは可能であると解されています。
相続開始後・遺産分割前に共同相続人の一部が処分した遺産
相続の開始から遺産分割までの間に,共同相続人の一部が相続財産を処分してしまった場合,遺産分割時においては,すでにその財産は無くなっているわけですから,遺産分割の対象とならないのが原則です。
もっとも,これを遺産分割の対象としないとすると,共同相続人間で不公平を生じてしまいます。
そこで,改正民法(2019年7月1日から施行)では,共同相続人全員の同意がある場合には,遺産分割前に処分された相続財産が遺産分割時に存在するものとみなすことができるものとされました(民法906条の2第1項)。
この場合,相続財産を処分した共同相続人の同意は不要です(民法906条の2第2項)。
したがって,相続財産を処分した共同相続人以外の共同相続人全員の同意があれば,遺産分割前に処分された相続財産が遺産分割時に存在するものとみなすことができます。
相続開始前に共同相続人の一部が処分した遺産
例えば,被相続人が生きている間に,共同相続人の一部が,被相続人の現金や預貯金を無断で使っていた場合などのように,相続開始前に共同相続人の一部が被相続人の財産を処分していることがあります。
相続開始前に共同相続人の一部が被相続人の財産を処分していた場合,その財産は相続開始時に存在していないのですから,そもそも相続財産ではありません。したがって,遺産分割の対象にはなりません。
また,前記民法906条の2の制度(遺産分割前に処分された相続財産を遺産分割時に存在するものとみなす制度)は,あくまで,被相続人の財産が,相続開始時に相続財産として存在していたことが前提です。
したがって,相続開始前に共同相続人の一部が被相続人の財産を処分していた場合には,適用されません。
この場合は,別途,訴訟等によって,処分をした共同相続人に対して不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をするほかないでしょう。
遺産分割対象財産に該当するか否かの具体例
遺産分割の対象となる財産であるか否かについて,典型的な財産を挙げてみます。
現金
現金は,遺産分割の対象となる財産です。
預金・貯金(預貯金債権)
前記のとおり,預金・貯金(預貯金債権)は,遺産分割の対象となる財産です。
生命保険金
前記のとおり,生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。ただし,内容によっては,特別受益による持戻しの対象となることはあります。
死亡退職金
前記のとおり,死亡退職金は遺産分割の対象とはなりません。また,特別受益による持戻し対象ともならないと考えるのが一般的です。
不動産
不動産(土地・建物)は,遺産分割の対象となる財産です。
動産(自動車・宝飾品等)
自動車などの動産は,遺産分割の対象となる財産です。ただし,特定ができない場合には,遺産分割対象財産とはならないと解されています。
社員たる地位・社員権
株式会社の社員たる地位(株式)・社員権は,相続によって相続人らの準共有となるので,遺産分割の対象となる財産に含まれると解されています。特例有限会社の場合も同様です。
他方,合名・合資・合同会社(持分会社)の社員たる地位(持分)・社員権は,相続財産に含まれないため,遺産分割の対象とはなりません。
社債・国債
社債・国債は単なる債権ではなく,相続人の準共有となるものであり,遺産分割の対象となると解されています。
投資信託
各投資信託の取扱いによって,可分のものと考えるか不可分のものと考えるのかという違いがあります。
可分のものであれば,遺産分割対象財産とはなりませんが,不可分のものであれば,準共有となり遺産分割対象財産となると解されています。