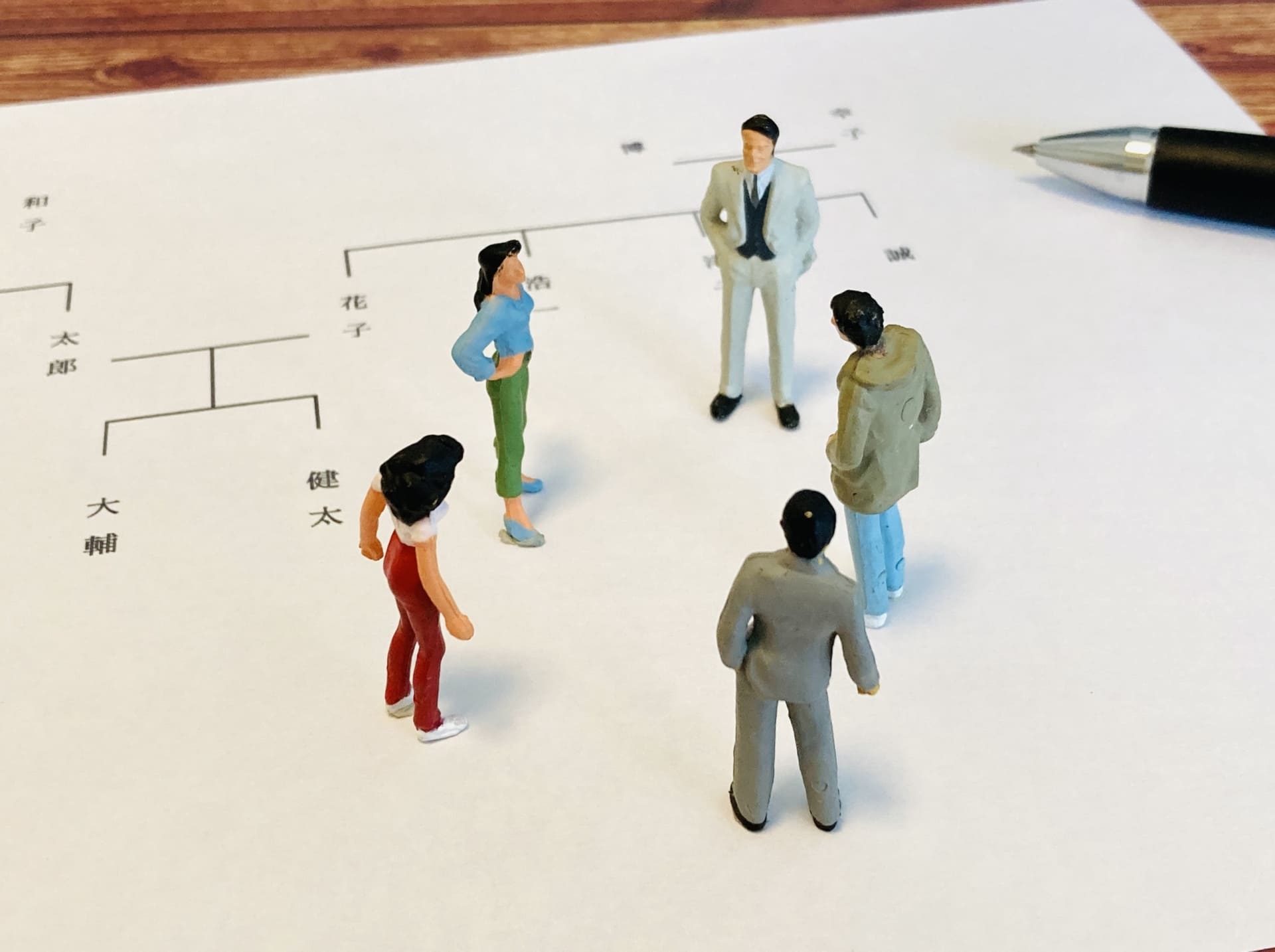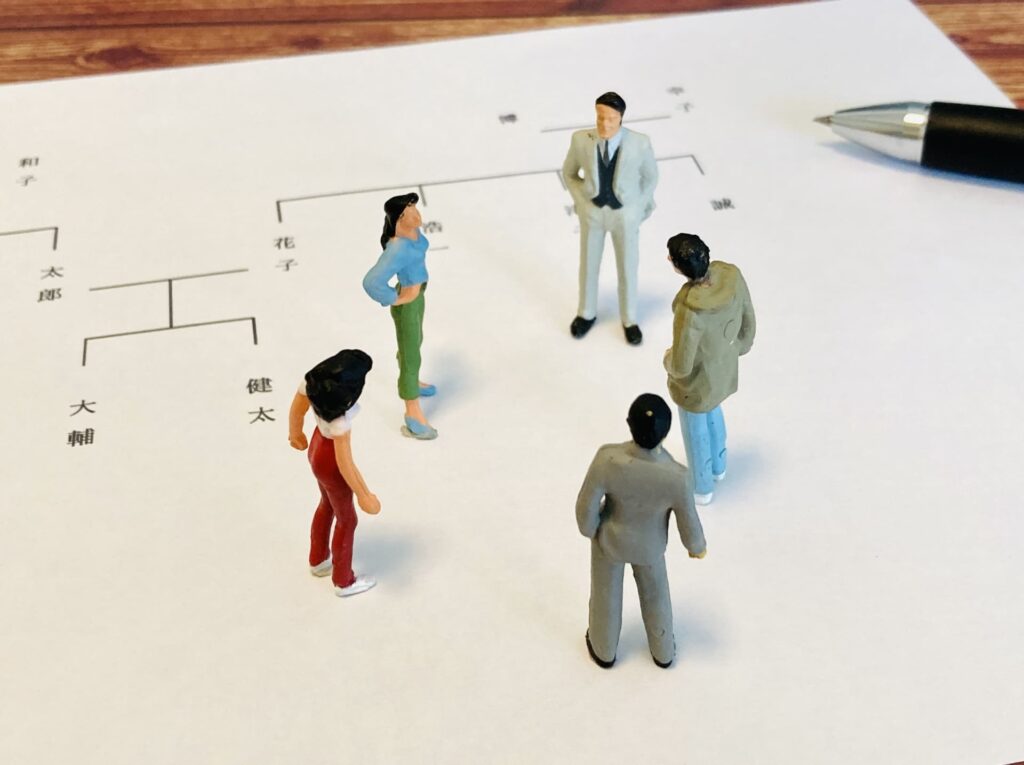
被相続人が,共同相続人のうちの一部に対し,婚姻・養子縁組のため,または,生計の資本として生前贈与をしていた場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。
特別受益がある場合は,その特別受益の「持戻し」をして相続分を計算します。具体的には,生前贈与を相続財産額に加算した上でみなし相続財産とし,そのみなし相続財産をもとに各共同相続人の一応の相続分を決め,さらに,生前贈与や遺贈を受けた相続人の相続分から生前贈与や遺贈を受けた額を控除します(民法903条1項)。
なお,被相続人が特別受益の持戻し免除の意思表示をした場合には,持戻しはされません(民法903条3項)。
特別受益(の持戻し)とは
民法 第903条
第1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
第2項 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
第3項 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
第4項 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
共同相続人のうちの一部の人が,相続開始前に被相続人から生前贈与を受けていたり,または,遺贈によって法定相続分以上の財産を受け取ることがあります。
生前贈与がされていた場合,その贈与によってその財産や利益は被相続人の財産ではなくなるので,相続が開始したとしても,それらは相続財産(遺産)には含まれません。
また,遺贈によって特定の相続人だけに多くの相続財産を遺すということは,原則として被相続人の自由です。
とはいえ,生前贈与や遺贈をまったく無視して通常どおりに法定相続分に基づく相続財産を分配すると,生前贈与や遺贈を受けた共同相続人とそうでない他の相続人との間で不公平が生じます。
そこで,共同相続人の一部に対して生前贈与や遺贈があった場合には,その生前贈与や遺贈も考慮した上で相続分を決定し,共同相続人間における不公平を是正しようとする制度が「特別受益(の持戻し)」という制度です。
具体的には,共同相続人のうちに被相続人から生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合に,生前贈与を相続財産額に加算した上で各共同相続人の相続分を決め,生前贈与や遺贈を受けた相続人の相続分から生前贈与や遺贈を受けた額を控除することになります(民法903条1項)。
特別受益がある場合の相続分の算出方法のことを,特別受益の「持戻し(もちもどし)」と呼んでいます。
特別受益があると認められる場合
持戻しの対象となる特別受益があると認められるのは,以下の場合です(民法903条1項)。
- 遺贈または(婚姻・養子縁組のため,生計の資本としての)生前贈与があったこと
- 上記遺贈・生前贈与を受けた者が共同相続人であること
特別受益の対象となるのは,遺贈と生前贈与の場合だけです。売買によって財産が譲渡された場合などは含まれません(ただし,形式上は売買であっても,実質的には生前贈与といえるような場合には,含まれる可能性はあります。)。
また,ここでいう生前贈与は,婚姻・養子縁組のための贈与か,生計の資本としての贈与でなければなりません。
そして,当然のことですが,遺贈や生前贈与を受けた者が共同相続人であるということが必要です。相続人でない者に対する遺贈や贈与は,特別受益の対象とはなりません。
特別受益の持戻しによる相続分の算定方法
特別受益があると認められた場合であっても,贈与や遺贈によって得た財産を返還しなければならないわけではありません。あくまで,贈与や遺贈の額を考慮して相続分を計算するにとどまります。
特別受益の持戻しがある場合、相続分は、以下のように計算することになります。
- まず,相続財産の額に婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本としての生前贈与の額を加算します(遺贈は,もともと相続財産に含まれているので,加算は不要です。)。生前贈与額が加算された相続財産のことを「みなし相続財産」といいます。
- 次に,みなし相続財産を法定相続分によって配分します。配分された相続分は「一応の相続分」と呼ばれることがあります。
- 最後に,生前贈与や遺贈を受けた共同相続人(受益相続人)の一応の相続分から,生前贈与および遺贈を受けた額を控除し,各共同相続人の具体的相続分を確定させることになります。
なお,生前贈与および贈与額の控除によって,受益相続人の具体的相続分が計算上ゼロまたはマイナスになった場合には,その受益相続人は相続分を受け取ることができません(民法903条2項)。
ただし,マイナスになった場合でも,生前贈与や遺贈によって得た利益を返還したり,他の共同相続人に渡したりする必要まではありません。
算定の具体例
例えば,Aが,遺産として1億円を遺して死亡し,そのAにはB,C,D,Eの4人の子(全員嫡出子)がおり,この3人のほかには相続人はいないとします。
原則どおりに考えると,B・C・D・Eにも2500万円ずつ法定相続分が認められることになります。
ところが,Bは2000万円の生前贈与を受けており,これが特別受益であると認められたとするとどうなるでしょう?
この場合,まず,相続財産1億円に生前贈与分2000万円を加算してみなし相続財産とします。したがって,みなし相続財産は1億2000万円となります。
次に,このみなし相続財産1億2000万円を,法定相続分に従って分配し,一応の相続分を定めます。BCDEは各4分の1の法定相続分がありますから,各人の一応の相続分は3000万円ずつとなります。
最後に,受益相続人であるBの相続分3000万円から生前贈与を受けた2000万円を控除します。したがって,Bの具体的相続分は1000万円になります。
そうすると,相続財産1億円は,Bが1000万円,C・D・Eがそれぞれ3000万円ずつを相続することになります。
持戻しの免除
前記のとおり,被相続人が共同相続人のうちの一部に対して婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本としての生前贈与や遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈は特別受益として扱われます。
もっとも,被相続人が特別受益の持戻しをしなくてもよいという意思表示をしていたときは,特別受益の持戻しはされません。これを「持戻し免除の意思表示」といいます(民法903条3項)。
改正民法(2019年7月1日から施行)では,配偶者保護のため,婚姻期間20年以上の夫婦の一方が,他方に対して居住用建物またはその敷地を生前贈与していたときは,その生前贈与について明確な持戻し免除の意思表示がなかった場合でも,持戻し免除の意思表示をしたものと推定するものとされています(民法903条4項)。