民法
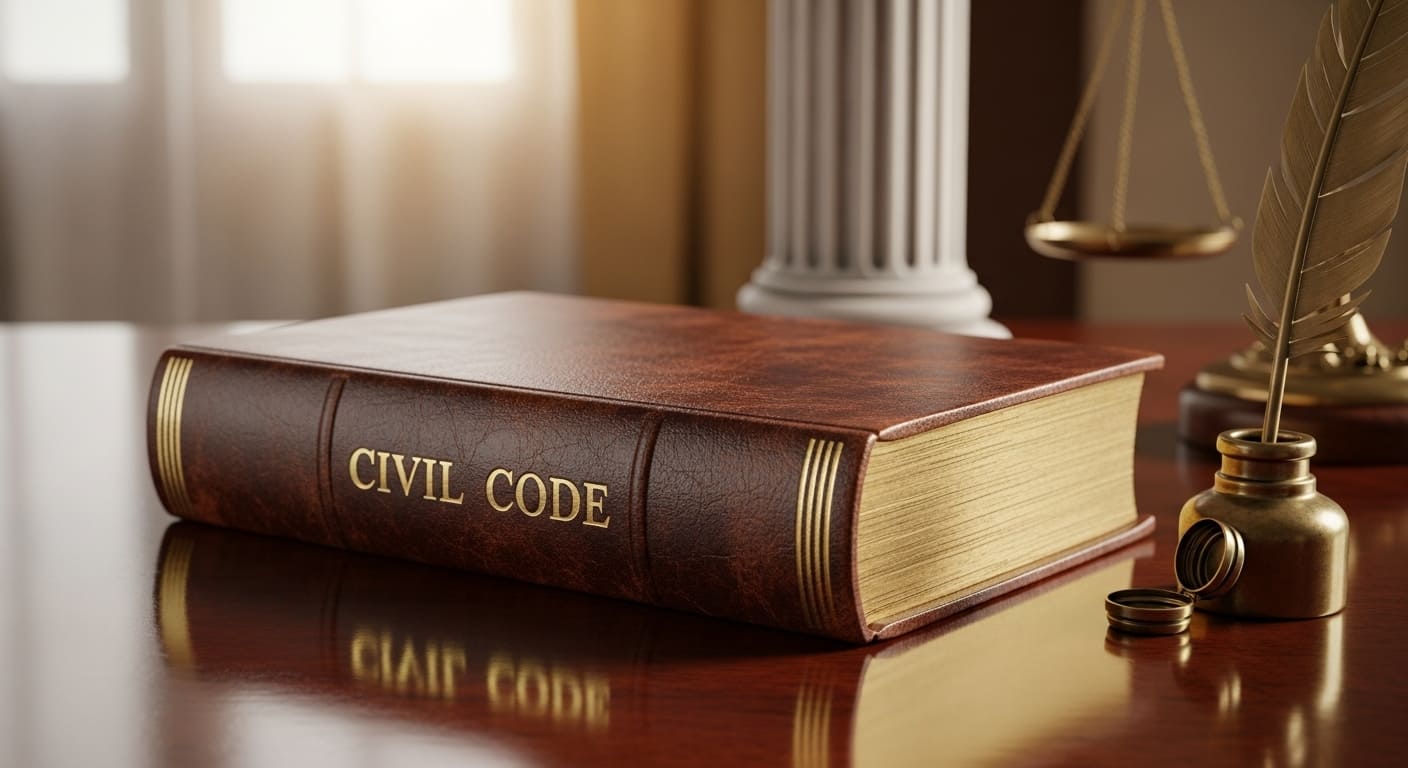 民法
民法 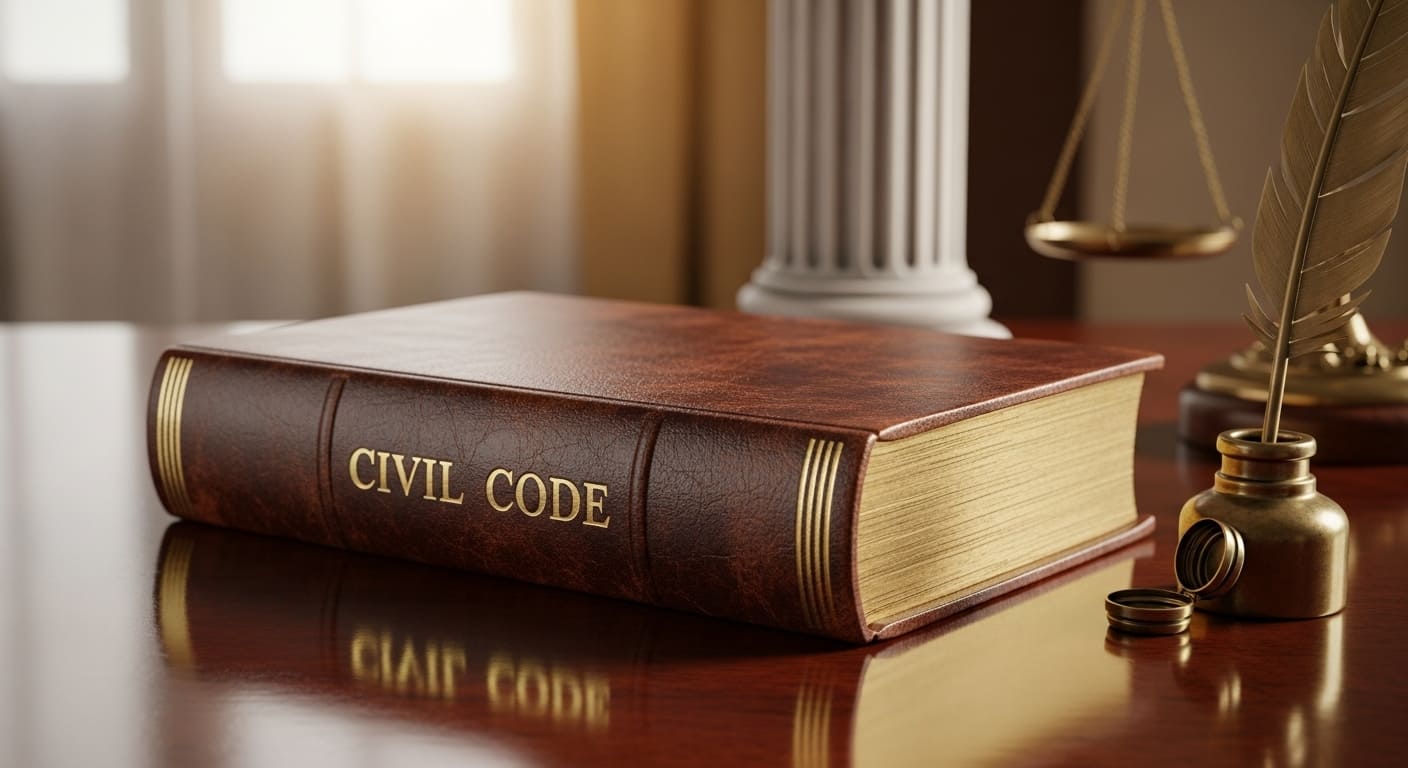 民法
民法 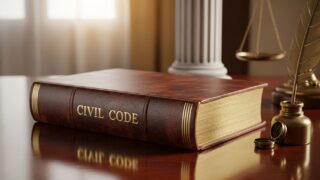 契約の効力
契約の効力 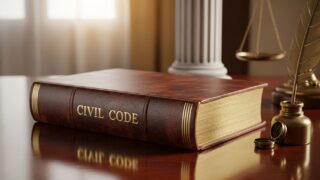 共同抵当
共同抵当 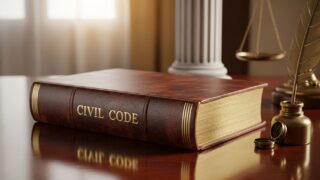 共同抵当
共同抵当 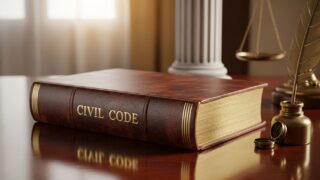 共同抵当
共同抵当 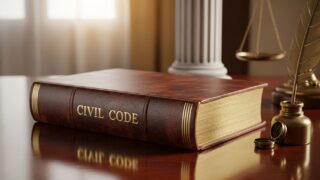 抵当権
抵当権 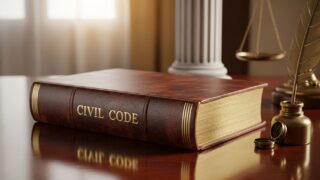 消費貸借
消費貸借 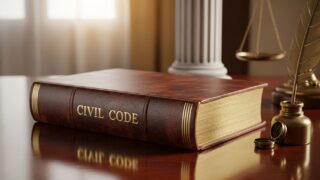 履行遅滞
履行遅滞 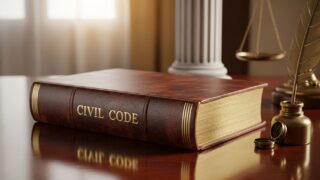 利息
利息 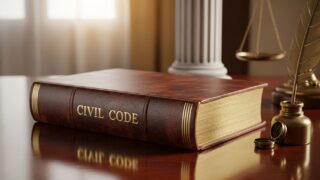 利息
利息 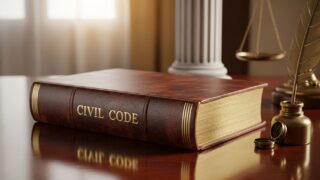 不当利得
不当利得