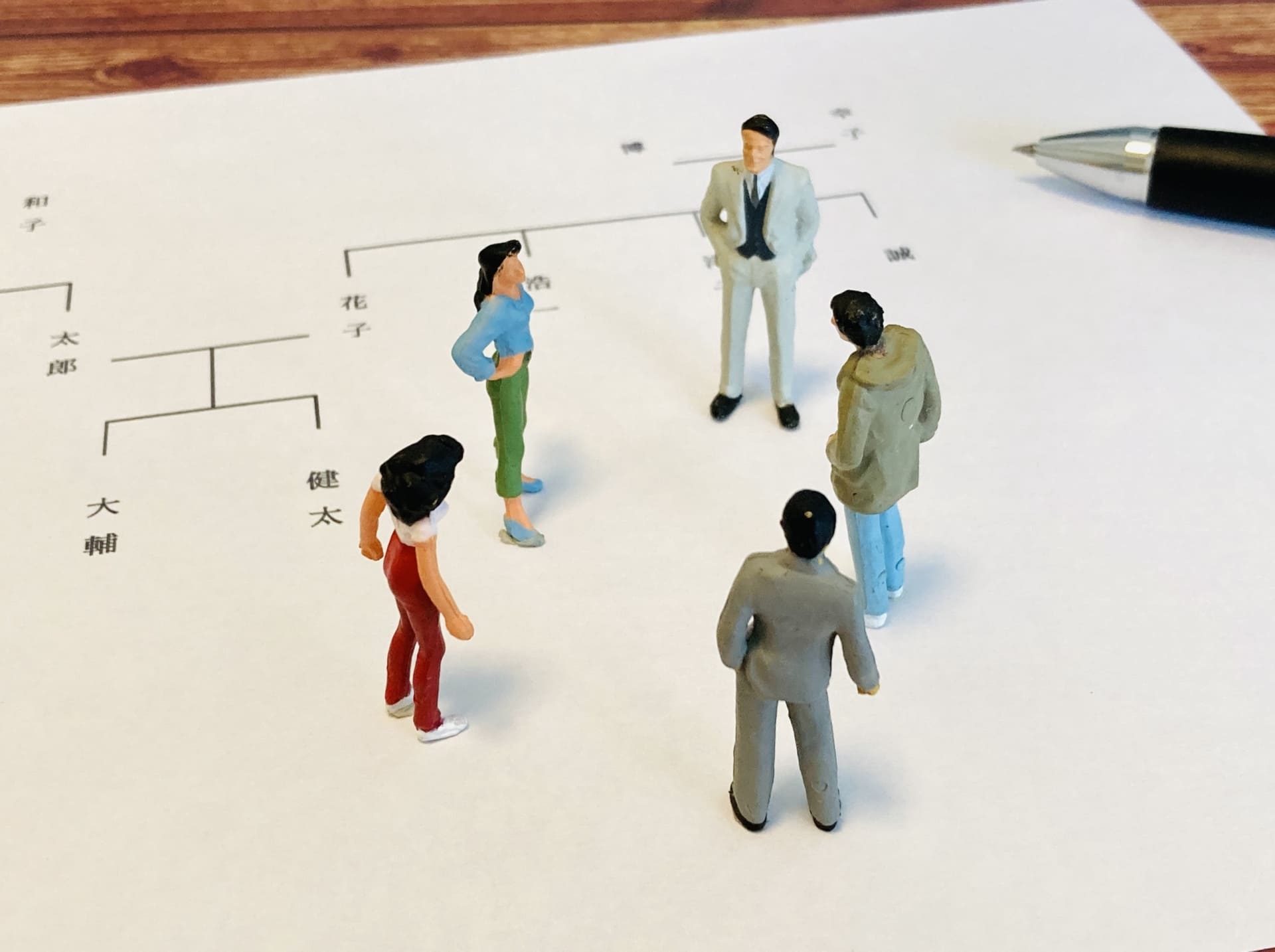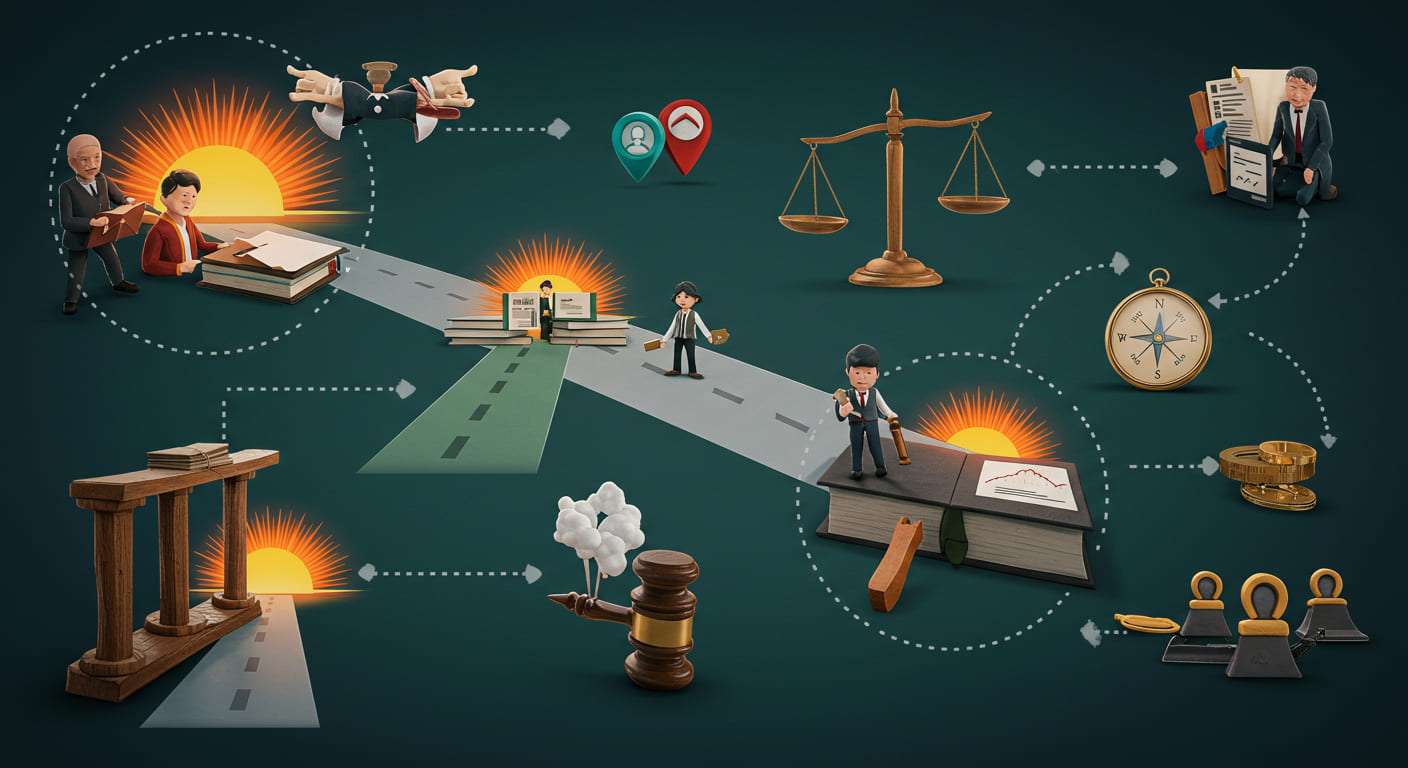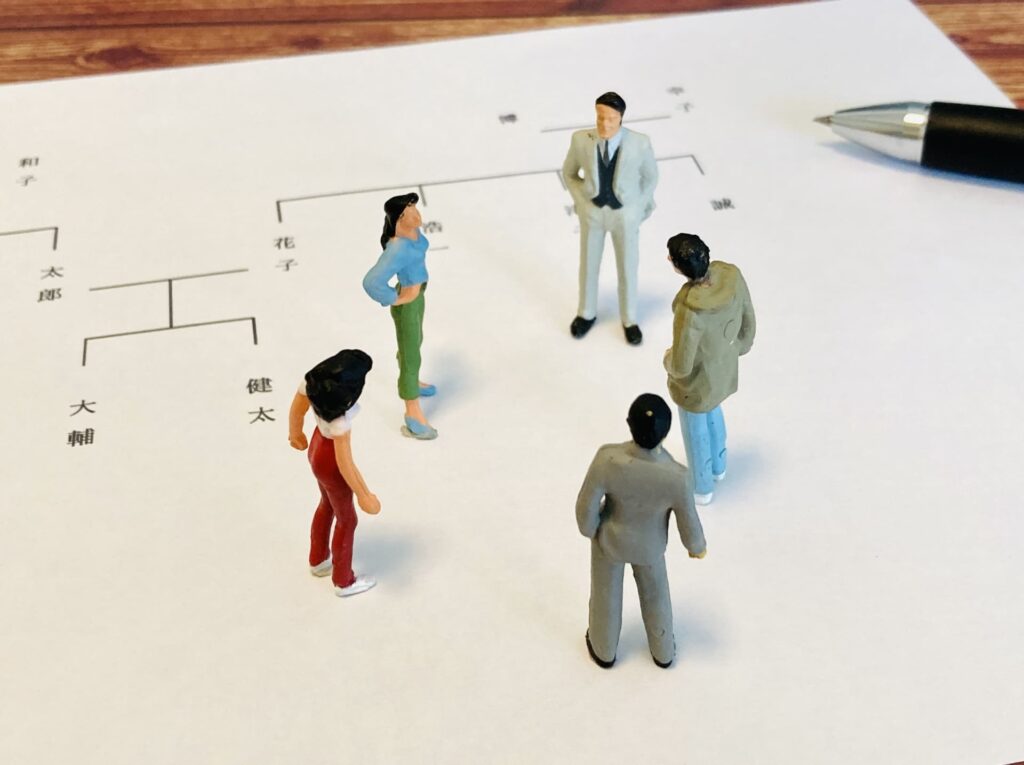
相続は、被相続人の死亡によって開始されますが、実際に死亡が未確認であっても死亡したものとして扱われ、それによって相続が開始されることがあります。具体的には、失踪宣告や認定死亡の制度があります。
相続の開始と死亡
民法 第882条
- 相続は、死亡によって開始する。
遺産の相続は,被相続人が死亡した時から開始されます(民法882条)。他に特に相続開始原因はありません。「被相続人の死亡」が唯一の相続開始原因です。
この相続開始原因たる「死亡」とは,基本的に生物学的・医学的な意味での死亡を意味します。ただし,具体的に,死亡とはどのような状態を意味するのかという,法的な議論があります。
一般的には,心臓の拍動停止,呼吸停止,瞳孔反射の消失(いわゆる「3徴候」)を基準としていますが,たとえば,脳死もここでいう「死亡」に含めるべきかというような議論もあります。
もっとも,これら生物学的・医学的意味での「死亡」の判断は,やはり専門家の意見を尊重すべきですから,医師の死亡診断書の記載に従うのが一般的でしょう。
被相続人の死亡が証明できない場合
上記のとおり,相続開始原因となる「死亡」とは,生物学的・医学的な意味での死亡を指すというのが原則です。
ところが,事故や災害などの場合,死亡したことはほとんど確実であるけれども,遺体を発見できないので,死亡したことを医学的に確実に証明することができない場合があり得ます。
このような場合,たとえば,遺体が発見されるまで待っていなければならないとすると,いつまでも相続の手続をとることができません。
そうなると,相続人だけでなく,被相続人に利害関係がある第三者も,不安定な状況に立たせてしまうおそれがあります。
そこで,上記のように死亡したことを確実に証明できないという場合でも相続を開始できるように,一定の要件を満たす場合には,その被相続人は死亡したものとして取り扱うことができるという法制度が用意されています。
被相続人が死亡したものとして扱う法制度
死亡したことを確実に証明できないという場合でも,ある人を死亡したものとして取り扱う法制度として,「失踪宣告」と「認定死亡」という制度があります。
失踪宣告とは,家庭裁判所によって失踪宣告という決定をしてもらうことにより,その宣告を受けた人を死亡したものとみなすという制度です。
失踪宣告の場合には,遺族などの利害関係人が,家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることになります。
認定死亡とは,死亡した可能性が極めて高いという推測に基づいて,ある人が死亡したことを推定するという制度です。
戸籍法上の制度で,遺体の発見ができないため診断書が作成できず死亡届を作成できないような場合に,官公庁の報告によって戸籍に死亡の記載をするための制度です。
失踪宣告の場合は,死亡と「みなす」ことになりますから,仮に宣告を受けた人が生きていたとしても,再度家庭裁判所に失踪宣告の取消をしてもらわなければなりません。
他方,認定死亡の場合にはあくまで死亡と「推定する」にすぎませんから,認定死亡とされた人が生きていたならば,そのことを証明すれば覆すことができます。