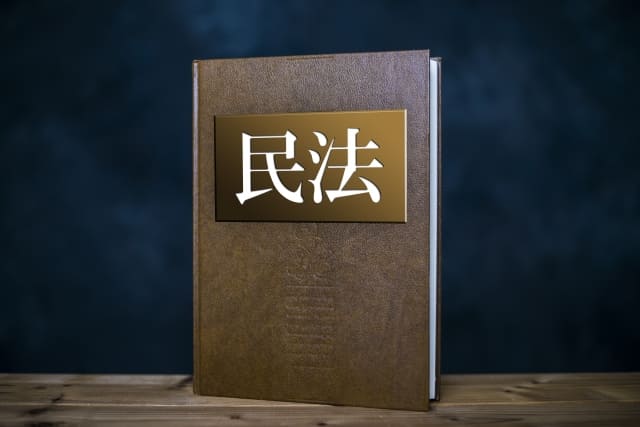遺産共有の記事一覧
相続人が複数人いる場合,相続が開始から遺産分割されるまでの間,相続財産は,共同相続人間での共有(または準共有)になるのが原則です。
遺産共有の記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
遺産共有の概要

前記のとおり、相続人が複数人いる場合,相続が開始から遺産分割されるまでの間,相続財産は,共同相続人間での共有(または準共有)になるのが原則です(民法898条1項)。
この場合に、相続財産について共有に関する規定を適用する場合には、それぞれの共同相続人の共有における権利の割合(持分)は,法定相続分または遺言による指定相続分に応じて決められることになります(民法898条2項)。
もっとも、金銭その他の可分債権は、遺産共有にならず、相続開始により、各共同相続人が相続分に応じて分割して承継すると解されています(ただし、預貯金債権は、分割ではなく準共有となります。)。