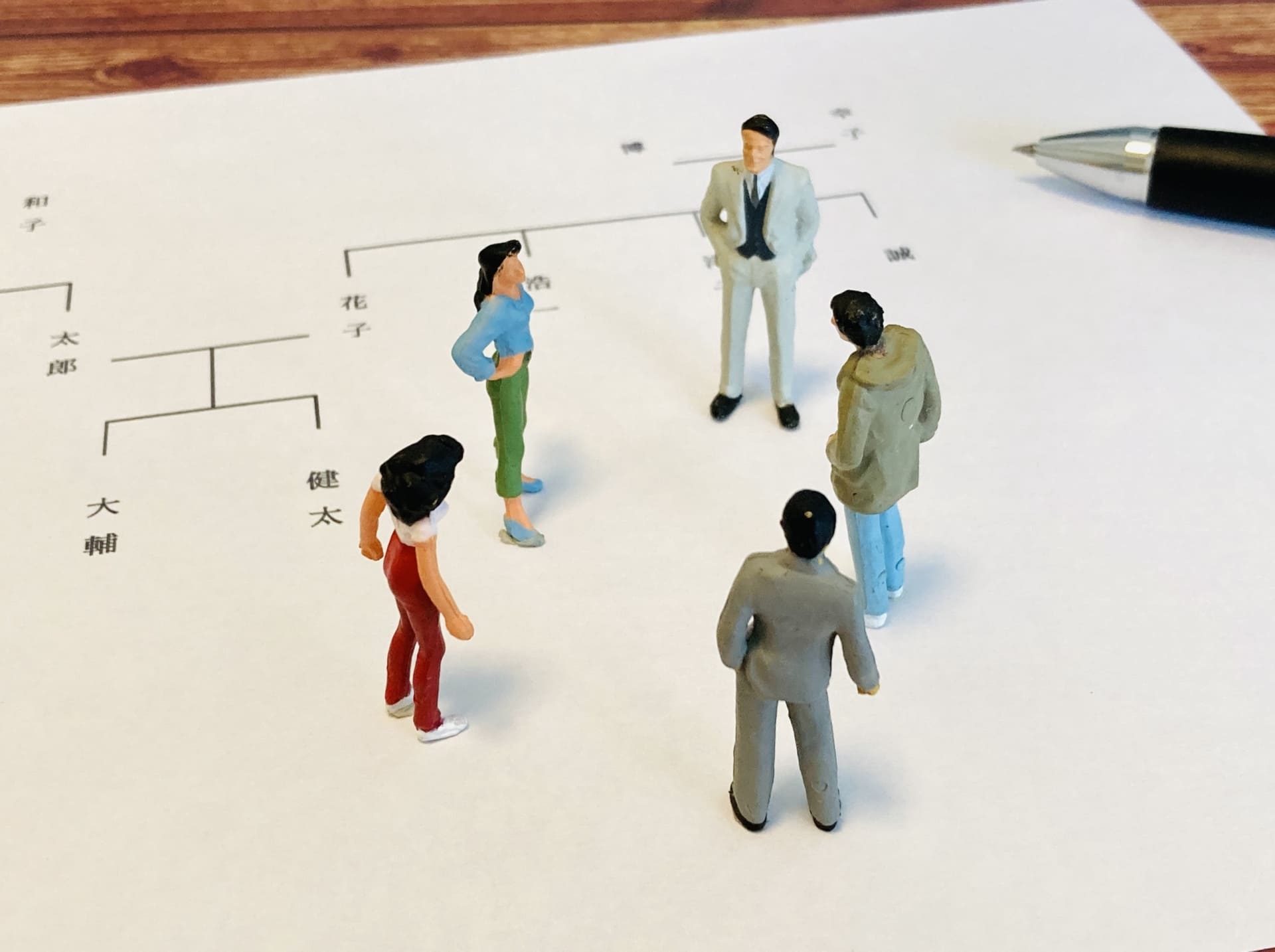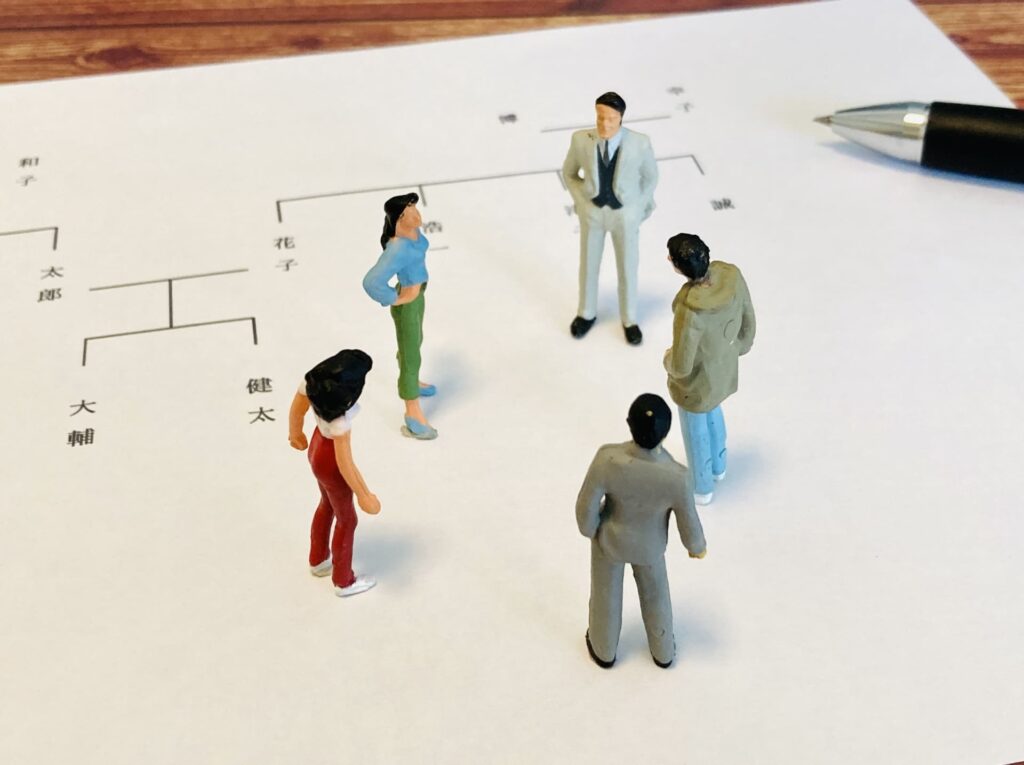
遺産分割の方法には,現物分割,代償分割,換価分割といった方法があります。現物分割が原則ですが,相続人間で合意がある場合には,現物分割以外の方法をとることも可能です。また,遺産の一部分割も認められています(民法907条)。
遺産分割の方法(遺産の分け方)
遺産争いが生じた場合,これを解決するための方法として「遺産分割」があります。
遺産分割とは,文字どおり,遺産(相続財産)を共同相続人に分配するという手続ですが,これには,さまざまな方法があります。
具体的には,遺産分割の方法として,現物分割・換価分割・代償分割などの方法があります。
現物分割
遺産分割方法の1つである「現物分割」とは,遺産に属する個々の財産をその形状や性質を変更することなく分割するという方法です。要するに,遺産の現物をそのまま分配する方法です。
遺産分割においては,できる限り遺産の現物をそのまま相続人に受け継がせるのが望ましい上,最も単純で分かりやすい方法であることから,現物分割が遺産分割方法の原則的な方法とされています。
例えば,相続財産として土地があったとして,その土地を分筆し,一部を共同相続人Aに,残部を共同相続にBに分割するというような場合です。
また,複数の相続財産がある場合に,その相続財産ごとに分割するのではなく,ある相続財産は共同相続人の一人に,別の相続財産は別の共同相続人に,というように財産の現物を個別に分割する場合もあります(「個別分割」と呼ばれることもあります。)。
例えば,相続財産として甲土地と乙土地があったとして,甲土地はAに,乙土地はBに分割するような場合です。
代償分割
遺産分割方法の1つに「代償分割」という方法があります。「債務を負担させる方法による遺産分割」とも呼ばれています。
代償分割とは,一部の相続人に相続分を超える額の財産を取得させる代わりに,他の相続人に対して超える部分の額に相当する代償金を支払う債務を負担させるという方法です。
例えば,共同相続人として子AとB(相続分はそれぞれ2分の1ずつ)がおり,相続財産として価値1000万円の土地があったとします。
この場合,現物分割であれば,この土地をAとBとで2分の1ずつ分割することになるでしょう。
しかし,Aがどうしても土地全部を利用取得したいという場合,Aとしては,分割というわけにはいきません。共有にすると不便ですし,換価もできません。
そこで,AがBに対して代償金としてBの相続分に相当する500万円を支払う代わりに,Aが土地の所有権の全部を取得するという方法が代償分割です。
なお,遺産分割審判においては,以下の要件を充たす場合でなければ,代償分割の方法はとれないと解されています。
- 以下の「特別の事情」があること(家事事件手続法195条)
- 現物分割が不可能である場合
- 現物分割をすると分割後の財産の経済的価値を著しく損なうため,不適当である場合
- 特定の遺産に対する特定の相続人の占有利用状態を特に保護する必要がある場合
- 共同相続人間に代償金の支払いの方法によることについて,概ね争いが無い場合
- 債務を負担することになる相続人に代償金を支払うだけの資力(支払能力)があること(最一小判平成12年9月7日・家月54巻6号66頁)
換価分割
遺産分割方法には「換価分割」という方法もあります。この方法は,相続財産を換価して,それによって取得した金銭を分配するという方法です。
相続財産や代償分割が困難である場合や共同相続人全員が望んでいる場合などには,この換価分割が用いられることがあります。
その他の分割方法
前記までに述べてきたとおり,遺産分割には様々な方法がありますが,もちろん,これのみに限るというわけではありせん。
遺産分割の手続は,基本的に,共同相続人間での話し合いによって定められるものですから,合意ができるのであれば,上記以外の方法での遺産分割も当然に可能です。
例えば,望ましくはないとされていますが,あえて遺産を相続分に応じて共有とする共有分割も可能です。
もちろん,法定相続分にこだわらない遺産分割も可能です。
例えば,共同相続人として子A・B・Cがいるという場合に,三者はそれぞれ3分の1ずつの相続分を有していますが,これを,Aは2分の1,BとCは4分の1ずつとすることも可能ですし,さらには,BとCは事実上相続をほとんどせず,Aにだけ遺産を集中させるというような分割も可能です(いわゆる「事実上の相続放棄」)。
ただし,審判となった場合には,相続分に応じた現物分割が原則とされています。
遺産の一部分割
民法 第907条
第1項 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
第2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
これまで述べてきた現物分割などの遺産の具体的な分け方とは異なりますが,遺産分割の方法として,遺産の一部だけを分割できるのかどうかという問題もあります。
紛争の一回的な解決からすると遺産の全部を遺産分割する方が望ましいことは間違いありません。
もっとも,全部の遺産を対象にすることによって,かえって解決が遅れてしまうこともあります。
また,遺産の処分権者はあくまで相続人ですから,共同相続人全員が一部分割を望む場合には,その意思を尊重する必要もあります。
そこで,改正民法(2019年7月1日施行)では,遺産の一部を他の遺産から独立して分割することが認められています(民法907条)。
ただし,遺産分割審判においては,遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には,一部分割は認められません(民法907条2項但し書き)。