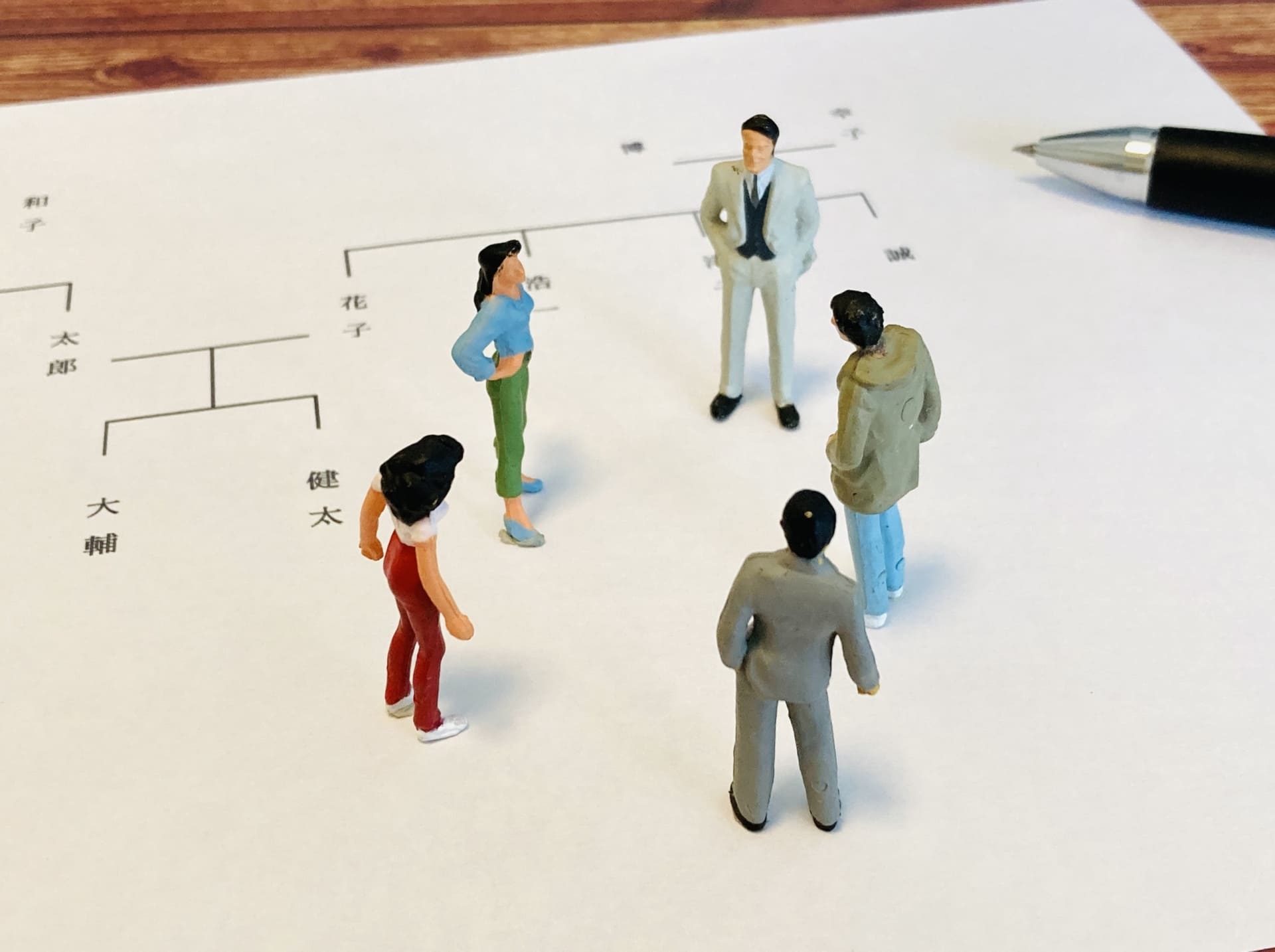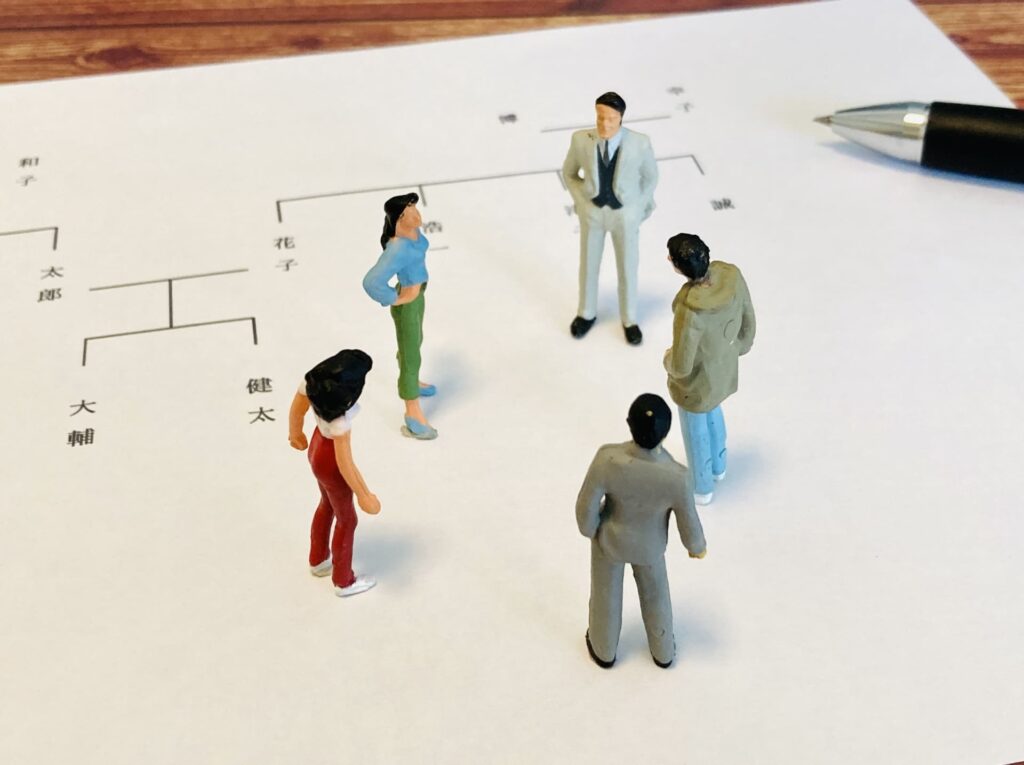
遺産分割審判は,家庭裁判所の裁判官が,審判という決定をもって,遺産分割方法を決めるという手続です。遺産分割審判で遺産分割をすることを「審判分割」といいます。
遺産分割審判・審判分割とは
民法 第907条
第1項 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
第2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
遺産(相続財産)について相続人間等で争いが生じてしまった場合には「遺産分割」の手続を行う必要があります。この遺産分割によって,どのように遺産を分けるのかを取り決めることになります。
遺産分割の具体的な手続としては,遺産分割の「協議」「調停」「審判」の3つがあります。このうち,協議は裁判外の手続ですが,調停と審判は家庭裁判所における裁判手続です。
遺産分割審判は,家庭裁判所の裁判(家事審判)手続です。協議や調停と異なり,家庭裁判所の裁判官が,審判という決定をもって,遺産分割方法を決めるという手続です。遺産分割審判で遺産分割をすることを「審判分割」といいます。
遺産分割調停との関係
遺産分割は,まず協議を行い,それが調わなかった場合に裁判手続を利用できることになっています(民法907条2項本文)。
遺産分割の裁判手続には,前記のとおり,調停と審判があります。もっとも,遺産分割事件では,まず審判前に調停を経なければならないという「調停前置主義」は採用されていません。
そのため,原則論でいえば,協議が不調の場合には,調停または審判のどちらでも申立てができるということになります。
もっとも,遺産分割事件は,家族・親族間の紛争ですから,話し合いになじみやすい事件類型です。
そこで,実際には,いきなり遺産分割審判を申し立てた場合でも,職権で調停に付されるというのが,一般的でしょう。その意味では,事実上,調停前置主義のような運用がとられているといえます。
したがって,はじめに遺産分割審判を申し立てた場合でも,裁判所の職権で調停に付され,調停が行われることになります。その調停が不調に終わった場合には,審判に戻ることになります。
また,はじめから遺産分割調停を申し立てていたという場合でも,調停が不成立になった場合には,調停の申立て時に審判の申立てもあったものとみなされるため,自動的に審判に移行することになります。
したがって,あらためて遺産分割審判申立てをする必要はありません。
遺産分割審判の手続
遺産分割審判の手続は,協議や調停と異なり,話し合いだけの手続ではありません。訴訟のように,各当事者が主張とそれを裏付ける証拠資料を提出し,それに基づいて裁判官が審判という判断をするという手続です。
とはいえ,遺産分割事件は話し合いになじむ事件類型ですから,審判においても,まったく話し合いがなされないというわけではありません。随時,裁判官をまじえた話し合いが行われるのが通常です。
協議や調停(審判手続中の調停も含む。)は,当事者の意思に基づく合意ですから,私的自治の原則によって,法定相続分や遺言と異なる遺産分割方法を定めることも可能です。自由度が高いということです。
しかし,遺産分割審判における分割(審判分割)は,合意に基づくものではなく,裁判官が他律的に決定するものですから,法定相続分を変更することはできませんし,遺言を尊重する必要もあります。
したがって,審判分割では,具体的相続分に即した共同相続人間の均衡を考慮して,相続分に従った分割が行われなければならないとされています(最高裁事務総局家庭局「昭和42年3月開催家事審判官会同概要」)。
要するに,遺産分割審判で認められるのは,遺言または法定相続分に基づく遺産分割です。ただし,もちろん,調停において合意に至っている事項や,特別受益や寄与分などの法的主張は取り入れられます。