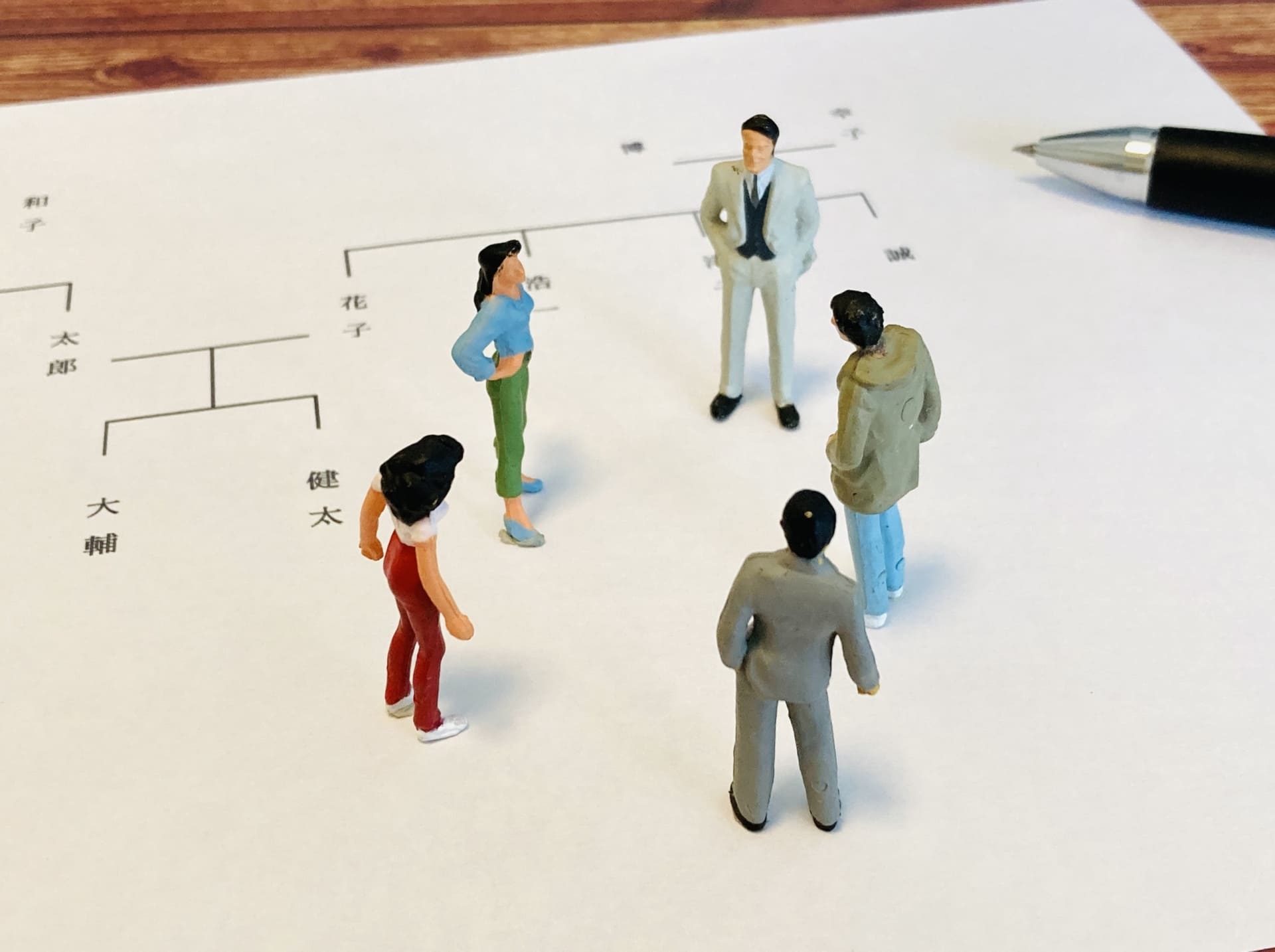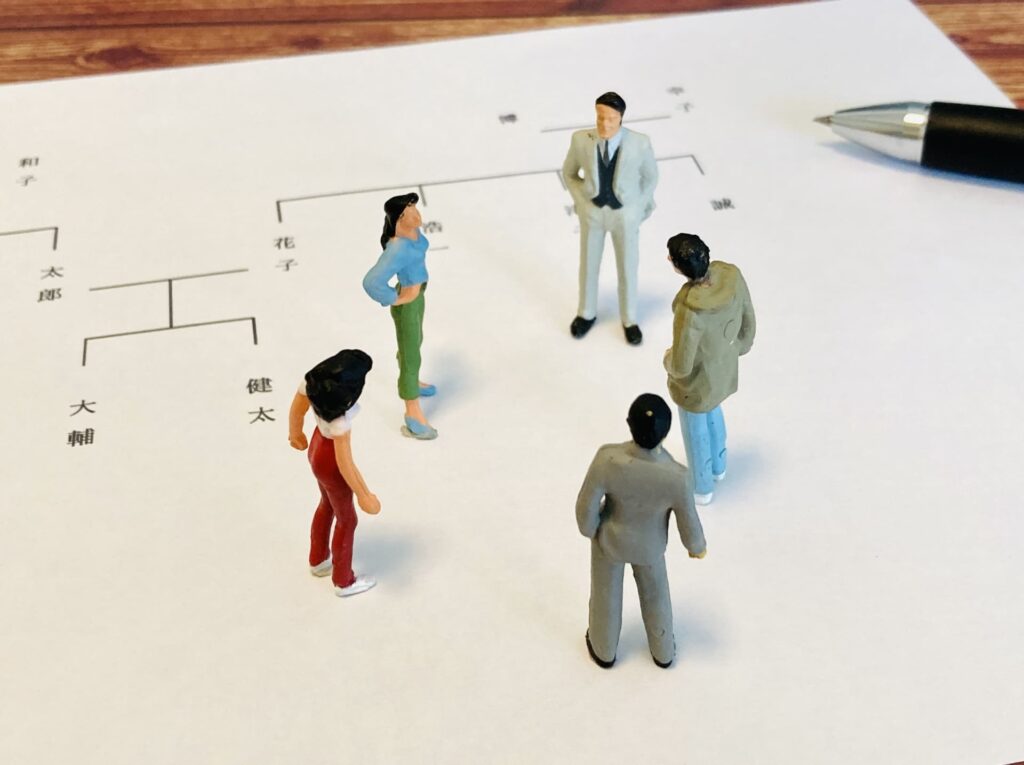
遺産分割の具体的な手続きとしては,相続人らによる遺産分割協議と,裁判手続である遺産分割調停や遺産分割審判によるものがあります。
遺産分割の各種手続
相続が開始されると,被相続人が有していた一切の権利義務は,被相続人の一身に専属するものを除いて,相続財産(遺産)として,相続人に包括的に承継されます(民法896条)。
相続人が複数人いる場合,相続財産は,原則として,その複数人の相続人(共同相続人)の間で共有(または準共有)とされます。
この共有とされた相続財産を各共同相続人に個別的に帰属させるための手続が「遺産分割」です。
遺産分割の具体的な手続きとしては,相続人らによる協議と,裁判手続である調停や審判によるものがあります。
加えて,相続開始後の手続ではないですが,被相続人が自ら遺産分割方法を遺言で定めておく遺産分割方法の指定も,この遺産分割の手続の1つといえるでしょう。
遺言による遺産分割方法の指定
民法 第908条
- 第1項 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 第2項 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 第3項 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
- 第4項 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 第5項 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
遺産を遺す側の方(被相続人となる人)は,遺言で,ご自身の意思を相続に反映させることができます。そして,この遺言では,相続が開始した後の遺産分割の方法についても定めておくことができます。これを「遺産分割方法の指定」といいます。
遺産分割方法の指定は,遺産争いが生ずる前に,遺産を遺す側の人が争いにならないように行うものですから,後述する協議・調停・審判などとは異なります。
遺産分割をするなら,このように分割してくださいと指定するものですので,遺産分割の手続そのものではなく,遺産の分け方それ自体を指定するというものですが,遺産分割に関連する手続とはいえるでしょう。
また,遺産分割は,相続開始後に共同相続人らが行うものですから,被相続人は当然のことながら関与できません。
したがって,この遺産分割方法の指定は,遺産分割について被相続人の意思を及ぼすことのできる手段として意味があるといえます。
ただし,被相続人は,遺言で,遺産分割方法の指定ではなく,もっと根本的に,相続分すら指定できるので,遺産分割方法の指定だけが被相続人の意思を相続に及ぼすものというわけではありません。
遺産分割の協議
民法 第907条
第1項 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
第2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
実際に相続が開始された場合には,各共同相続人への遺産分割をしなければなりません。
もっとも,相続の問題は,財産関係の問題であるとはいえ,やはり家族・親族の問題という側面も否定できません。「法は家庭に入らず」の原則もある程度は考慮する必要があります。
また,遺産分割事件の特性として,法律の規定で割り切った解決をすることが必ずしも妥当ではない場合が少なくないということもあります。
つまり,どちらかといえば,関係当事者による話し合いで解決する方が,多少は円満な解決になりやすいという面があるということです。
そのため,民法上,遺産分割をする場合には,いきなり裁判手続を利用することはできず,まずは,共同相続人間でどのように遺産分割をすべきかを協議すべきとされています。これを「遺産分割協議」といいます(民法907条1項)。
具体的には,遺産分割協議をしたものの話がつかなかった場合または協議に参加しない共同相続人がいるなど協議自体ができなかった場合にはじめて,遺産分割の裁判手続を利用できるものと定められています(民法907条2項)。
協議は,あくまで裁判外での話し合いですから,基本的には,共同相続人だけで行われることになります(もちろん,第三者に間に入ってもらってもかまいません。)。
ただし,協議が成立したら,その後で言った言わないの紛争の蒸し返しが生じないように,遺産分割の協議書を作成しておくべきでしょう。できれば,公正証書にしておくのがよいと思います。
共同相続人間の親密さが高い場合や紛争性が小さい場合における相続については,おそらく,ほとんどの場合,この協議によって解決していると思われます。
協議による遺産分割のことを「協議分割」と呼ぶことがあります。
遺産分割の調停
家事事件の場合,審判を行う前に,必ず調停を行わなければならないという類型の事件があります。このことを「調停前置主義」といいます。
遺産分割の場合には,この調停前置主義は適用されません。したがって,協議が調わなかったり,協議ができなかった場合には,いきなり,家庭裁判所に審判を申し立てることも可能です。
もっとも,前記のとおり,遺産分割事件は話し合いに向いている類型の事件ではあります。
そのため,調停を経ずに審判を申し立てたとしても,家庭裁判所の職権で,まずは調停が行われることになる(これを「調停に付される」ということがあります。)のが通常です。
遺産分割調停とは,話し合いです。ですが,協議の場合と異なり,共同相続人だけで話し合いをするわけではなく,裁判官または裁判所が選任した調停委員が間に入って,相続人間の話し合いを調整していくことになります。
裁判官はもちろん,調停委員も,弁護士等の相続実務に通じた人が選任されることになっていますので,法律の定めや裁判例・実際の解決事例などを踏まえて話し合いをすすめていくことになります。
そのため,多分に感情的になりやすい当事者だけでの話し合いよりも,客観的な意見や合理的な意見が提案されていくことになります。それだけに,話がつく可能性が高くなります。遺産分割の裁判の大半が,この調停で解決していきます。
調停による遺産分割のことを「調停分割」と呼ぶことがあります。
遺産分割の審判
遺産分割審判とは,調停と異なり,裁判官が遺産分割方法を決定するという裁判です。
前記のとおり,遺産分割については調停前置主義がとられていないので,調停を経ずに審判を申し立てることができます。
もっとも,通常の場合は,まず調停に付されることになりますので,調停が不成立の場合に,はじめて審判が行われることになるでしょう。
審判では,訴訟の場合と同じように,各共同相続人が,それぞれに主張とそれを裏付ける資料を提出します。裁判官は,それらをもとに審判を下します。
もっとも,審判が開始された後も,話し合いがもたれることはよくあることです。そして,その話し合いも考慮に入れて審判が下されることになります。遺産分割の最終的な手段といえるでしょう。
ただし,協議や調停で解決することがほとんどですので,審判まで行くというのは,もはや話し合いは全く不可能なほどにかなり激烈に争われているなど,稀な場合でしょう。
審判による遺産分割のことを「審判分割」と呼ぶことがあります。