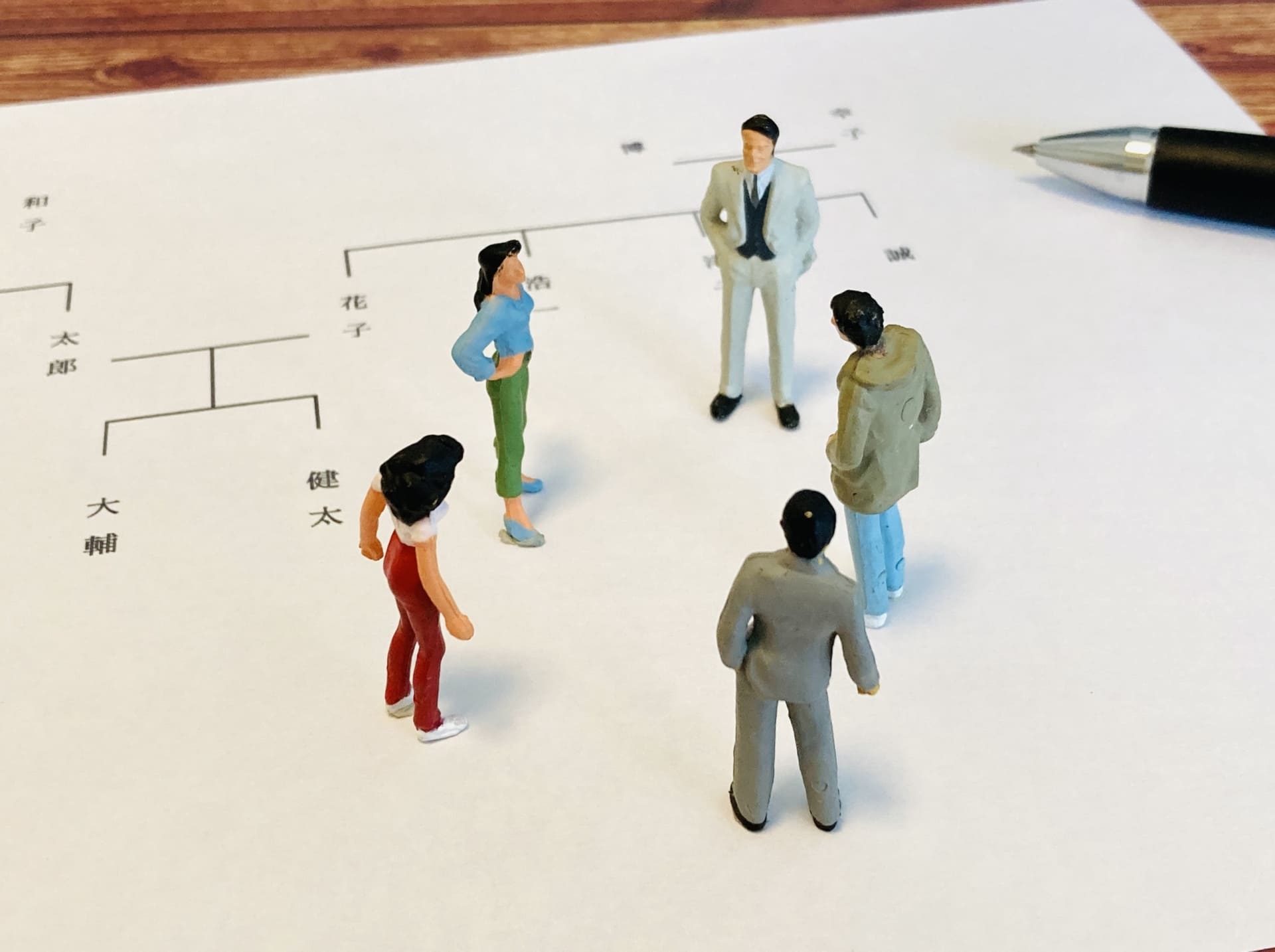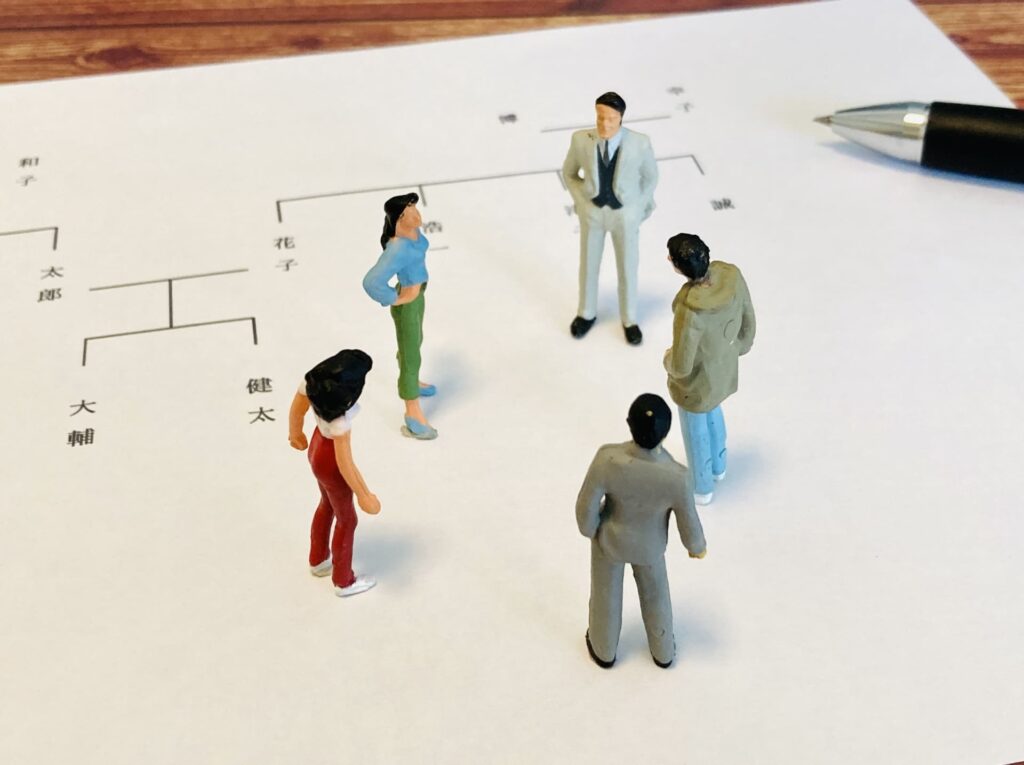
相続財産であっても,金銭その他の可分債権は,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日,最判平成16年4月20日等)。したがって,金銭その他の可分債権は,遺産分割の対象にはならないのが原則です。
ただし,共同相続人全員が同意すれば,可分債権を遺産分割の対象にすることは可能です。なお,可分債権のうち預貯金債権については,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると解されています(最大判平成28年12月19日,最一小判平成29年4月6日)。
相続における金銭その他の可分債権
民法 第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。民法 第898条
第1項 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第2項 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。民法 第899条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
相続が開始されると,被相続人が有していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されます(民法896条)。
相続人が複数いる場合には,その相続財産は,遺産分割によって具体的な相続分が確定するまでの間,各共同相続人にその各自の相続分に応じて共有になるのが原則です(民法898条,899条)。
もっとも,金銭債権に代表される可分債権は,遺産分割を経ずとも,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日,最三小判平成16年4月20日等)。
たとえば,相続財産として1000万円の金銭債権があり,相続人として,相続分4分の3のAと,相続分4分の1のBがいたという場合,遺産分割を経ずに,相続開始によって,Aに750万円の,Bに250万円の金銭債権が相続されるということです。
遺産分割における金銭その他の可分債権の取扱い
前記のとおり,金銭その他の可分債権は,相続の開始によって,遺産分割を経ることなく,各共同相続人に対して,それぞれの相続分に応じて当然に分割されて帰属することになります。
したがって,金銭その他の可分債権については,遺産分割をする必要がないのが原則です。各共同相続人は,各自で,分割相続された金額を債務者に請求すればよいだけになるということです。
ただし,共同相続人全員が同意すれば,金銭その他の可分債権を遺産分割の対象にすることができます。
預貯金債権の取扱い
この可分債権のうちで,特に問題となることが多いものは,やはり預金・貯金払戻請求権(預貯金債権)でしょう。
預貯金債権とは何かというと,要するに,被相続人名義の銀行などの預貯金口座からお金を引き出す権利(債権)ということです。
預貯金債権については,かつては,他の可分債権と同様,遺産分割の対象にならないと解されていました(最三小判平成16年4月20日等)。
しかし,預貯金は,決済機能が重視され,現金とそれほど異ならないものとして扱われているのが通常であることなどから,現在では,預貯金払戻請求権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると解されるようになっています(最大判平成28年12月19日,最一小判平成29年4月6日)。
したがって,可分債権は遺産分割の対象にならないのが原則であるものの,例外的に,可分債権の内でも預貯金債権については遺産分割の対象になる,ということになります。
相続財産である預貯金の払戻し
民法 第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治29年法律第89号)第909条の2の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。
預金・貯金の債権が遺産分割の対象になるとすると,金融機関側としては,当然,遺産分割が確定するまでは払い戻しに応じないという対応になるでしょう。
とはいえ,被相続人の葬儀費用などのために,遺産分割前に急いで預貯金を引き出さなければならない場合もあります。
そこで,改正民法(2019年7月1日から施行)では,新たに,仮払いの制度が設けられました。
具体的には,各共同相続人は,150万円を上限として,相続開始時における預貯金債権額の3分の1に自身の法定相続分を乗じた金額までなら,それぞれ単独で預金・貯金の払戻しができるようになりました(民法909条の2前段,民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)。
150万円を超える金額を払い戻すためには,上記の仮払いではなく,家庭裁判所における遺産分割前の預貯金債権仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)などを利用することになります。
最大判平成28年12月19日の預貯金債権以外への適用の是非
前記のとおり,最大判平成28年12月19日により,預貯金債権については,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと判断されました。
この最大判平成28年12月19日では,預貯金債権以外の可分債権についての判断はされていません。
したがって,預貯金債権以外の可分債権については,従前どおり,遺産分割の対象にはならないと考えられています。
ただし,上記最大判平成28年12月19日においては,預貯金以外の可分債権を遺産分割の対象とすべきとの意見も補足意見も付されており,今後は,預貯金以外の可分債権を遺産分割においてどのように扱うべきかが議論の対象となっていくと思われます。