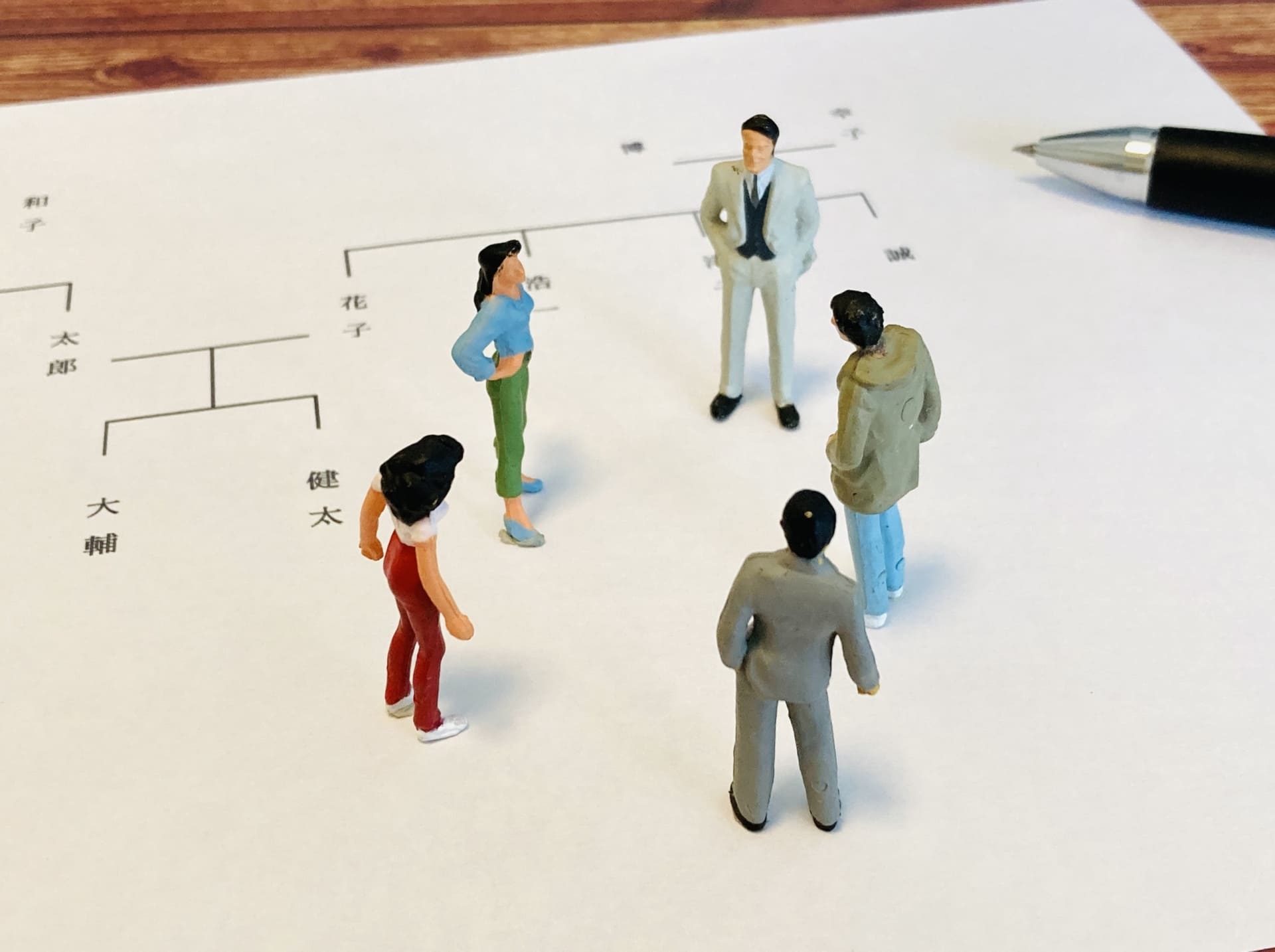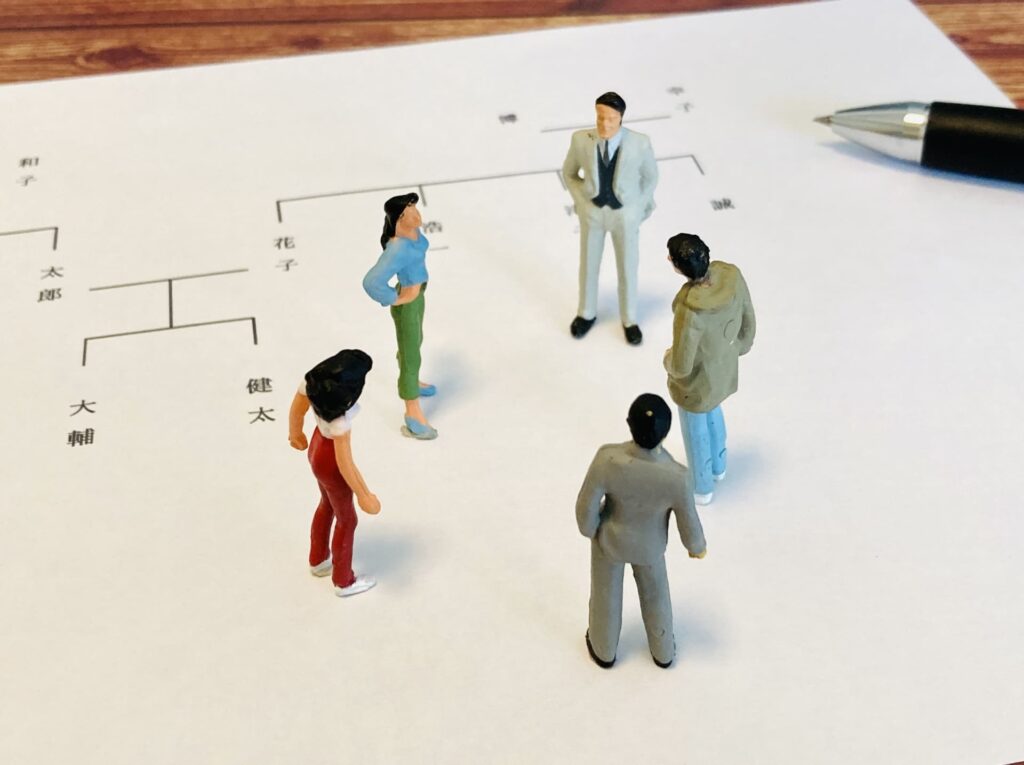
遺産分割の対象となる財産の範囲の確定の基準時は,遺産分割時と解するのが一般的です。また,遺産分割の対象となる財産の評価の確定の基準時も,同様に,遺産分割時と解するのが一般的です。
ただし,相続人間の合意によって,遺産分割対象財産の範囲や評価の確定の基準時を,遺産分割時とは別の時期に定めることは可能です。
遺産分割の対象となる財産の確定
遺産分割の紛争を解決するためには,そもそも遺産分割の対象となる財産の範囲やその価額評価を確定させておく必要があります。
もっとも,時期によっては,財産の存否の問題が生じてしまっている場合もあります。たとえば,相続開始の時には現存していたものの,遺産分割時には滅失してしまっているというような場合です。
このような場合,どの時点における財産を遺産分割対象財産として扱うのかということによって,遺産分割の内容も変わってきます。
前記の例でいえば,相続開始の時点を基準とすれば,当該財産は遺産分割の対象となり得ますが,遺産分割時を基準とすれば,当該財産はすでに滅失しているため,遺産分割の対象にならないということになります。
また,財産の評価についても変更が生ずることがあります。たとえば,不動産などは時期によってその価額が変わってきますから,どの時点を評価の基準とするのかによって,遺産分割の内容も変わってきます。
そこで問題となるのは,どの時点における財産を遺産分割の対象とし,また評価するのかということです。すなわち,遺産分割対象財産の範囲・評価の基準時をどの時点に設定するのかという問題です。
遺産分割対象財産の範囲確定の基準時
前記のとおり,どの時点を遺産分割対象財産の範囲を確定するのかに関する基準時とするのかということは,遺産分割をするに当たって大きな問題です。
この問題については,基準時を相続開始時とする見解(相続開始時説)と遺産分割時とする見解(遺産分割時説)とがありますが,実務では,遺産分割時説がとられています。
したがって,遺産分割審判がなされる場合,基本的に,遺産分割対象財産の範囲の確定時期は,その審判の時ということになります。
もっとも,遺産分割協議や遺産分割調停において,当事者間で,遺産分割対象財産の範囲確定の基準時を相続開始時とするという合意をすることは,もちろん自由です。
当事者間でそのような合意がなされれば,遺産分割の基準時は相続開始時ということになります。
もっといえば,もし相続人間で話がつくのであれば,相続開始時であろうと,遺産分割時であろうと,それ以外の時期であろうとかまわないということです。
結局,基準時が問題となるのは,相続人間で話がつかずに審判となった場合ということです。
ただし,遺産分割審判には既判力がありません。要するに,審判で遺産分割対象財産の範囲を決めたとしても,遺産確認訴訟によって覆されてしまうおそれがあるということです。
そのため,特定の財産が遺産分割対象財産に含まれるかどうか自体について争いがある場合には,まず遺産確認の訴えを提起すべきであるということになります。
遺産分割対象財産の評価確定の基準時
遺産分割対象財産の範囲は,遺産分割時に確定させるということであるとしても,その財産の価額をどの時点で評価すべきかということは,一応別の問題です。
これについても,やはり相続開始時説と遺産分割時説とがありますが,遺産分割対象財産の範囲確定の基準時と評価基準時を異ならせるのは不自然ですから,実務上,評価の基準時についても,遺産分割時説が採用されています。
したがって,審判の場合であれば,遺産分割対象財産は遺産分割時の価額をもって評価されることになります。
ただし,遺産分割協議・調停の場合には,相続人間の話し合いで,どの時点を評価の基準時とするかも決めることができます。
理屈で言えば,相続人間の話し合いで,遺産の範囲の確定の基準時と評価の基準時を別々に定めることも可能です。
しかし,範囲と評価を別個にするのは不自然ですし,かえって紛争を大きくしてしまうおそれがありますから,遺産の範囲の確定と評価の基準時は同じ時期とするのが通常です。