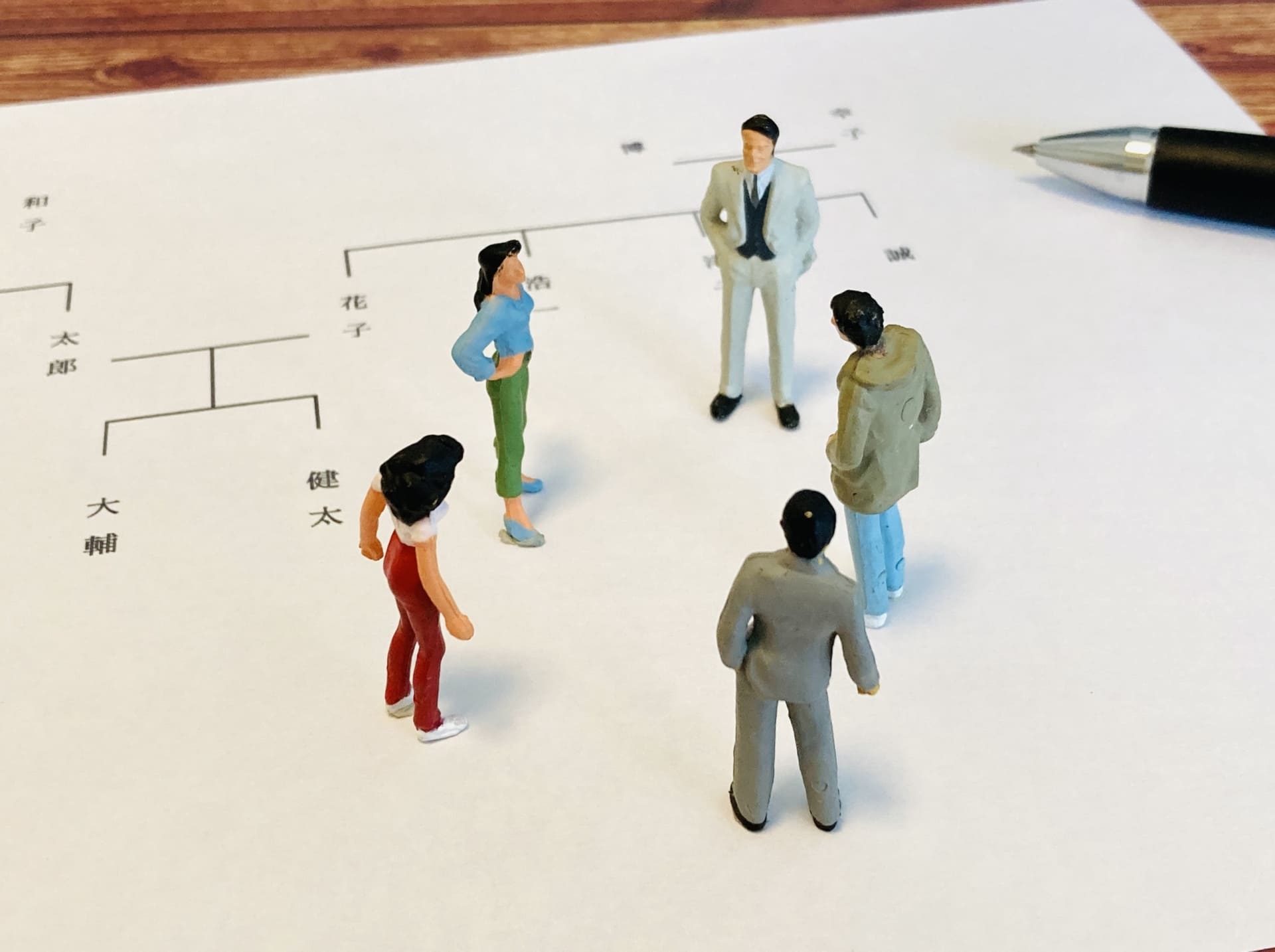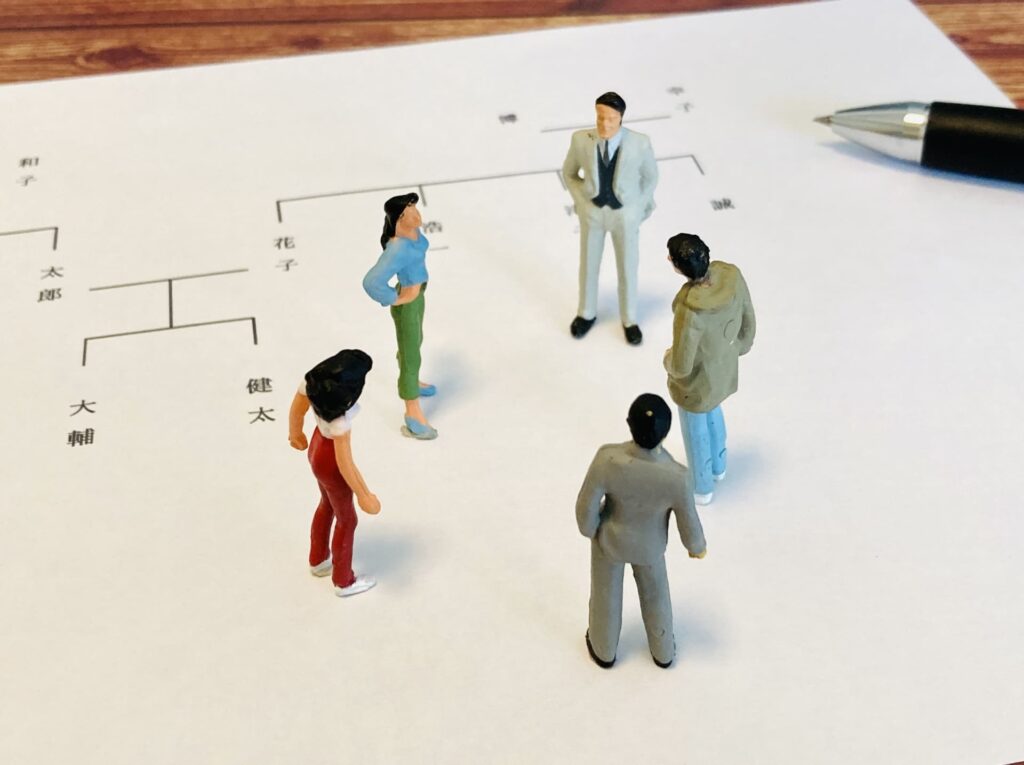
相続財産として最も典型的なものといえば,やはり預金・貯金(預貯金債権)でしょう(なお,ここでいう預金・貯金は,金融機関に預けている預金・貯金です。)。
預金・貯金(預貯金債権)は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されています(最大判平成28年12月19日,最一小判平成29年4月6日)。
実際の預金・貯金の遺産分割においては,相続人の誰か1人に預貯金口座を帰属させた上で,過不足を代償金として支払う形で調整することが多いと思われます。
預金・貯金の法的意味
相続財産のうちで最も典型的なものは,預金・貯金ではないでしょうか(※なお,ここで言う預金・貯金とは,銀行などの金融機関に預け入れている預金・貯金のことです。現金として保管している,いわゆる「タンス預金」のことではありません。)。
預金・貯金を実際に金銭を管理保管しているのは銀行等です。預貯金があるということは,つまり,銀行等が保管している金銭を払い戻す権利があるということです。
したがって,法的にいえば,預金や貯金というものは,預けている銀行等に対してその預貯金の払戻しを請求できるという請求権(債権)のことなのです。
そのため,預金・貯金(預貯金債権)は,現金と異なる取り扱いがなされることになります。
相続における預貯金債権の取扱い
民法 第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。民法 第898条
第1項 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第2項 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。民法 第899条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
相続が開始されると,相続財産は,遺産分割によって各共同相続人の具体的な相続分が確定するまでの間,各自の相続分(指定相続分または法定相続分)に応じて共有とされるのが原則です(民法898条1項)。
もっとも,例外はあります。それが「可分債権」です。可分債権の典型例は「金銭債権」です。
金銭債権その他の可分債権は,他の相続財産と異なり,相続開始によって当然に分割され,各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて分割された債権を取得するものとされています(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日,最三小判平成16年4月20日等)。
預貯金払戻請求権(預貯金債権)も金銭債権ですから,可分債権に含まれます。したがって,預貯金債権も遺産分割の対象にならないはずです。
実際,かつては,最高裁判例においても,預貯金払戻請求権は遺産分割の対象とならないと解されていました(最三小判平成16年4月20日等)。
もっとも,預貯金は,決済機能が重視され,現金とそれほど異ならないものとして扱われているのが通常です。
そこで,現在では,預貯金払戻請求権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されるようになっています(最大判平成28年12月19日,最一小判平成29年4月6日)。
預金・貯金の遺産分割
前記のとおり,現在では,預金・貯金も遺産分割の対象になります。
預金・貯金の残高は,通帳を記帳して確認すればすぐに分かります。通帳がない場合には,金融機関から取引明細や残高証明を取り寄せることになります。財産評価は容易です。
具体的な分割方法としては,金額ごとに配分するという方法も考えられますが,端数の処理などが煩雑になります。
そのため,相続人の誰か1人に預貯金口座を帰属させた上で,過不足を代償金として支払う形で調整することが多いと思われます。
相続開始後遺産分割前に預貯金の払戻しをした場合
民法 第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治29年法律第89号)第909条の2の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。
前記のとおり,預金・貯金(預貯金債権)も遺産分割の対象になりますから,相続開始後は,遺産分割が確定するまで,共同相続人のうち誰か1人単独で預金・貯金の払い戻しはできないのが原則です。
実際,金融機関側も,共同相続人全員の同意がない限り,共同相続人単独での払戻しには応じないのが通常でした。
もっとも,葬儀費用などが急ぎ必要となるため,遺産分割の確定や共同相続人全員の同意を取り付けている時間がないこともあり得ます。
改正民法(2019年7月1日から施行)では,新たに,預貯金債権の一部行使の制度が設けられました。
具体的には,各共同相続人は,150万円を上限として,相続開始時における預貯金債権額の3分の1に自身の法定相続分を乗じた金額までなら,それぞれ単独で預金・貯金の払戻しができるようになりました(民法909条の2前段,民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)。
150万円を超える金額を払い戻すためには,上記の預貯金債権一部行使ではなく,共同相続人全員の同意を得て払い戻しをしてもらうか,家庭裁判所における遺産分割前の預貯金債権仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)を利用することになります。
民法909条の2を利用した場合の預貯金の遺産分割
前記のとおり,各共同相続人は,民法909条の2に基づく預貯金債権の一部行使制度を利用して,それぞれ単独で一定額の預金・貯金の払戻しを受けることが可能となりました。
この預貯金債権の一部行使制度を利用した場合,払戻しを受けた金額について,その共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなすものとされています(民法909条の2後段)。
したがって,預貯金債権の一部行使制度による払戻しは,遺産分割の対象にはなりません。
もっとも,払戻額が預貯金債権の一部行使制度を利用した相続人の具体的相続分を超えていた場合には,後の遺産分割において,その超過部分についての精算が必要となります。
仮分割仮処分を利用した場合の預貯金の遺産分割
相続開始後遺産分割前の預貯金払戻しにおいて,預貯金債権の一部行使制度ではなく,家庭裁判所の仮分割仮処分を利用した場合は,あくまで仮に払戻しを受けたに過ぎないので,その払戻した預金・貯金も遺産分割の対象になります。
つまり,仮分割仮処分による払戻しがなかったものとして預金・貯金を遺産分割することになります。
なお,この場合も,払戻額が仮払いを利用した相続人の具体的相続分を超えていた場合には,後の遺産分割において,その超過部分についての精算が必要となります。
第三者に対する権利主張
遺産分割により取得した預金・貯金(の払戻請求権)を第三者に主張することができるかどうかについては,その第三者が権利関係に介入してきたのが遺産分割前なのか,それとも遺産分割後なのかによって異なってきます。
遺産分割前の第三者
民法 第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
遺産分割前に預金・貯金(の払戻請求権)について権利関係を有するに至った第三者(以下「遺産分割前の第三者」と言います。)は,民法909条ただし書きの「第三者」として保護されます。
この場合,遺産分割前の第三者が預金・貯金につき対抗要件を備えると,遺産分割により預金・貯金を取得した相続人は,その第三者に対して当該預金・貯金が自分に帰属することを主張できなくなってしまいます。
例えば,遺産分割前に,相続財産である預金・貯金を,共同相続人のうちの1人に対して債権を有する債権者が差し押さえ,その差押えの通知が銀行に送達された場合,遺産分割により預金・貯金を取得した相続人は,その債権者に対して差し押さえられた部分の預金・貯金は自分のものであると主張できなくなります。
遺産分割後の第三者
民法 第899条の2
第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
第2項 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
遺産分割が終わった後に預金・貯金(の払戻請求権)について権利関係を有するに至った第三者(以下「遺産分割後の第三者」と言います。)は,民法909条ただし書きの「第三者」には当たりません。
しかし,相続による権利の承継は,法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができないとされています(民法899条の2第1項)。
したがって,遺産分割により預金・貯金を取得したとしても,その払戻請求権について対抗要件を備えておかなければ,相続人は,その第三者に対して,法定相続分を超える部分について預金・貯金が自分のものであることを主張できなくなってしまいます。
債権の債務者に対する対抗要件は,債務者への通知または債務者からの承諾(民法467条1項)です。第三者に対する対抗要件は,確定日付のある証書による債務者への通知または債務者からの承諾(同条2項)です。
対抗要件を備えるための具体的な方法としては,預貯金払戻請求権の場合,債務者は当該預金口座を開設している銀行等の金融機関ですから,その金融機関に対し,共同相続人全員が,遺産分割により承継した旨の通知を配達証明付きの内容証明郵便で郵送するのが原則です。
もっとも,共同相続人全員が通知をしなくても,法定相続分を超える部分を取得した相続人が,遺産分割の内容を明らかにして確定日付のある証書による通知をすれば,共同相続人全員が通知をしたものとみなされます(民法899条の2第2項)。
他方,法定相続分の部分については,対抗問題とはなりません。共同相続人は,対抗要件を備えなくても,法定相続分については第三者に対して権利を主張できます。