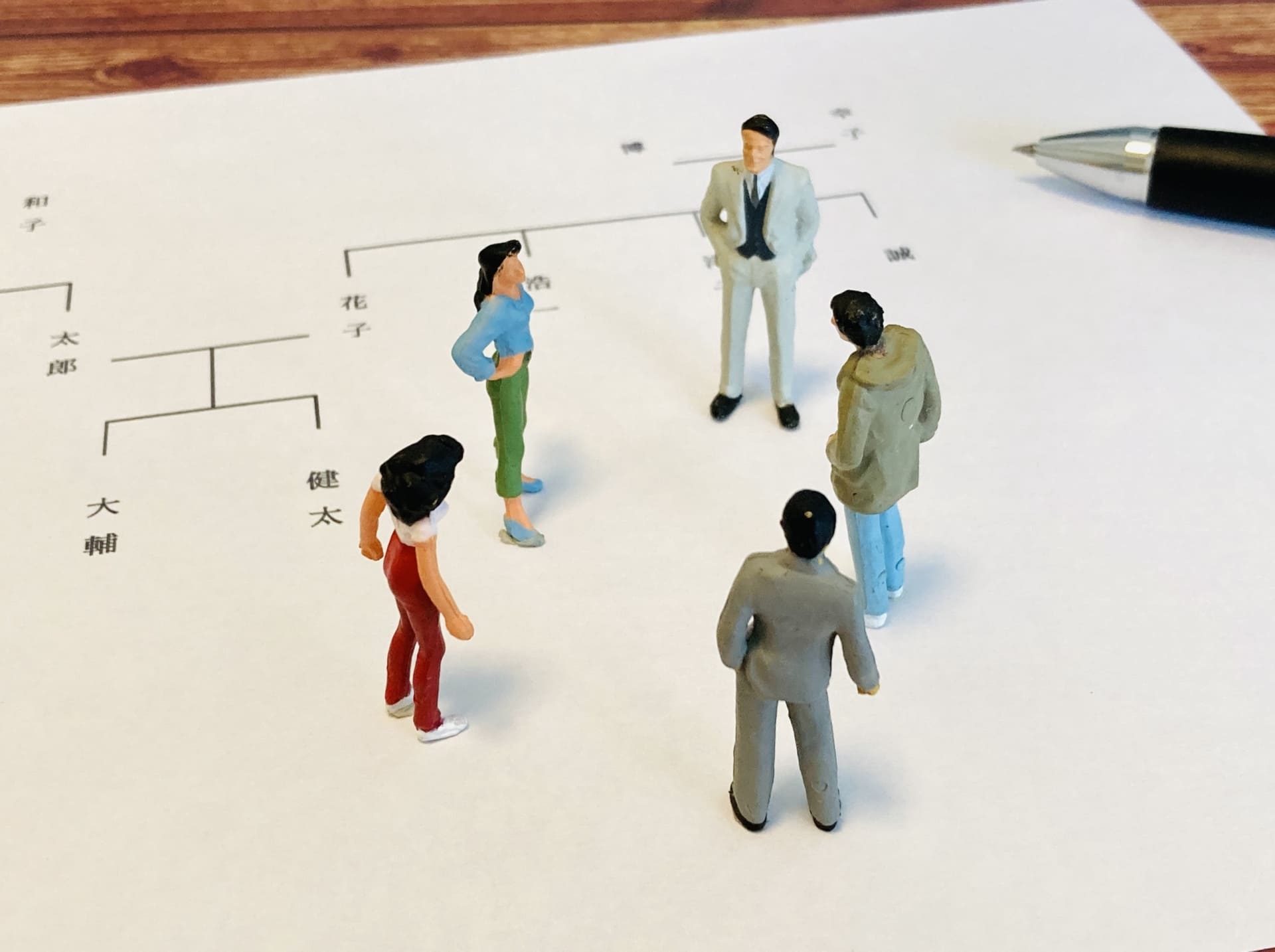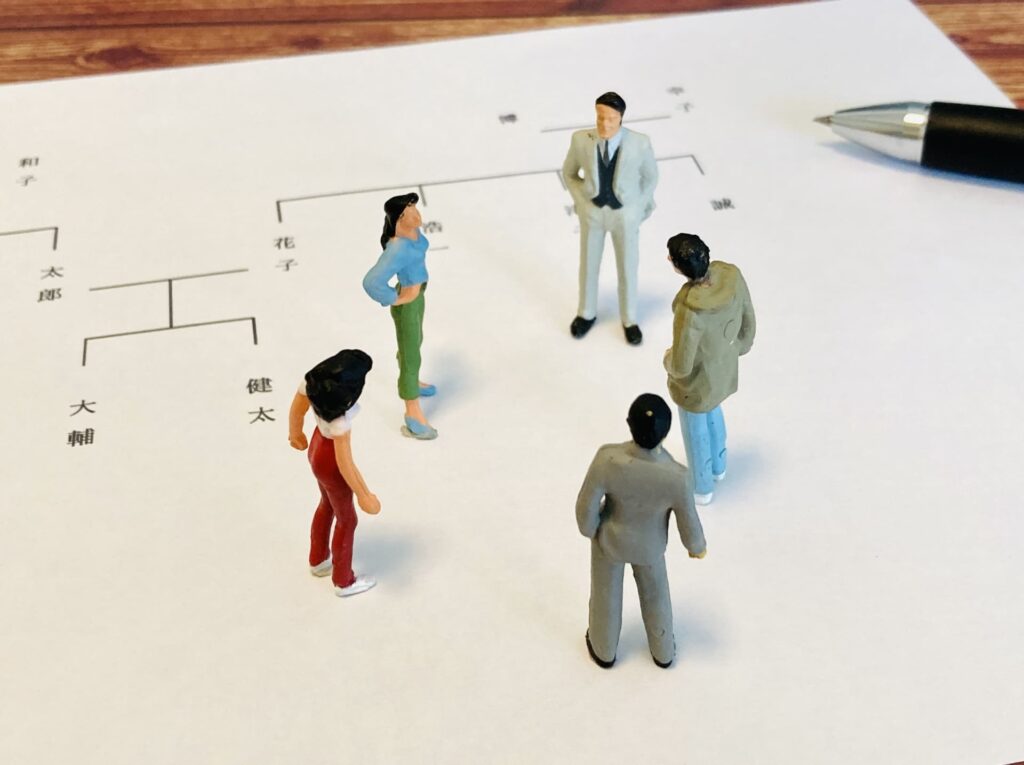
遺産分割の対象となる財産の評価額は,遺産分割の方法に影響を及ぼします。もっとも,それぞれの財産によって評価方法は異なってきます。
遺産分割においては,その対象となる財産の価額をいかに評価するのかということが大きな問題となることも少なくありません。
遺産分割の対象となる財産価額の評価の問題
遺産分割においては,どの財産を遺産分割の対象とするのかということが問題となることがあります。
しかし,それ以上に大きな問題となり得るのが,その遺産分割対象財産とされた財産の価額をどのように評価するのかという問題です。
ある財産を,10万円と評価するのか,それとも100万円と評価するのかでは,相続分に大きな違いが生じてきます。
そのため,ある遺産分割対象財産の価額をどのように評価するのかということは,非常に切実な問題となることがあります。
しかも,遺産分割において,個別の財産の価額をどのように評価すべきかということは,法令で明確には定められていません。
そのため,どのような評価方法を採用するのかということは,遺産分割における重大な問題となってくるのです。
とはいえ,遺産分割対象財産にはさまざまなものがあります。現金や預貯金など,その価額が容易に評価できるものばかりではありません。査定方法によって評価が異なるものもあり得ます。
そのため,それぞれの遺産分割対象財産に応じて,その評価の方法を考える必要があります。
遺産分割対象財産の評価の基準時
遺産分割対象財産の価額を定めるに当たって,まず問題となるのが,その算定の基準時の問題です。基準時の問題というのは,要するに,どの時点をもって,遺産分割対象財産の価額を定めるのかということです。
財産の価額は,時期によって異なることがあります。相続開始時であれば10万円であったものが,遺産分割審判時であれば100万円になっていた,ということもあるでしょう。
特に,財産価値の大きい不動産の場合には,相続開始時と,遺産分割の審判が成立した時とでは,非常に大きな違いが生じているような場合があります。
そこで,どの時点を遺産分割対象財産の評価の基準時とするのかということは,実際には切実な問題となることが少なくないのです。
これについては諸説ありますが,実務上は,遺産分割審判時を評価の基準時とすることが通常です。
もっとも,審判まで行かず,協議や調停で話し合いがつくような場合には,話し合いの中で評価の基準時をどの時点とするのかを決めて,それに基づいて相続人間で合意をすることになります。
現金の評価
現金は,基準時における合計金額をそのまま評価額とします。
預貯金の評価
預金・貯金(払戻請求権)も,基準時における預貯金の残高をそのまま評価額とします。
不動産の評価
最も財産価額の評価において紛争が生じやすい遺産分割対象財産は,やはり不動産(の所有権)でしょう。
この不動産については,固定資産評価額・路線価または倍率方式によって算定される相続税評価額・公示価格といった公的な評価基準があります。
どの評価基準も一長一短があり,どれが優れているというものでもないため,実務上では,不動産鑑定士や専門業者等に時価を査定をしてもらって,その査定金額を基準とすることが多いと思います。
借地権・借家権の評価
ある土地に対する借地権やある建物に対する借家権が,遺産分割対象財産であるという場合もあります。
借地権や借家権も土地や建物を利用できるという,所有権に準じて不動産を利用できるという権利ですから,その価額を算定する必要があります。
借地権については,更地とした場合の価額の6割から8割前後を借地権の価額とすることが多いでしょう。
実際には,前記不動産の所有権の場合と同様に,借地権価額を不動産鑑定士や専門業者等に査定してもらうことになるでしょう。
借家権については,財産評価基本通達において定められた基準に従って算定するのが通常です。もっとも,この場合も,やはり,不動産鑑定士等に価額を算定してもらうのが一般的かと思います。
動産の評価
動産も,評価方法によって金額が異なってくることがあります。
減価償却価値などから算定する方法もありますが,この方法によると,必ずしも現実の価値を算定できるとは限りません。
やはり動産も,動産の種類に応じて,その価額を査定できる専門家に依頼して査定・鑑定してもらう方がよいでしょう。
特に,骨とう品や美術品などは,専門の鑑定士や専門業者等に依頼して評価額を出してもらうことになります。
株式の評価
株式は,上場している会社の株式であれば,基準時における株式の株価を基準とします。
上場していない会社の株式の場合には,株価が公開されていませんから,公認会計士等によって,時価を算定してもらうほかないでしょう。
社債・国債の評価
社債や国債は債権ですが,遺産分割対象財産となると解されています。したがって,遺産分割のためにその価額を評価する必要があります。
社債・国債には,割引発行のもの,利付のもの,元利均等償還が行われるものがあります。
上場されている社債・国債であれば,基準時における時価が公表されていますので,これを評価額とすることができます。
利付の社債・国債の場合は,この時価額に既に発生している利息を足して,そこから源泉徴収額を控除して評価額を計算します。
もっとも,社債・国債の計算には複雑な面があります。したがって,これについても,公認会計士等の専門家に計算してもらう方が確実でしょう。