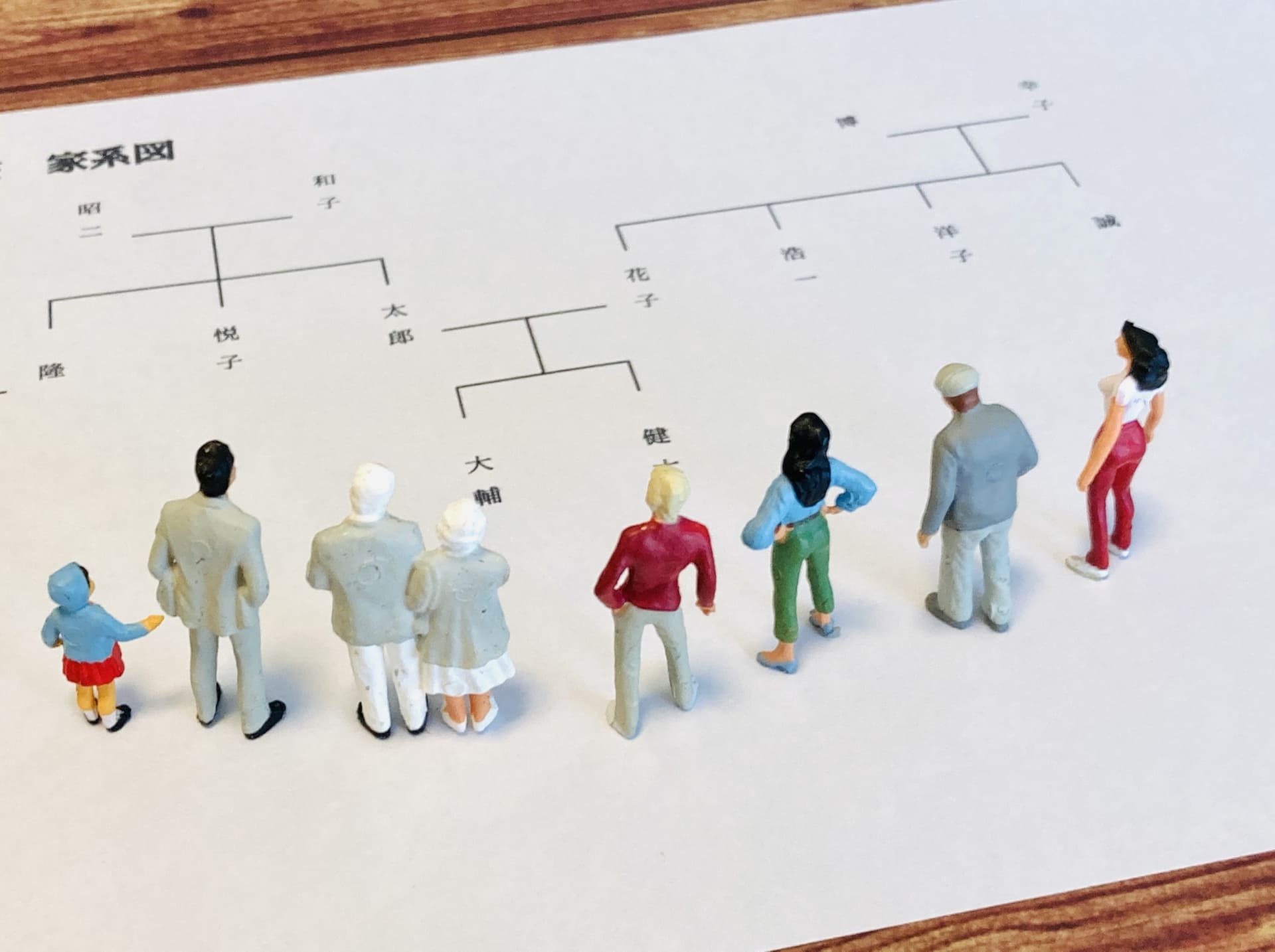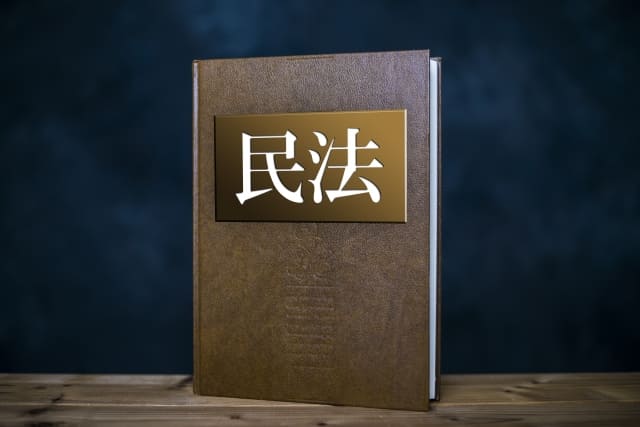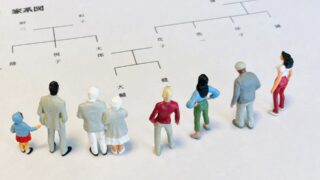法定相続分の記事一覧
相続においては,誰にどの程度の割合で相続財産が相続されるかについては法律で定められています。この法律で定められている相続の割合のことを「法定相続分」といいます。
法定相続分の記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
法定相続分の概要
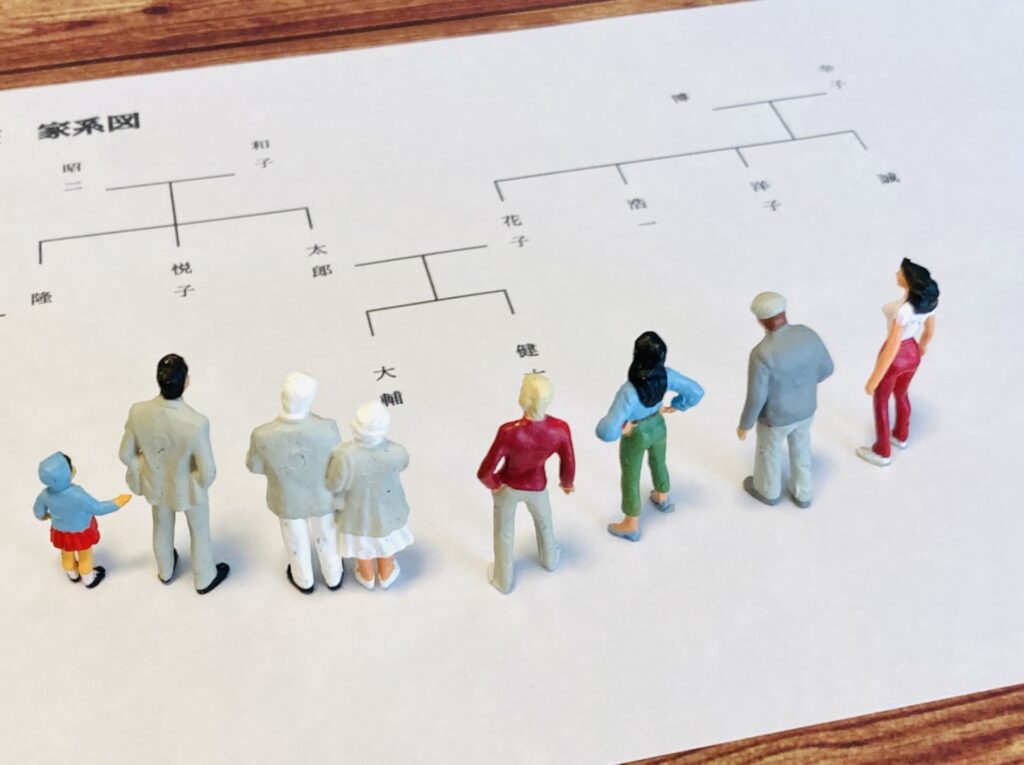
前記のとおり、相続においては,誰にどの程度の割合で相続財産が相続されるかについては法律で定められています。この法律で定められている相続の割合のことを「法定相続分」といいます。
相続人が複数いる場合の法定相続分は、基本的に頭割りです。ただし、配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となるため、以下のようになります。
- 「配偶者と子」が相続人となる場合には,配偶者が2分の1,子が2分の1の相続分
- 「配偶者と直系尊属」が相続人となる場合には,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1の相続分
- 「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となる場合には,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1の相続分
これらの場合の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」が複数いる場合は、それぞれの相続分を頭割りすることになります。
例えば、配偶者と兄弟姉妹3人がいた場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分はそれぞれ「4分の1×3分の1=12分の1」ずつということになります。
この法定相続人である「子」については、かつては嫡出子と非嫡出子で異なる扱いがされていました。もっとも、最高裁判所大法廷平成25年9月4日判決で非嫡出子の相続分差別規定が違憲と判断されてから法改正され、現在では同じ扱いになっています。
なお、相続資格が重複する場合には、その重複した相続資格に基づいて、そのそれぞれの相続分をすべて取得できます。