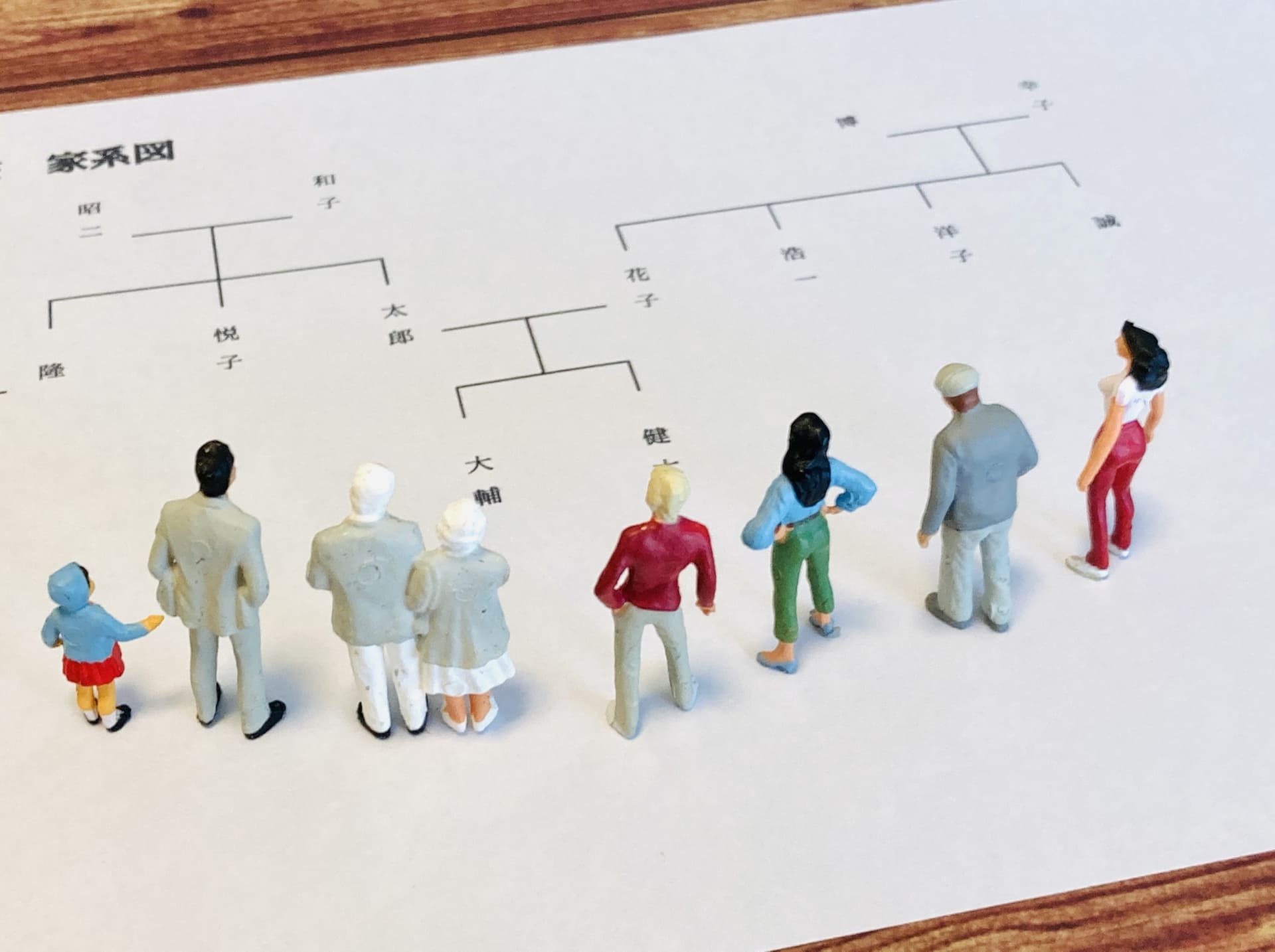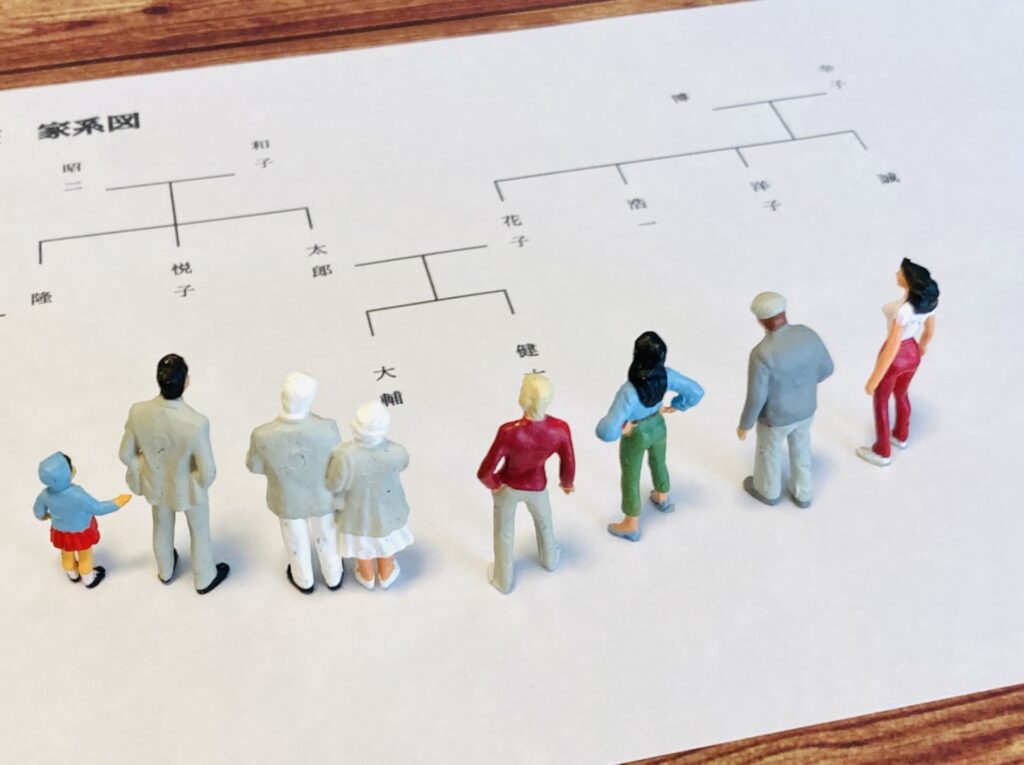
相続資格が重複する場合には,通常とは異なる方法で法定相続分を計算しなければなりません。この場合、重複した複数の相続資格に基づいて,そのそれぞれの法定相続分をすべて取得できることになります。
相続資格が重複する場合の取扱い
誰が法定相続人となり,その法定相続人にどの程度の法定相続分が認められるのかについては,民法で原則が定められています。
法定相続人となるのは,子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者です。子が第1順位,直系尊属が第2順位,兄弟姉妹が第3順位です。配偶者は常に相続人となります。
ある人が法定相続人となったとしても,たとえば「子」の立場として,あるいは「直系尊属」の立場として,というように,1つの法定相続人の資格だけであるということが通常でしょう。
もっとも,まれに,複数の相続資格を重複して有しているという場合があります。例えば,孫を養子縁組したことにより,その孫が「子」であると同時に,代襲相続人でもあるというような場合です。
このような相続資格が重複する場合にどのように取扱うべきかということが問題となります。
結論からいえば,重複した複数の相続資格に基づいて,そのそれぞれの相続分をすべて取得できることになります。
相続資格が重複する場合の具体例
相続資格が重複する場合としては,前記の養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を有するという場合が挙げられます。また,非嫡出子を養子縁組した場合も同様に扱われるのかという点も問題となります。
養子としての相続資格と代襲相続人としての相続資格の重複
例えば,Aには,長男Bと長女Cがおり,長男Bには子D(Aからみれば孫)がいたとします。長男BがAよりも早く亡くなったため,後継者が必要であるということで,Aは孫Dと養子縁組をしました。配偶者はすでに亡くなっています。
この場合に,Aが死亡すると,相続人は「子」である長女Cと養子縁組をしたDということになります。さらに,長男BはA死亡前に亡くなっているので代襲相続が発生し,DはさらにBの代襲相続人ということにもなります。
そして,前記のとおり,相続資格が重複する場合には,その各相続資格の相続分のすべてを受け取ることができますから,Dは,子としての相続分と代襲相続人としての相続分を両方譲り受けることになります。
具体的には,Dは,子としての相続分【3分の1(子が3人いるため)】と,代襲相続人としての相続分【3分の1(Bの相続分)】の合計【3分の2】の相続分を承継するということになります。
非嫡出子を養子縁組した場合
非嫡出子(いわゆる婚外子)を,嫡出子にするために,養子縁組するという場合があります。この場合も,ある意味では,養子としての相続資格と非嫡出子としての相続資格があるというようにもみえます。
しかし,非嫡出子を養子縁組するというのは,あくまで非嫡出子を嫡出子にすることが目的です。非嫡出子と嫡出子という2つの資格が生ずるわけではありません。
したがって,非嫡出子を養子縁組した場合には,相続資格の重複は生じません。その養子は,「子」としての相続分を承継するだけということになります。
なお,かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とする規定が効力を有していましたが,現在では,すでに最高裁判所大法廷決定(最大決平成25年9月4日)によってその規定は違憲無効であるとされていますので,非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分は対等のものとして扱われることになります。