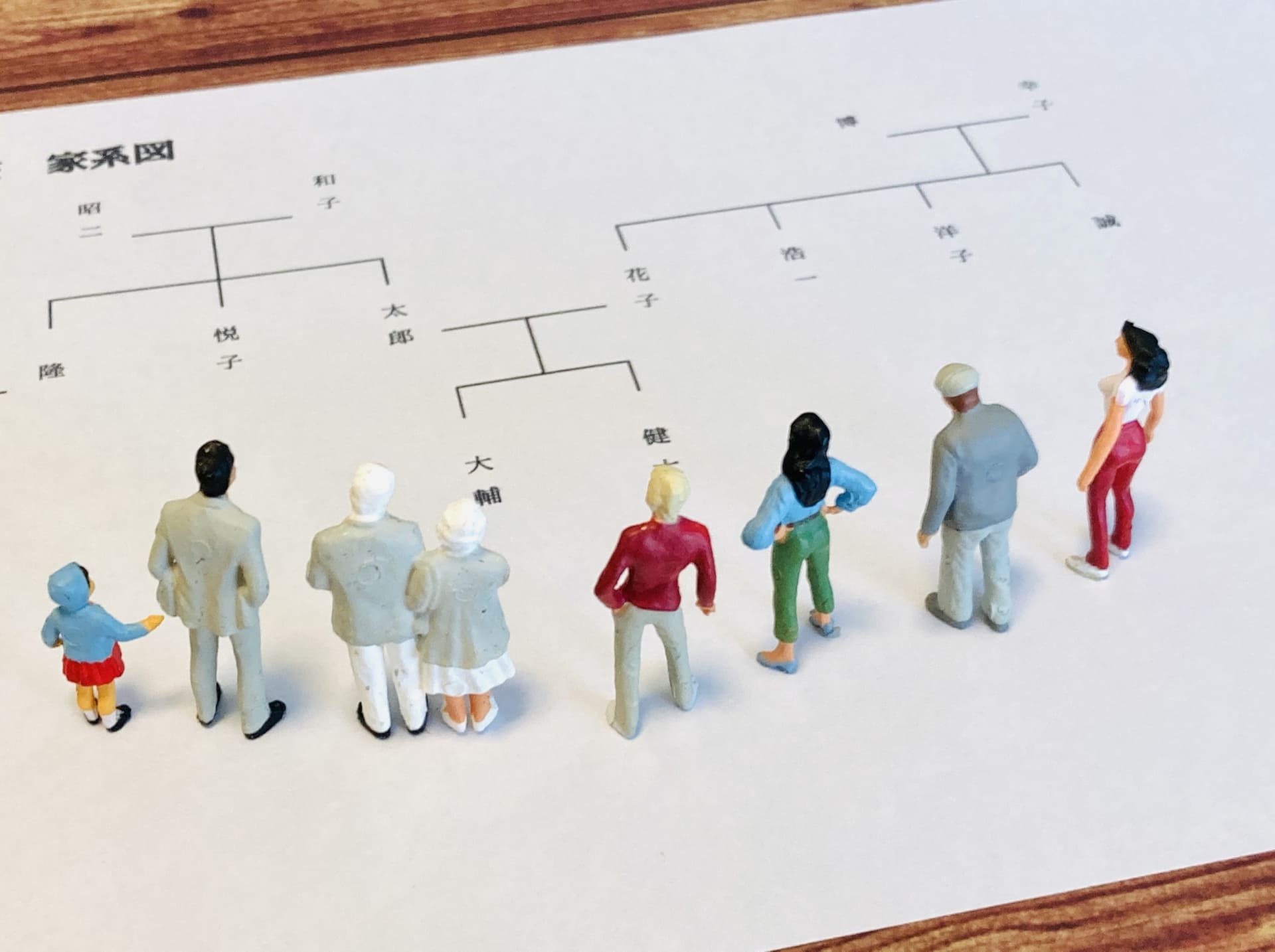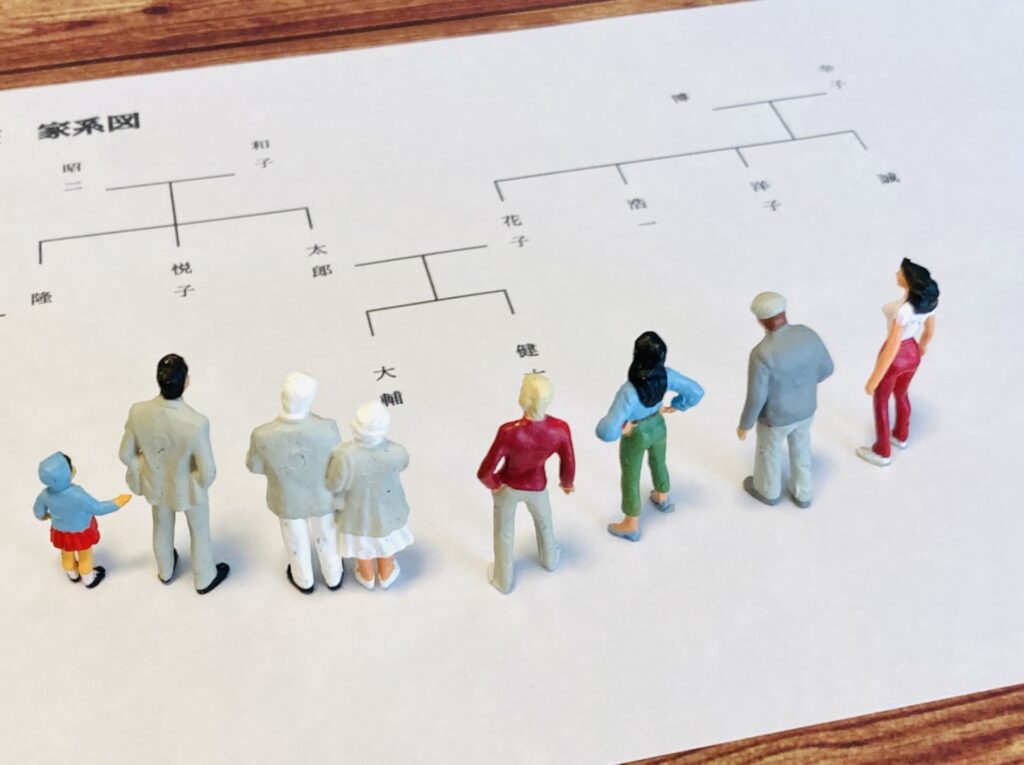
相続人間における相続財産(遺産)の分配の割合のことを「相続分」といいます。この相続分には,法定相続分と指定相続分の2種類があります。
相続分とは?
遺産相続においては,被相続人の有していた一切の権利義務(相続財産)は,相続人に分配されることになります。
相続人が1人であれば,その相続財産はすべてその1人の相続人に承継されることになるので,遺産の分配の割合等を気にすることはないでしょう。しかし、相続人が複数いるいるような場合には,相続財産の分配の割合が問題となってきます。
この,相続人間における相続財産(遺産)の分配の割合のことを「相続分」といいます(なお,相続財産全体に対する相続人の権利や地位そのもののことを,相続分と呼ぶ場合もあります。)。
この相続分には,法定相続分と指定相続分の2種類があります。
法定相続分
民法 第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
第1号 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
第2号 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
第3号 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
第4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
誰が相続人となり,どの割合の相続分を取得するかということは,原則として,民法によって規定されています。この民法に基づいて認められる原則的な相続分のことを「法定相続分」と呼んでいます。
そのため,遺言を作成していなかったり,遺産分割によって法定相続分と異なる相続分を定めなかったりするなどのような手続をとらなければ,この法定相続分に応じて遺産の分配がなされることになります。
相続人(法定相続人)となるのは,民法上,「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」と定められています。配偶者は常に相続人となりますが,それ以外の立場については順位が定められています(民法887条、889条、890条)。
「子」が第1順位,「直系尊属」が第2順位,「兄弟姉妹」が第3順位です。したがって,「子」がいるときは「子」が,「子」がいないときは「直系尊属」が,「直系尊属」がいないときは「兄弟姉妹」が相続人となるということです。
同順位の相続人が複数いる場合には,頭割りで相続分が決まります(民法900条4号本文)。例えば,「子」が3人いれば,「子」に割り当てられた相続分は,各人に3分の1ずつ認められるということです。
配偶者がいる場合には,法定相続分も異なってきます(民法900条1号から3号)。
- 「子」が相続人となる場合には,配偶者に2分の1が与えられ,「子」にも2分の1が与えられます。
- 「直系尊属」が相続人となる場合には,配偶者に3分の2が与えられ,「直系尊属」には3分の1が与えられます。
- 「兄弟姉妹」が相続人となる場合には,配偶者に4分の3が与えられ,「兄弟姉妹」に4分の1が与えられるということになります。
なお,配偶者がいる場合の,「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」とは,個々の子・直系尊属・兄弟姉妹を意味しません。言ってみれば,子・直系尊属・兄弟姉妹というカテゴリーに相続分が割り当てられるといった方がよいかもしれません。
つまり,「子」が相続人となる場合には,配偶者に2分の1が与えられ,「子」には2分の1が与えられるといいましたが,ここでいう「子」が複数人いたとしても,その複数人の子全体に与えられる相続分は2分の1ということです。
したがって,例えば,法定相続人が配偶者と3人の子であったという場合には,配偶者に2分の1の相続分,3人の子各人に(2分の1÷3=6分の1)の相続分が割り当てられるということになるということです。
また,相続資格が重複する場合には,その両方の相続資格に基づいて相続分を承継することになります。
指定相続分
民法 第902条
第1項 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
第2項 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
前記のとおり,民法では,法定相続分が定められていますが,被相続人の意思の尊重という見地から,被相続人は,遺言によって,相続分を指定することができます。
この被相続人の遺言によって指定される相続分のことを「指定相続分」といいます。
指定相続分が定められた場合には,法定相続分の民法の規定は適用されないことになります。指定相続分を定めることを,相続分の指定と呼んでいます。
ただし,相続分の指定は,遺言によってする必要があります。遺言以外の方法でした相続分の指定は法的効力を持ちません。また,相続分の指定によっても,法定相続人の遺留分を侵害することはできません。