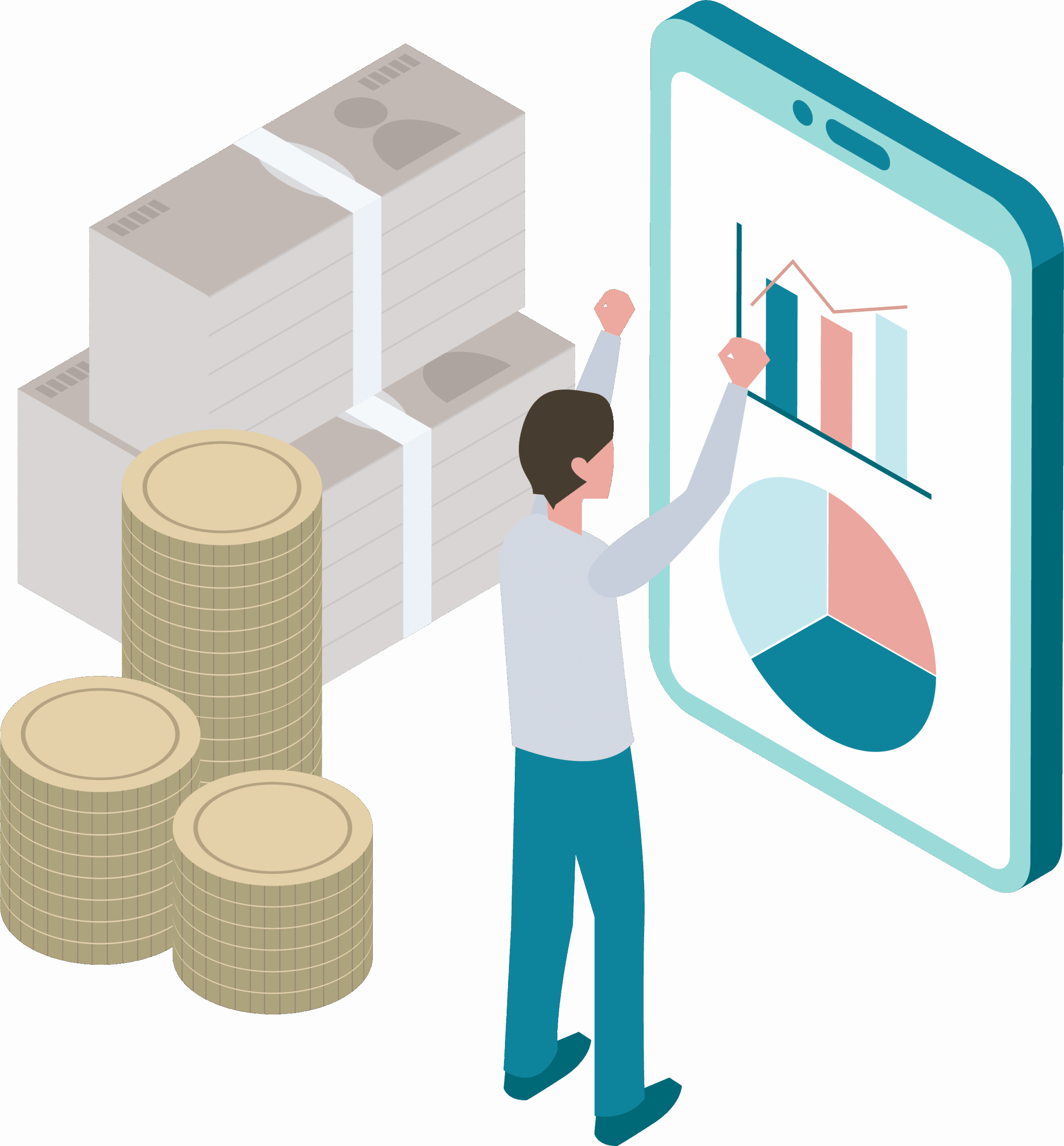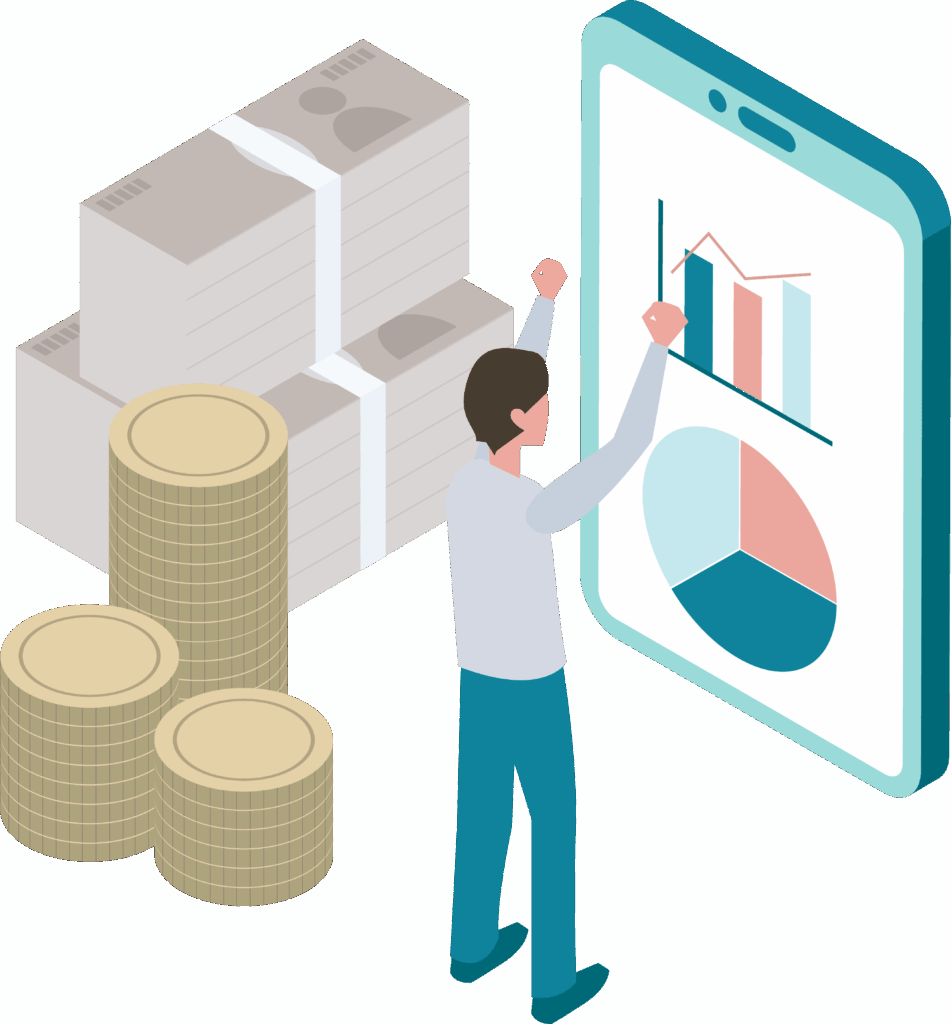
投資信託の投資家には,それを解約することで元本の償還を受けたり,または分配金を受領できる権利がありますので,投資信託にも財産的価値があります。したがって、投資信託も相続財産(遺産)に含まれます。
投資信託の財産的価値
投資信託とは,多数の投資家が投資信託の販売会社を通じて拠出した資金を,投資専門家が株式等の有価証券・不動産等に投資し,その投資運用によって得た利益を投資家に分配するという金融商品のことをいいます。
代表的な投資信託としては,MMF(マネー・マネジメント・ファンド)やMRF(マネー・リザーブ・ファンド)などがあります。
日本においては,法的な投資信託として,委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託が認められています(投資信託及び投資法人に関する法律2条3項)。
投資信託をする場合,その投資家について受益証券という有価証券が作成されます。ただし,この受益証券は,投資信託取扱い証券会社等が保管するため,実際には,投資家に対して交付はされないのが通常です。
上記のとおり,投資信託の投資家は,投資運用によって得た利益の分配を受ける権利(収益分配請求権)を有しています。
また,投資信託の投資家は,投資信託を解約または証券会社等に対する受益証券買取りを請求する権利(償還金請求権)を有しており,中途で換金することも可能です。
このように,投信信託投資家は,収益分配請求権や償還金請求権があります。これらの権利は受益権と呼ばれています。
投資信託受益権があれば,利益分配を受けたり,またはそれを解約するなどして換金ができますから,財産的価値があります。
投資信託受益権の相続財産性
前記のとおり,投資信託の投資家には,投資運用による利益の分配を受ける権利や,投資信託の解約等をして金銭を受け取ることができる権利などの財産的価値のある受益権が認められています。
したがって,被相続人が投資信託の投資家であった場合,その投資信託受益権は,相続財産に含まれることになります。
投資信託受益権の準共有
投資信託受益権に基づく収益分配請求権や解約による償還金請求権は,金銭債権の性質を有しているといえます。
そうすると,金銭債権という可分債権である以上,原則論からすれば,相続の開始によって,遺産分割を経ずに,各共同相続人に対して,それぞれの相続分に従って,当然に分割して相続されることになるはずです。
もっとも,投資信託受益権は,金額を単位するものではなく,その口数を単位としており,一単位未満での権利の行使が認められていません。
また,投資信託の投資家には,収益分配請求権や償還金請求権だけでなく,信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権(投資信託及び投資法人に関する法律15条2項)等の委託者に対する監督的機能を有する権利も受益権として認められています。
そうすると,投資信託投資家の有する受益権は,純然たる可分な金銭債権だけの権利であるとはいえません。
そこで,投資信託受益権については,相続人が複数いる場合には,共同相続人にそれぞれの相続分に従って当然に分割されるものではなく,共同相続人全員の準共有になると解されています。
この点につき,最高裁判例も,MMF・MRFについて「投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照らせば,共同相続された上記投資信託受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」として,「本件遺産分割審判によって上告人ら及び被上告人の各持分4分の1の割合による準共有となった」と判示しています(最三小判平成26年2月25日)。
相続開始後の投資信託分配金
投資信託については,前記の投資信託受益権のほか,相続開始後に,被相続人の預貯金口座等に投資信託分配金が振り込まれるなどした場合に,その分配金をどのように取扱うべきかという問題もあります。
相続開始後の投資信託分配金は,相続財産である投資信託受益権によって発生した金銭債権ですから,相続財産の果実とみることもできます。
したがって,遺産分割を待たずに,各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて,当然に取得できると解することも可能です。
しかし,最高裁判所は,前記投資信託受益権の性質を理由として,相続開始後遺産分割までに支払われた分配金は,各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて当然に取得できるものではないと判示しています(最二小判平成26年12月12日)。