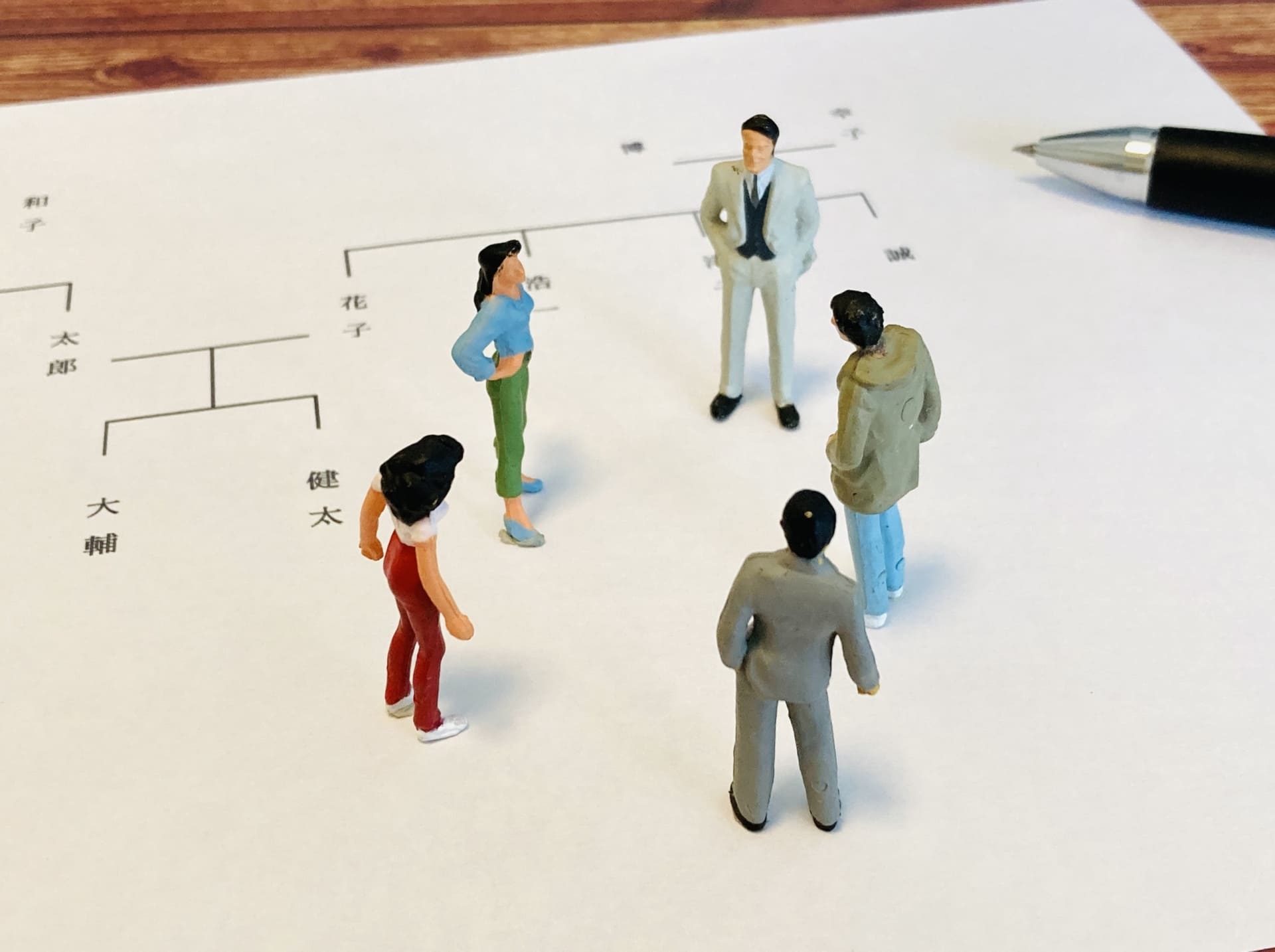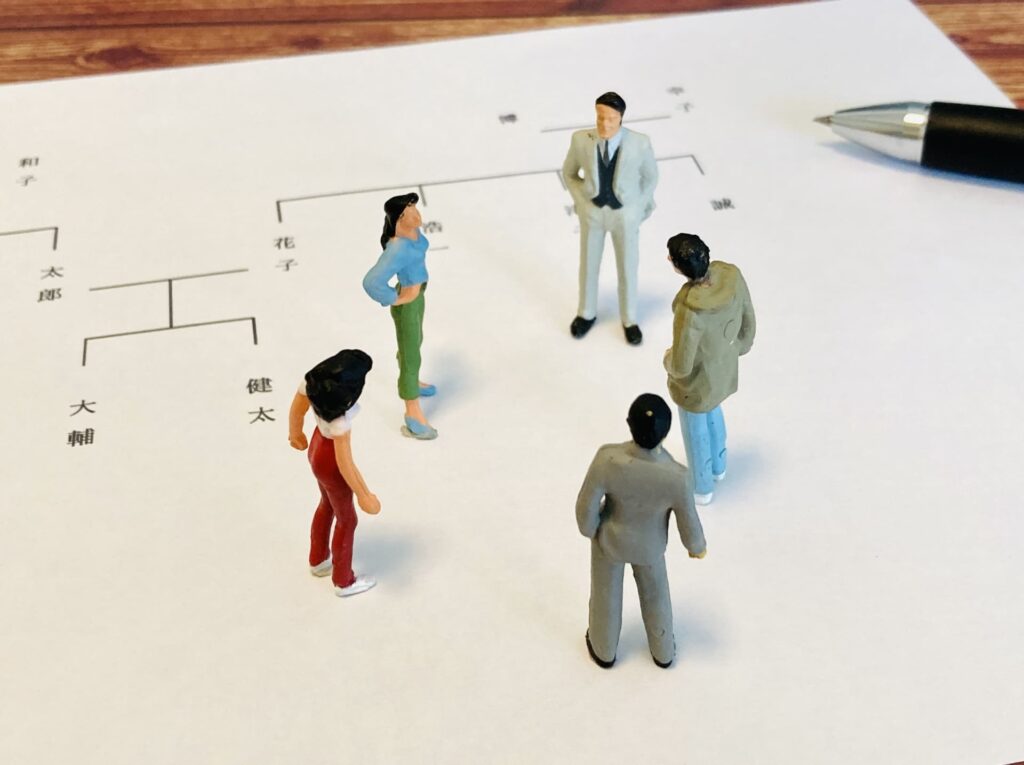
相続が開始されると,被相続人の一身に専属したものを除いて,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されることになります(民法896条)。相続財産には,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も含まれます。
相続人が複数人いる場合は,各共同相続人の相続分に応じて,共同相続人間で相続財産を共有(または準共有)することになるのが原則です。
ただし,預貯金債権を除く金銭その他の可分債権は,それぞれの相続分に従って,当然に分割承継されるため,共同相続人間での準共有にはならないと解されています。
相続の効力・効果
民法 第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
遺産相続が開始されると,被相続人の一身に専属したものを除いて,「相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」ことになります(民法896条)。
この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」から「被相続人の一身に専属したもの」を除いたものを「相続財産」といいます。
相続財産には,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も含まれます。したがって,相続が開始されると,被相続人の資産だけでなく負債も相続人がすべて受け継ぐことになります。
相続人が複数人いる場合であれば,その複数人の相続人(複数人の相続人を「共同相続人」といいます。)が,遺産分割によって確定されるまでの間,その相続財産を共有することになるのが原則です。
相続財産の包括承継
前記のとおり,相続人は,相続財産を包括的に承継することになります。
ある人がある人の財産等を受け継ぐことを「承継」といいますが,この承継には,「包括承継」と「特定承継」とがあります。
包括承継とは,一般承継ともいい,一切の権利・義務を受け継ぐことをいいます。これに対し,特定承継とは,権利・義務の一部を受け継ぐことをいいます。
特定承継の場合,資産の一部だけを受け継ぐとか,負債の一部だけ受け継ぐということもあります。
相続では,特定承継はされず,包括承継されることになります(ただし,遺産分割の結果,資産や負債の一部だけ承継することになる場合はあります。)。
なお,包括承継がなされるのは,法人であれば合併や会社分割の場合などがありますが,個人(自然人)の場合にはこの遺産相続の場合です。
共同相続人がいる場合
民法 第898条
第1項 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第2項 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。民法 第899条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
遺産相続によって,被相続人に属した一切の権利義務は相続人に包括承継されます。
もっとも,相続人といっても,1人の場合もあれば複数人の場合もあります。
相続人が1人の場合であれば,すべての相続財産がその1人に包括承継されることになるだけですが,相続人が複数いる場合には,相続財産は,共同相続人に法律の定めに従って分配されることになります。
この法律で規定された基本的な相続財産の分配の割合のことを「法定相続分」といいます。
相続人が複数である場合,相続が開始されると,まずその相続財産は,いったん共同相続人の共有となります(民法898条1項)。共同相続人が共有する財産については、法定相続分に応じて各共同相続分に持分が割り当てられます(民法898条2項)。
そして,共同相続人は,それぞれの相続分に応じて相続財産を包括承継することになります(民法899条)。
例えば,被相続人に妻と2人の子がいた場合,妻が2分の1,子がそれぞれ4分の1ずつ法定相続分を持っています。
この場合に,相続財産として土地と建物があったとすると,その土地の共有持分は, 妻が2分の1,子がそれぞれ4分の1ずつとなり,建物の共有持分も,妻が2分の1,子がそれぞれ4分の1ずつ,ということになります。
もちろん,遺言や遺産分割によって,これと異なる割合にすることは可能です。
ただし,預貯金債権を除く金銭その他の可分債権は,遺産相続後に相続人間で共有にはならず,それぞれの相続分に従って,当然に分割承継されると解されています(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日,最三小判平成16年4月20日等)。