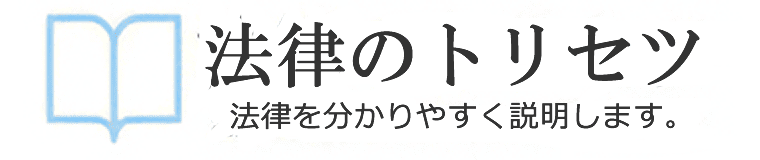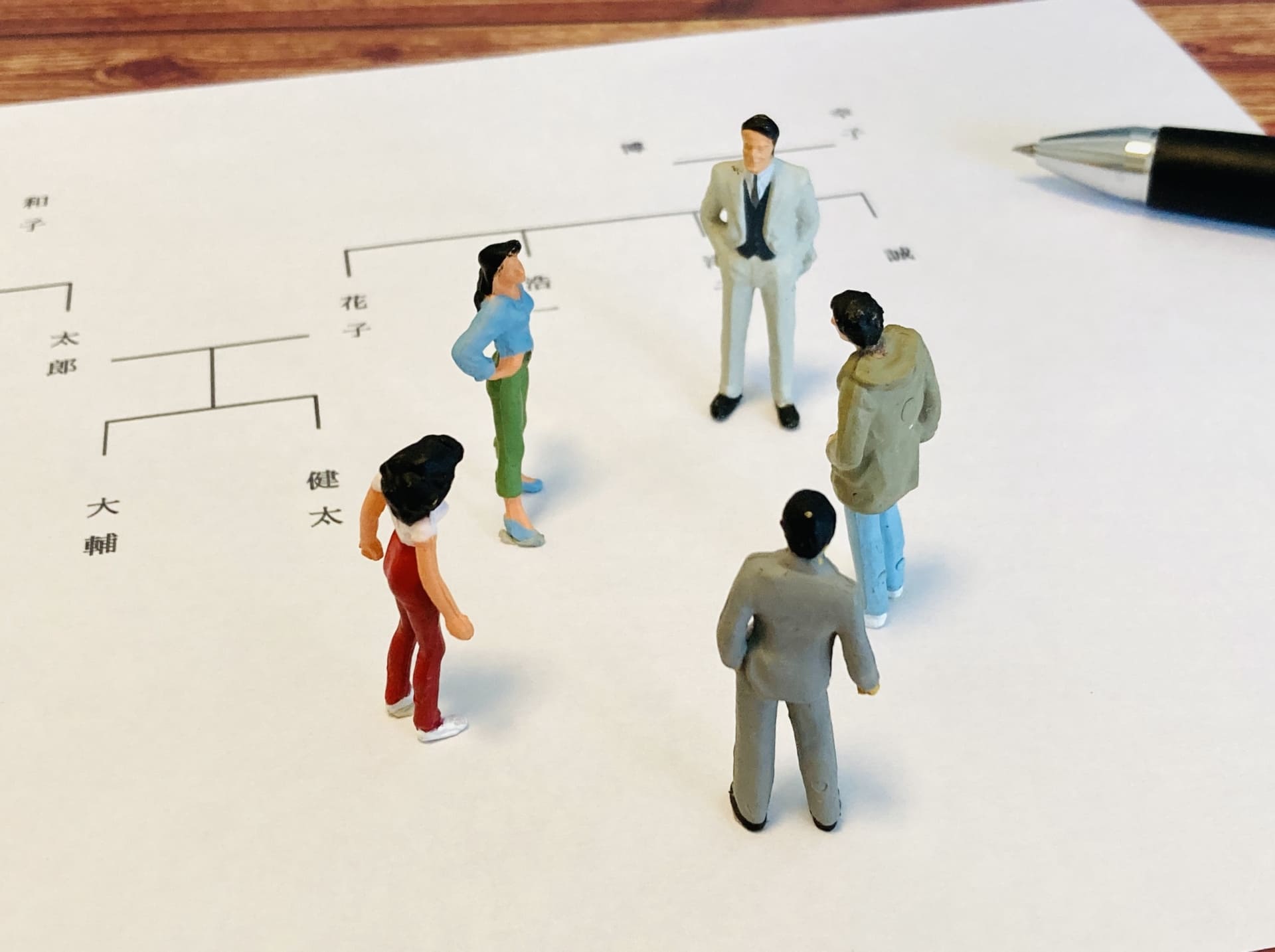この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
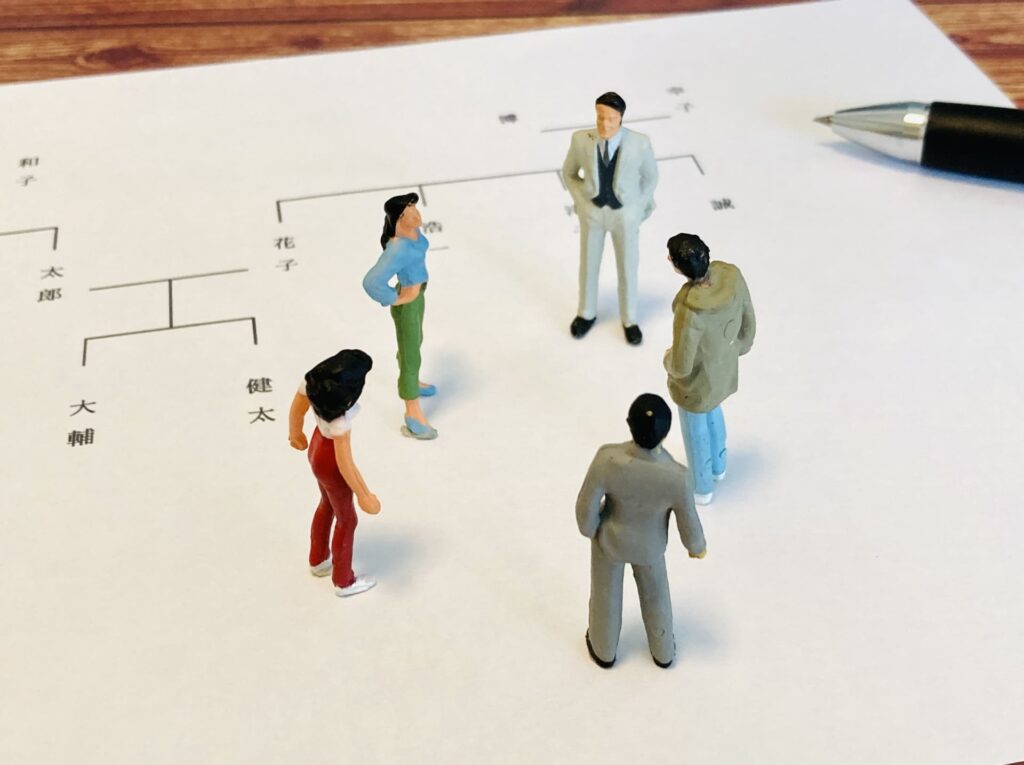
相続が開始されると,被相続人が有していた権利義務(相続財産)が相続人に承継されることになりますが,例外的に被相続人の一身に専属した権利義務は相続財産に含まれません。
相続財産とならない被相続人の一身専属権利義務
民法 第896条
- 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続が開始されると,被相続人が有していた権利・義務は,原則として,すべて相続財産に含まれ,そして,それは相続人に包括的に承継されることになります(民法896条本文)。
しかし,例外的に,相続財産に含まれない被相続人の権利義務があります。それは,「被相続人の一身に専属した」権利義務(以下「被相続人の一身専属権利義務」といいます。)です(民法896条条ただし書き)。
相続財産に含まれないのですから,当然,この被相続人の一身専属権利義務は,相続人に承継されないことになります。つまり,被相続人の死亡によって,その権利や義務も消滅するということです。
この被相続人の一身専属権利義務とは,その権利義務の性質上,被相続人のみに帰属すべきものを意味します。
簡単にいえば,被相続人「その人」でなければ成立しない又は認められるべきではないような権利や義務のことです。
帰属上の一身専属性と行使上の一身専属性
この一身専属性という場合,講学上,「帰属上の一身専属性」と「行使上の一身専属性」という区分があると解されています。
帰属上の一身専属性とは,ある特定の人だけしか有することができないという意味での一身専属性を意味します。
行使上の一身専属性とは,誰でも有することが可能であるけれども,権利を行使したり義務を履行したりできる人は限定されるという意味での一身専属性です。
相続財産に含まれない被相続人の一身専属権利義務という場合の一身専属性は,上記のうちの「帰属上の一身専属性」を意味しています。
したがって,行使上の一身専属性しかない権利義務については,相続財産に含まれることになります。
被相続人の一身専属権利義務が相続財産とならない理由
この被相続人の一身専属権利義務が,なぜ相続財産に含まれないのかといえば,それは,そもそもこの一身専属権利義務が,被相続人その人を対象としている権利や義務だからです。
そもそも,被相続人の「一身」に「専属」するというくらいですから,そもそも,被相続人以外の人がその権利や義務を有しているのは適当でないような性質を有する権利や義務であるということです。
そして,その権利や義務は,被相続人自身も,またその権利義務の相手方も,被相続人一代限りのものと考えているでしょうから,相手方に不当な不利益を被らせるおそれもありません。
そのため,被相続人の一身専属権利義務は,相続財産に含まれず,相続人に承継されることがないのです。
被相続人の一身専属権利義務の具体例
被相続人の一身専属権利義務としては,以下のようなものがあります。
民法上では,以下のようなものが一身専属権利義務として規定されています。
- 使用貸借契約における借主の地位
- 代理における本人・代理人の地位
- 雇用契約における使用者・被用者の地位
- 委任契約における委任者・受任者の地位
- 組合契約における組合員の地位
また,明文規定はないものの,法律解釈上,以下のようなものも一身専属権利義務と考えられています。
- 代替性のない債務(有名画家が絵を描く債務など)
- 親権者の地位
- 扶養請求権者の地位
- 生活保護給付の受給権者の地位
- 公営住宅の使用権
上記以外の権利や義務であっても,解釈上,被相続人の一身専属権利義務に当たり,相続財産に含まれないと解されているものはあります。