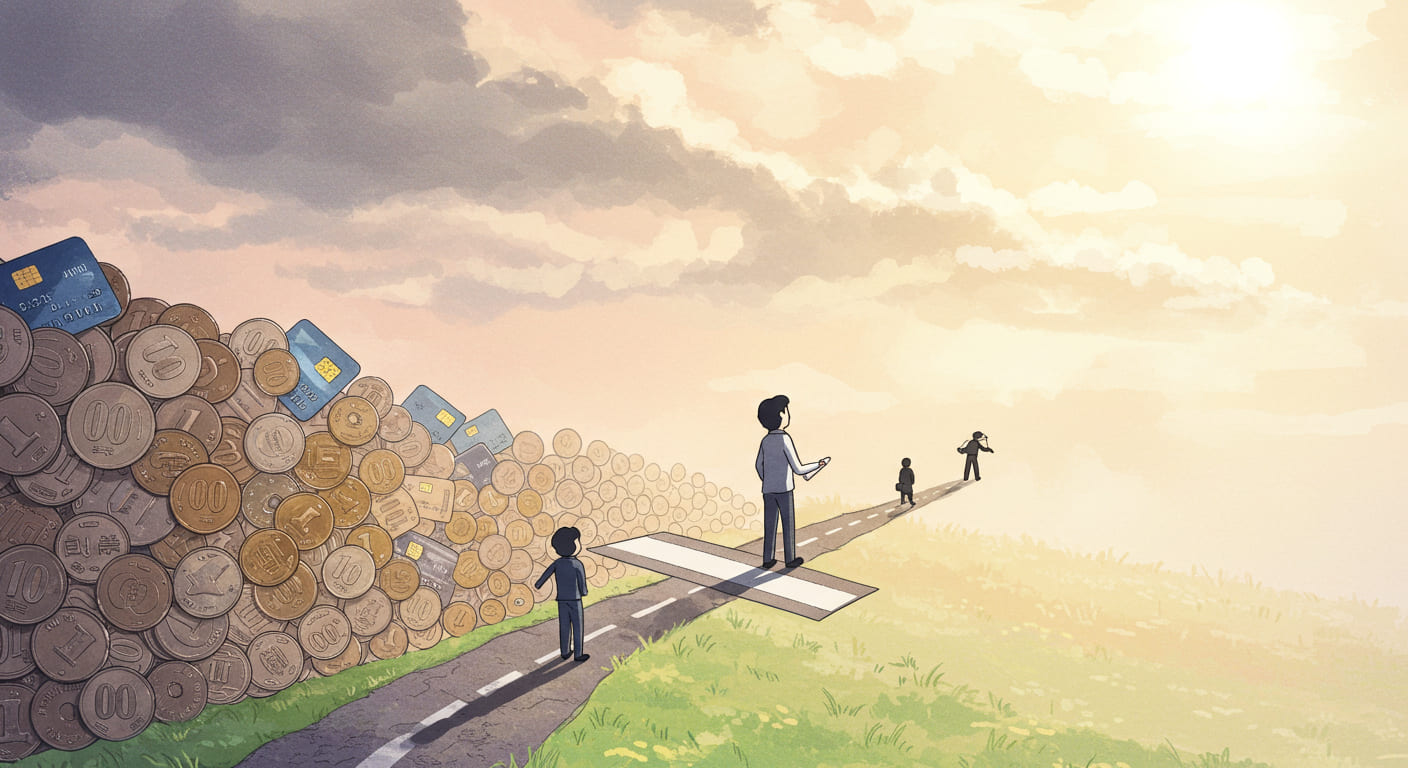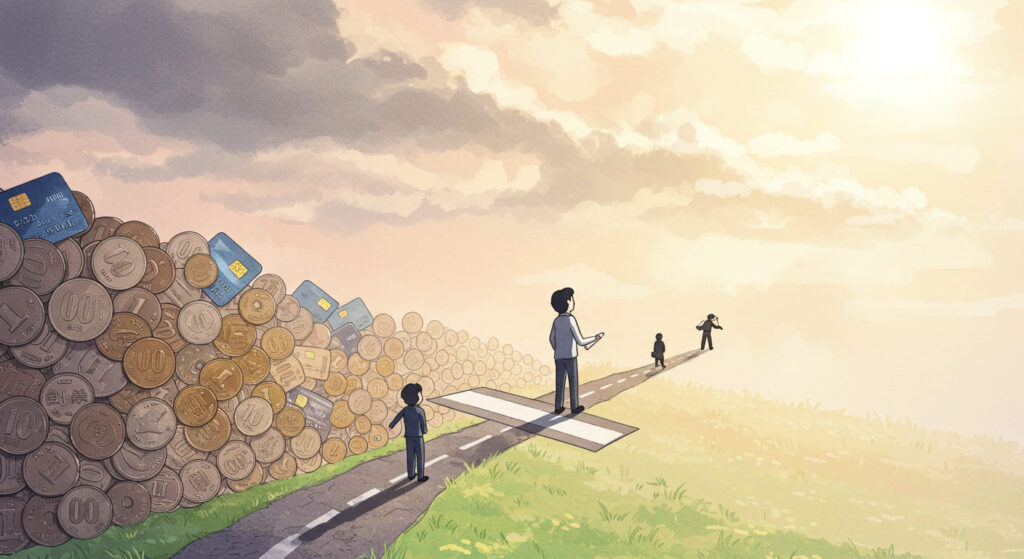
破産債権者を害することを知っていたかどうかにかかわらず,支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者が破産債権者を害する行為(詐害行為)をした場合,その行為は破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります(破産法160条1項2号)。
ただし,否認されるのは,詐害行為によって利益を受けた受益者が,その行為の当時に,支払停止または破産手続開始の申立てがあったこと並びに破産債権者を害する事実を知っていた場合に限られています。
破産者が支払停止または破産手続開始の申立て後にした破産債権者を害する行為の否認とは
破産法 第160条
第1項 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
第2号 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。
この否認権の類型の1つに「詐害行為否認」があります。
さらに,この詐害行為否認にもいくつかの類型があり,そのうちの1つが,破産法160条1項2号に規定されている「破産者が支払停止または破産手続開始の申立ての後にした破産債権者を害する行為の否認」です。
「破産者が支払停止または破産手続開始の申立ての後にした破産債権者を害する行為の否認(以下「2号否認)と言います。)」には,以下の要件が必要となります。
- 破産者の行為であること
- 破産債権者を害する行為であること(詐害行為)
- 詐害行為が支払停止または破産手続開始申立て後にされたものであること
- 詐害行為によって利益を受けた者(受益者)が,その行為の当時,破産債権者を害する事実を知っていたこと
「破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認」も,破産法160条1項1号の「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認」(以下「1号否認」といいます。)と同様,破産者による詐害行為が対象となります。
しかし、2号否認は、1号否認と異なり、支払停止等の後の詐害行為に限定されています。また、詐害意思は不要とされています。
要件1:破産者の行為であること
詐害行為として否認される行為は、破産者の行為に限られます。第三者の行為では、この詐害行為否認の対象になりません。
要件2:詐害行為をしたこと
2号否認の要件として「破産債権者を害する行為」がなされていることが必要です。この行為のことを「詐害行為」といいます。
詐害行為の意味
破産法160条1項2号の詐害行為は,破産法160条1項1号の詐害行為と同じく,破産者の責任財産を絶対的に減少させる行為を意味します。
債権者への弁済(破産手続であれば破産債権者への配当)の原資となる財産を責任財産といいます。それを絶対的に減少させてしまう行為が詐害行為に該当します。
詐害行為の範囲
単に財産を積極的に減少させてしまった場合だけではなく,債務を増大させてしまった場合も,ここでいう「詐害行為」に当たります。
債務が増えるということは,当然,その債務を請求するため新たな債権者が破産手続に参加してきます。その結果,既存の破産債権者の配当は減少してしまいます。
したがって、債務が増えるということは配当すべき財産が減るということですから、やはり詐害行為に該当することになるのです。
また,この詐害行為には,担保供与行為と債務消滅行為は含まれません。債務消滅行為の代表的な例は、借金の弁済です。
これらは,「詐害的債務消滅行為の否認(破産法160条2項)」または「偏頗行為否認(破産法162条)」の対象となります。
責任財産の絶対的な減少の意味
責任財産を絶対的に減少させるという言葉の意味はなかなか難しいのですが、簡単に言えば、財産を全体的に考えたときに明らかに財産が減ってしまっている場合を言います。
例えば,Aさんは全部で500万円の財産を持っていました。ところが,そのうちの200万円の価値ある自動車を100万円でBさんに売ってしまいました。
財産を全体的に見ると,Aさんの財産は400万円になってしまったわけですから,絶対的に減少したということができます。
これに対し,上記の自動車を200万円で売ったとしましょう。そうすると,自動車はなくなりましたが,代わりに200万円の現金を手に入れたのですから,財産全体としては500万円のままで変わりありません。
つまり,絶対的に減少したとは言えないのです。したがって,破産法160条1項1号の詐害行為否認には当たらないのです(ただし、破産法161条で定める「相当対価を得てした処分行為の否認」の対象となる可能性はあります。)。
要件3:支払停止または破産手続開始申立て後であること
前記のとおり,2号否認の場合も,否認の対象となるのは,破産者による詐害行為であるという点は同じです。
もっとも,異なる点もあります。それは,2号否認の場合には,1号否認と異なり,詐害行為をした時期に限定があるという点です。
つまり,2号否認の場合には,「支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後」になされた破産者の詐害行為のみが,否認の対象となるということです。
支払停止とは,弁済能力の欠乏のために,弁済期の到来した債務を一般的かつ継続的に弁済することができない旨を外部に表示する債務者の行為のことです。
この「支払停止」は,「支払不能」という「状態」を客観的に表す「行為」を意味します。要するに,「支払停止」という行為をすることは,「支払不能」という状態であると言ってるようなものだ,ということです。
支払停止の代表例は,手形不渡りによる銀行取引停止です。
弁護士に債務整理を依頼して受任通知を発送した場合も、それ以降、支払いを停止しますから、この支払停止に当たるといえます。
次に,「破産手続開始の申立て」ですが,これはそのままです。破産手続開始の申立てをした後にした詐害行為も,否認の対象となります。
このように、「支払停止」や「破産手続開始の申立て」の後に行った「詐害行為」だけが,2号否認の対象となるのです。
要件4:受益者が悪意であったこと
受益者の悪意が要件とされることも、1号否認と同様です。
つまり、2号否認の場合も,受益者が善意の場合には,詐害行為否認をすることができないという意味です。
もっとも,2号否認と1合否認の場合とで異なる点もあります。それは,受益者が何について善意または悪意だったのか(何を知らなかったのかまたは知っていたのか)という,認識の対象の点です。
1号否認の場合は、「破産債権者を害する事実」について善意(知らなかったとき)には否認できないと規定されています。
これに対して、2号否認の場合は、「破産債権者を害する事実」だけでなく「支払の停止または破産手続開始の申立てがあった事実」について善意であった(知らなかった)ときも、否認できないと規定されています。
したがって、2号否認の場合は、受益者が、詐害行為の当時、「破産債権者を害する事実」と「支払の停止または破産手続開始の申立てがあったこと」の両方について悪意の(知っていた)場合のみ否認できるというわけです。
詐害意思が不要とされるのはなぜか?
1号否認では、詐害行為をいつしたのかという点は問題となっていません。「詐害意思」をもって「詐害行為」をおこなったかどうかが問題となっています。
これに対して、2号否認では、詐害行為をいつしたのかという詐害行為の時期が問題となりますが、その反面、「詐害意思」は必要とされていません。
支払停止行為や破産手続開始の申立てをするということは,支払不能であることが客観的に明らかになったということを意味します。
つまり,実質的に破産状態に陥っているということ(こういう状態のことを「危機時期」と呼ぶことがあります。)です。
実質的な破産状態になった以降は、債権者の平等を図るため、破産者による財産の自由な処分は原則として許されなくなります。
そのため,危機時期にあるにもかかわらず,詐害行為をしてしまった以上は,原則として否認の対象となると考えられます。
言いかえれば,支払停止や破産手続開始の申立て後の詐害行為は、詐害意思などなくても否認できるということです。
他方、1号否認の場合は、支払停止前であっても否認の対象となるとされます。
しかし,支払停止や破産手続開始の申立て前は,原則として財産の処分は個人(破産者)の自由です。
それにもかかわらず,悪気なく詐害行為に当たる行為をしただけで否認されてしまうというのは破産者に酷です。
そこで、1号否認の場合には、悪気がある場合、つまり詐害意思がある場合だけ否認の対象となるとされているのです。