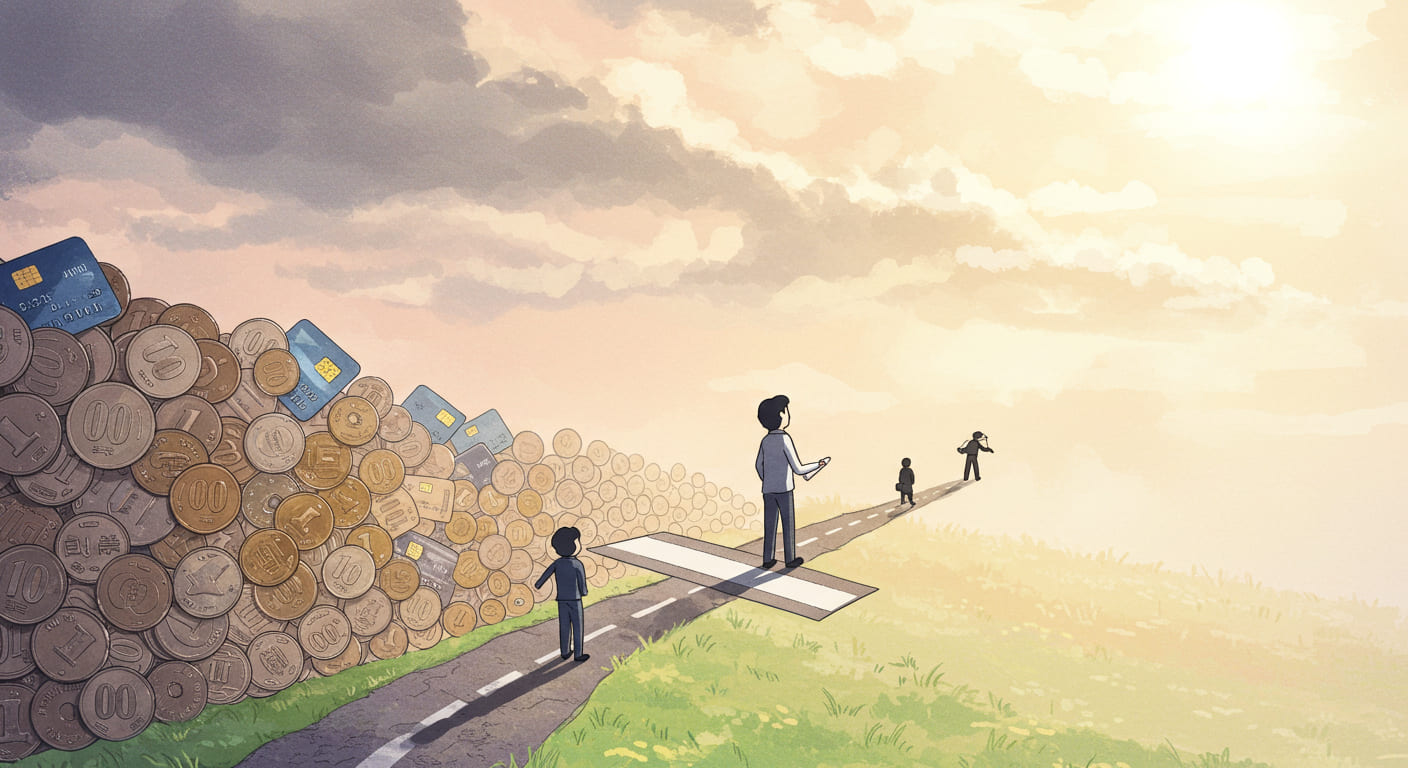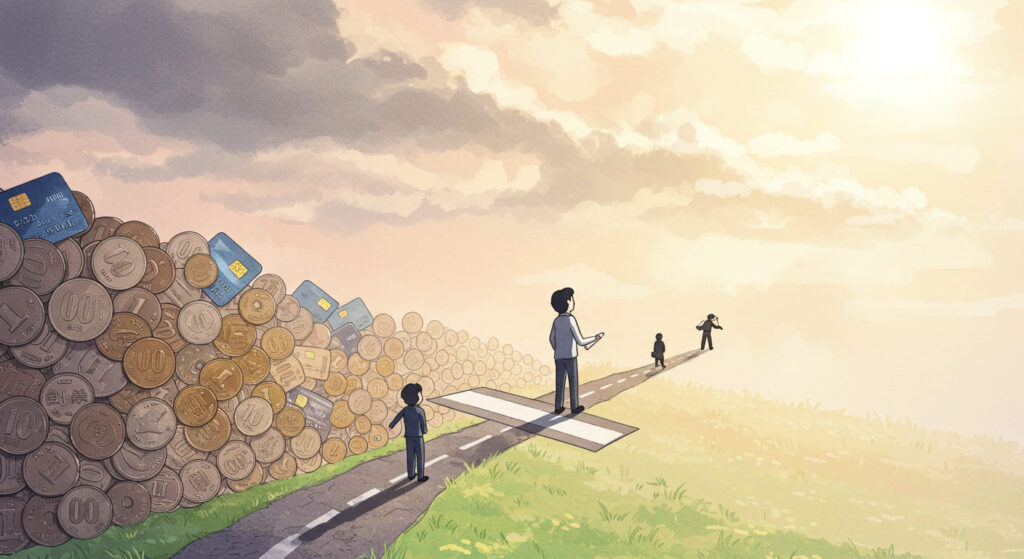
預金・貯金(払戻請求権)は,破産手続において換価処分の対象となります。したがって,預金・貯金は,自己破産すると解約され,解約返戻金は破産管財人によって回収されるのが原則です。
ただし,多くの裁判所では,預金・貯金の残高合計額が20万円以下である場合には,自由財産として扱われ,解約しなくてもよいものとされています。
自己破産における預金・貯金の取扱いの原則
法的に言うと,預金・貯金は現金とは別物です。現金というのはあくまでも手持ちのお金です。
これに対して預金・貯金は,銀行等にお金を預けてあるということですから,お金を持っているのはあくまで銀行等です。預貯金残高に相当する現金を持っているのは銀行等ということになります。
では,預貯金者が持っているのは何かといえば,債権です。銀行等に対して預貯金として預けているお金を返せと言える権利を持っているのです。
法的にいえば,消費寄託契約に基づく預託金返還請求権ということになります。一般に預金・貯金払戻請求権などと呼ぶこともあります。
この預貯金払戻請求権は差押禁止債権には当たりません。
したがって,法律上当然に自由財産となるものではないので,自己破産をすると,破産財団に組み入れられ,換価処分が必要となり,没収されてしまうのが原則です。
ただし,後述のとおり,裁判所によっては,一定の金額までの預金・貯金であれば処分の対象にならないような運用がされています。
各地方裁判所における預金・貯金の取扱い
前記のとおり,預金・貯金の債権は,原則としては,自由財産に当たらないため,自己破産をした場合には,換価処分しなければならないことになります。
もっとも,東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとして多くの裁判所では,残高が20万円以下の預貯金は,自由財産の拡張基準により,自由財産として扱うことになっています。
つまり,残高が20万円以下の預金・貯金は,自己破産しても持っていることが許されることになります。
この残高金額は,持っているすべての預金・貯金の口座の残高合計で計算されるのが通常です。
例えば,預貯金口座をABCの3つ持っていて,A口座には10万円,B口座には6万円,C口座には5万円あったとします。この場合,各口座残高を個別にみると残高20万円を超える口座はありません。
しかし,3つの預金・貯金口座残高を合計すると21万円の残高があるということになるので,換価処分が必要ということになります。
逆に,すべての口座の残高を合計しても20万円以下の場合には,すべての口座を解約しなくてもよいことになります。
預金・貯金の残高が20万円以上ある場合
前記のとおり、東京地裁や大阪地裁などであっても、預金・貯金の残高が20万円を超えている場合には、換価処分の対象になります。
換価処分の対象となる場合には、破産管財人がその口座を解約して預金・貯金残高を回収し、債権者への弁済や配当などに使われることになります。
この20万円の判断の基準時は、破産手続開始決定の時です。そのため、破産手続開始前に預金・貯金を引き出して現金として持っておくのが通常でしょう。手持ちの現金であれば、99万円まで自由財産として残しておけるからです。
ただし、あまりに破産手続開始の直前に大きな金額を引き出すと、直近現金化という問題が生じる可能性がないとはいえません。
そのため、通常は、自己破産の準備を始めた段階(弁護士等に依頼した段階)から、引き落としなどで必要な分だけ口座に残しておき、それ以外は引き出すという習慣をつけておいた方がよいでしょう。
なお、破産手続開始決定の時期によっては、給料日などと重なってしまい、申立ての時点では20万円未満であったものの、開始時点では給料などが振り込まれて20万円を超えてしまうということもあります。
その場合には、個別に自由財産の拡張を申し立てて、20万円を超えた理由を説明すれば、拡張を認めてもらえるのが普通でしょう。
預貯金と同時廃止の関係
同時廃止となるのは,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときです。したがって,預貯金の残高と他の財産を併せても,破産手続費用を支払うのに足りない場合には,同時廃止となります。
さらに,前記のとおり,東京地裁では,残高合計が20万円以下の預貯金は自由財産として扱われます。つまり,残高合計が20万円以下の預貯金は破産財団に組み入れられないことになります。
そのため,預貯金の残高が20万円以下の場合、預貯金以外の財産で破産手続費用を支払うのに不足するときには、同時廃止となります。
例えば,破産手続開始時に残高合計が15万円の預貯金とそれ以外に10万円の財産を持っていたとします(他の財産・免責不許可事由は無いものとします。)。
この場合,破産法の原則でいくと,合計で25万円の財産があることになるので,同時廃止とはなりません。しかし,東京地裁の基準で考えると、預貯金は自由財産となり破産財団に組み入れられませんから、破産財団としては預貯金を除いた10万円しか無いということになります。
したがって,20万円の破産手続費用を支払うだけの財産が無いということになるので,同時廃止となります。
ただし,これはあくまで各裁判所の「運用」です。その他の裁判所では異なる運用がとられている場合もあります。
場合によっては,財産が25万円あると判断されて,管財手続(個人の場合は少額管財)となるということも無いとは言えませんので,あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。
なお、大阪地裁では、現金と預貯金の合計額が50万円以下であれば、同時廃止として扱われる運用になっています。