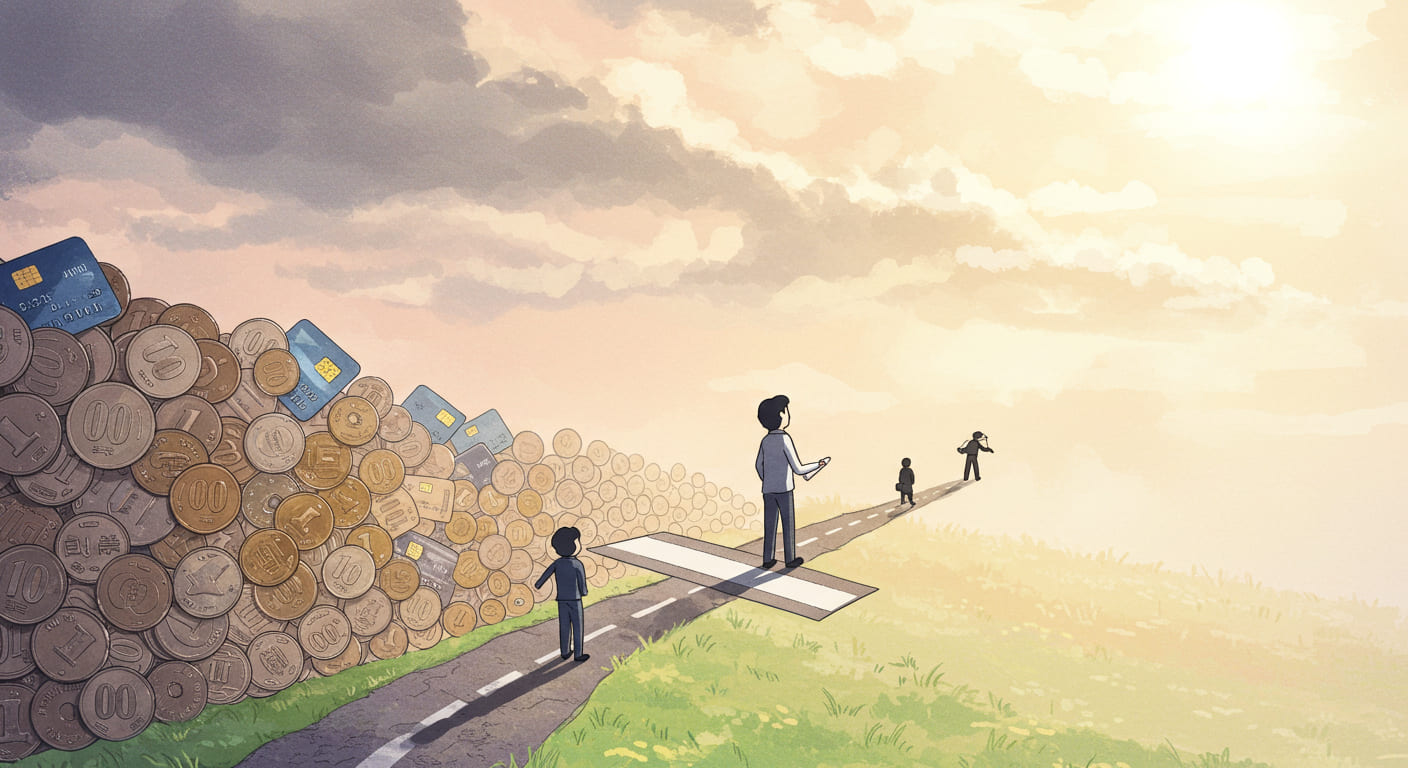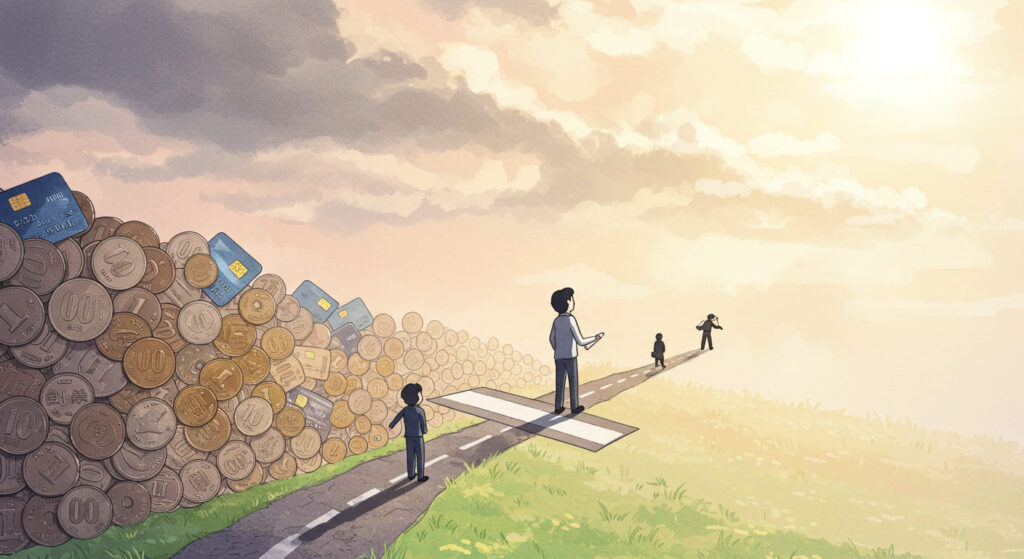
自己破産の手続において債権者に弁済または配当される金銭の原資は、破産財団に属する財産を換価処分することによって捻出することになります。個人の自己破産の場合、破産財団に組み入れられる財産は、以下の要件を満たしている財産です。
- 財産的価値(換価価値)があること
- 破産手続開始時に破産者が有していること
- 差押えが可能であること
- 現金の場合は99万円を超える部分だけであること
- 自由財産の拡張が認められたものでないこと
- 破産管財人によって破産財団から放棄されたものでないこと
破産財団に組み入れられる財産の要件
破産法 第2条
- 第12号 この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。
- 第13号は省略
- 第14号 この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
破産法 第34条
- 第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
- 第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
- 第3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
- 第1号 民事執行法(昭和54年法律第四号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
- 第2号 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
- 第4項 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
- 第5項 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
- 第6項 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
- 第7項 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
自己破産の手続においては,破産者の財産は破産管財人によって管理・換価処分され(破産法78条1項),それによって得られた金銭を債権者に弁済または配当することになります。
この破産管財人によって管理・処分される財産の総体を「破産財団」といいます。
この破産財団に属する財産は,もともとは破産者の財産です(破産法34条1項)。もっとも,破産者のすべての財産が破産財団に組み入れられるわけではありません。自由財産に該当する財産は、破産財団に組み入れられません。
破産財団に組み入れられる財産は,以下の要件を満たす財産です。
財産的価値(換価価値)があること
破産財団に組み入れられるものは、まず第一に、財産的価値(換価価値)のある財産でなければなりません。
この財産は,「物」には限られません。債権や特定の権利のような観念的なものも,お金に換えることができるものであれば,破産財団に組み入れられる「財産」に含まれます。
また,権利だけでなく営業ノウハウのようなものも,金銭に換えることができるものである限り,「財産」に含まれると考えられています。
他方,物であろうと権利であろうと,そもそも金銭に換えられないもの(換価できないもの)は,破産財団に組み入れられる財産には含まれないことになります。
破産手続開始時に破産者が有していること
破産財団に組み入れられる「財産」は,破産者の財産であることは当然ですが,破産者のすべての財産というわけではありません。
破産財団に組み入れられる破産者の財産は,破産手続開始時に破産者が有しているものに限定されています。
破産手続は,裁判所の破産手続開始決定によって開始されますから,この開始決定時に破産者が持っている財産だけが破産財団に組み入れられることになります。
したがって、開始決定より後に破産者が手に入れた財産(これを「新得財産」といいます。)は、自由財産となり、破産財団に組み入れられることはありません。
また,開始決定より前に失った財産も,破産財団には組み入れられないのが原則です。ただし,開始決定より前に失った財産については,場合によっては否認権行使によって,破産財団に強制的に組み入れられることもあります。
差押えが可能であること
法律上、差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)は、自己破産の手続においても自由財産となります(破産法34条3項2号)。したがって、破産財団に属する財産は、差押えが可能なものでなければなりません。
差押えと破産手続
強制執行とは,債務者が債務を履行しなかった場合に,国家権力の力を借りて強制的に債務を履行させる手段のことをいいます。差押えは,この強制執行の1つです。
差押えとは、債務者が有している物や債権などの財産を債権者が強制的に自分のものにして、自分の債権に充てることをいいます。
これはよく考えてみると,破産手続に共通するところがあります。破産も強制執行と同じように,債務者の財産を強制的に処分して債権に充てるという点で共通するのです。
違うのは,強制執行が特定の債権者と特定の債務者の財産の清算だけを目的としているのに対し,破産はすべての債権者と債務者のすべての財産を清算することを目的としているという点だけです。
そのため,破産は包括的な強制執行の性質を有していると言われることがあります。
差押えが可能であること
破産手続が上記のような包括的強制執行の性質を有していると考えられていることから,破産財団に組み入れられるものは,破産手続開始時に破産者が有している財産のうちで差押えが可能なものだけに限られるとされています。
差押えが禁止されている財産(これを「差押禁止財産」といいます。)は,破産手続開始時に破産者が有しているものであっても,破産財団に組み入れることはできません。
差押禁止財産は強制執行において処分が禁止される以上,包括的な強制執行の性質を有する破産においても,やはり換価処分を禁止する必要があるからです。
現金の場合は99万円を超える部分だけであること
現金は、もちろん財産的価値があります。したがって、破産財団に組み入れられる財産です。
もっとも、民事執行法では、66万円以下の現金は差押禁止財産とされています(民事執行法131条3号、民事執行法施行令1条)。破産法では、この範囲を拡大し、99万円以下の現金は自由財産とされています(破産法34条3項1号)。
したがって、破産財団に組み入れられる現金は、99万円を超える場合です。99万円を超える場合には、その超えた部分のみが、破産財団に組み入れられます。
自由財産の拡張が認められた財産でないこと
自由財産となるのは、新得財産、差押禁止財産、99万円以下の現金です。もっとも、これらに当たらない財産であっても、裁判所の決定によって、自由財産の拡張が認められた財産は、自由財産として扱われます。
したがって、破産財団に組み入れられる財産は、裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産ではないことが必要となります。
破産財団から放棄された財産でないこと
例えば、換価価値が低く、換価処分する費用の方が換価して得られる金銭よりも大きいような場合、破産管財人は、裁判所の許可を得て、その財産を破産財団から放棄することができます(破産法78条2項12号)。
破産財団から放棄された財産は自由財産になります。したがって、破産財団から放棄された財産は、破産財団に組み入れられません。
まとめ
破産財団の要件として,破産手続開始時に破産者が有していることや差押えが可能なことを挙げてきました。個人破産においては、破産財団に組み入れられる財産=自由財産に該当しない財産です。
要するに、破産財団に組み入れられる財産の要件と自由財産の要件は裏返しの関係にあるのです。