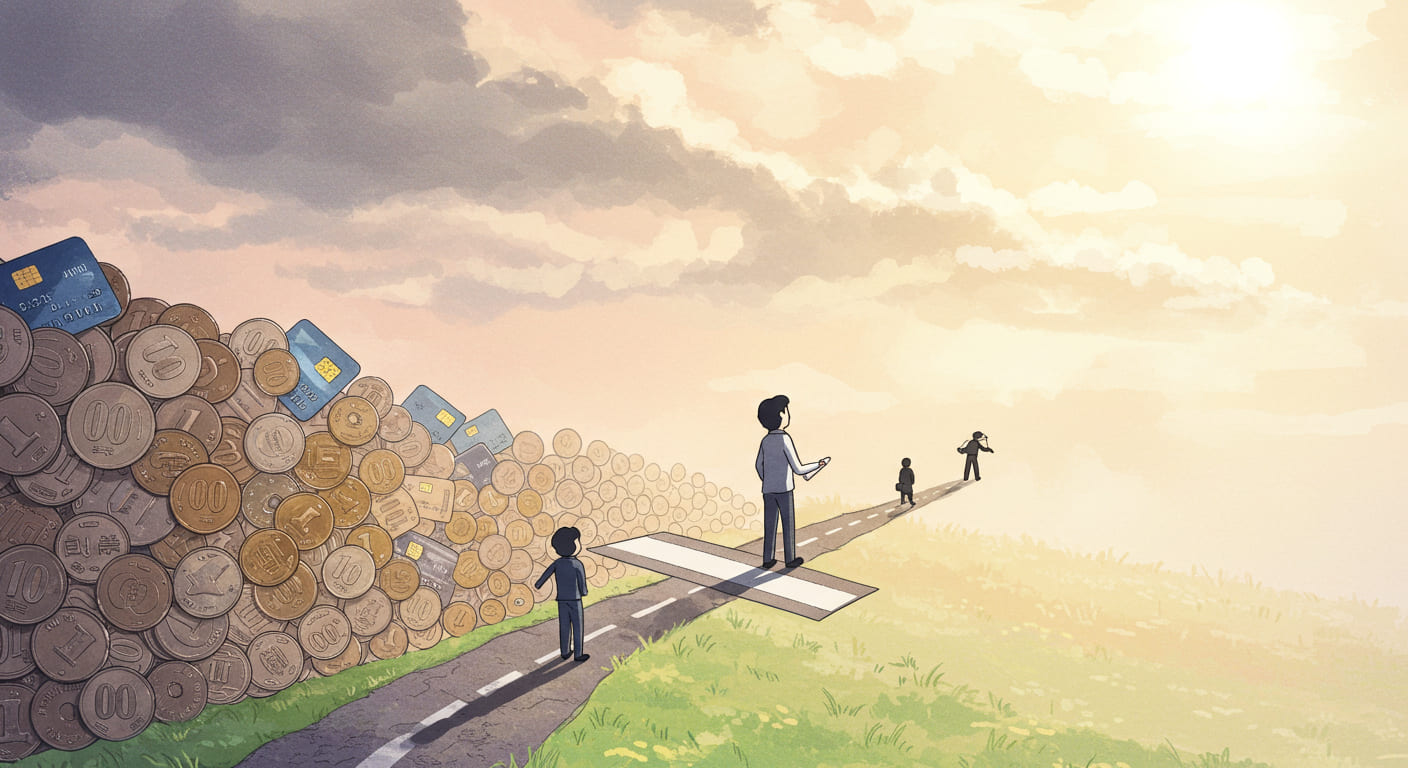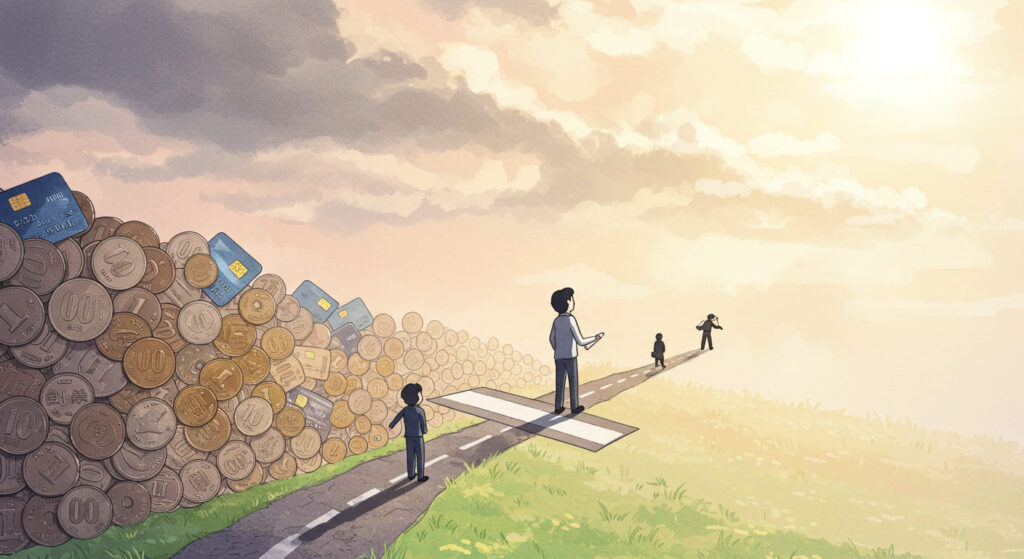
免責されない非免責債権の1つに「罰金等の請求権」があります。罰金等の請求権とは、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料の請求権のことです。これらは、自己破産しても免責されません。
非免責債権となる罰金等の請求権
破産法 第253条
- 第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
- 第7号 罰金等の請求権
個人(自然人)の自己破産の目的は,免責の許可を受けることです。免責とは,借金など債務の支払い義務を免除してもらうことをいいます。
もっとも,免責の許可を受けたかどうかにかかわらず,そもそも免責許可によっても,支払い義務を免れることができない債権があります。そのような債権のことを非免責債権といいます。
この非免責債権の1つに「罰金等の請求権」があります(破産法253条1項7号)。
罰金等の請求権とは
破産法第97条第6号には「罰金,科料,刑事訴訟費用,追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。) 」と規定されています。
つまり,罰金等の請求権とは,以下の請求権の総称ということです。
- 罰金の請求権
- 科料の請求権
- 刑事訴訟費用の請求権
- 追徴金の請求権
- 過料の請求権
これらは、犯罪や法令違反などに対する制裁として課される金銭の請求権です。これらを自己破産で免責できるとすると、制裁としての機能を失ってしまいます。そのため、非免責債権とされているのです。
「罰金」「科料」の請求権
「罰金」と「科料」は,いずれも刑罰として強制的に取り立てられる金銭のことです。簡単に言うと、犯罪を犯したときに罰として取られるお金です。
取立てられる金額が1万円以上の場合を罰金、1万円未満(1000円以上1万円未満)の場合を科料といいます。
この罰金および科料の請求権は、非免責債権となります。
「過料」の請求権
前記の「科料」と「過料」は、読み方は同じく「かりょう」ですが、内容は異なります。過料は、犯罪を犯したことにより刑罰として取り立てられる罰金や科料とは異なるものです。
「過料」とは,刑罰以外の理由で強制的に取り立てられる金銭のことです。行政上の規律違反を犯した場合などに取り立てられるお金です。
この過料の請求権は、非免責債権となります。
「追徴金」の請求権
「追徴金」制度とは、犯罪に使われたり、犯罪によって犯人が手に入れた物は本来没収すべき物ですが、それを没収できなかった場合、その代わりに金銭を支払わせるという制度です。
例えば,詐欺によって犯人が高額の宝石などを騙し取ったとします。この場合,本来ならばその宝石を没収すべきです。ところが,この宝石はすでに海外へ売り飛ばされて見つからなくなってしまいました。
そういう場合,この宝石の価額を追徴金として犯人に支払わせることになります。
この追徴金の請求権も、非免責債権となります。
「刑事訴訟費用」の請求権
「刑事訴訟費用」とは、刑事訴訟をするに際して必要となった費用のことです。被告人は、無罪とならない場合には、刑事訴訟費用を負担しなければならないことがあります。
刑事訴訟費用としては、通訳料、翻訳料、鑑定費用、証人の日当や旅費、場合によっては国選弁護人の報酬などがあります。なお、私選の弁護士費用は含まれません。
この刑事訴訟費用の請求権も、非免責債権となります。