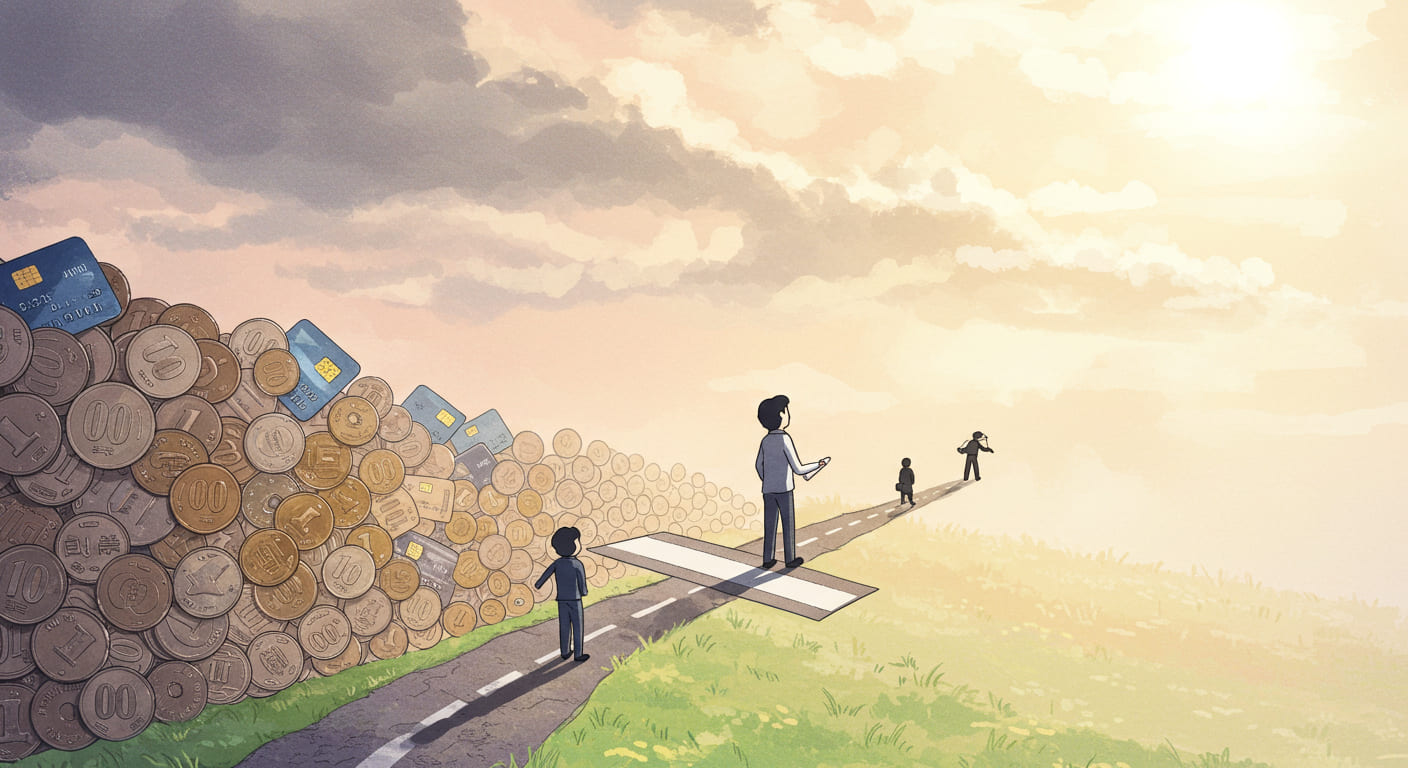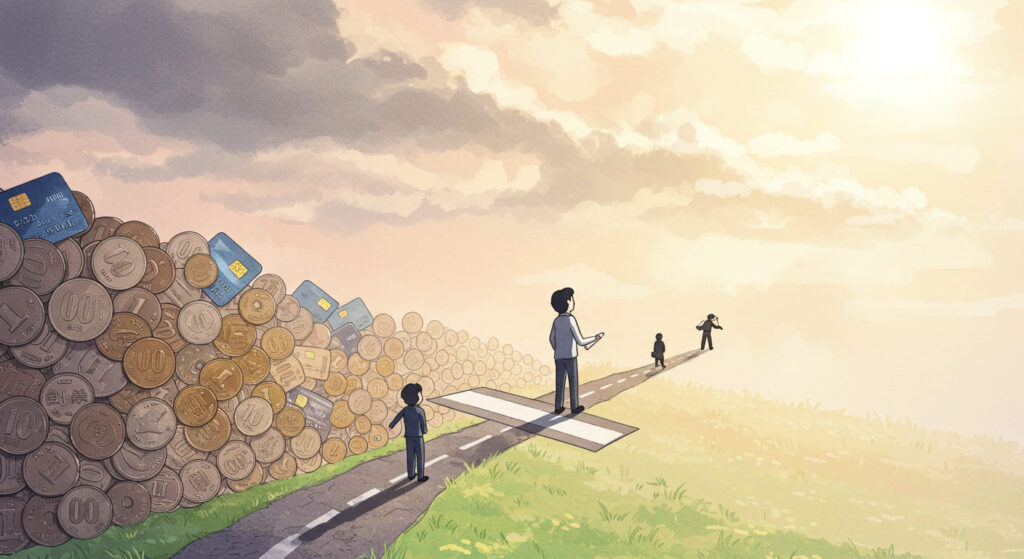
自己破産手続には,大きく分けると,破産管財人が選任され,その破産管財人が財産の調査・管理・換価処分や免責の調査を行う「管財手続(管財事件)」と,破産管財人が選任されず,破産手続開始と同時に破産手続が廃止により終了する「同時廃止手続」とがあります。
ただし,東京地方裁判所などでは,管財手続になる場合であっても,引継予納金の額を少額化し,手続を簡易迅速化させた「少額管財」の運用が行われています。
また、厳密に言うと、財産の換価処分を行って債権者に弁済・配当する「破産手続」と免責を許可するかどうかを審査する「免責手続」は別個の手続です。ただし、破産手続と免責手続は一緒に進められるのが通常です。
そのため、一般に自己破産の手続という場合には、破産手続と免責手続の両方を含めているのが普通でしょう。
自己破産の意味
破産手続とは,破産者の財産を換価処分して,債権者に弁済または配当するという裁判手続です。この破産手続は,債権者からも,または破産をする債務者自身からも申立てをすることができます。
債権者が債務者の破産を申し立てることを「債権者破産申立て」といいます。これに対して,破産する債務者自身が,自らの破産を申し立てることを「自己破産」と呼んでいます。
債権者申立ての場合も自己破産申立ての場合も,手続きの基本的な流れは同じです。
自己破産の手続において裁判所から免責許可決定を受けることができれば,支払い切れなかった借金・債務の支払義務を免れることができます。
自己破産の手続の種類
破産手続には,大きく分けると2つの種類があります。
それは,破産管財人が選任される「管財事件(管財手続)」と破産管財人が選任されない「同時廃止事件(同時廃止手続)」です。
また、東京地方裁判所や大阪地方裁判所など多くの裁判所で、管財事件について引継予納金を少額とする「少額管財」の運用が実施されています(裁判所によって名称が異なる場合があります。)。
管財手続
破産手続の原則的形態は「管財手続」です。
管財手続とは,裁判所により破産管財人が選任され,その破産管財人が破産者の財産を調査した上で管理・換価処分し,それによって得た金銭を債権者に弁済・配当をする手続です。
債権者に弁済・配当するほどの財産が無い場合には,弁済・配当をせずに破産手続は終了となります。これを異時廃止といいます。異時廃止で終了する場合のことを「異時廃止事件」と呼ぶこともあります。
同時廃止手続
破産手続においては,例外的に「同時廃止」によって終了することがあります。
同時廃止手続とは,破産者に破産財団を構成する財産がないことが明らかな場合(つまり,債権者に配当する財産がないことが明らかな場合)に,破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産廃止決定をするという手続です。
異時廃止は,破産管財人による調査の結果,配当すべき財産がないため,破産手続開始決定後に破産手続が廃止となる場合です。
これに対して,破産手続開始決定時点で配当すべき財産がないことが明らかなため,開始決定と同時に破産手続が廃止となるのが同時廃止です。
少額管財
個人の自己破産の場合でも,管財事件として扱われることはあります。
ただし,個人(自然人)の破産の場合には,管財事件であっても「少額管財」という制度が用いられるのが一般的です。
少額管財とは,管財手続の運用方法の1つです。これは,手続を簡素化して破産管財人の業務を軽減する代わりに,破産申立てにおいて納付すべき予納金の金額を少額にすることを認めるという手続です。
現在では,東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとして数多くの裁判所において,少額管財の運用(または,それに類する運用)がなされています。
東京地方裁判所・大阪地方裁判所では、引継予納金の額は20万円からとされています(いずれも弁護士が代理人となっている場合のみ。)。
個人の自己破産の場合には,主として,上記少額管財手続と同時廃止手続のいずれかが採用されることになります。
ただし,非常に稀ではありますが,債権者数が非常に多いとか,処分すべき財産が非常に多いような場合には,少額でない管財事件として扱われる場合もまったくないわけではありません。
破産手続と免責手続
前記のとおり,破産手続とは,破産者の財産を換価処分して,債権者に弁済または配当するという裁判手続です。この破産手続は,破産法によって定められています。
個人の破産の場合,借金の支払義務を免除してもらうことが自己破産の主たる目的ですが,法的にいうと,破産手続には借金等の債務の支払義務の免除という効果はありません。
破産手続は,単に財産を処分して,各債権者に対して配当等をするというだけです。
会社など法人の場合であれば,破産によって法人自体がなくなりますので,債務も消滅することになり,支払義務免除といったことは考える必要はありません。
しかし,個人の場合は,破産したからといって消滅するわけではありません。破産手続後も生活をしていかなければならないのです。したがって,破産手続によっても支払いきれなかった債務の支払義務の免除が必要となってきます。
そこで,個人の破産手続においては,破産手続とは別個に,免責手続という手続が行われます。その免責手続において,裁判所によって免責許可決定がされれば,これによって債務の支払義務の免除の効力が発生することになります。
この破産と免責の手続は同時に申立てを行い,手続も同時進行するのが通常ですので,両者は一体の手続といってよいでしょう。
一般的に個人の「自己破産」の手続が述べられている場合には,破産手続と免責手続の両方を含めた意味で述べられていることが多いでしょう。
自己破産の手続の流れ
管財手続であっても,同時廃止手続であっても,自己破産の手続を開始してもらうためには,管轄の裁判所に対して自己破産の申立て(破産手続開始・免責許可の申立て)をしなければなりません。
破産手続開始・免責許可の申立ては,「破産手続開始・免責許可の申立書」を裁判所に提出する方式によって行います。
申立てを受理した裁判所は,破産手続開始の要件を充たしているかどうかを審査し,要件を充たしていると判断した場合には,破産手続開始の決定をします。
この際に,破産管財人を選任するかどうか,つまり,管財手続とするか同時廃止で終了させるかどうかが決められます。
同時廃止の場合,破産手続開始と同時に,破産手続を廃止させる決定がされ,破産手続は開始と同時に終了します。あとは,免責手続のみを行うことになります。
これに対し,管財手続になる場合には,破産手続開始決定と同時に,破産管財人が選任され,自由財産を除く債務者(破産者)の財産の管理処分権は,破産管財人に専属することになります。
そして,破産管財人が,財産の調査・管理・換価処分を行っていきます。また,免責不許可事由の有無や裁量免責事由の有無などの免責に関する調査も行われます。
破産手続開始から概ね2~3か月後に,同時廃止の場合であれば免責審尋,管財手続の場合であれば債権者集会が行われます。
同時廃止の場合には,免責審尋の後,裁判所によって免責に関する決定がなされるとすべての手続が終了となります。
管財手続の場合には,管財業務が終了していれば,債権者集会は1回で済みますが,終了していないのあれば,終了するまで,債権者集会は2回,3回・・・と続行されていきます。
管財業務が終了し,配当するだけの破産財団が集まらなかった場合には,その債権者集会で破産手続は異時廃止により終了となります。
そして,債権者集会に引き続いて,同時廃止と同じように,免責審尋が行われ,その後に裁判所によって免責に関する決定がなされます。
配当するだけの破産財団が集まっていた場合には,債権者集会は終了して免責審尋が行われ,その後,配当手続に入ります。
配当が終了すると破産手続は終了になりますが,免責許可決定自体はその前にされるのが一般的です。