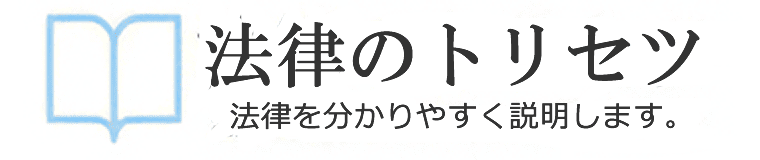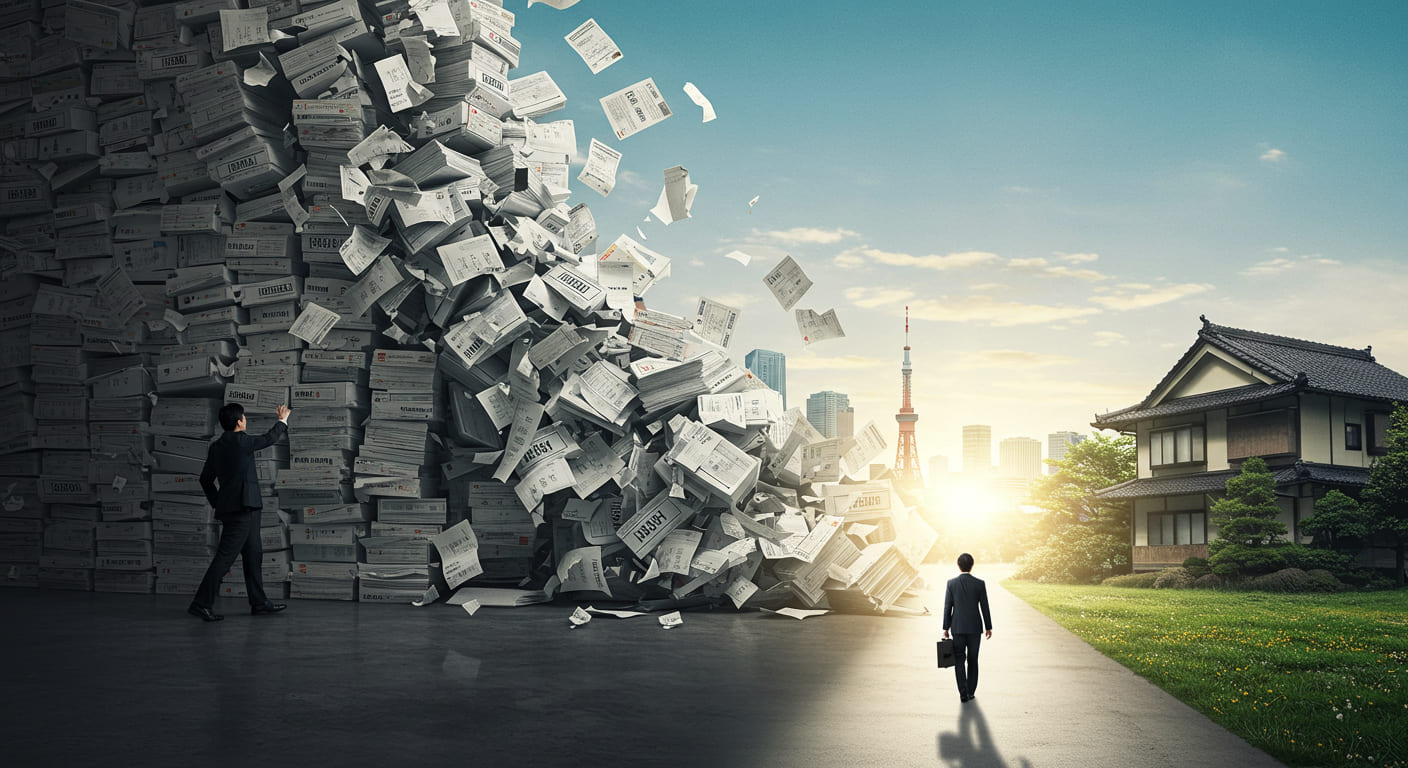この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
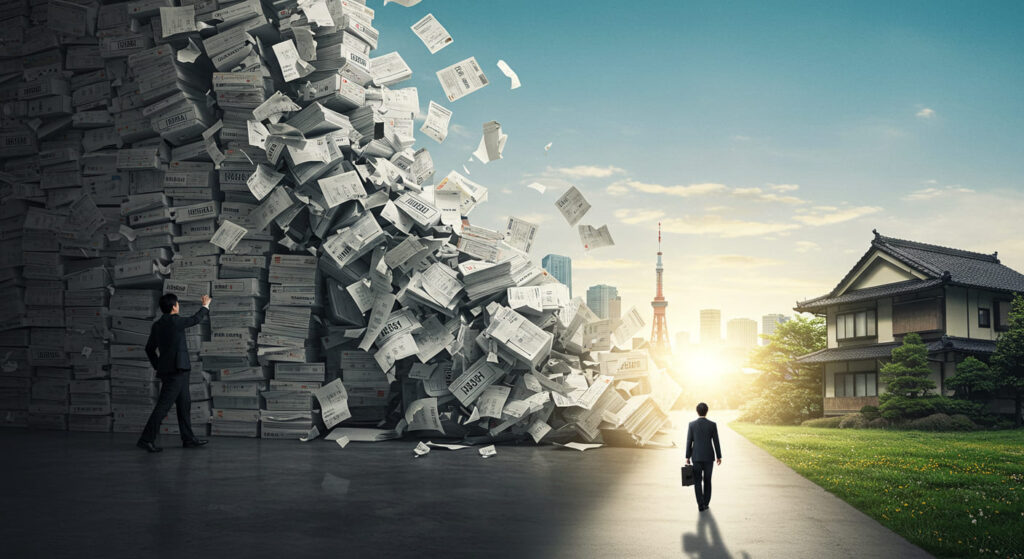
利息制限法所定の制限利率を超える利息が元本に充当されることをはじめて判断した判例として,最高裁判所大法廷昭和39年11月18日判決があります。
制限超過利息の元本充当と引き直し計算
貸金業者からの借金について債務整理を行う場合、貸金業者から取引履歴の開示を受けて、それをもとに引き直し計算を行います。
引き直し計算とは、貸金業者との間で行ってきたすべての貸し借りの取引を利息制限法所定の制限利率に直し、制限超過利息をすべて借入れ元本に充当しながら、利息制限法に従った正式な債務残高に計算をし直していく計算手法のことです。
現在では,当たり前になっている引き直し計算という手法ですが、最初から当然に認められていたわけではありません。
上記のとおり、引き直し計算は、利息制限法所定の制限利率を超える利息を支払った場合に、その制限超過利息を貸金元本に充当する計算方法です。したがって、制限超過部分を元本に充当することができることが根拠となっています。
もっとも,利息制限法には,かつて「債務者において超過部分を任意に支払つたときは,その返還を請求することができない」とする規定がありました(利息について旧利息制限法1条、遅延損害金について旧利息制限法4条。現在ではいずれも削除)。
この規定があったため,債務者が任意に制限超過利息を返済をすると,その制限超過利息の返還を請求できなくなる以上,貸主が制限超過部分を受け取っても,それが任意の返済である限り有効な支払いになると解釈されていました。
そして,支払済みの制限超過利息が有効な利息の支払いと解釈できる以上,その制限超過利息が元本に充当されることもないと考えられていました。現に、かつての最高裁判例も、制限超過部分の元本充当は認められないと判断していました。
つまり,引き直し計算はできないと解釈されていたのです。
その従前の判例を変更し,利息制限法の制限超過部分を元本に充当することができると判断した判例が,最高裁判所大法廷昭和39年11月18日判決(以下「最大判昭和39年11月18日」といいます。)です。
最大判昭和39年11月18日の判断
最大判昭和39年11月18日は、以下のとおり判示しています(一部抜粋)。
債務者が,利息制限法(以下本法と略称する)所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息,損害金を任意に支払つたときは,右制限をこえる部分は民法491条により残存元本に充当されるものと解するを相当とする。
(中略)
債務者が利息,損害金の弁済として支払つた制限超過部分は,強行法規である本法1条,4条の各1項により無効とされ,その部分の債務は存在しないのであるから,その部分に対する支払は弁済の効力を生じない。従つて,債務者が利息,損害金と指定して支払つても,制限超過部分に対する指定は無意味であり,結局その部分に対する指定がないのと同一であるから,元本が残存するときは,民法491条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。
本法1条,4条の各2項は,債務者において超過部分を任意に支払つたときは,その返還を請求することができない旨規定しているが,それは,制限超過の利息,損害金を支払つた債務者に対し裁判所がその返還につき積極的に助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。
また,本法2条は,契約成立のさいに債務者が利息として本法の制限を超過する金額を前払しても,これを利息の支払として認めず,元本の支払に充てたものとみなしているのであるが,この趣旨からすれば,後日に至つて債務者が利息として本法の制限を超過する金額を支払つた場合にも,それを利息の支払として認めず,元本の支払に充当されるものと解するを相当とする。
更に,債務者が任意に支払つた制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは,経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。右の解釈のもとでは,元本債権の残存する債務者とその残存しない債務者の間に不均衡を生ずることを免れないとしても,それを理由として元本債権の残存する債務者の保護を放擲するような解釈をすることは,本法の立法精神に反するものといわなければならない。
引用元:裁判所サイト
基本的な判断の枠組み
上記判決の基本的な判断の枠組みは、以下のとおりです。
弁済の充当の指定とは、債務者が債務を返済(弁済)する際に、どの債務に対して支払いをするのかを指定できるとする制度です。
例えば、利息・遅延損害金・元本の債務が存在する場合、債務者は、支払いをする際に、利息・遅延損害金・元本のどれに対して支払いをするのかを指定できます。
本件の場合、債務者は、利息や遅延損害金を指定して弁済をした場合、本来であれば、弁済充当指定により、その支払いは利息や遅延損害金に支払ったことになる(充当される)はずです。
しかし、最大判昭和39年11月18日は、上記の判断枠組みにあるように、たとえ債務者が利息や遅延損害金を指定して制限超過部分を弁済したとしても、充当指定は効力を生じないので、民法491条により元本に充当されるとしたのです。
判断の理由付け
上記の判断の根拠として、最大判昭和39年11月18日は、以下の理由を挙げています。
- 旧利息制限法1条・4条は、任意に制限超過利息を支払った場合に、その返還に裁判所が積極的に助力を与えないとした趣旨にすぎない
- 利息の天引きの場合、制限超過部分の支払いを元本への支払いとみなしている旧利息制限法2条の趣旨は、後日に利息を支払う場合にも妥当する
- 制限超過部分が元本に充当されると考えることは、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする利息制限法の立法趣旨に合致する
前記の判断において最も障害となるのは、「債務者において超過部分を任意に支払つたときは,その返還を請求することができない」とする旧利息制限法1条・4条の各規定です。
しかし、これらの規定は、任意に制限超過利息を支払った場合に、その返還に裁判所が積極的に助力を与えないとした趣旨にすぎないことを理由に挙げています。
つまり、債務者が任意に制限超過部分を支払った場合、これを返還するよう請求することまでは認められないものの、制限超過利息の支払いとその受領までも有効となるものではない(制限超過部分の支払は無効であることには変わりがない)と判断をしているのです。
この旧利息制限法1条・4条との関係については、以下のように判断しています。
以上のような理由から、最大判昭和39年11月18日は、従前の判例を変更して、利息制限法所定の制限利率を超える利息を支払った場合、その制限超過部分は、民法491条により元本に充当されるとの判断をしています。
最大判昭和39年11月18日が実務に与えた影響
この最大判昭和39年11月18日によってはじめて,制限超過部分の元本充当が認められるようになり,利息制限法違反の取引について元本充当計算(引き直し計算)の手法をとることができるようになりました。
その意味では,債務整理において,最も重要な判例といってよいでしょう。
ただし,この判決においては,債務者が弁済充当指定をした場合でなく、当事者間で弁済充当指定の合意があった場合にはどうなるのかについてまでは判断されていません。
また、元本充当後の制限超過部分の利息の返還,すなわち,過払い金の返還についても認められていません。
元本充当指定合意がある場合の判断や過払い金返還請求について、この判決よりも後の判決(最三小判昭和43年10月29日、最大判昭和43年11月13日)まで待つことになります。