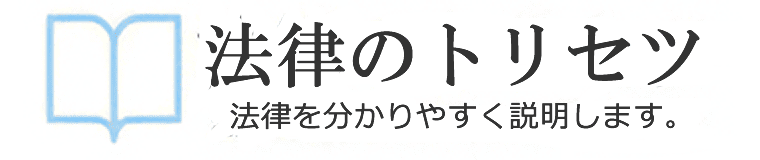この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の規定に基づいて債権の回収・管理を専門的に行う会社のことを債権回収会社(サービサー)といいます。債権管理・回収業務を行うためには,法務大臣の許可が必要とされています。
債権回収会社(サービサー)とは
貸金などの債権の回収について依頼を受けて業務として行うことは、弁護士法で定める「法律事務」に当たります。そのため、原則として、弁護士以外は行うことができません。
もっとも,バブル崩壊後,不良債権の増大に伴い,この不良債権を専門的に管理・回収する企業を設立して,不良債権処理を早急に進めていくことが社会的に必要とされるようになりました。
つまり,債権の管理回収を専門とする株式会社の設立が必要となってきたのです。この債権管理回収を専門に行う株式会社のことを「債権回収会社(サービサー)」といいます。
とはいえ,現在でも問題となることがありますが,脅迫的・威圧的・執拗な取立てを行うような業者や暴力団関係者が債権回収を専門的に行うようになると,不良債権処理のためとはいっても,債務者の生活を不必要に脅かすことになってしまいます。
そこで,弁護士法の特例として不良債権処理のための債権回収会社の設立を認めつつも,債権管理回収業を法務大臣による許可制として債権回収の適正を図るための法律として「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が制定されています。
債権回収会社の規制
前記のとおり,債権回収の代行を業務として行うためには,サービサー法により,法務大臣の許可が必要とされています。この許可なく債権回収を業務として行うことはできません(サービサー法2条、3条)。
法務大臣から許可を受けるためには,サービサー法に規定されている厳格な要件が必要となります。株式会社であれば,どこでもサービサーとなれるわけではありません。
例えば,資本金5億円以上であること,弁護士が常務に従事する取締役に加わっていること,暴力団関係者とのかかわりがないこと,法務大臣の許可取消しやサービサー法等による罰金刑の執行をうけたことがある場合にはそれがなくなったときから一定期間を経過していること等の要件が必要となっています(サービサー法5条)。
取締役となる弁護士に適格性があるかどうかは,法務省から日本弁護士連合会(日弁連)に対する意見聴取が行われ,それに基づいて各弁護士会からの推薦が行われます。
なお,法務大臣の許可を受けていない業者が,他の業者の委託を受けて債権回収業務を行うことはできません(サービサー法19条1項)。
そのような違法な無許可業者からの請求が来た場合には,専門家に相談すべきです。また,まったくの架空請求の場合もあります。
そのような場合には警察等に相談することも必要でしょう。債権回収会社から請求が来た場合,念のため,下記ページを確認しておいた方がいいでしょう。
債務整理との関係
この債権回収会社が行うことのできる債権回収は,「特定金銭債権」の回収です。この特定金銭債権には,貸金業者の貸金債権も含まれます。
したがって,債務整理の相手方が債権回収会社となる場合は少なくありません。
債務整理を依頼した弁護士や司法書士が貸金業者や銀行などに対して受任通知を送付した後,その債権が債権回収会社に譲渡されて債権者が変更になる場合や債権回収会社に取立てを委託する場合もあるでしょう。
ケースバイケースですが,むしろその方が交渉がしやすくなるということもあります。
また,弁護士が債権回収会社に受任通知を送付すると, 債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条に基づき,貸金業者に受任通知を送付した場合と同様,債務者に対する直接の取立てが停止されることになります。