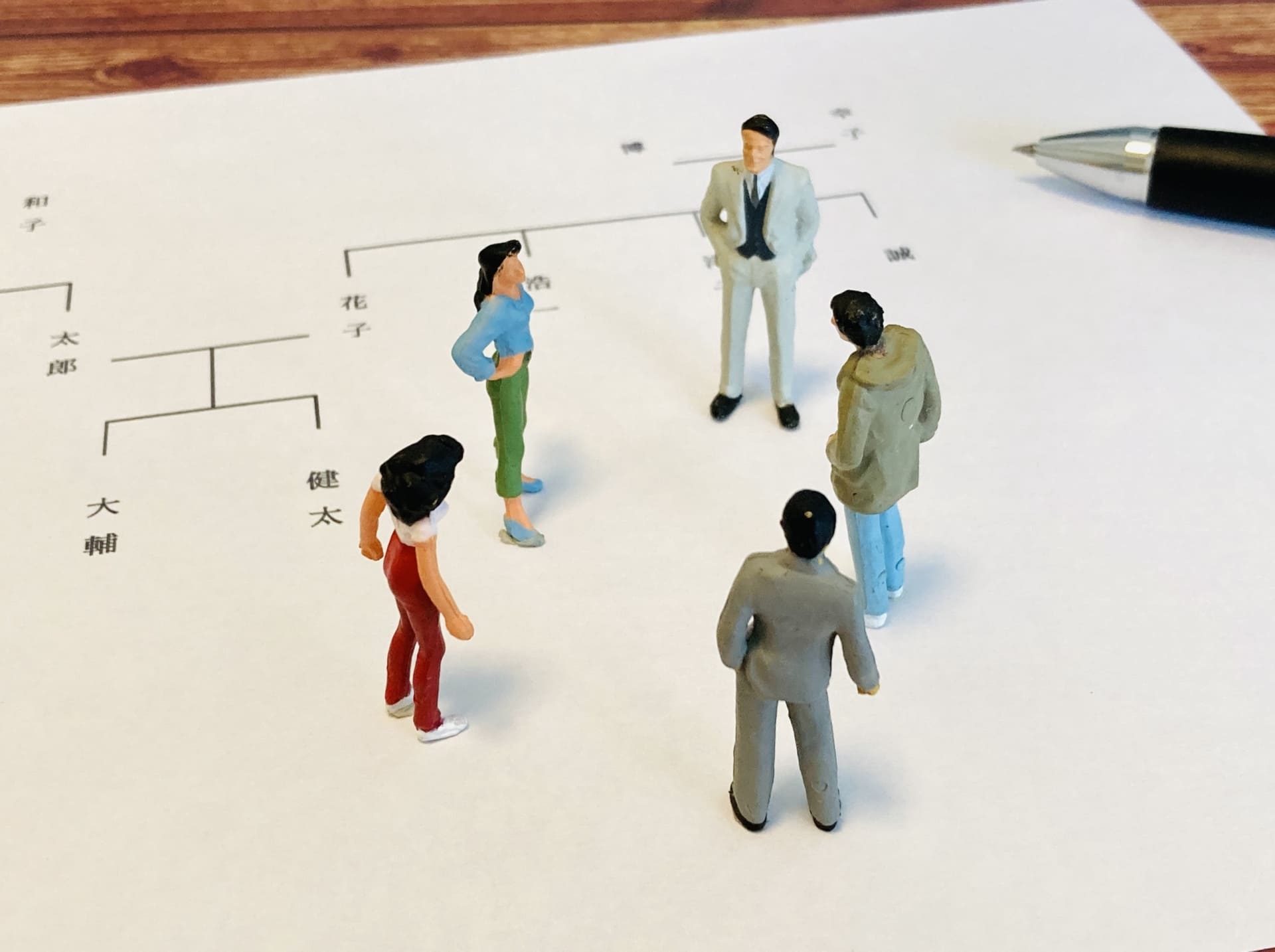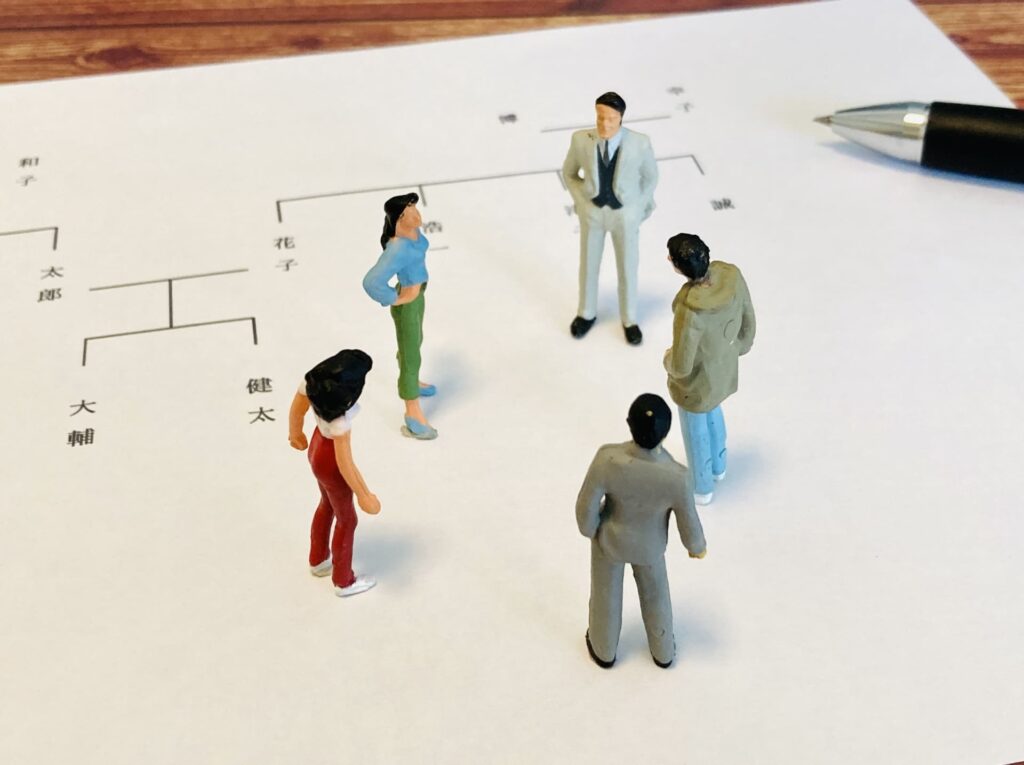
推定相続人から相続資格を奪う方法としては,「遺言」による場合と「推定相続人の廃除」による場合とが考えられます。
推定相続人から相続資格を奪うことができる場合
相続が開始された時に法定相続人となるべき人のことを,相続開始前の段階では「推定相続人」と呼んでいます。
相続人としての資格が失われる制度として,相続欠格があります。もっとも,この相続欠格は,一定の欠格事由がある場合に,当然にその相続資格が失われることを意味しますから,相続資格を「奪う」という場合とは違います。
ここでいう相続資格を「奪う」とは,被相続人の意思で,特定の相続人から相続資格をはく奪する場合のことをいいます。
推定相続人から相続資格を奪う方法としては,「遺言」による場合と「推定相続人の廃除」による場合とが考えられます。
遺言による相続資格のはく奪
遺言による相続資格のはく奪といっても,厳密にいえば,遺言で相続資格そのものをはく奪することができるというわけではありません。
(※ただし,後記の相続人の廃除を遺言に記載しておくことはできます。また,相続人でないものとするという記載が,遺言で相続人の廃除をする意思で記載されたものであるという認定がなされる場合もあり得ます。)。
遺言ですることができるのは,相続分を法定相続分とは異なる配分にすることができるというだけです。
ある推定相続人を相続人ではないものとする,というような遺言をすることはできませんし,このような遺言をしても(推定相続人の廃除の場合を除いては)効力を生じません。
もっとも,遺言で,ある特定の相続人にだけはまったく財産を相続させないということは可能です。
例えば,子AとBが推定相続人である場合,法定相続分は2分の1ずつですが,遺言で,Aにすべての財産を相続させるという遺言をすることは可能であるということです。
この場合,Bは相続資格を奪われたわけではありませんが,事実上,相続を受けられなくなるので,相続資格を奪われるのに等しい効果が生ずるといえるでしょう。
ただし,兄弟姉妹を除く法定相続人には,遺留分があります(民法1042条)。この遺留分は遺言によっても侵害することができません。したがって,遺留分を侵害する限度で遺言は効力を失います。
上記の例でいうと,Bには遺留分があります。Bの遺留分は相続財産の4分の1ですから,この4分の1の限度で遺言は効力を失い,相続開始後,Bは全財産を相続したAに対して,この遺留分に相当する金額の支払いを請求することができます。
推定相続人の廃除による相続資格のはく奪
民法 第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
前記のとおり,遺言の場合には,推定相続人が遺留分権者であれば,すべて相続できないようにすることはできません。
もっとも,被相続人に対して虐待をしてきたり,見捨てていたりしたような推定相続人に,遺留分すら相続させたくないという場合はあるでしょう。
そこで,法は,被相続人の意思を尊重するため,推定相続人の廃除という制度を用意しています。
具体的にいえば,被相続人に対する虐待,重大な侮辱その他著しい非行があった推定相続人(遺留分のある相続人に限る)の相続資格をはく奪するという制度です。
この相続人の廃除が認められると,その推定相続人は相続資格を失い,相続分はおろか遺留分もなくなることになります。なお,前記のとおり,相続人の廃除は,遺言で定めておくこともできます(遺言廃除)。