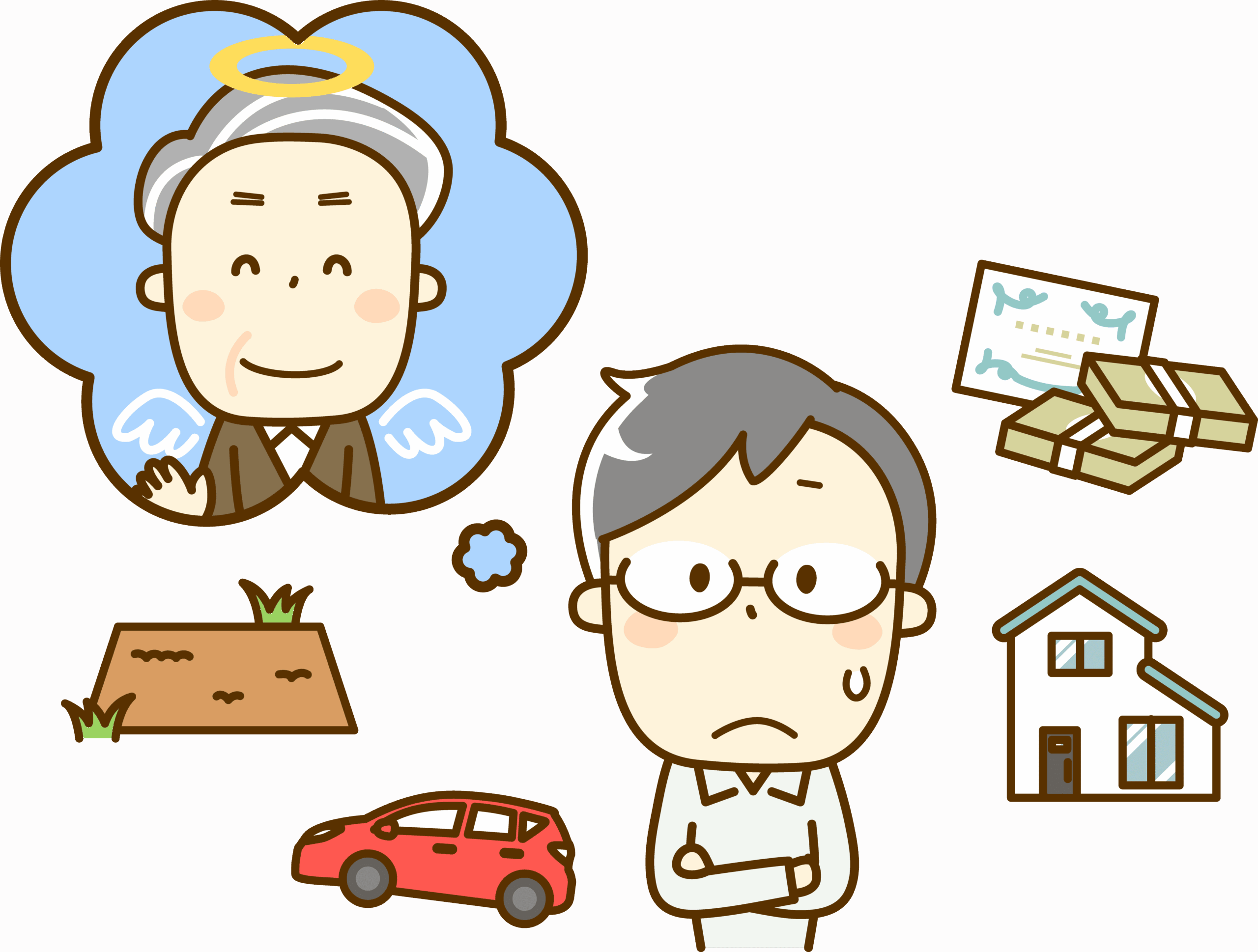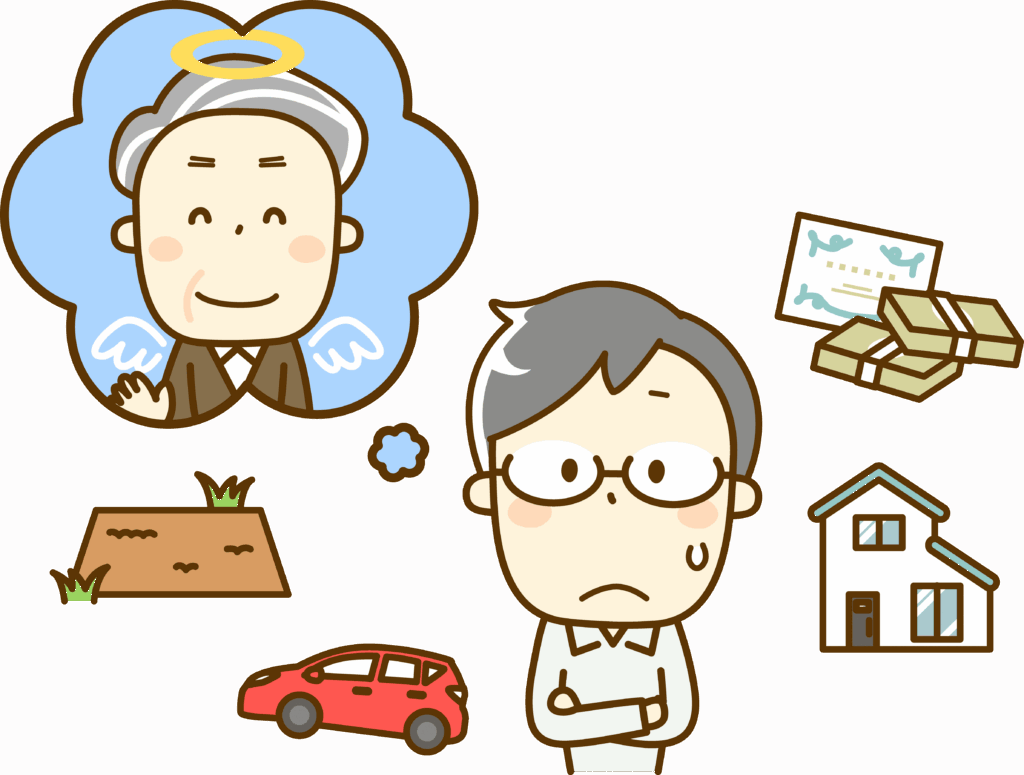
相続人が,留保を付けずに相続をする旨の意思表示をすることを,相続の単純承認といいます。この単純承認をするには、特段の行為を必要としません。
単純承認とは?
民法 第920条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
相続人は,相続をするかしないかの選択権を有しています。相続人が,相続をするという意思表示をすることを,相続の承認といいます。
この相続の承認には,単純承認と限定承認があります。
このうち,相続の単純承認とは,何らの留保もつけずに相続をするという意思表示をすることをいいます(民法920条)。つまり,原則どおりに相続することを受け入れるということです。
単純承認をすると,相続の原則どおり,その単純承認をした相続人は,被相続人の一切の権利義務を「無限に」承継することになりますので,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も,すべてそのまま受け継ぐことになります。
したがって,相続した財産が資産よりも負債が大きいという場合には,相続財産からだけでは負債を弁済しきれないので,相続人固有の財産で相続した負債を弁済しなければならなくなります。
単純承認をする場合には,そのことをよく考えておかなければならないでしょう。
単純承認の手続
単純承認をする場合には,相続放棄や限定承認の場合と異なり,特別な手続をとる必要ありません。
後述のとおり,法定単純承認という制度がありますので,放っておいても,相続開始を知った時から3か月が経過すれば,自動的に単純承認をしたものとみなされるからです。
ただし,もちろん,あえて単純承認の意思表示をすることもできますが,あまり意味はないということになります。
もっとも,逆にいえば,放っておくと勝手に単純承認が成立し,負債も含めた相続財産全部を承継しなければならなくなるということでもありますので,注意をしなければならないでしょう。
法定単純承認
民法 第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
第1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
第2号 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
第3号 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。民法 915条 第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
単純承認は,前記のとおり,あえて単純承認をする旨の意思表示をすることもできますが,通常は,法定単純承認が成立して,単純承認の効果が生ずるというのが一般的かと思います。
法定単純承認とは,一定の事由がある場合には,単純承認をしたものとみなすという制度のことをいいます(民法921条)。
この法定単純承認が成立すると,単純承認をしたものとみなされる結果,それ以降は,相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
法定単純承認は,以下の事由がある場合に成立することになります。
上記の事由がある場合には法定単純承認が成立してしまい,それ以上,限定承認や相続放棄をすることができなくなりますので,限定承認や相続放棄を検討されている場合は,上記の法定単純承認事由には十分に注意しておく必要があります。