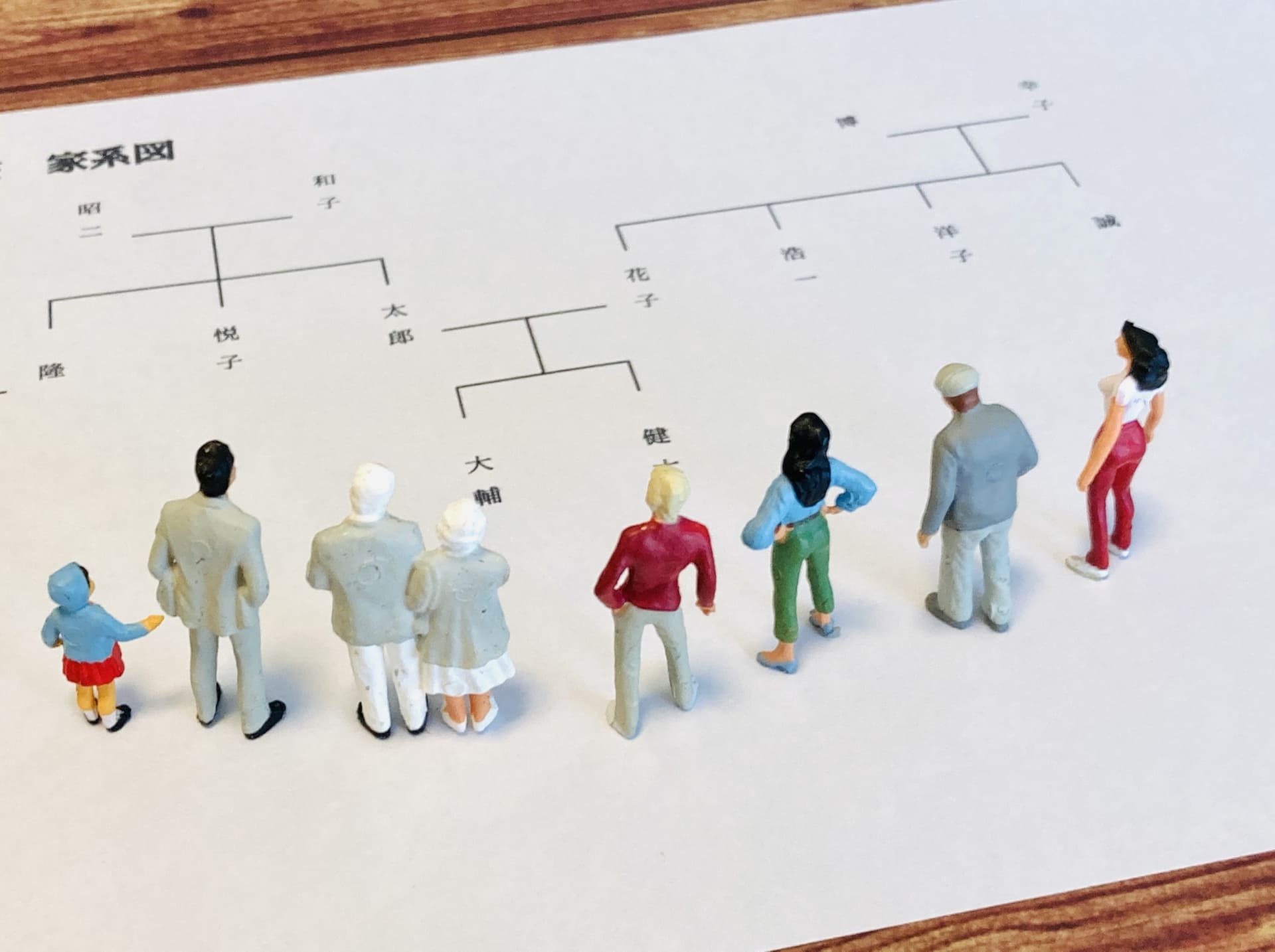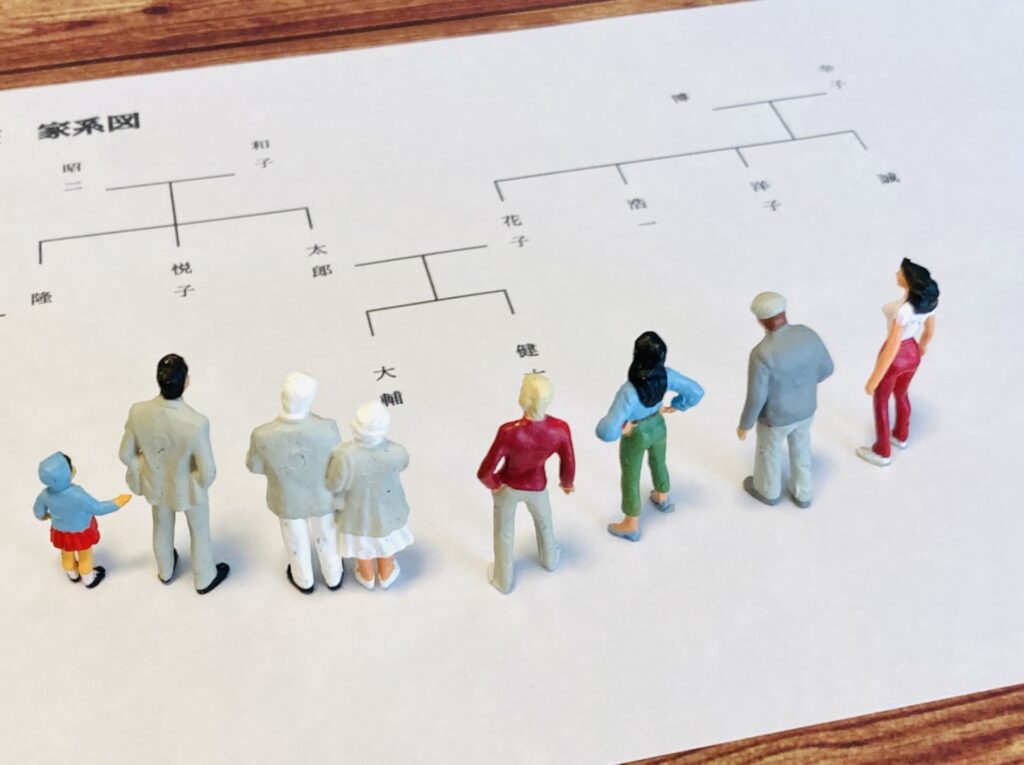
「遺贈(いぞう)」とは,遺言によって,他人に無償で財産の全部または一部を与える(贈与する)行為のことをいいます(民法964条)。
遺贈をした被相続人・遺言者のことを「遺贈者(いぞうしゃ)」と言い,遺贈によって相続財産を与えられた人のことを「受遺者(じゅいしゃ)」と言います。また,遺贈に伴う手続きや行為を実行すべき義務を負う人のことを「遺贈義務者」と言います。
遺贈(いぞう)とは?
民法 第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
遺贈(いぞう)とは,遺言によって,他人に無償で財産の全部または一部を与える(贈与する)行為のことをいいます(民法964条)。
遺贈の相手方は,相続人に限られません。相続人ではない第三者を相手方とすることも可能です。したがって,遺贈であれば,第三者に対しても遺産を譲り渡すことが可能です。
法は,相続において被相続人の意思を最大限尊重するため,遺言という制度を設け,被相続人は,この遺言を自由に定めることができるものとしています。これを「遺言自由の原則」といいます。
この遺言自由の原則の最たるものが遺贈です。そのため,遺言の自由とは,遺贈の自由を意味するといってもよいでしょう。
遺贈の当事者
遺贈をした被相続人・遺言者のことを「遺贈者(いぞうしゃ)」と言います。
他方,遺贈によって相続財産を与えられた人のことを「受遺者(じゅいしゃ)」と言います。前記のとおり,相続人のみならず,第三者も受遺者とすることができます。
なお,遺贈の内容を実現するために一定の手続きや行為をしなければならないこともあります。例えば,遺贈の目的物を引き渡す行為をしなければならない場合などです。
このような場合に,遺贈に伴う手続きや行為を実行すべき義務を負う人のことを「遺贈義務者」と言います。
遺贈義務者は,遺言で反対の意思表示がされていない限り,遺贈の目的物や権利を相続開始時の状態で受遺者に引き渡しまたは移転する義務を負うものとされています(民法998条)。
特定遺贈と包括遺贈
遺贈には,「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
特定遺贈とは,受遺者に与えられる目的物や財産的利益が特定されている場合の遺贈のことを言います。
他方,包括遺贈とは,遺産の全部または一定割合で示された部分を受遺者に与える場合の遺贈のことを言います。
包括遺贈のうち与えられる遺産が全部の場合を「全部包括遺贈」と言い,一部割合部分のみの場合を「割合的包括遺贈」と言います。
特定遺贈の場合,受遺者は当該遺産の権利のみを与えられます。これに対し,包括遺贈の場合,受遺者は,相続人と同一の権利義務を有することになります(民法990条)。
包括受遺者が相続人と同一の権利義務を有するというのは,相続人として扱われるということではなく,当該遺産の権利だけでなく,それに伴う義務も受遺者に移転するという意味です。
相続人以外の第三者に相続財産を承継させる方法
相続財産は,法定相続人に承継されるのが原則です。遺言で相続人の相続分を指定することは可能ですが,第三者を相続人に指定することはできません。
つまり,それぞれの法定相続人の相続分をどのような割合にするのかということを定めることはできますが,誰を相続人とするかを定めることはできません。
例えば,法定相続人でない第三者のAさんに相続をさせたいという場合に,遺言で「Cを相続人とする」と定めたとしても,その遺言には相続人指定の効力がないということです。
もっとも,事情によっては,法定相続人には財産を相続させたくない,あるいは,第三者に相続財産を譲り渡さなければならない理由がある,ということもあるでしょう。
そこで,法定相続人以外の第三者に財産を譲り渡させるために用いられる方法が,遺贈です。
遺贈によっても,相続人でない第三者を相続人にすることはできませんが,第三者に対して相続財産を譲り渡すことは可能となります。
遺贈と遺留分侵害額請求権
前記のとおり,遺贈をすれば,誰に対して,どのような財産を,どのくらい与えるのかを定めることができます。遺贈であれば,財産を承継させる相手が法定相続人でない第三者であっても可能です。
しかし,いかに被相続人の意思を尊重すべきとはいえ,相続人らの期待もある程度尊重する必要はあります。そのため,兄弟姉妹を除く法定相続人は,遺言によっても侵害できない「遺留分」が与えられています。
遺贈も遺言としてなされるものである以上,この遺留分を侵害する場合,侵害を被った遺留分権利者は,受遺者に対し,遺留分侵害額を請求することが可能です。
したがって,遺贈をする場合には,遺留分のことについて十分に注意をしておかなければならないでしょう。