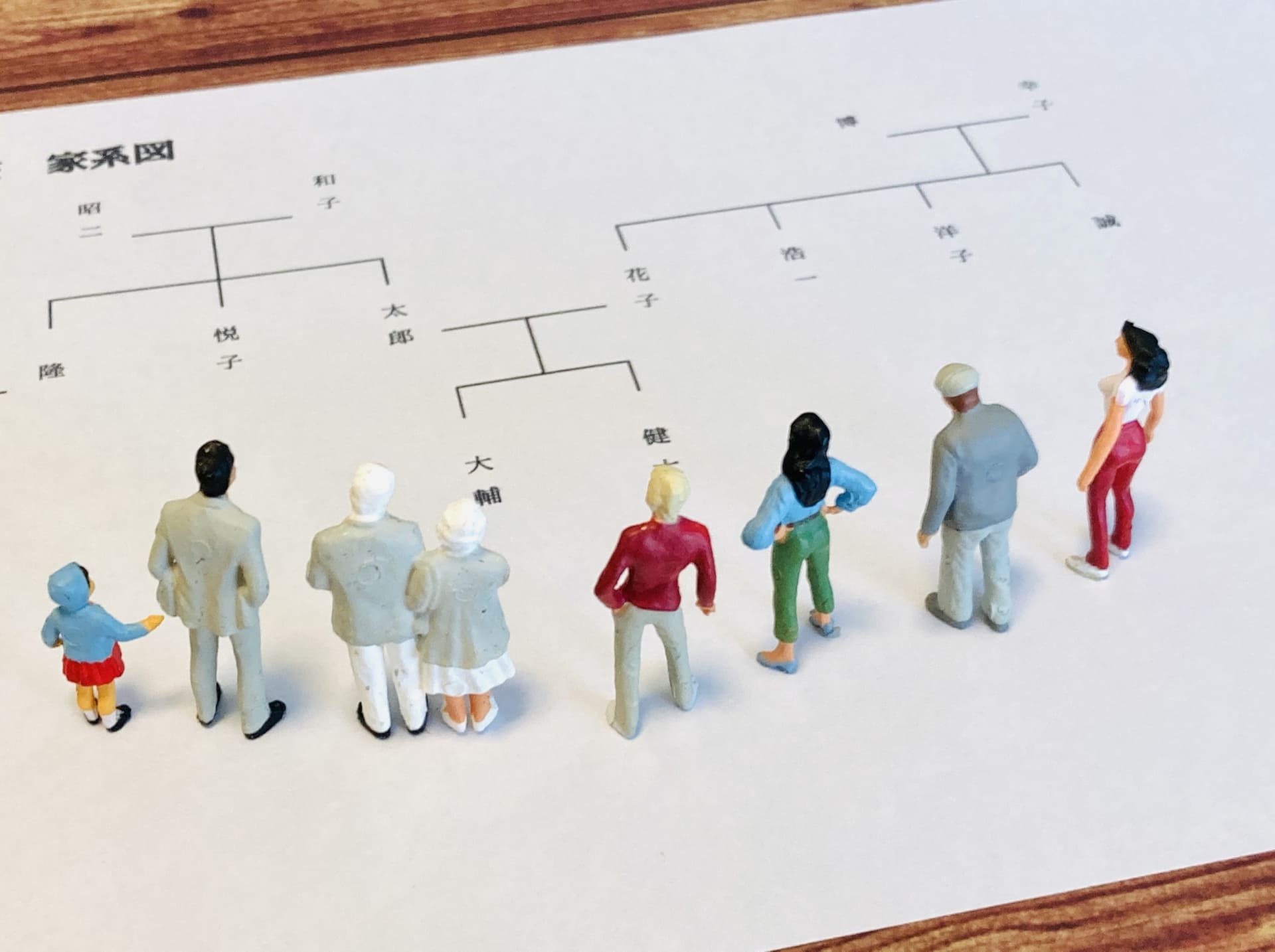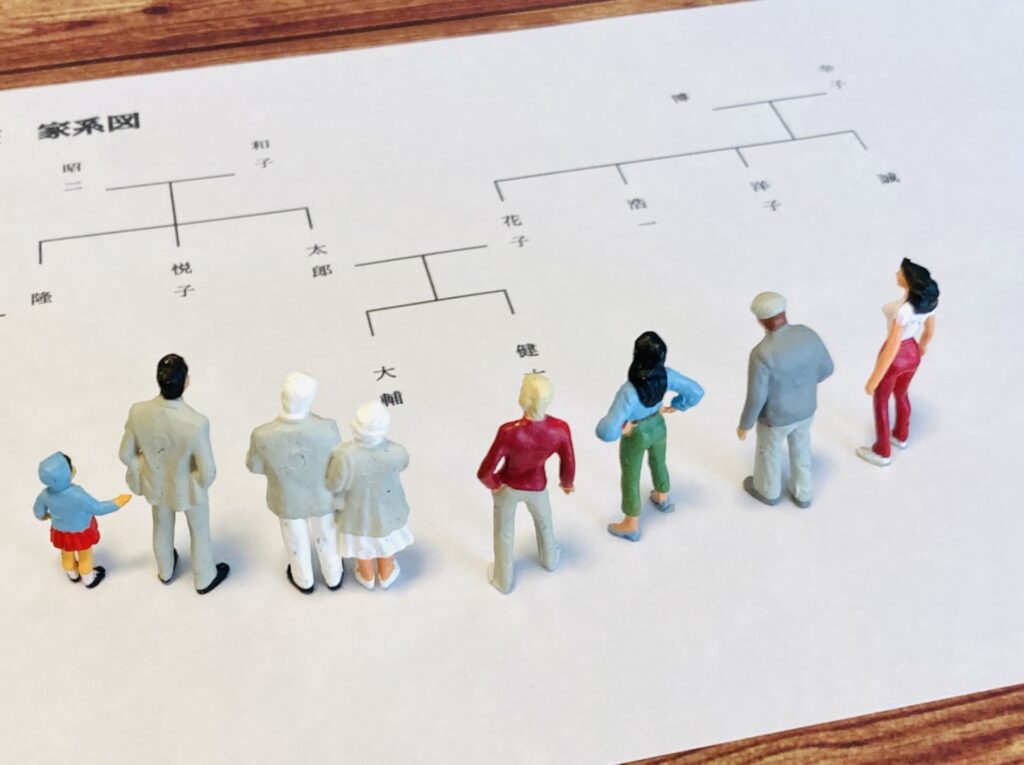
遺言があったとしても,その遺言の内容を実現するためには,相続の開始後に遺言の執行を行わなければならない場合があります。
もっとも,遺言で定められた事項のすべてについて遺言執行が必要となるというわけではありません。遺言事項には,遺言執行が必要となる事項とそうでない事項があります。
遺言事項と遺言の執行
遺言は,被相続人(亡くなられた方)の最後の意思表示です。そのため,法定の方式に則った遺言が作成されていた場合,相続が開始されると遺産の分配等は,遺言に従って行われることになります。
遺言に記載されていれば何でも法的効力を有するというわけではありませんが,基本的に相続財産(遺産)の分配方法等に関する記載事項は,法的効力を有することになります。
また,一定の身分的な事柄(子の認知など)についても,法的効力を有するものとされています。
このような遺言に記載された事項のうち,例えば,相続分の指定,遺産分割方法の指定,相続人間の担保責任の指定,未成年後見人の指定などの遺言事項については,それらが遺言に記載されていたということだけで,相続開始後,特に特別な行為を要せずに,法的効力を有することになります。
ところが,遺言事項のなかには,その遺言事項を法的に実現するためには,単に遺言に記載されているというだけでは足りず,それを実現するために特別な手続等をとらなければならないというものもあります。
そして,この遺言の内容を法的に実現するために必要となる行為をすることを「遺言の執行」と呼んでいます。
つまり,遺言には,そもそも遺言に記載しても法的効力のない事項,遺言に記載しておけばそれだけで法的効力を生ずる事項,遺言に記載しておくだけでは足りず遺言執行行為をしなければ確定的な法的効力を生じない事項があるということです。
遺言執行が必要となる遺言事項
遺言の執行が必要となる行為としては,以下のものが挙げられます。以下の事項を実現するためには,遺言執行が必要である以上,遺言執行者を指定することが必須となります。
遺言による認知
民法 第781条
第1項 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
第2項 認知は、遺言によっても、することができる。
子の認知は,通常生前に行われますが,遺言で子の認知をすることもできます。これを「遺言認知」または「死後認知」と呼んでいます(民法781条2項)。
この遺言認知は,単に遺言に記載していただけでは足りず,相続開始後に,別途,市町村役場に認知届を提出する必要があります。この遺言による認知届の提出という行為は,遺言執行者にしかできません(戸籍法64条、60条、61条)。
遺言による推定相続人の廃除
民法 第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
推定相続人の廃除とは,被相続人の意思によって,被相続人に対して虐待等を行った推定相続人(相続人となる予定の者)を相続人から外すという制度です。
この推定相続人の廃除も,通常は生前に行われますが,遺言によってすることもできます。これを「遺言廃除」と呼んでいます(民法893条)。
推定相続人の廃除をするためには,家庭裁判所による判断が必要となります。遺言廃除の場合も同様です。
そのため,遺言廃除の審判等を家庭裁判所に申立てなければなりませんが,この申立て及び手続の追行は遺言執行者にしかできません。
遺贈
民法 第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
遺言では,相続人以外の者に対して財産を贈与するという意思表示も可能です。これを「遺贈」といいます(民法964条)。
この遺贈を実現するための行為(例えば,不動産の所有権移転登記など)は,遺言執行者が行わなければならないとされています。
遺言による一般財団法人の設立における定款の作成
民法 第152条
第1項 一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
第2項 設立者は、遺言で、次条第1項各号に掲げる事項及び第154条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
第3項 第10条第2項の規定は、前二項の定款について準用する。
遺言で,その相続財産を利用して一般財団法人を設立するということを定めておくことも可能です。
ただし,この遺言による一般財団法人の設立においては,その定款は遺言執行者が作成して署名押印しなければならないとされています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条)。